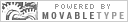|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年02月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年09月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
- 2015年03月
- 2015年02月
- 2015年01月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年08月
- 2014年07月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年09月
- 2011年08月
- 2011年07月
- 2011年06月
- 2011年05月
- 2011年04月
- 2011年03月
- 2011年02月
- 2011年01月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年09月
- 2010年08月
- 2010年07月
- 2010年06月
- 2010年05月
- 2010年04月
- 2010年03月
- 2010年02月
- 2010年01月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年09月
- 2009年08月
- 2009年07月
- 2009年06月
- 2009年05月
- 2009年04月
- 2009年03月
- 2009年02月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年09月
- 2008年08月
- 2008年07月
- 2008年06月
- 2008年05月
- 2008年04月
- 2008年03月
- 2008年02月
- 2008年01月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年09月
- 2007年08月
- 2007年07月
- 2007年06月
- 2007年05月
- 2007年03月
- 2007年02月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年07月
- 2006年06月
- 2006年05月
- 2006年04月
-
体験授業では「足部の機能解剖」について講義を聞いていただきます。そして、足の採型用の特殊なスポンジ「トリッシャム」を使って自分の足の型を採ってみましょう!
さらに、立位時の足の荷重状況を反映する「フットプリント」を採って、自分の足を分析してみましょう!
入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!
義肢装具士を体感する1日 OPEN CAMPUS 2016 実学が未来のキミを強くする!
★☆当日のスケジュール☆★ ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩 ◇12:00 体験授業(自分の足を分析してみよう!) ◇13:35 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:35 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)
★POINT お昼休憩に軽食をご用意いたします。 ※採型を体験していただきますので、汚れてもよい服装でご参加ください。
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
義肢装具士は『モノづくり』と『コミュニケーション』の仕事です。 自分のつくりだしたモノが、目の前で喜ばれる そんな仕事にやりがいを感じるキミを応援します!" target="_blank">10月29日(土)足の構造を分析してみよう! -
平成28年度 義肢装具学科 入学試験についてご案内します。
推薦一次・一般一次試験の出願を下記の通り受付けます。
受験希望の方はご確認の上、出願手続をお願いします。
◆試験科目 推薦入学試験: 一般教養(国語・コミュニケーション英語ⅠⅡ・適性(空間把握))・面接 一般入学試験: 一般教養(国語・コミュニケーション英語ⅠⅡ英語)・適性(ペーパークラフト実技)・面接
◆試験日程 推薦一次:平成28年10月8日(土) 出願期間:平成28年10月1日(土)~平成28年10月6日(木) 必着
一般一次:平成28年10月8日(土) 出願期間:平成28年10月1日(土)~平成28年10月6日(木) 必着
義肢装具学科では随時、学校見学および義肢装具製作施設見学ツアーを行っています。大切なあなたの進路決定のために、ぜひご参加ください!ご連絡お待ちしています!
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">平成29年度 推薦一次・一般一次入学試験 出願期間のご案内
" target="_blank">平成29年度 推薦一次・一般一次入学試験 出願期間のご案内 -
11:30~ 休 憩
オープンキャンパスでは、在校生が参加者の皆さんと直接お話しをさせていただきます。学校生活や講義内容について、在校生から実際の話が聞けることも、本校のオープンキャンパスの大きな特色です!
 11:45~ 学生企画「わたしの一週間」
ここでは2年生の学生さんが、一週間の学校生活や義肢装具を学ぶ楽しさについて発表をしてくれました。
参加者の皆さんも学生さんの発表に興味津々の様子でした。
11:45~ 学生企画「わたしの一週間」
ここでは2年生の学生さんが、一週間の学校生活や義肢装具を学ぶ楽しさについて発表をしてくれました。
参加者の皆さんも学生さんの発表に興味津々の様子でした。
 12:00~ ランチタイム
参加者の皆さんと在校生が一緒にランチをとりながら、楽しい雰囲気のなかでいろいろなご質問にお答えしています。
12:00~ ランチタイム
参加者の皆さんと在校生が一緒にランチをとりながら、楽しい雰囲気のなかでいろいろなご質問にお答えしています。
 12:30~ 体験授業
午後からはいよいよ体験授業です。
まず、義肢装具学科で行われている講義内容と同じレベルの講義をそのまま受講していただきます。今回のテーマは「下腿義足のアライメント」でした。失われた部分の義足を製作しただけでは、
立ったり、歩いたりすることができないことを理論的に理解して
いただけたと思います。義肢装具士はモノづくりだけでなく、患者様に適切にフィッティングさせる技術が必要です。
12:30~ 体験授業
午後からはいよいよ体験授業です。
まず、義肢装具学科で行われている講義内容と同じレベルの講義をそのまま受講していただきます。今回のテーマは「下腿義足のアライメント」でした。失われた部分の義足を製作しただけでは、
立ったり、歩いたりすることができないことを理論的に理解して
いただけたと思います。義肢装具士はモノづくりだけでなく、患者様に適切にフィッティングさせる技術が必要です。
 今回は下腿義足と大腿義足のユーザーにご協力いただきました。
今回は下腿義足と大腿義足のユーザーにご協力いただきました。
 まずは下腿義足ユーザーの歩行観察です。講義で聞いた歩行観察のポイントを思い出して、じっくり観察してみましょう。
歩行中に義足が地面に着いている時間はほんの一瞬ですが、この一瞬にいろいろな体の変化を観察できたと思います。
まずは下腿義足ユーザーの歩行観察です。講義で聞いた歩行観察のポイントを思い出して、じっくり観察してみましょう。
歩行中に義足が地面に着いている時間はほんの一瞬ですが、この一瞬にいろいろな体の変化を観察できたと思います。
 それでは、義足の調整をしてみましょう!
先生はネジを何回かまわしたようですが、歩行にどのような変化が現れるでしょうか?
それでは、義足の調整をしてみましょう!
先生はネジを何回かまわしたようですが、歩行にどのような変化が現れるでしょうか?
 義足を調整した後に、再度歩いていただきます。
先ほどの歩行と比べて、どこが変化したか分かりますか?
義足を調整した後に、再度歩いていただきます。
先ほどの歩行と比べて、どこが変化したか分かりますか?
 続いて、大腿義足ユーザーのデモンストレーションです。
大腿義足は、切断端(四肢が残存している部分)とソケットが“吸着”することで義足を懸垂しています。フィッティングが良いソケットは切断端にピッタリと吸着しているため、力いっぱい引っ張っても義足が抜けません!
続いて、大腿義足ユーザーのデモンストレーションです。
大腿義足は、切断端(四肢が残存している部分)とソケットが“吸着”することで義足を懸垂しています。フィッティングが良いソケットは切断端にピッタリと吸着しているため、力いっぱい引っ張っても義足が抜けません!
 次は、パラリンピックなどでも使用される「スポーツ用下腿義足」の走行デモンストレーションです。参加者の皆さんは初めて見るカーボン製の足部、通称“板バネ”での走行に興味津々でした!
次は、パラリンピックなどでも使用される「スポーツ用下腿義足」の走行デモンストレーションです。参加者の皆さんは初めて見るカーボン製の足部、通称“板バネ”での走行に興味津々でした!
 次は義足ユーザーへの“質問コーナー”です。
参加者の皆さんの素朴な疑問にお二人とも快くお答えいただき、和やかな歓談となりました。
次は義足ユーザーへの“質問コーナー”です。
参加者の皆さんの素朴な疑問にお二人とも快くお答えいただき、和やかな歓談となりました。
 最後は義足歩行を疑似体験できる“模擬義足”の装着です。
慣れないうちは立つのもやっとですが・・・。
最後は義足歩行を疑似体験できる“模擬義足”の装着です。
慣れないうちは立つのもやっとですが・・・。
 先生や在校生からの“義足の歩き方”のアドバイスを受けて、上手に歩けるようになりましたね!
先生や在校生からの“義足の歩き方”のアドバイスを受けて、上手に歩けるようになりましたね!
 こちらは“模擬大腿義足”に挑戦中ですね!
大腿義足は膝上の切断なので、膝関節は人工の関節“膝継手”に置き換えられます。自分で膝の曲げ伸ばしをコントロールできるようにならないと義足に体重をかけることがとても怖い、ということがよくお解りいただけたと思います。
こちらは“模擬大腿義足”に挑戦中ですね!
大腿義足は膝上の切断なので、膝関節は人工の関節“膝継手”に置き換えられます。自分で膝の曲げ伸ばしをコントロールできるようにならないと義足に体重をかけることがとても怖い、ということがよくお解りいただけたと思います。
参加者(保護者)の声 とても楽しく、良いオープンキャンパスでした。次も参加したいと思います。 (高校3年)
2回目の実習体験でしたが、前回より上手にできてうれしかったです。歩行観察では、少しの角度のズレで足の動きだけではなく、上半身のゆれ方が大きくなっていたのがとても興味深かったです。 (高校3年)
模擬義足を装着してみて、違和感に戸惑いました。太ももの筋肉がとても疲れた感じがしました。貴重な体験ができて良かったです。 (高校3年)
義肢装具士について知らなかったことがたくさんありましたが、今日の講義でたくさん知ることができました。 (高校3年)
知っていたこともあったけど、知らないことも多く聞けて良かったです。次のオープンキャンパスも参加したいと思います。 (高校3年)
体験授業がとても面白かったです。また、質問の答えが分かりやすかったです。 (高校3年)
今回は模擬義足を装着するという貴重な体験をさせてもらいました。入試がとても不安でしたが、先輩方のアドバイスをいただき少し気分が軽くなりました。合格できるように頑張ります。 (高校3年)
模擬義足の装着体験をさせて頂きました。歩くのがとても難しく、気を抜くと膝が曲がって転倒してしまいそうでした。ユーザーさんの気持ちを体験できました。 (高校3年)
義肢装具士の業務には様々な分野があることを知ってとても驚きました。義足をつけて歩くことができ、良い体験ができました。 (高校2年)
初めて義肢装具士養成校に来て、色々なことを知る事ができて、さらに義肢装具士に興味を持ちました。とても大変そうな学校生活だと思いましたが、同じ目標を持つ学生ばかりなので、とても楽しそうでした。また来てみたいと思います。 (高校2年)
体験授業で実際に義足を使われている方のお話が聞けて、とても面白かったです。今後の進路の候補として考えたいと思いました。 (高校2年)
説明が分かり易く、良かったです。学生さんの普段の生活についても分かり良かったです。義足ユーザーの方とお話ができて良かったです。とても丁寧なわかりやすいオープンキャンパスでした。 (保護者)
義肢装具士という職業にとても興味を持つことができ、子供がこの職業に就けるようサポートしていきたいと思いました。 (保護者)
先生方も学生さんもまとまりがある感じがして、とても良い学校だと思いました。義肢装具士は、今まで自分の身近になかった世界でしたが、参加して大きく社会貢献ができる職業だと分かり、とても好意的に感じることができました。先生方や学生さんの感じもとても親切で良かったです。ぜひ、ここで学ばせたいと思いました。よろしくお願い致します。 (保護者)
今日は学生発表を聞きたくて参加させて頂きました。先生方や生徒さんの雰囲気も良く、いつも気持ちの良い対応をして下さるので、今回も安心しました。お世話になると思いますが、よろしくお願い致します。 (保護者)
参加者の皆さん、今回もご参加いただき、ありがとうございました!今後も義肢装具学科の魅力を伝えるコンテンツをたくさんご用意して皆様のご参加をお待ちしています!" target="_blank">NEW! OPEN CAMPUS『義足ユーザーの歩行を観察してみよう!』 -
陽性モデルを修正する前に、骨標本で骨盤の解剖学的な特徴を十分に理解し、採型が正確に行われたかを確認して行きます。
 大腿骨の位置を捉えて釘を打ち込みます。IRCソケットは常に骨の位置を確認しながら陽性モデル修正を行います。
大腿骨の位置を捉えて釘を打ち込みます。IRCソケットは常に骨の位置を確認しながら陽性モデル修正を行います。
 実際に義足を装着して立位をとった状態を想定し、製作上のすべての基準となるアライメントを設定します。緻密な作業が続きますが、ソケットの適合性を高めるにはこのような緻密な作業の積み重ねが重要となります。
実際に義足を装着して立位をとった状態を想定し、製作上のすべての基準となるアライメントを設定します。緻密な作業が続きますが、ソケットの適合性を高めるにはこのような緻密な作業の積み重ねが重要となります。
 香川先生のデモンストレーションの進行に合わせて、製作工程が板書されます。細かな修正ポイントが丁寧に示されていて、一目瞭然ですね!
香川先生のデモンストレーションの進行に合わせて、製作工程が板書されます。細かな修正ポイントが丁寧に示されていて、一目瞭然ですね!
 さあ、いよいよ実践です!
香川先生の陽性モデルをよく観察して、正確に再現することを心掛けましょう!
さあ、いよいよ実践です!
香川先生の陽性モデルをよく観察して、正確に再現することを心掛けましょう!
次は、ソケットのフィッティング作業の様子をレポートします。 3年生の製作したソケットが、どのような結果となるか楽しみです! " target="_blank">NEW! 3年生 IRCソケットの陽性モデル修正が行われました。 -
前期に引き続き、香川貴宏先生(㈱松本義肢製作所)にご指導いただきます。IRCソケットは、四辺形ソケットと比べ、より厳密な坐骨周辺の適合性が求められるため、骨形状を解剖学的に理解していることが重要となります。
 IRCソケットは坐骨周辺の形状を正確に採型することが必要となるため、二人一組で採型します。
IRCソケットは坐骨周辺の形状を正確に採型することが必要となるため、二人一組で採型します。
 採型を終えると、陰性モデルのチェックを行います。
IRCソケットの適合の要となる、「骨M-L径」が採寸した数値と合致しているか確認をします。
採型を終えると、陰性モデルのチェックを行います。
IRCソケットの適合の要となる、「骨M-L径」が採寸した数値と合致しているか確認をします。


 メインで採型をする人、採型者をサポートする人、お互いの息が合っていないと上手く採型できません。切断者の負担も考えて、段取り良く採型して下さいね!
メインで採型をする人、採型者をサポートする人、お互いの息が合っていないと上手く採型できません。切断者の負担も考えて、段取り良く採型して下さいね!
次回は、陽性モデル修正の様子をレポートします! 10月からは後期の授業が始まりますので、引き続き講義の様子をどんどんお伝えして行きます!" target="_blank">NEW! 3年生 大腿義足の採型実習が行われました。 -
深谷先生(写真左)、藤田先生(写真右)は本学院の卒業生であり、義肢パーツメーカーに勤務する義肢装具士として現在どのように義肢ユーザーと関わっているのか、仕事の楽しさや魅力などを交えながらご講義いただきました。
 義肢装具士は多種多様な義肢パーツの特徴を理解している必要があります。膝継手や足部の機能が義足ユーザーの生活にどのように影響するのか、しっかり勉強して下さいね!
義肢装具士は多種多様な義肢パーツの特徴を理解している必要があります。膝継手や足部の機能が義足ユーザーの生活にどのように影響するのか、しっかり勉強して下さいね!
最後に、「模擬義足」を使って義足足部の感触を一つ一つ体験しました。ご紹介いただいた足部のなかには、小走りができる高機能なものから、ゆっくり歩きで安全性を重視した低活動者向けのものまで幅広くあり、学生たちもこれらの感触の違いに驚いていたようです。
深谷先生、藤田先生本当にありがとうございました! " target="_blank">NEW! ottobock社の義足膝継手特別講義が行われました。 -
「入試直前対策講座」と題し、いよいよ間近に迫った10月からの入学試験のポイントについて詳細にお話しします。
入試に備えてしっかりと情報収集をしてください!!
筆記試験の出題傾向と学習の要点、面接試験の重要ポイントなどについて具体的に説明を行います。ポイントをおさえて、ぜひ入学試験のご参考にしてくださいね!
義肢装具士を体感する1日 OPEN CAMPUS 2016 実学が未来のキミを強くする!
★☆当日のスケジュール☆★ ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩 ◇11:45 入試直前対策講座(入試に備えてしっかりと情報収集!) ◇12:50 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇12:50 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇13:15 終 了(予定)
筆記試験の出題傾向と学習の要点 面接試験の重要ポイントなどについて具体的に説明を行います!
義肢装具士は『モノづくり』と『コミュニケーション』の仕事です。 自分のつくりだしたモノが、目の前で喜ばれる そんな仕事にやりがいを感じるキミを応援します!" target="_blank">9月10日(土)入試直前対策講座! -
2年生が担当している患者様については2年生が事前に説明をします。
 熱心にメモを取り、質問をする1年生
熱心にメモを取り、質問をする1年生
 患者様とも関わらせていただきました
患者様とも関わらせていただきました
 やや緊張気味。でも、せっかくの機会を逃さないように、積極的にお話をしようと頑張っています。
やや緊張気味。でも、せっかくの機会を逃さないように、積極的にお話をしようと頑張っています。
見学後には2年生と質疑応答の時間。1年生から沢山良い質問が出ました。 2年生も1年生からの質問に答え、その後、さらに1年生のレポート添削も2年生がしてくれます。 2年生は先輩が後輩を育てようとする姿勢が学生のうちから身についており、1年生が少しでも理解できるように説明も工夫し、準備をしていました。 1年生は今回の見学で学習へのモチベーションがさらに高まったようです! これから専門科目がさらに進んできます。 今回の経験と知識をぜひ結び付けてくださいね。 " target="_blank">聴能1年生が学内臨床見学をしました -
「保育園にお邪魔して、手を取り一緒に遊んで話をしてきました。」「園児は元気いっぱいで、水遊びなどがとても楽しかった、行ってよかった」という声がほとんどでした。

そして、子どもの正常発達の理解が深まったようです。学生の気づきや感想で印象的なものを少し紹介します。
「保育士さんの声のトーンの違いで園児の理解が違うことがわかりました」 「2-3歳でも自分でロッカーに荷物を入れて連絡帳を提出できていました。また、一人で着替えをし、昼寝後の布団たたみができることにびっくりしました」 「3歳児は思ったより人の話を理解して、助詞を使った話をすることに驚きました」
書ききれないほどたくさんありますので、このくらいにしておきます。 5歳と3歳の違いに気付くことも多かったようです。 また、「譲ってあげる心を育てる」など保育士さんのおはなしややさしさも印象に残っているようでした。
保育園の方々、お忙しい中本当にありがとうございました。
" target="_blank">補聴1年生の保育実習レポートです -
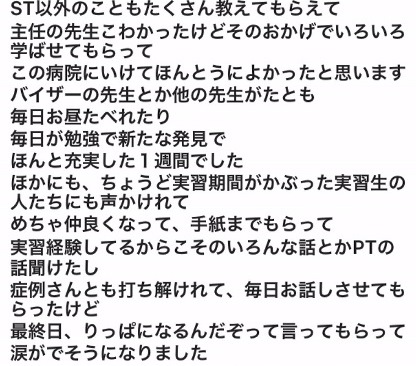
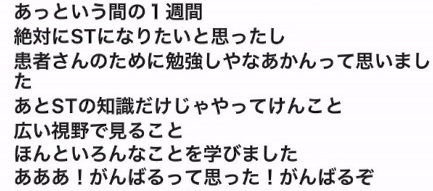
Yさんの感想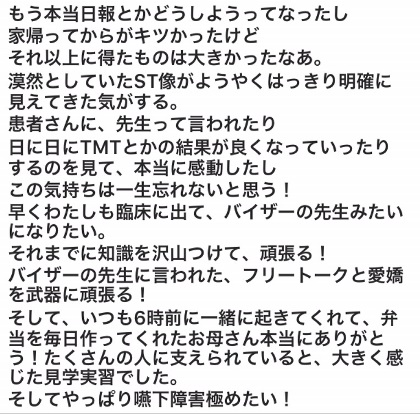
実習指導者の臨床される姿を見て、「言語聴覚士になりたい!」という気持ちを新たにした学生がたくさんいます。 お世話になった先生方、本当にありがとうございました。 先生方より頂いた実習生へのアドバイス、励まし、注意などをしっかりフィードバックいたしますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
 実習指導者の聴能19期 井村 舞先生を囲んで。ちなみに両脇はNさんでもYさんでもありません。
実習指導者の聴能19期 井村 舞先生を囲んで。ちなみに両脇はNさんでもYさんでもありません。
" target="_blank">補聴2年生が見学実習から帰ってきました -
体験授業では「筋電義手」の仕組みを学び、電動ハンドを自身の電気信号でコントロールする体験ができます!
また、実際の義手ユーザーにお越しいただき、義手の装着や操作方法についてデモンストレーションを見学していただきます!
体験実習では参加者のみなさんの筋電位を導出し、実際に筋電義手の操作訓練を体験していただきます!
また、今回のオープンキャンパスでは「学生企画 一週間の学生生活」と題し、3年生の先輩から毎日どんな風に学校で過ごしているか?、どんな授業を受けているか?などなど、皆さんの気になる「学校生活」についてプレゼンテーションをしてもらいます!!
先生はもちろん、在校生と話す機会もたくさんありますので、入試情報や学生生活など、どんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!
義肢装具士を体感する1日 OPEN CAMPUS 2016 実学が未来のキミを強くする! ★☆当日のスケジュール☆★ ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩(在校生とおしゃべりして情報収集!) ◇11:45 学生企画(在校生による学校生活のプレゼンテーション!) ◇12:00 昼 食(在校生と軽食をとりながら、気軽に何でも聞いちゃおう!) ◇12:30 体験授業(筋電義手に触れてみよう!) ◇15:00 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:00 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇15:30 終 了(予定) 義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス! 義肢装具士は『モノづくり』と『コミュニケーション』の仕事です。 自分のつくりだしたモノが、目の前で喜ばれる そんな仕事にやりがいを感じるキミを応援します!" target="_blank">8月20日(土)筋電義手に触れてみよう! -
学生と話そうコーナー : 学生の本音が聞けます
 学生と話そうコーナー : 何でも質問して下さい
学生と話そうコーナー : 何でも質問して下さい
仕事紹介を聞き、「言語や聴覚についてより理解ができ、参加して良かった。」という意見や、学内ツアーに参加し、「実際に使用する道具などを見て実感できた。」という声を聞くことができました。
 STが使用する道具を説明します
STが使用する道具を説明します
次回は9月17日(土)に開催予定です。学院にご興味のある方はぜひお越しください。お待ちしています。
 オープンキャンパス来てくださーい。人形のアイちゃんも待ってますよ。
オープンキャンパス来てくださーい。人形のアイちゃんも待ってますよ。

" target="_blank">オープンキャンパスの様子です -
分解して洗って干す
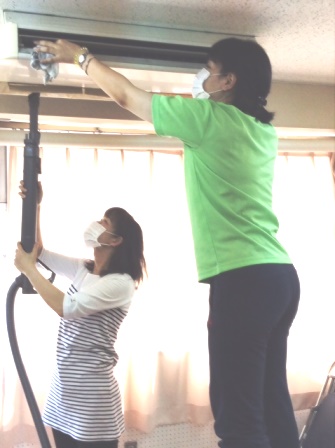 マスクは必須
マスクは必須
今日の名古屋は35度を超える猛暑日。 エアコンの掃除はエアコンを入れられないため、汗がぼたぼた。 大倉先生が音楽をかけて(誰の曲かは内緒です)、汗だく、変なテンションになりながら、真夏の大掃除は行われました。
 なぞのテンション その1 ファブリーズ二刀流
なぞのテンション その1 ファブリーズ二刀流
 なぞのテンション その2 マイレイコップ(家から持参)を持つ大倉先生
なぞのテンション その2 マイレイコップ(家から持参)を持つ大倉先生
訓練室の空気がすっきりした気がします(当学院比)。 なにやら気持ちもすっきりして、打ち上げ気分でアイスクリームを食べる教員たちでした。 ちなみに園田先生は男らしく(?)顔を水洗いしてすっきりしていました 笑。 " target="_blank">真夏の大掃除 教員編 - 訓練課題を制作中・・・ " target="_blank">臨床実習奮闘中!!
-
宿から海を眺める学生たち どの部屋もオーシャンビューでした
 2日目も隙あらばアイスクリームを食べる女子
2日目も隙あらばアイスクリームを食べる女子
 全員集合!
全員集合!
2日間、楽しく無事に過ごせました。 学外授業担当係さん、おつかれさまでした。
" target="_blank">補聴2年生学外授業4 (写真のみ)
会場は愛知県小牧市の義肢装具製作会社、(株)松本義肢製作所です。 義肢や装具、車椅子など多岐に渡る製品が義肢装具士の手によってオーダーメイドで製作される様子を見学していただきます。 当日は施設の方に、義肢装具製作会社での義肢装具士の役割や、医療における義肢装具製作施設の役割についてご説明いただきます!
当日のスケジュール ◇12:30 受 付((株)松本義肢製作所 現地集合) ◇13:00 学科説明 ◇14:00 休 憩 ◇14:15 特別講義(施設の方から義肢装具士の役割についてご説明) ◇15:15 休 憩 ◇15:30 施設見学(義肢装具士の現場を見学しよう!) ◇16:30 終 了(予定 現地解散)
◆会 場 株式会社 松本義肢製作所(愛知県小牧市大字林210-3) ※イベントに関するお問い合せは、本学までご連絡ください。
◆アクセス 【名古屋駅よりお越しの場合】 名古屋―小牧駅(乗り換え2回) 名古屋市営地下鉄桜通線 『名古屋』 ↓ 名古屋市営地下鉄桜通線・徳重行 『久屋大通』 (乗り換え1回目) ↓ 名古屋市営地下鉄名城線・右回り大曽根・本山方面 『平安通』 (乗り換え2回目) ↓ 名古屋市営地下鉄上飯田線・犬山行 『小牧』下車 ※上飯田線は上飯田からそのまま名鉄小牧線に連絡しています。
【名鉄小牧駅より】 名鉄小牧線 小牧駅・小牧原駅から あおい交通(ピーチバス桃花台循環コース・桃花台行)古雅(こが)3丁目下車 小牧駅前-古雅3丁目 11:05発-11:23着 11:35発-11:53着 12:05発-12:23着 徒歩約10分 篠岡交差点右折、市立篠岡保育園裏
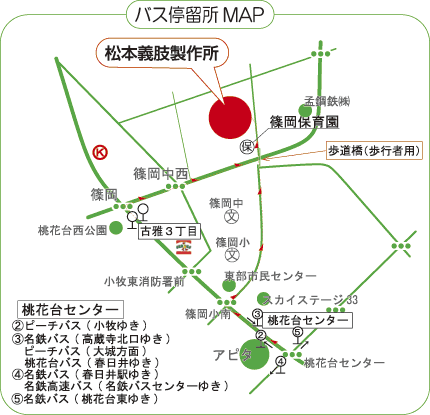
※アクセスに関するお問い合わせは、学院事務(052-482-8788)までご連絡ください。 ※公共交通機関をご利用ください。 ※詳しいアクセスMAPはこちらをご参照ください。
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
第3回オープンキャンパスの様子はコチラ
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">8月3日(水)義肢装具士の現場を見学してみよう!
" target="_blank">8月3日(水)義肢装具士の現場を見学してみよう!-
答えは「NO~~~」
 「え?琵琶湖のイラストってどうやって描けばいい?」
「え?琵琶湖のイラストってどうやって描けばいい?」
 優勝チーム!
優勝チーム!
さらにさらにその後は花火大会。 海の向こうに、鳥羽での打ち上げ花火を見ながら、海辺で始まりました。 その日はあいにくの強風、ろうそくの火がすぐに消えてしまいます。 そのため「火ちょうだ~い」とオリンピックの聖火リレーならぬ、花火リレーが行われ、よりコミュニケーションが深まったのでした。
 浜辺での花火
浜辺での花火
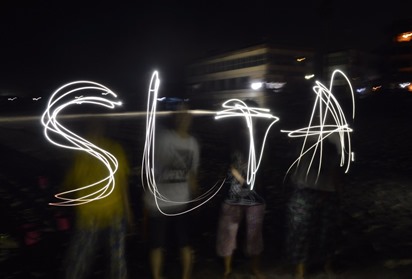 失語症の代表的な検査SLTA!
失語症の代表的な検査SLTA!
 流暢性の評価と言えば・・・・BENSON!
流暢性の評価と言えば・・・・BENSON!
" target="_blank">補聴2年生学外授業 その3 -
「この木は甘いんじゃない?」
その後は、バーベキュー大会。 炭ではなく、薪を使っての火おこしにやや苦戦する学生たち。 でもバーベキューは大成功、〆の焼きそばまでしっかり食べ、おなか一杯となりました。
 肉を配給中
肉を配給中
 薪を使って火をおこします
薪を使って火をおこします
 まずはお肉とお野菜を焼きま~す
まずはお肉とお野菜を焼きま~す
 焼きそば麺投入!
焼きそば麺投入!
 食後のデザート、隙あらばアイスクリームを食べる女子たち
食後のデザート、隙あらばアイスクリームを食べる女子たち
「先生、私たち飛んできます!ブログに乗せて下さいっ!」とスカイコースターに向かう勇者たち。 空中で「私たち、立派なSTになりま~す」と叫んだそうです。
 余裕で手を振る勇者
余裕で手を振る勇者
 つるされる勇者たち
つるされる勇者たち
 勇者たちを見守るクラスメートたち
勇者たちを見守るクラスメートたち
 つるされ・・・
つるされ・・・
 飛んでます~
飛んでます~
 " target="_blank">補聴2年生学外授業 その2
" target="_blank">補聴2年生学外授業 その2 -
週間天気では、曇り時々雨になっていたけれど、目的地である南知多だけは学外授業の間は晴天とのこと。事実、電車に乗っている間は雨が降っていたのに、内海に着くころはすっかり晴れていました。 運の強い補聴2年生です。

内海駅から南知多グリーンバレーまではウォーキング。 たっぷり30分くらいかかったけれど、鶯のさえずりや川のせせらぎをBGMに学生たちは虫の話や植物の話に花が咲きます。 急な上り坂になろうがおかまいなしで、歩きながらジャンケンゲームに没頭する学生たちを見て、「若さ」を感じる教員でした。 " target="_blank">補聴2年生学外授業 その1 -
 学院名が長くて・・・
学院名が長くて・・・
 「初日にどちらに伺うか聞き忘れた~」
「初日にどちらに伺うか聞き忘れた~」
これまた恒例の「先輩による服装チェック」です。髪型、髪色、スカート丈、襟もと、かばん、腕時計などなど3年生から厳しい指導、アドバイスが入ります。
 チェックの順番待ち「襟元だいじょうぶかしら?」
チェックの順番待ち「襟元だいじょうぶかしら?」
今年は初めて「3年生に聞いてみよう」を試みました。3年生が去年の見学実習で「こうすれば良かったと思う事、反省する事など」を2年生に伝えてもらうコーナーです。
「病院で特に多い患者さんを聞いておいて、復習をしておきました。ちなみに私が実習した病院では嚥下患者さんが多かったです」 「積極的に片付け、掃除を手伝いました」 「嚥下障害ポケットマニュアルを買ったんですけど、コレいいです!」

 ピースする先輩と緊張気味の後輩
ピースする先輩と緊張気味の後輩
1週間とはいえ、初めての実習。緊張している2年生は3年生の話を熱心に聞いていました。しっかり見学して、今まで机上で学んできたことをしっかり身につけて下さいね。
" target="_blank">見学実習オリエンテーション -
2016年第5回オープンキャンパスを7月23日(土)に開催いたします!
今回の体験授業では実際の義足ユーザーをお招きし「義足の歩行観察」を行います! 話題のスポーツ用義足によるデモンストレーションも行います! 義肢装具士を体感するチャンス!!
また、今回のオープンキャンパスでは「学生企画 一週間の学生生活」と題し、2年生の先輩から毎日どんな風に学校で過ごしているか?、どんな授業を受けているか?などなど、皆さんの気になる「学校生活」についてプレゼンテーションをしてもらいます!!
先生はもちろん、在校生と話す機会もたくさんありますので、入試情報や学生生活など、どんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!
義肢装具士を体感する1日 OPEN CAMPUS 2016 実学が未来のキミを強くする!
★☆当日のスケジュール☆★ ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩(在校生とおしゃべりして情報収集!) ◇11:45 学生企画(在校生による学校生活のプレゼンテーション!) ◇12:00 昼 食(在校生と軽食をとりながら、気軽に何でも聞いちゃおう!) ◇12:30 体験授業(義足ユーザーの歩行を観察してみよう!) ◇15:00 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:00 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇15:30 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! 本物の義肢装具を見て、触れるチャンス! 将来の進路選択に向けてバッチリ情報を集めちゃおう!
義肢装具士は『モノづくり』と『コミュニケーション』の仕事です。 自分のつくりだしたモノが、目の前で喜ばれる そんな仕事にやりがいを感じるキミを応援します!
みなさんの参加をお待ちしています!
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
 " target="_blank">7月23日(土)義足ユーザーの歩行を観察してみよう!
" target="_blank">7月23日(土)義足ユーザーの歩行を観察してみよう! - 今日はこの学内実習に取り組んでいる学生の感想を紹介します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 早いもので学内実習に取り組んで3か月がたちました。 この学内実習は、先生方が受け持っている患者様にご協力いただいて、 実際に検査や訓練を担当させていただくというものです。 私は失語症の方を担当させていただいています。 患者様の症状やコミュニケーションで困っていることなどを調べるため、 グループで計画を立てた検査や情報収集をし、 さらにどんな訓練をしていくべきかを何度も話し合って、 1か月ほど前から訓練をさせていただいています。 1年間勉強してきたことでも、 実際にやってみると疑問や失敗だらけで、自分の未熟さを痛感します。 それでも、先生方の厳しくも温かいご指導を受けたり、 患者様と会っていろんなことをお話しすると、 「もっと頑張りたい」という気持ちになれます。 大変ですが、その分とてもやりがいがあって楽しいです。 (聴能言語学科2年生 Aさん) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ グループで一人の患者様のことを一生懸命考えている姿にも、 STとなった近い将来の姿を重ねて嬉しくなりますね。 たまには厳しい一言も言いますが、 それは学生一人一人の成長を願っているからこそ、です。 次の春にはSTとして現場で患者様に向き合うのですから。 学内臨床で培った力がSTとなった時にきっと生かされると信じています。 " target="_blank">学内実習がんばっています!
-
朝早くから学生会がお昼のカレーを作ってくれました!
いつものように他学科の先生方や事務の皆さんにもお裾分けをして喜んでいただけました。美味しいものはみんなで!分け合う心が大切ですね!!
 暑い中、頑張って掃除した後のカレーは美味しいですね!
暑い中、頑張って掃除した後のカレーは美味しいですね!
 最後の一杯をかけてじゃんけん!
最後の一杯をかけてじゃんけん!
1・2年生は夏休みに海合宿を企画しているようです。 そして、2年生は8月から初めての臨床実習がはじまります。 3年生は臨床実習もいよいよ後半戦、あと少し頑張ってください!
それぞれ充実した夏休みになるといいですね!" target="_blank">NEW! 夏の大掃除カレー! -
2016年第4回オープンキャンパスを7月9日(土)に開催いたします!
義肢装具士のモノづくりは、患者さんの体を採型するところから始まり、個々に合った義肢や装具を製作します。また、できあがった製品を生活の場面に合わせて使いやすいように調整することも義肢装具士の大切な仕事です。 オープンキャンパスでは、義肢装具士を体感できる魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています! 義肢装具学科の先生はもちろん、在校生と話す機会もありますので、入試情報や学生生活など、どんどん質問して医療専門職としての義肢装具士の魅力を体感してください!
義肢装具士を体感する1日 OPEN CAMPUS 2016 実学が未来のキミを強くする!
★☆当日のスケジュール☆★ ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明(義肢装具士や学科の特色など詳しくご説明!) ◇11:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇11:30 個別相談(授業のこと、入試のことなど何でも相談!) ◇12:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! 本物の義肢装具を見て、触れるチャンス! 将来の進路選択に向けてバッチリ情報を集めちゃおう!
義肢装具士は『モノづくり』と『コミュニケーション』の仕事です。 自分のつくりだしたモノが、目の前で喜ばれる そんな仕事にやりがいを感じるキミを応援します!
みなさんの参加をお待ちしています!
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
 " target="_blank">7月9日(土)義肢装具士をもっと知ってみよう!
" target="_blank">7月9日(土)義肢装具士をもっと知ってみよう! -
学生の一人が竹を背負って登校したそうです。その子は「かなり怪しい人に見られた」と笑ってました。
短冊にはいろんな願いが書かれていて、中に「枝豆になりたい」というものがありました。 どういう意味なのでしょうか? いま流行っているのでしょうか? たけし軍団にいたつまみ枝豆さんの事?(歳がばれます)よく分かりませんが、私はやはり枝豆は「なる」よりは「食べたい」と思います。
季節の行事って良いですね。 私も病院勤務時代に作業療法士さんたちと作った七夕飾りを思い出して、久しぶりに作ってみました。 学生がたくさ~ん知識を得られるように(大量を願う)網飾りにしてみました。もうすぐ夏休みです。いろんな経験を積んで知識も深めて下さいね。
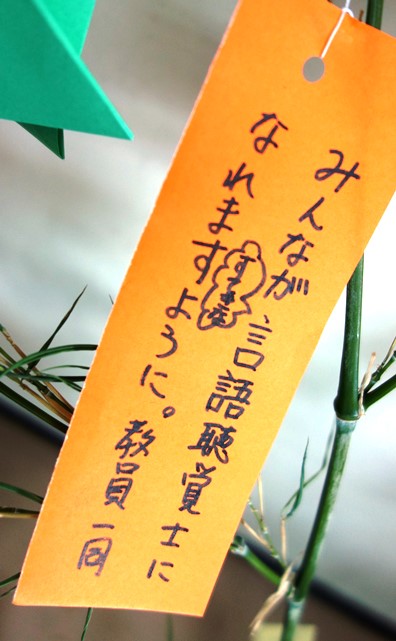 教員の願いは一つ「みんなが素敵な言語聴覚士になれますように」
教員の願いは一つ「みんなが素敵な言語聴覚士になれますように」
" target="_blank">☆☆七夕祭り☆☆ -
学生時代は立ち入り禁止場所にてお茶を飲む卒業生
近況報告の後は昔話(?)に花が咲き、半日近く滞在する人もいます。 予想外な卒業生が来て「やっぱり学校はいい~、落ち着く~」と言われると、少し涙腺がゆるみそうになります。
相談でも、求人探しでも、何にも用事がなくても(笑)、教員室に卒業生が顔を出してくれると、安心します。名古屋駅まで来たら、ぜひ学院まで足を延ばして下さいね。 " target="_blank">卒業生が来る季節? -
そして、最後には一人ひとりへのコメント付き『お守り栄養ドリンク』のプレゼント。 1年生にとっては、 不安も多かった4月の入学以来、 勉強面、生活面で多くのサポートをしてくれた2年生に対しての お礼の気持ちもあることと思います。 臨床実習で多くのことを学んで学院に帰ってきたとき、 1年生から、より「大きくなった先輩」と思ってもらえるように 全力で取り組んでくださいね! 楽しい壮行会でした。" target="_blank">臨床実習壮行会! -
今回のオープンキャンパスより、看板をリニューアル!
可愛いイラストは、義肢装具学科の女子学生がデザインしてくれました!「医療職」を表す「白衣」、「義肢装具士」を表す「義足」、「言語聴覚士」を表す「訓練カード」となっています。
後方の大きな垂れ幕も新たに作成し、賑やかな雰囲気の中で参加者の皆さんをお迎えします!
 10:00~ 受付
この日の名古屋は、梅雨の合間の快晴!
とても暑い1日となりましたが、遠方から多くの皆さんにご参加いただきました。
10:00~ 受付
この日の名古屋は、梅雨の合間の快晴!
とても暑い1日となりましたが、遠方から多くの皆さんにご参加いただきました。
 10:30~ 学科説明
専任教員より「義肢とは?装具とは?」「義肢装具士の業務とは?」などの説明から始まり、義肢装具学科の特色や、国家試験対策、最新の入試情報などを詳しくご説明させていただきました。
10:30~ 学科説明
専任教員より「義肢とは?装具とは?」「義肢装具士の業務とは?」などの説明から始まり、義肢装具学科の特色や、国家試験対策、最新の入試情報などを詳しくご説明させていただきました。
 11:30~ 休 憩
オープンキャンパスでは、在校生が参加者の皆さんと直接お話しをさせていただきます。学校生活について、講義内容について、在校生から本当の声が聞けることも、本校のオープンキャンパスの大きな特色です!
11:30~ 休 憩
オープンキャンパスでは、在校生が参加者の皆さんと直接お話しをさせていただきます。学校生活について、講義内容について、在校生から本当の声が聞けることも、本校のオープンキャンパスの大きな特色です!
 11:45~ 学生企画「わたしの一週間」
今回は2年生の学生が、学校生活や義肢装具を学ぶ大変さや楽しさについて発表してくれました。学生視点からの分かり易い発表に、参加者の皆さんは聞き入っていました。人に自分の考えを正確に伝える、これも義肢装具士に求められるコミュニケーション能力のひとつですね!
学生さん、素晴らしい発表をありがとうございました!
11:45~ 学生企画「わたしの一週間」
今回は2年生の学生が、学校生活や義肢装具を学ぶ大変さや楽しさについて発表してくれました。学生視点からの分かり易い発表に、参加者の皆さんは聞き入っていました。人に自分の考えを正確に伝える、これも義肢装具士に求められるコミュニケーション能力のひとつですね!
学生さん、素晴らしい発表をありがとうございました!
 12:00~ 昼 食
参加者の皆さんと在校生が一緒に昼食をとりながら、引き続き学生の視点から見た学生生活についてお話ししています。
12:00~ 昼 食
参加者の皆さんと在校生が一緒に昼食をとりながら、引き続き学生の視点から見た学生生活についてお話ししています。
 なぜ義肢装具士を目指したのか、本校を選択したのか、自分の想いを熱く語る学生の姿に、保護者の皆さんも聞き入っていました。
なぜ義肢装具士を目指したのか、本校を選択したのか、自分の想いを熱く語る学生の姿に、保護者の皆さんも聞き入っていました。
 12:30~ 体験授業
午後からは体験授業です。
まず、日ごろ義肢装具学科で行っている講義内容と全く同じ講義を受講していただきます。テーマは「脳卒中片麻痺患者の装具療法」です。脳卒中片麻痺患者の病態から始まり、映像による歩行観察、短下肢装具の目的や製作工程について、分かり易くご説明します。患者さんの病気や症状について、詳しく理解することが義肢装具を製作する上でとても大切です。
12:30~ 体験授業
午後からは体験授業です。
まず、日ごろ義肢装具学科で行っている講義内容と全く同じ講義を受講していただきます。テーマは「脳卒中片麻痺患者の装具療法」です。脳卒中片麻痺患者の病態から始まり、映像による歩行観察、短下肢装具の目的や製作工程について、分かり易くご説明します。患者さんの病気や症状について、詳しく理解することが義肢装具を製作する上でとても大切です。
 実際の授業と同じように「理論」を学んだ後は「実践」です!
まずは、教員によるデモンストレーション。骨標本を見ながら、装具製作時に重要となる、人体の構造についてご説明します。
実際の授業と同じように「理論」を学んだ後は「実践」です!
まずは、教員によるデモンストレーション。骨標本を見ながら、装具製作時に重要となる、人体の構造についてご説明します。
 そして、いよいよギプス包帯による身体の採型です。
教員が手順を説明しながら手際よく採型する様子に、参加者の皆さんは見入っていました。
そして、いよいよギプス包帯による身体の採型です。
教員が手順を説明しながら手際よく採型する様子に、参加者の皆さんは見入っていました。
 ギプス包帯が巻き終わると、陰性モデルを取り外すための切開です。刃物を身体に向けて使用するという作業を見て、参加者の皆さんはとても驚いていました!
ギプス包帯が巻き終わると、陰性モデルを取り外すための切開です。刃物を身体に向けて使用するという作業を見て、参加者の皆さんはとても驚いていました!
 いざ、実践!
先ほどの説明のとおり、装具製作時に重要となるポイントにマークをします。
骨標本で見た、骨の形状を思い出しながら正確に・・・・・・
いざ、実践!
先ほどの説明のとおり、装具製作時に重要となるポイントにマークをします。
骨標本で見た、骨の形状を思い出しながら正確に・・・・・・
 では、いよいよギプス包帯を巻いてみましょう!
では、いよいよギプス包帯を巻いてみましょう!
 ギプス包帯の水分の絞り方から巻き方まで、先生がデモンストレーションで行った手順が再現できるよう、学生さんがサポートをします。
「すべての手順には意味がある!」、講義中に先生方から何度も言われていることですね!
ギプス包帯の水分の絞り方から巻き方まで、先生がデモンストレーションで行った手順が再現できるよう、学生さんがサポートをします。
「すべての手順には意味がある!」、講義中に先生方から何度も言われていることですね!
 いよいよギプス包帯の切開です。
初めて手にする「ギプス刀」。身近な刃物であるカッターナイフとは全く違う感触に参加者の皆さんは苦戦していました。
先生は簡単そうに切っていましたが、体験してみて初めて難しさが分かりましたね!
いよいよギプス包帯の切開です。
初めて手にする「ギプス刀」。身近な刃物であるカッターナイフとは全く違う感触に参加者の皆さんは苦戦していました。
先生は簡単そうに切っていましたが、体験してみて初めて難しさが分かりましたね!
初めて巻くギプス包帯の感触はいかがでしたか? ただ単にギプス包帯を巻いている訳ではないことが、よくご理解いただけたと思います。参加者の皆さんには、ひとつの作業の中にたくさんの知識と技術の集積が必要なことを実体験していただきました。
参加者(保護者)の声 今回初めて参加したのですが、全国の義肢装具士の数に対して装具を必要としている人の数がとても多い事など知らなかった事を知れてよかったです。また機会があれば参加したいと思います。 (社会人)
義肢装具士について知ることができました。イメージ通りだったことと、そうでなかったことが分かったので、また改めてしっかり考えたいと思います。 (大学4年)
交通の便が整っていて、学校までとても来やすかったです。義肢装具士とは何か、まだ表面しか理解できていませんが、またオープンキャンパスに参加し、より深く知りたいと思いました。 (高校3年)
大変そうですが、もし義肢装具士になれたら活躍の場が沢山あって、やりがいのありそうな仕事だと思いました。今度も機会があったら是非来てみたいです。 (高校3年)
今回のオープンキャンパスで話を聞いて義肢装具士について少し理解できました。またオープンキャンパスにきて理解を深めたいと思いました。 (高校3年)
学校が掲げるテーマが、根本から葉先までしっかりとしていて、とても良かったです。大変楽しかったです。 (高校3年)
義肢装具士について知ることができました。体験授業は難しかったですが、2回体験させて頂けてよかったです。 (高校1年)
今回2回目の参加なのですが、実際に足の型をとって、初めての体験授業だったので失敗もありましたが、とても丁寧に教えて頂き、楽しく体験できました。次回の実際に義肢装具士さんが働いている現場に行くことにも興味があるので参加したいです。 (社会人)
体験授業、採型など楽しく取り組ませていただきました。次回以降のオープンキャンパスにも是非参加したいです。 (社会人)
採型を初めてやらせて頂きましたが、やはり難しく、上手くできませんでしたが、学生さんが手助けをしてくれたので、上手くできました!学生さんも楽しくやっていて、いつも学校の中でもこういう感じなのかなと、とても親しみやすかったです。 (高校3年)
体験授業で、装具の有無による歩行を観察した際に、患者さんの歩行ががらりと変わったので驚きでした。 (高校3年)
短下肢装具の採型を体験することができ、義肢装具士の仕事がイメージしやすくなりました。学生の方にはお休みの日にお世話頂いて、ありがとうございました。 (保護者)
色々とお話を聞かせて頂き、知らなかった事、知りたい事がわかり、良かったです。入学後には相当な努力を要しそうですが、子供が目指すならば応援したいです。 (保護者)
生徒さん、先生方から気軽に話しかけて頂いて、退屈どころか楽しく過ごさせて頂きました。本人がヤル気を出してくれればと思います。 (保護者)
暑い中、長時間ご参加いただき、ありがとうございました! 次回、7月9日(土)も義肢装具士の魅力を伝えるコンテンツをたくさん用意して皆様の参加をお待ちしています!" target="_blank">NEW! OPEN CAMPUS「短下肢装具の採型をしてみよう!」 - 今年の1年生も松本先生のご講義から良い刺激をいただきました。 お忙しいところご講義いただき、ありがとうございました!" target="_blank">NEW! 1年生 松本芳樹先生の特別講義が行われました。
-
適合評価の前に、完成した靴型装具を磨いて仕上げます。ここでは一般的な靴のメンテナンス方法についても学習します。
 さあ、いよいよ適合評価です。アライメントが適切に設定されているか、靴底の高さは適切に設定されているか、美しく吊り込みが出来ているかなど、多くのチェック項目を先生が一足ずつ評価します。
さあ、いよいよ適合評価です。アライメントが適切に設定されているか、靴底の高さは適切に設定されているか、美しく吊り込みが出来ているかなど、多くのチェック項目を先生が一足ずつ評価します。
 では、装着して歩いてみましょう!
静止立位時から歩行時へと、段階的に評価項目は増えていきます。歩行状態を観察し、装着者が安定的に歩行できているかを確認します。
では、装着して歩いてみましょう!
静止立位時から歩行時へと、段階的に評価項目は増えていきます。歩行状態を観察し、装着者が安定的に歩行できているかを確認します。
 日ごろ何気なく履いている靴ですが、適切なアライメントや靴底の設定をしないと歩容に影響するだけでなく、“疲れ”の原因にもなります。装着者の歩行から問題点を、適切な対処方法をしっかり学びましょう!
日ごろ何気なく履いている靴ですが、適切なアライメントや靴底の設定をしないと歩容に影響するだけでなく、“疲れ”の原因にもなります。装着者の歩行から問題点を、適切な対処方法をしっかり学びましょう!
2年生は8月下旬からいよいよ臨床実習が始まります。 学生たちは今回製作した靴を履いて臨床実習に臨みますので、ぜひ彼らの足元に注目して下さい!" target="_blank">NEW! 2年生 靴型装具の適合評価が行われました。 -
前回製作したラスト(木型)に底材を取り付け、甲革を吊り込む準備をします。
 この吊り込み作業は、靴全体の出来ばえに大きく影響するため、作業手順をしっかり頭にイメージしてから始めます。
先生が製作した製品を見て、どのように吊り込んだら綺麗に仕上げられるか学生たちも真剣です!
この吊り込み作業は、靴全体の出来ばえに大きく影響するため、作業手順をしっかり頭にイメージしてから始めます。
先生が製作した製品を見て、どのように吊り込んだら綺麗に仕上げられるか学生たちも真剣です!
 いざ、実践です!
甲革には2枚の皮革が重ねられており、2枚の皮革を接着しながら吊り込んでいきます。接着剤が硬化する前に吊り込み作業を終えなければならないため、時間との勝負です!
いざ、実践です!
甲革には2枚の皮革が重ねられており、2枚の皮革を接着しながら吊り込んでいきます。接着剤が硬化する前に吊り込み作業を終えなければならないため、時間との勝負です!
 吊り込みが終わったら、靴底を加工していきます。接着剤を塗るというシンプルな作業にも、美しい靴づくりの基礎が詰まっています。
吊り込みが終わったら、靴底を加工していきます。接着剤を塗るというシンプルな作業にも、美しい靴づくりの基礎が詰まっています。
 靴底を貼り付け、「コバ」と呼ばれる箇所を削っていきます。
早く靴を履きたいという焦る気持ちを落ち着けて、甲革に傷をつけないように作業して下さいね!
靴底を貼り付け、「コバ」と呼ばれる箇所を削っていきます。
早く靴を履きたいという焦る気持ちを落ち着けて、甲革に傷をつけないように作業して下さいね!
 さあ、いよいよ靴の形になってきました!
最後に靴底のすべり止めを貼り合わせて、最後の仕上げとなります!
さあ、いよいよ靴の形になってきました!
最後に靴底のすべり止めを貼り合わせて、最後の仕上げとなります!
 ラスト(木型)から靴を外し、靴ひもを通しているところです。
紳士靴の靴ひもはスニーカーと違った通し方をします。今回このことを初めて知った学生も多かったようです。また、この製作実習では「靴の磨き方」についても教えていただけます。
ラスト(木型)から靴を外し、靴ひもを通しているところです。
紳士靴の靴ひもはスニーカーと違った通し方をします。今回このことを初めて知った学生も多かったようです。また、この製作実習では「靴の磨き方」についても教えていただけます。
次回は適合の様子をレポートします!" target="_blank">NEW! 2年生 靴型装具が完成しました。 -
美しいロームシアター大ホールにて
 " target="_blank">第17回言語聴覚学会に参加してきました
" target="_blank">第17回言語聴覚学会に参加してきました - http://www.tsuzuki-kitsuon.com/
都筑澄夫先生は、当学院の開設(1985年)より20年近く教鞭をとられ、たくさんの都筑チルドレンが輩出されました。 そんな都筑チルドレンの教員や非常勤講師の先生で過日「おかえりなさい、 都筑先生!の会」が開かれました。焼酎を飲みながら、久しぶりの都筑節を聞き、楽しく過ごしました。
都筑先生が近くにいらっしゃる安心感。これからも相談、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。 プレゼント進呈
プレゼント進呈
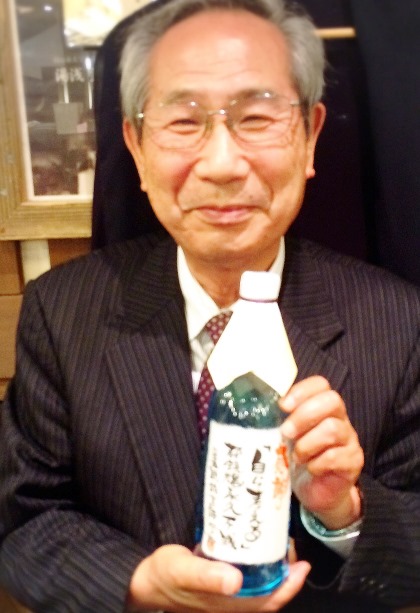 メッセージ付き焼酎 & 銅製カップ
メッセージ付き焼酎 & 銅製カップ
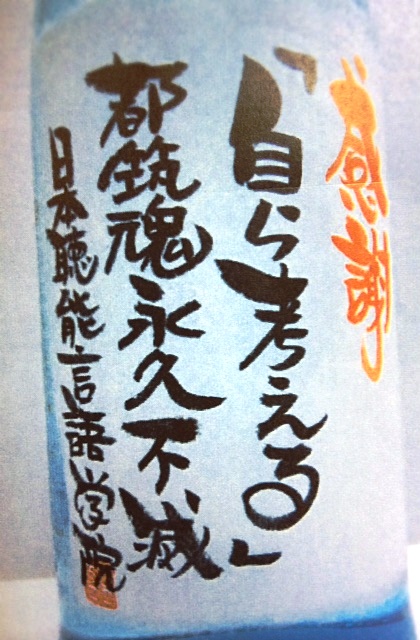 メッセージは 感謝!「自ら考える」都筑魂 永久不滅
メッセージは 感謝!「自ら考える」都筑魂 永久不滅
 全員で記念写真
全員で記念写真
後日、某居酒屋で若宮ST同窓会の会報「都筑先生に聞く!(仮題)」インタビューが行われました。またまた焼酎を飲みながらの総時間4時間にわたるロングインタビュー、現在絶賛(?)編成中です。 同窓会会員の皆様はお楽しみに!
" target="_blank">都筑澄夫先生、名古屋へおかえりなさい -
まず始めに、義足製作の基準となる角度を設定します。人間にはそれぞれ固有のアライメント(立位時の下肢関節角度)があります。先生のアドバイスを参考に、義足使用者が快適に立位をとることができるアライメント設定をして下さいね!
 切断端のなかで体重支持ができる箇所はモデルを削り、不可能な箇所は除圧を目的に石膏を盛り付けます。
切断端のなかで体重支持ができる箇所はモデルを削り、不可能な箇所は除圧を目的に石膏を盛り付けます。
 学生ひとり一人が義足を製作しますが、グループごとに同じモデル被験者を担当しているため、学生同士の情報交換がとても重要となります。ここから義足製作への興味がさらに深まっていきます。
学生ひとり一人が義足を製作しますが、グループごとに同じモデル被験者を担当しているため、学生同士の情報交換がとても重要となります。ここから義足製作への興味がさらに深まっていきます。
次回は、ソフトインサート製作の様子をお伝えします。" target="_blank">NEW! 2年生 下腿義足の陽性モデル修正が行われました。 -
会社に到着すると奥村社長様と西井部長様にお出迎えいただき、まずは会社の概要についてご説明いただきました。
 次に、社内を見学させていただきました。
社内各部署の説明や現在製作している製品について、細かくご説明いただきました。
次に、社内を見学させていただきました。
社内各部署の説明や現在製作している製品について、細かくご説明いただきました。
 学生たちは施設内で製作されている製品の数々に興味津々の様子です。これまで授業で学んだ装具が実際に製作されている現場を見て、学生たちは積極的に質問をしていました!
学生たちは施設内で製作されている製品の数々に興味津々の様子です。これまで授業で学んだ装具が実際に製作されている現場を見て、学生たちは積極的に質問をしていました!
 続いて、併設されているCAD/CAMセンターを見学しました。CAD/CAMシステムを用いた装具製作の手法について、実際にデモンストレーションをしていただきました。
続いて、併設されているCAD/CAMセンターを見学しました。CAD/CAMシステムを用いた装具製作の手法について、実際にデモンストレーションをしていただきました。
 パソコン上で陽性モデル修正を行う工程を見せていただきました。
この部署では日本聴能言語福祉学院の先輩がオペレーターとして活躍しており、学生たちのCAD/CAMへの興味はさらに高まったようです。
パソコン上で陽性モデル修正を行う工程を見せていただきました。
この部署では日本聴能言語福祉学院の先輩がオペレーターとして活躍しており、学生たちのCAD/CAMへの興味はさらに高まったようです。
 パソコン上での陽性モデル修正が終わると、このデータを基に発砲ウレタンを切削機で削り修正し、実際の陽性モデルが出来上がります。手作業であれば1時間以上かかる作業を短時間で終えることができます。
パソコン上での陽性モデル修正が終わると、このデータを基に発砲ウレタンを切削機で削り修正し、実際の陽性モデルが出来上がります。手作業であれば1時間以上かかる作業を短時間で終えることができます。
 最後にCAD/CAMセンターの前で記念撮影。
最後にCAD/CAMセンターの前で記念撮影。
お忙しい時間帯にもかかわらず、ご対応いただきました奥村社長様、西井部長様、社員の皆様にお礼申し上げます。 ありがとうございました。
義肢装具について学びはじめて2カ月が過ぎた1年生。 義肢装具について少し理解してから見る実際の製作現場はどうだったでしょうか? この機会に、学内での学習内容が臨床でどのように実践されているのかを考え、今後の学業の糧にしてほしいと思います!" target="_blank">NEW! 1年生 東名ブレース株式会社 見学レポート -
装具の土台となる“あぶみ”という部品に基準線を引くところから作業が始まります。この最初の基準線を正確に設定することが何より大切です!
 専用の工具を使って、あぶみの曲げ加工を行います。この部分の加工が数ミリのずれると、後の作業に大きく影響してきます。
専用の工具を使って、あぶみの曲げ加工を行います。この部分の加工が数ミリのずれると、後の作業に大きく影響してきます。
 次に、組み上げる支柱とのはめ合いを良くするために、精密ヤスリを使って継手部の微調整を行います。
次に、組み上げる支柱とのはめ合いを良くするために、精密ヤスリを使って継手部の微調整を行います。
 あぶみと支柱の連結が完成しましたね!さあ、ここからいよいよ側方支柱の曲げ加工です!
あぶみと支柱の連結が完成しましたね!さあ、ここからいよいよ側方支柱の曲げ加工です!
 今回は紙面上に描かれた下腿部の輪郭に合わせて支柱の曲げ加工を行います。金属材料の特性や曲げ加工のポイントなどを先生が分かり易く説明しながらデモンストレーションを行います。
今回は紙面上に描かれた下腿部の輪郭に合わせて支柱の曲げ加工を行います。金属材料の特性や曲げ加工のポイントなどを先生が分かり易く説明しながらデモンストレーションを行います。
 さあ、実際に金属支柱を曲げ加工してみましょう!
さあ、実際に金属支柱を曲げ加工してみましょう!
 正確に曲げ加工しているようでも、金属支柱を捻ってしまっているようですね。どの箇所で修正するべきかを見分ける視点が大切です!
正確に曲げ加工しているようでも、金属支柱を捻ってしまっているようですね。どの箇所で修正するべきかを見分ける視点が大切です!
 金属支柱の曲げ加工が終わったら、次は2本の支柱を連結する“半月”の曲げ加工を行います。この半月の取り付けが最終的な装具の出来ばえに影響するので、さらに慎重な作業が必要ですね!
金属支柱の曲げ加工が終わったら、次は2本の支柱を連結する“半月”の曲げ加工を行います。この半月の取り付けが最終的な装具の出来ばえに影響するので、さらに慎重な作業が必要ですね!
作業を通して金属材料の特性を把握することに四苦八苦している学生が多いようですが、新たな課題で自分の得意分野を見つけた学生もいたようです。 製作する中で少しずつコツを掴んで行って下さいね!" target="_blank">NEW! 1年生 金属支柱付短下肢装具の製作実習が始まりました。 -
まずは切断端(四肢の残存している部分)の採寸、採型を行います。
採寸や採型はその後のソケット適合の良し悪しを左右する重要な工程となります。
先生のデモンストレーションを見て、学生自身が考え、理解して実践することが大事ですね!
 義足製作には患者様とのコミュニケーションも重要です。切断端の客観的な情報だけでなく、患者様の職業や生活環境、趣味などあらゆる情報が義足製作に反映されます。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
義足製作には患者様とのコミュニケーションも重要です。切断端の客観的な情報だけでなく、患者様の職業や生活環境、趣味などあらゆる情報が義足製作に反映されます。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
 次はマーキングです。マーキングとはギプス包帯で採型をする前に、骨突起部の位置や圧痛点など、断端の情報を陰性モデルに転写することができるため、切断端に直接マークします。
次はマーキングです。マーキングとはギプス包帯で採型をする前に、骨突起部の位置や圧痛点など、断端の情報を陰性モデルに転写することができるため、切断端に直接マークします。
 次に、いよいよ採型です。切断端を採型する際の膝関節角度や手技が、その後の作業に大きく影響します。デモンストレーションのように、骨の位置や軟部組織の性質を把握しながら、正確に採型しましょう!
次に、いよいよ採型です。切断端を採型する際の膝関節角度や手技が、その後の作業に大きく影響します。デモンストレーションのように、骨の位置や軟部組織の性質を把握しながら、正確に採型しましょう!
次回は陽性モデル修正の様子をお伝えします!" target="_blank">NEW! 2年生 下腿義足の製作実習が始まっています。 -
去る6月7日(火)、3年生が2年生の後半から進めてきた卒業研究の進捗状況を報告する「中間報告会」が行われました。3年生にとっては11月に行われる本発表に向けて、研究テーマの方向性や今後の研究計画などを再確認するための重要な発表会です。
研究の背景、目的、研究手法など、ここでは参加者に分かりやすいプレゼンテーションが求められます。約半年間をかけて行ってきた研究の成果を、どのグループも自信を持って発表していました!
 報告会には教務の先生方と2年生が参加しました。2年生にはまだ分からない用語もあったと思いますが、先輩方の研究内容を理解しようと真剣に聞いている姿が印象的でした。
報告会には教務の先生方と2年生が参加しました。2年生にはまだ分からない用語もあったと思いますが、先輩方の研究内容を理解しようと真剣に聞いている姿が印象的でした。
3年生は後輩や先生方からの質問に対し、分かり易い回答をしていました。また、先生方からいただいた貴重なアドバイスを、今後の研究に活かして下さい! 3年生は6月13日より8週間の臨床実習が始まります。その間は学生同士でなかなか連絡もとれないと思いますが、時間を見つけて少しずつ研究を進めて行きましょう!
3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">NEW! 3年生 『卒業研究中間報告会』が行われました。 -
後半では面接(集団)の練習を行いました。 ・どうしてこの病院を希望しましたか? ・なぜ言語聴覚士になろうと思ったのですか? ・座右の銘はありますか? などの質問を答えてもらいました。自分では気づかない癖が出てしまったり、頭が真っ白になって固まってしまう学生も・・・ 意中の所に就職できるように、しっかり練習をしていきましょう!! " target="_blank">補聴3年生 就職ガイダンスがありました -
まずはグループに別れて、それぞれが目指す職種について分かり易く説明していきます。
日ごろ専門的な勉強をしているものの、“職種の役割”を分かり易く説明するということは意外に難しいと感じた学生が多かったようです。“医療現場における義肢装具士の役割とは何か”を日ごろから考えていることが大切ですね!
 次に、いよいよ珪山会グループの病院スタッフから動画を交えて実際の「症例提示」が行われます。お互いの職種の理解を深めた後に、今度は自職種の視点から症例に対する専門的なアプローチについてディスカッションしていきます。
次に、いよいよ珪山会グループの病院スタッフから動画を交えて実際の「症例提示」が行われます。お互いの職種の理解を深めた後に、今度は自職種の視点から症例に対する専門的なアプローチについてディスカッションしていきます。
 義肢装具学科の学生たちも頑張ってプレゼンしていますね!現在の病状に合った装具選択や予後予測など、義肢装具士の視点で他職種の学生さんに分かり易く説明していました。
義肢装具学科の学生たちも頑張ってプレゼンしていますね!現在の病状に合った装具選択や予後予測など、義肢装具士の視点で他職種の学生さんに分かり易く説明していました。
 このグループでは、求められる装具の機能について白熱したディスカッションが展開されていました!
このグループでは、求められる装具の機能について白熱したディスカッションが展開されていました!
3年生の皆さん、2日間お疲れ様でした。 専門職種間連携教育の教育プログラムが実践できるのは、複数学科を持つ珪山会グループ系列校の大きなメリットです。この講義で学んだことを卒後の臨床現場でも大いに活かして下さいね!
秋には各校2年生を対象にした専門職種間連携教育の講義も予定されています! " target="_blank">NEW! 3年生 専門職種間連携教育(IPE)が行われました。 -
まずは陽性モデル上で靴のデザインを設計します。
自分の履く靴ですから、デザインもこだわっていますね!
 次に、靴に挿入する足底板(中敷き)を製作します。
次に、靴に挿入する足底板(中敷き)を製作します。
 プラスチック材料を用いて陽性モデルと足底板を一体に熱成形加工し、チェックシューズの形に整えます。このチェックシューズを用いて仮合わせを行い、陽性モデルの最終的な形を決定します。
プラスチック材料を用いて陽性モデルと足底板を一体に熱成形加工し、チェックシューズの形に整えます。このチェックシューズを用いて仮合わせを行い、陽性モデルの最終的な形を決定します。
 次に木型(ラスト)を製作するため、先ほど調整した陽性モデルを再び熱成形加工します。
次に木型(ラスト)を製作するため、先ほど調整した陽性モデルを再び熱成形加工します。
 熱成形加工したプラスチックの内部に樹脂を流し込み、再びプラスチック製の木型(ラスト)を製作します。
熱成形加工したプラスチックの内部に樹脂を流し込み、再びプラスチック製の木型(ラスト)を製作します。
 木型が完成すれば、いよいよ甲革(アッパー)の吊り込み準備に入ります。靴ひもを通す穴の位置をデザインし、仮止めをしています。穴の位置や数も靴を美しく見せる重要なポイントになります。
木型が完成すれば、いよいよ甲革(アッパー)の吊り込み準備に入ります。靴ひもを通す穴の位置をデザインし、仮止めをしています。穴の位置や数も靴を美しく見せる重要なポイントになります。
少しずつ靴の形に近づいてくると、学生たちも楽しそうです! 次は、甲側(アッパー)の吊り込み作業をレポートします!" target="_blank">NEW! 2年生 靴型装具(実習)チェックシューズを製作しました。 -
仮合わせから得られた情報を基に、装具装着に必要なベルトを製作し取り付けていきます。工業用ミシンを使ってきれいに縫製することの難しさを実感した学生も多かったようです。
 この学生はベルトの取り付け位置の確認をしていますね。
取り付け角度やベルトの長さを正確に合わせるなど、患者様への繊細な心配りが必要です。
この学生はベルトの取り付け位置の確認をしていますね。
取り付け角度やベルトの長さを正確に合わせるなど、患者様への繊細な心配りが必要です。
 最後に、ベルトを装具本体に取り付けて完成です!
最後に、ベルトを装具本体に取り付けて完成です!
 いよいよ納品時の最終的な適合作業です!
装具装着の方法、ベルトを締める順番など、患者様やご家族に分かり易く説明するために必要な項目を学習します。
いよいよ納品時の最終的な適合作業です!
装具装着の方法、ベルトを締める順番など、患者様やご家族に分かり易く説明するために必要な項目を学習します。
 次に、最終的な歩行を観察します。仮合わせの段階との違いを判断し、より適合の良い装具になっているか確認します。
次に、最終的な歩行を観察します。仮合わせの段階との違いを判断し、より適合の良い装具になっているか確認します。
 最後に、装具を外した際の体表のチェックを行います。
プラスチック短下肢装具を装着される患者様のなかには感覚障害のために装具が圧迫していても痛みを感じない場合があります。
装具を外した後は必ず、圧迫されて皮膚が変色している箇所はないか確認することが大切です。
さあ、1年生が製作した装具はどうだったでしょう?
最後に、装具を外した際の体表のチェックを行います。
プラスチック短下肢装具を装着される患者様のなかには感覚障害のために装具が圧迫していても痛みを感じない場合があります。
装具を外した後は必ず、圧迫されて皮膚が変色している箇所はないか確認することが大切です。
さあ、1年生が製作した装具はどうだったでしょう?
 初めて製作した装具が完成した時の様子です!
このグループはお互いの装具を見せ合いながら、具体的な反省点などをディスカッションしていました。
初めて製作した装具が完成した時の様子です!
このグループはお互いの装具を見せ合いながら、具体的な反省点などをディスカッションしていました。
 「記念に撮影させて下さい!」のお願いに応えてくれました。
とても嬉しそうですね!
「記念に撮影させて下さい!」のお願いに応えてくれました。
とても嬉しそうですね!
「自分で製作した装具を実際に装着してもらえることに、とても感動しました!」
と、笑顔で話してくれた1年生たち。 初めての製作実習でみんな悪戦苦闘していましたが、装具が完成した時の喜びもひとしおだったようです。 この喜びを忘れずに、次の製作課題も頑張りましょう!" target="_blank">NEW! 1年生 プラスチック短下肢装具が完成しました。 -
☆☆お名前を教えてください。 ・松川 智美です。
☆☆出身の学科は? ・補聴言語学科です。
☆☆STになろうと思ったきっかけは何ですか? ・旅行会社に勤務していた時にお客様と接するなかでことばの大切さを再認識したのですが、私にとって大切だと考えていたことばにご不自由さを抱えている方々がいらっしゃり、その方々の支えになれる職業(言語聴覚士)があることを知ったことがきっかけです。
☆☆どのような病院で働いていらっしゃったのですか? ・超急性期~在宅期まで、乳児~成人までを対象とする総合病院に12年間勤務していました。
☆☆働く上でのモットー(とか、気を付けている事)などは何かありますか? ・患者様の病気や障害だけをみるのではなく、「人」をみてその方らしい生活が送れるよう一緒に考え、寄り添うことのできる言語聴覚士でありたいと思っています。あと、普段からなるべく笑顔でいるように心がけています。
☆☆「職業病だなぁ」と感じるときはどんな時ですか? ・スーパーなどに行くとついつい介護食や離乳食のコーナーに立ち寄り、新製品をチェックしてしまうことでしょうか。
☆☆とっても穏やかなのですが、穏やかでいられる秘訣は? ・自分では穏やかとは思っていないのですが、のんびりしているのでそのように見えるのかもしれません(笑)。
☆☆最後に、意気込みを! ・慣れないことが多く、ご迷惑をおかけすることがあると思いますが、学生さん達と一緒に成長できるよう、頑張りたいと思います! " target="_blank">聴能言語学科に新しい先生です!!!! -
まずは、医学的根拠に基づいた装具のデザインを学びます。
脳卒中片麻痺患者が装着することを想定し製作しているこの装具は、装具のカットラインによってその機能が大きく変わります。患者様の病態を理解すると共に、装具に求められる機能や材質の特性などを学び、装具のデザインを決定します。
 仮合わせの前に設計したカットラインに合わせてトリミング加工をしている様子です。徐々に装具の形になってきましたね!
仮合わせの前に設計したカットラインに合わせてトリミング加工をしている様子です。徐々に装具の形になってきましたね!
 次は、いよいよ仮合わせです。装具を完成させる前に、患者様に一度装具をフィッティングする工程です。まずは先生が仮合わせの一連の流れをデモンストレーションし、義肢装具士がチェックすべき項目を一つずつ説明しています。
次は、いよいよ仮合わせです。装具を完成させる前に、患者様に一度装具をフィッティングする工程です。まずは先生が仮合わせの一連の流れをデモンストレーションし、義肢装具士がチェックすべき項目を一つずつ説明しています。
 次に、装具装着時の歩行を観察します。
歩行時に装具が身体に及ぼす影響を観察し、最終的な装具のカットラインを決定します。
次に、装具装着時の歩行を観察します。
歩行時に装具が身体に及ぼす影響を観察し、最終的な装具のカットラインを決定します。
 さあ、実際に装具を装着してみましょう!
仮合わせのチェック項目を確認し、フィッティングの悪い箇所はどこか、その原因はどこにあるのか、しっかり考察して下さいね!
さあ、実際に装具を装着してみましょう!
仮合わせのチェック項目を確認し、フィッティングの悪い箇所はどこか、その原因はどこにあるのか、しっかり考察して下さいね!
 仮合わせを行うことで、これまで学習してきた作業の一つ一つが装具全体のフィッティングに影響することに気付いたのではないでしょうか?
仮合わせを行うことで、これまで学習してきた作業の一つ一つが装具全体のフィッティングに影響することに気付いたのではないでしょうか?
次はいよいよ完成です。 仮合わせで不具合のあった箇所を修正し、最後はしっかりとフィッテングした装具に仕上げましょう!" target="_blank">NEW! 1年生 プラスチック短下肢装具の仮合わせを行いました。 -
実際に石膏を削る前に、まずは四辺形ソケットの体重支持理論を再確認します。
 陽性モデルのどの部分を削ると義足完成後にどのような影響が出るのか、実際の臨床例を基に具体的な方法論が示されます。一つひとつの工程にすべて目的があることを理解し、学生たちの興味は益々高まったようです。
陽性モデルのどの部分を削ると義足完成後にどのような影響が出るのか、実際の臨床例を基に具体的な方法論が示されます。一つひとつの工程にすべて目的があることを理解し、学生たちの興味は益々高まったようです。
 製作理論に基づき、いざ実践!
製作理論に基づき、いざ実践!
 徐々に四辺形ソケットの形状に近づいてきましたね!
陽性モデル修正は、筋の走路や骨の形状など、解剖学的に人体の構造を理解をしていないと形状を具現化することはできません。
学生たちは香川先生の陽性モデルを何度も触って、微妙な形状の違いを把握しようと一生懸命でした。
徐々に四辺形ソケットの形状に近づいてきましたね!
陽性モデル修正は、筋の走路や骨の形状など、解剖学的に人体の構造を理解をしていないと形状を具現化することはできません。
学生たちは香川先生の陽性モデルを何度も触って、微妙な形状の違いを把握しようと一生懸命でした。
次回はソケット熱成形作業とベンチアライメント設定までの様子をレポートします!" target="_blank">NEW! 3年生 陽性モデル修正に思いを込めて! -
始めに、陽性モデルに適切なアライメントラインを設定します。
ラインの見方や線の引き方など、製作上の基礎を学んでいきます。
 実際にアライメントラインを引いてみましょう!
装具の治療効果に関わる重要な作業なので、正確に設定することが大切です。
実際にアライメントラインを引いてみましょう!
装具の治療効果に関わる重要な作業なので、正確に設定することが大切です。
 設定したアライメントラインを基準に、陽性モデルを修正していきます。学生たちは先生のデモンストレーションを食い入るように見ていますね。
設定したアライメントラインを基準に、陽性モデルを修正していきます。学生たちは先生のデモンストレーションを食い入るように見ていますね。
 この学生は足底の削り修正をしていますね。足底の削り方ひとつで装具の安定性に影響するため、慎重な作業が必要です。
この学生は足底の削り修正をしていますね。足底の削り方ひとつで装具の安定性に影響するため、慎重な作業が必要です。
 この学生は盛り修正をしています。初めて使用する材料や工具に少し戸惑い気味ですが、徐々に慣れて行って下さいね!
この学生は盛り修正をしています。初めて使用する材料や工具に少し戸惑い気味ですが、徐々に慣れて行って下さいね!
 最後に、アライメント設定やモデル修正が適切に行われているか先生にチェックしてもらいます。
こうしたやり取りの中から、義肢装具を製作していくための視点が養われていきます。
最後に、アライメント設定やモデル修正が適切に行われているか先生にチェックしてもらいます。
こうしたやり取りの中から、義肢装具を製作していくための視点が養われていきます。
次は、プラスチックの熱成形、仮合わせの様子をレポートします!" target="_blank">NEW! 1年生 プラスチック短下肢装具の陽性モデル修正が行われました。 -
首相官邸内で安倍内閣総理大臣との記念撮影。
 安倍総理より「内閣総理大臣表彰」を受ける香川先生。
安倍総理より「内閣総理大臣表彰」を受ける香川先生。
 安倍総理大臣への金メダル受賞報告の様子。
安倍総理大臣への金メダル受賞報告の様子。
政府インターネットテレビ 「国際アビリンピック金メダリストへの内閣総理大臣表彰」
 国際アビリンピック(フランス)競技中の香川先生。
国際アビリンピック(フランス)競技中の香川先生。
日本代表選手として様々なプレッシャーがあったと思いますが、素晴らしい結果を残され、学生たちにとても良い刺激をいただきました。 香川先生、本当におめでとうございました!" target="_blank">NEW! 香川先生が「内閣総理大臣表彰」を授与されました。 -
やる気満々!(お料理の腕前は…?)
 男子もお手伝いです。
男子もお手伝いです。
 焼き上がりが楽しみ~(^^)
入学して3週間近く経ち、
学院生活にまだまだ慣れない学生も多い時期です。
また、社会人経験を経た新入生にとっては、
1日ずっと座っていることに慣れない学生もいたりします。
毎日の講義に圧倒?されているかもしれません。
この会は2年生との交流の場でもあります。
1年生からは、不安に思っている勉強のしかたや講義についての質問がでたり、出身地の話で盛り上がったり。
和やかな会となりました。
焼き上がりが楽しみ~(^^)
入学して3週間近く経ち、
学院生活にまだまだ慣れない学生も多い時期です。
また、社会人経験を経た新入生にとっては、
1日ずっと座っていることに慣れない学生もいたりします。
毎日の講義に圧倒?されているかもしれません。
この会は2年生との交流の場でもあります。
1年生からは、不安に思っている勉強のしかたや講義についての質問がでたり、出身地の話で盛り上がったり。
和やかな会となりました。

 数ヵ月後に実習を控え講義や演習で忙しくしている2年生にとっても
よい息抜きの時間になったのではないでしょうか?
数ヵ月後に実習を控え講義や演習で忙しくしている2年生にとっても
よい息抜きの時間になったのではないでしょうか?
 最後は全員で!
今回の新入生の多くは、入学前に学院のオープンキャンパスにきてくれています。
やはり、実際に来てみることで、先輩たちの姿だったり、学院の雰囲気、
学院の教育体制についてなどをより具体的に知ることができます。
言語聴覚士に興味のある方は、ぜひオープンキャンパスにお越しください!
今年度最初のオープンキャンパスは、
5/28(土)午後に開催いたします。
最後は全員で!
今回の新入生の多くは、入学前に学院のオープンキャンパスにきてくれています。
やはり、実際に来てみることで、先輩たちの姿だったり、学院の雰囲気、
学院の教育体制についてなどをより具体的に知ることができます。
言語聴覚士に興味のある方は、ぜひオープンキャンパスにお越しください!
今年度最初のオープンキャンパスは、
5/28(土)午後に開催いたします。

なお、当日ご都合がつかない場合は、お気軽に学校見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。
なお、学校見学は曜日によっては20:00までは可能です(19:00までにはお越しください)。 " target="_blank">新1年生の歓迎会を行いました!
" target="_blank">新1年生の歓迎会を行いました! -
装具を製作する前に脳卒中片麻痺の病態と短下肢装具の適応について講義を受けます。1年生には少し難しい講義ですが、「なぜ装具が必要なのか?」を理解した上で装具を製作することが重要ですね!

次は、いよいよ採型です。 最初に先生のデモンストレーションを学生全員で見学します。 ギプス包帯の性質や採型の手順、作業全体の時間配分など細かく説明を受けています。
 先生のデモンストレーションを見ながら真剣にメモをとっていますね!大切なのは作業のポイントを見逃さない観察力ですよ!
先生のデモンストレーションを見ながら真剣にメモをとっていますね!大切なのは作業のポイントを見逃さない観察力ですよ!
 今回の採型は下腿部の形状がきれいに採型されているだけでなく、立位のアライメントが正確に再現されていることも重要ですね!
今回の採型は下腿部の形状がきれいに採型されているだけでなく、立位のアライメントが正確に再現されていることも重要ですね!
 では、いよいよ学生同士で採型してみましょう!
では、いよいよ学生同士で採型してみましょう!
 いざ採型してみると、先生のデモンストレーションの中に採型のポイントが沢山あったことに気づいたのではないでしょうか?
いざ採型してみると、先生のデモンストレーションの中に採型のポイントが沢山あったことに気づいたのではないでしょうか?
 義肢装具士は患者様の病態を理解し、採型をするところからモノづくりが始まります。
1年生のみなさん、一歩ずつ義肢装具士への道を歩んで行ってくださいね!
義肢装具士は患者様の病態を理解し、採型をするところからモノづくりが始まります。
1年生のみなさん、一歩ずつ義肢装具士への道を歩んで行ってくださいね!
◇◇◇ お知らせ ◇◇◇ 第3回オープンキャンパス 6月18日(土)では、『脳卒中片麻痺の装具療法』をテーマに体験授業を行います。今回のレポートでご紹介したように、「脳卒中片麻痺の装具療法」についての講義に続き、「短下肢装具の採型実習」を体験して頂けます!
義肢装具学科の先生はもちろん、在校生と話す機会もたくさんありますので、入試情報や学校生活など、どんどん質問して医療専門職としての義肢装具士の魅力を体感してください!!
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">NEW! 1年生 義肢装具基本工作論が始まりました。
" target="_blank">NEW! 1年生 義肢装具基本工作論が始まりました。

 ※中日新聞 2016年(平成28年)5月2日(月曜日)より
※中日新聞 2016年(平成28年)5月2日(月曜日)より
日本聴能言語福祉学院では山本君のリオデジャネイロ・パラリンピックでの活躍を期待しています!引き続き、全校を挙げて応援して行きます! ガンバレ山本先輩!" target="_blank">NEW! 山本篤君が日本パラで世界新記録の快挙!-
今回購入した書籍は62冊、ほとんどが新刊です。 一部をご紹介します。卒業生の著書もあります。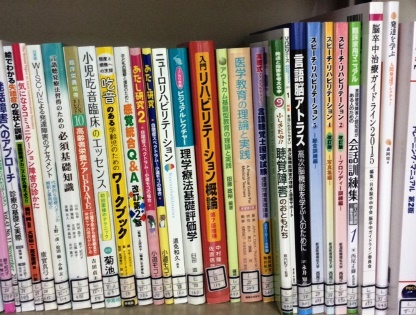
図解やさしくわかる言語聴覚障害、発話障害へのアプローチ、 言語脳アトラス、失語臨床の認知神経心理学的アプローチ 吃音のある学齢時のためのワークブック、感覚統合Q&A 標準小児科学第8版(医学書院)、脳卒中ガイドライン2015、
医学書は高価なので、図書室でじっくり閲覧できたり、 家でも読めるのは嬉しいですよね。
図書室の蔵書は全て言語聴覚士に関係のある書籍ですが、 毎年このペースで増え続けており、4,000冊を超えています。 学院の歴史を感じますね。
学院に来たことのない方は、百聞は一見にしかず、 ぜひ5月28日のオープンキャンパスで確かめてください。
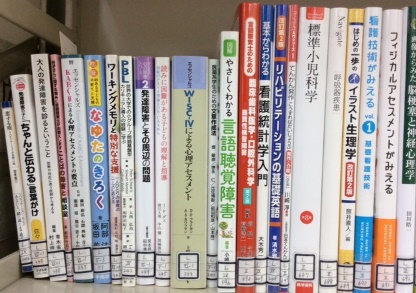 " target="_blank">新刊入りました!
" target="_blank">新刊入りました! -
まずは足部の状態をよく観察します。胼胝(タコ)や靴擦れのある部分はないか、足の皮膚感覚、足関節の可動域など、細かくチェックします。
 次に、フットプリントを用いて足底圧を評価します。
足底のどの部分に荷重がかかっているか、足の輪郭や骨の位置関係を把握することができます。
次に、フットプリントを用いて足底圧を評価します。
足底のどの部分に荷重がかかっているか、足の輪郭や骨の位置関係を把握することができます。
 次に、足の周径を測ります。靴の基となる木型(ラスト)を製作する上で重要な情報ですので、しっかりポイントをおさえて計測します。
次に、足の周径を測ります。靴の基となる木型(ラスト)を製作する上で重要な情報ですので、しっかりポイントをおさえて計測します。
 そして、いよいよ採型です。靴のヒールの高さや、つま先の角度などを設定して採型を行います。
そして、いよいよ採型です。靴のヒールの高さや、つま先の角度などを設定して採型を行います。
 採型した石膏モデルを基に、木型(ラスト)を製作します。ここでは足部の機能解剖と靴の適合理論について講義が行われます。
採型した石膏モデルを基に、木型(ラスト)を製作します。ここでは足部の機能解剖と靴の適合理論について講義が行われます。
 学生が陽性モデルの修正ポイントについて先生に質問していますね。
1年生の製作実習と比べて工程も多く、複雑なので分からないところはその場で解決することが大切です!
学生が陽性モデルの修正ポイントについて先生に質問していますね。
1年生の製作実習と比べて工程も多く、複雑なので分からないところはその場で解決することが大切です!
 フットプリントを基に製作する靴のデザインを決め、採寸した数値を基準に陽性モデルを修正します。
フットプリントを基に製作する靴のデザインを決め、採寸した数値を基準に陽性モデルを修正します。
靴型装具は、適合の良し悪しを自分で体感できる唯一の装具といえます。自分自身の足の形状や特徴をよく把握して、適合の良い靴型装具を製作してくださいね!" target="_blank">NEW! 2年生 下肢装具Ⅰ「靴型装具」の製作実習が始まりました。 -
競技場で黙々と製作課題に取り組む香川先生。
義肢装具製作に一切の妥協を許さない香川先生の技術を見て、世界中の審査員がとにかく感心していたようです。
 制限時間内に製作課題が完成し、香川先生も少し緊張が解けていますね!
制限時間内に製作課題が完成し、香川先生も少し緊張が解けていますね!
 競技終了後、表彰式があり見事に「金賞」を受賞した様子です。
世界中の記者から長時間のインタビューを受けても、競技の疲れを見せずにいつもの優しい笑顔で対応されていますね。
競技終了後、表彰式があり見事に「金賞」を受賞した様子です。
世界中の記者から長時間のインタビューを受けても、競技の疲れを見せずにいつもの優しい笑顔で対応されていますね。
 フランスから帰国後、香川先生が結果報告のために来校して下さいました!
教え子の活躍に中川先生もたいへん喜んでおられました。
フランスから帰国後、香川先生が結果報告のために来校して下さいました!
教え子の活躍に中川先生もたいへん喜んでおられました。
日本代表選手として様々なプレッシャーがあったと思いますが、素晴らしい結果を残され、学生たちにとても良い刺激をいただきました。 香川先生、本当におめでとうございました! " target="_blank">NEW! 香川先生が世界一の栄冠に輝きました! -
そして、どう訓練したらよいのか困っているSTも多いのでしょうか。2年前に同窓会で行われた「Re-Learning小児の吃音臨床について」は卒業生で会場があふれました。
当学院の吃音の講義は25コマで、ST養成校の中では多い方です。 「間接法による吃音訓練」の著者である都筑澄夫先生(開設時より20年近く当学院の教員でした)の集中講義もあります。 また上級生は学内臨床に参加できますし、年に一度「吃音友の会」と交流会もあるんです。
吃音に限らず、このドラマで言語聴覚士に興味が湧いた方はぜひオープンキャンパスにいらして下さいね。 " target="_blank">月9 「ラブソング」に言語聴覚士が!! -
初めての職場、学校から離れているし、不安もあったことでしょう。 そんな時に同窓の先輩がいた嬉しさが伝わってきて、こちらも嬉しくなりました。
そうなんです。日本聴能言語福祉学院は1985 年創立の伝統ある学校。 現在の卒業生は1200人。 言語聴覚士の養成校がまだまだ少ない時代でしたので、全国から学生が集まり、また各地に散らばっていきました。そんな具合で全国に卒業生がいます。 そんなことを彼女のメールで改めて気が付かされたのでした。 メールありがとう。学校にも遊びに来て下さいね。
追記: 実は、その聴能の先輩〇〇先生からも学院に連絡がありました。 「歓迎会で新卒の△△さんと話したよ、すごくいい子が来てくれてよかった」と。 お二人連れ立って、同窓会に参加してくれる日もあるのでしょうか。楽しみにしています。
" target="_blank">卒業生からのメール -
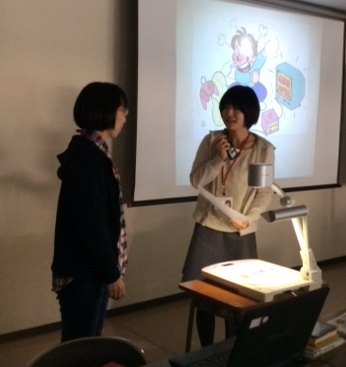 実物投影機を使用して実演しています。
実物投影機を使用して実演しています。
 見ている人も真剣。
" target="_blank">講義の様子です
見ている人も真剣。
" target="_blank">講義の様子です -
元気いっぱいの3年生
 下にローラーがついていて、押し出すように投げるそうです。
下にローラーがついていて、押し出すように投げるそうです。
 見た感じがカーリングそっくりです。しかしブラシで磨いたりはしません。
見た感じがカーリングそっくりです。しかしブラシで磨いたりはしません。
 チーム対抗でワイワイ言いながら、楽しくやっていました。体を動かしてしっかりストレスを発散して、今後の実習・国家試験に打ち勝ってくださいね。
" target="_blank">補聴3年生 スポーツの春??
チーム対抗でワイワイ言いながら、楽しくやっていました。体を動かしてしっかりストレスを発散して、今後の実習・国家試験に打ち勝ってくださいね。
" target="_blank">補聴3年生 スポーツの春?? - 追記 衝撃のシーンも多いので学生にはおすすめしませんが、同じく主人公が前向性健忘を持っている映画で「メメント」があります。時系列をさかのぼって話が進んでいきます。記憶の変容の怖さを感じる映画で、個人的には面白かったです。 " target="_blank">記憶障害の映画
-
学院の正面玄関では新入生を迎えるための「挨拶週間」が始まりました。これは学生たちが率先して行っている、義肢装具学科の伝統の1つです。
周囲の人たちにいつも気持ちの良い挨拶ができるということは、医療人としてとても大切なことだと義肢装具学科では考えています。 この伝統が、これからも受け継がれていくことを期待しています!" target="_blank">NEW! 挨拶から始まる義肢装具学科の伝統! -
去る4月2日(土)に、専門学校日本聴能言語福祉学院と中部リハビリテーション専門学校の合同入学式が行われました。
式典では中川教務主任より、一人ずつ名前が読み上げられ、新入生は緊張しながらも元気よく返事をしていました。
 義肢装具学科は今年で「創立30年目」を迎え、新入生はその記念すべき第30期生となります。
来週からは講義も始まり、義肢装具士になるための3年間がいよいよスタートします。
30期生の皆さん、「初心を忘れることなく」日々を大切に過ごして下さい!
義肢装具学科は今年で「創立30年目」を迎え、新入生はその記念すべき第30期生となります。
来週からは講義も始まり、義肢装具士になるための3年間がいよいよスタートします。
30期生の皆さん、「初心を忘れることなく」日々を大切に過ごして下さい!
" target="_blank">NEW! 第30期生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 - 当学院では、今後ともリハビリテーション教育の質の向上と充実に努めていきます。 " target="_blank">聴能・補聴両学科とも教育評価認定を受けました
-
開式のことばに始まり、教員が新入生一人一人の名前を読み上げると、学生たちは元気よく返事をしていました。
来賓の先生方の心のこもった祝辞を頂き、次に新入生代表による「誓いの言葉」となります。今年の代表は補聴言語学科の学生です。やや緊張しつつも、一言一言にメリハリが効いていて、積極的に学び、言語聴覚士の卵として3年間を全うしていこうという思いが伝わってきました。
教員もサポートしていきます。しっかり学んでいきましょう。 " target="_blank">入学式 -
まずは「MASソケット」開発の経緯、体重支持原理について講演を行いました。
 次に、採型時のポイントを動画で確認した後、実際に陽性モデル修正のデモンストレーションを行いました。参加者の皆さんは、臨床で活躍されている義肢装具士の方々ばかりですので、実際の製作の場面を想定した質問をたくさん頂戴しました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
次に、採型時のポイントを動画で確認した後、実際に陽性モデル修正のデモンストレーションを行いました。参加者の皆さんは、臨床で活躍されている義肢装具士の方々ばかりですので、実際の製作の場面を想定した質問をたくさん頂戴しました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
名和先生、ご講演お疲れ様でした。 学生の皆さんは現在春休み期間中ですが、教務の先生方は新学期の準備をしつつ、義肢装具士としての研修活動にも積極的に参加させていただいています! 最後に、長野県総合リハビリテーションセンターの義肢装具士の皆様、ご講演の準備をしていただき、誠にありがとうございました!" target="_blank">NEW! 「MASソケット」の研修会が行われました。 -
後輩たちの激励に応え―――
 国家試験全員合格!!合格率100%を達成!!
さらに、昨年度に引き続き就職内定率も100%を達成しました!!
第28期生の皆さん、そしてこれまで支えてこられたご家族の皆様おめでとうございます。
また、在学中にご指導いただきました講師の先生方に心より厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。" target="_blank">NEW! 速報!PO国家試験合格発表
国家試験全員合格!!合格率100%を達成!!
さらに、昨年度に引き続き就職内定率も100%を達成しました!!
第28期生の皆さん、そしてこれまで支えてこられたご家族の皆様おめでとうございます。
また、在学中にご指導いただきました講師の先生方に心より厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。" target="_blank">NEW! 速報!PO国家試験合格発表 - 速報!ST国家試験合格発表!
-
第27期生の門出をお祝いするように、校舎前の梅の花もきれいに咲きました。
 棚橋学院長先生より義肢装具学科総代が卒業証書を受け取りました。
棚橋学院長先生より義肢装具学科総代が卒業証書を受け取りました。
 理事長賞を受賞した神谷大地君、鵜飼敦子理事長先生より表彰していただきました。
理事長賞を受賞した神谷大地君、鵜飼敦子理事長先生より表彰していただきました。
 卒業式も終わり、緊張感がとけていい笑顔になっていますね!
卒業式も終わり、緊張感がとけていい笑顔になっていますね!
 教室に戻り、改めて学科内で『卒業証書授与式』が行われました。
在校生、保護者、来賓の皆さんと一緒に和やかな式となりました!
教室に戻り、改めて学科内で『卒業証書授与式』が行われました。
在校生、保護者、来賓の皆さんと一緒に和やかな式となりました!
 義肢装具学科顧問の髙見健二先生より、一人ひとりに卒業証書が授与されました。
義肢装具学科顧問の髙見健二先生より、一人ひとりに卒業証書が授与されました。
 卒業生から在校生全員に記念品が贈呈されました。
卒業生から在校生全員に記念品が贈呈されました。
 卒業生より、義肢装具学科への記念品として、校舎の写真が入った『校歌ボード』を寄贈していただきました。
卒業生より、義肢装具学科への記念品として、校舎の写真が入った『校歌ボード』を寄贈していただきました。
 最後に、校舎前で恒例の記念撮影を行いました。
3年間ご指導いただきました教務の先生方、ありがとうございました!
最後に、校舎前で恒例の記念撮影を行いました。
3年間ご指導いただきました教務の先生方、ありがとうございました!
第27期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます! 全国各地で皆さんが活躍されることを、教職員一同、期待しています!
~卒業記念パーティー編~ 卒業式後、名古屋市内のホテルにて『義肢装具学科第27期生 卒業記念パーティー』が盛大に行われました。
 卒業式から衣装を着替えて来賓をお迎えする卒業生たち。
卒業式から衣装を着替えて来賓をお迎えする卒業生たち。
 全国各地から卒業生のために非常勤講師の先生方や、臨床実習でお世話になった企業の皆様、OBの皆さんが大勢出席してくださいました。
全国各地から卒業生のために非常勤講師の先生方や、臨床実習でお世話になった企業の皆様、OBの皆さんが大勢出席してくださいました。
 パーティーの司会を務める卒業生、少し緊張気味ですね!
パーティーの司会を務める卒業生、少し緊張気味ですね!
 パーティーの最初に、鵜飼泰光理事長先生より卒業生へ温かいお祝いのお言葉をいただきました。
パーティーの最初に、鵜飼泰光理事長先生より卒業生へ温かいお祝いのお言葉をいただきました。
 最後に、義肢装具学科の教員へ記念品と花束の贈呈があり、先生方から卒業生に向けて、はなむけの言葉が贈られました。
最後に、義肢装具学科の教員へ記念品と花束の贈呈があり、先生方から卒業生に向けて、はなむけの言葉が贈られました。
第27期生のみなさん、3年間お疲れ様でした!!" target="_blank">NEW! 第27期生の皆さんご卒業おめでとうございます! -
義肢装具学科(義肢装具士養成課程)の2016年度のオープンキャンパス開催スケジュールを公開しました!
本年度は全14回開催!! 本学科のオープンキャンパスでは、参加するたびに毎回異なる製作実習を体験できます! ホントの授業を聞いて、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを体感してみよう!
装具の採型、義足の歩行観察、筋電義手、ホンモノの義足の組み立て、自分の足の分析などなど、初めて参加する方も、2回目3回目の方も、義肢装具士を楽しんで学べる魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています!!
実学が未来の君を強くする!
みなさんの参加をお待ちしています!
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
 " target="_blank">【義肢装具学科】OPEN CAMPUS 2016
" target="_blank">【義肢装具学科】OPEN CAMPUS 2016 -
社会人のための新しい支援制度!
国家資格(義肢装具士免許)を取得してキャリアアップ!
平成28年度4月に義肢装具学科に入学される方で、条件に該当する方は 『専門実践教育訓練給付金制度』 『教育訓練支援給付金制度』 が受けられることになりました!!
厚生労働省による中長期的なキャリアアップを目的とした雇用保険の給付制度です。 厚生労働省が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座は、一定の要件を満たした場合に、最大で144万円の給付金と離職時の基本手当の日額に相当する額の50%が受講期間中にハローワークから支給されます。
詳細は専門実践教育訓練給付金制度・教育訓練支援給付金制度についてもしくはハローワークのこちらのページでご確認ください。
受講開始の1か月前までに提出しなければならない書類もありますので本学科の受験および給付金の受給を検討されている方はハローワークまでご相談ください。 あなたの夢の実現、キャリアアップを応援します!!
" target="_blank">最大144万円+α給付!『専門実践教育訓練給付制度』のご案内 -
義肢装具士のモノづくりは、患者さんの体を採型するところから始まります、その採型したモデルをもとに個々に合った義肢や装具を製作します。
体験授業では実際に「短下肢装具の採型」を行っていただきます!
義肢装具士を体感するチャンス!!
入試情報や学生生活などどんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!
当日のスケジュール ◇12:00 受 付 ◇12:30 学科説明 ◇13:15 休 憩 ◇13:30 体験授業(短下肢装具の採型をしてみよう!) ◇15:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇16:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・この春、高校3年生になる方で義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
過去のオープンキャンパスの様子はこちら 第5回オープンキャンパス 第6回オープンキャンパス 第7回オープンキャンパス
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
 " target="_blank">3月13日(日)短下肢装具を採型してみよう!
" target="_blank">3月13日(日)短下肢装具を採型してみよう! -
約2ヶ月かけて製作してきた長下肢装具の適合評価が行われました。金属加工に悪戦苦闘しながら、ようやく完成まで漕ぎつけた学生が多かったようです。さあ、お互いに装着してみましょう!
 適合評価では、患者様に装着方法を指導するポイントや、装具が不適合だった場合の修正方法なども学習します。装具が下肢にあたっていないか、継ぎ手の位は適切か、ベルトの位置や長さは適切か、など細部にわたって確認をして行きます。
適合評価では、患者様に装着方法を指導するポイントや、装具が不適合だった場合の修正方法なども学習します。装具が下肢にあたっていないか、継ぎ手の位は適切か、ベルトの位置や長さは適切か、など細部にわたって確認をして行きます。
 担当教員がまずは静止立位時の適合状態をチェックして行きます。
装具が身体に正しく適合していることは勿論ですが、ベルトの縫製の仕上がりや金属支柱の曲げ加工の滑らかさなど、製作物としての出来ばえを評価します。また、製作物について学生に簡単なプレゼンテーションをしてもらい、義肢装具士として患者様の前で話すことをシミュレーションします。
担当教員がまずは静止立位時の適合状態をチェックして行きます。
装具が身体に正しく適合していることは勿論ですが、ベルトの縫製の仕上がりや金属支柱の曲げ加工の滑らかさなど、製作物としての出来ばえを評価します。また、製作物について学生に簡単なプレゼンテーションをしてもらい、義肢装具士として患者様の前で話すことをシミュレーションします。
 つぎに、実際に歩行しながら装具の適合状態を評価します。装具の膝継ぎ手の位置がずれている場合や歩行時に下肢のアライメント(各関節の角度)が変化する場合、金属支柱が体にあたる場合などがあります。これは採寸する段階で予測できればよいのですが、実際に装具を装着し歩行しなければ判断できないことが多くあります。
つぎに、実際に歩行しながら装具の適合状態を評価します。装具の膝継ぎ手の位置がずれている場合や歩行時に下肢のアライメント(各関節の角度)が変化する場合、金属支柱が体にあたる場合などがあります。これは採寸する段階で予測できればよいのですが、実際に装具を装着し歩行しなければ判断できないことが多くあります。
 近年、長下肢装具は脳卒中の急性期のリハビリテーションで重要視されており、処方されることが多い装具です。製作だけでなく、脳卒中の病態についてもしっかり学習して下さい!
近年、長下肢装具は脳卒中の急性期のリハビリテーションで重要視されており、処方されることが多い装具です。製作だけでなく、脳卒中の病態についてもしっかり学習して下さい!
2年生の専門科目の製作実習はこれで終了です。 3年生ではさらに高度な製作技術の習得が課題となります。2年生同様、一つずつ確実に積み上げて行って下さい! " target="_blank">NEW! 2年生 長下肢装具の製作実習が終了しました。 -
今回は金属材料を加工して装具を製作して行きます。
 修正した石膏モデル(陽性モデル)に合わせて金属を曲げ加工して行きます。体幹(胴体部分)の曲線に合わせて、金属製の支柱を滑らかに曲げ加工していますね!
修正した石膏モデル(陽性モデル)に合わせて金属を曲げ加工して行きます。体幹(胴体部分)の曲線に合わせて、金属製の支柱を滑らかに曲げ加工していますね!
 組み上げた金属枠の装具本体に、クロム革やフエルトで仕上げ加工を行います。ここでの作業は、製品としての完成度を高める大切な工程となるため、学生たちも繊細に作業しています!
組み上げた金属枠の装具本体に、クロム革やフエルトで仕上げ加工を行います。ここでの作業は、製品としての完成度を高める大切な工程となるため、学生たちも繊細に作業しています!
 最後に、前回製作した腰仙椎装具モールド型、ナイト型の適合評価を行いました。装具が規定の寸法通りに製作されているか、装具としての機能を十分満たしているか、義肢装具士の目線で具体的にチェックして行きます。
果して今回の装具は上手くフィッティングしていたでしょうか?
最後に、前回製作した腰仙椎装具モールド型、ナイト型の適合評価を行いました。装具が規定の寸法通りに製作されているか、装具としての機能を十分満たしているか、義肢装具士の目線で具体的にチェックして行きます。
果して今回の装具は上手くフィッティングしていたでしょうか?
さて、これで1年生の製作実習がすべて終了しました。 2年生では、実際の四肢切断者あるいは脳卒中片麻痺の方に義肢や装具を製作し、適合させることが製作実習の最終評価となります。今まで学んだ基本工作技術や専門知識を活かして、より良いモノが製作できるように頑張って下さいね!" target="_blank">NEW! 1年生 体幹装具の製作実習が終了しました。 -
試験前日の「壮行会」では東京に向かう先輩たちを激励するために、後輩たちが心のこもった熱い応援を披露してくれました!
 後輩たちが作ってくれた「魅せてやれ日聴の底力」の垂れ幕に、3年生たちは一気に勇気づけられました!
後輩たちが作ってくれた「魅せてやれ日聴の底力」の垂れ幕に、3年生たちは一気に勇気づけられました!
 名古屋駅を出発する時も、学生たちはいつものようにリラックスしているようですね!
名古屋駅を出発する時も、学生たちはいつものようにリラックスしているようですね!
 新幹線に乗ると、やはり参考書を開いてみんな黙々と勉強をしていました。
新幹線に乗ると、やはり参考書を開いてみんな黙々と勉強をしていました。
 前日は試験会場近くのホテルに宿泊し、試験当日を迎えました!
東京は雲ひとつ無い晴天に恵まれ、学生たちもリラックスして試験会場へ向かいます!
前日は試験会場近くのホテルに宿泊し、試験当日を迎えました!
東京は雲ひとつ無い晴天に恵まれ、学生たちもリラックスして試験会場へ向かいます!
 試験会場のTOC有明に到着しました!
試験場には既に他校の学生さんたちも到着しており、厳粛な空気の中でいよいよ国家試験の開始です!
試験会場のTOC有明に到着しました!
試験場には既に他校の学生さんたちも到着しており、厳粛な空気の中でいよいよ国家試験の開始です!
 午前、午後の試験を無事に終え、名古屋に戻るために試験会場から品川駅へ移動してきました。学生たちはいつも通りのリラックスした表情で、出題された問題についてあれこれ話をしています。
午前、午後の試験を無事に終え、名古屋に戻るために試験会場から品川駅へ移動してきました。学生たちはいつも通りのリラックスした表情で、出題された問題についてあれこれ話をしています。
 帰りの新幹線の車内では、出題に対する解答をお互いに確認し合っていますね!
帰りの新幹線の車内では、出題に対する解答をお互いに確認し合っていますね!
 こちらでも早速、お互いの解答について確認をしていますね。
国家試験が終わっても学生たちの探究心はまだまだ終わることはありません。さて、皆さんの結果はどうだったでしょうか?
こちらでも早速、お互いの解答について確認をしていますね。
国家試験が終わっても学生たちの探究心はまだまだ終わることはありません。さて、皆さんの結果はどうだったでしょうか?
この後、全員で学校に戻り、教務の先生方から受験の労をねぎらう温かいお言葉をいただき、2日間の日程を無事に終えました。 今回の試験結果は、3月28日(月)14時に厚生労働省より発表されます。" target="_blank">NEW! 3年生 第29回義肢装具士国家試験 -
香川先生は義肢装具学科のOBでもあり、国際大会への出場は後輩たちにとっても今後の良い励みになると思います!
 壮行会では本校の3年生たちが会場に飛び入り参加し、香川先生を激励するエールを送りました!
壮行会では本校の3年生たちが会場に飛び入り参加し、香川先生を激励するエールを送りました!
 日本聴能言語福祉学院は、香川先生のフランスでの健闘をお祈りしています!
日本聴能言語福祉学院は、香川先生のフランスでの健闘をお祈りしています!
義肢装具学科では随時、学校見学および義肢装具製作施設見学ツアーを行っています。香川先生の働く姿もみられるかも!?大切なあなたの進路決定のために、ぜひご参加ください!ご連絡お待ちしています!
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">NEW! 「第9回国際アビリンピック大会」壮行会
" target="_blank">NEW! 「第9回国際アビリンピック大会」壮行会 -
はじめに、骨格標本を使って体幹の機能や特徴を理解し、つぎに採型のポイントを学習して行きます。
 義肢装具の中でも採型範囲が広い体幹装具は、採型肢位が適切でないと後々の陽性モデル修正がとても大変です。しっかりデモンストレーションを見て、実践に繋げましょう!
義肢装具の中でも採型範囲が広い体幹装具は、採型肢位が適切でないと後々の陽性モデル修正がとても大変です。しっかりデモンストレーションを見て、実践に繋げましょう!
 では!早速採型してみましょう!
体幹装具を必要とする患者様は長時間立っていることが難しい方が大半です。姿勢が崩れないうちに、素早く採型することがポイントですね!
では!早速採型してみましょう!
体幹装具を必要とする患者様は長時間立っていることが難しい方が大半です。姿勢が崩れないうちに、素早く採型することがポイントですね!
 修正した陽性モデルに軟化させたプラスチックを熱成形して行きます。
陽性モデルの形にしっかりと沿わせ、装具に傷をつけないようにしなくてはいけません。プラスチックが冷める前に作業を終えなければならないため、学生たちは真剣な表情です!
修正した陽性モデルに軟化させたプラスチックを熱成形して行きます。
陽性モデルの形にしっかりと沿わせ、装具に傷をつけないようにしなくてはいけません。プラスチックが冷める前に作業を終えなければならないため、学生たちは真剣な表情です!
 熱成形したプラスチックを装具の形状にトリミングし、ベルトを取り付けて仕上げて行きます。
熱成形したプラスチックを装具の形状にトリミングし、ベルトを取り付けて仕上げて行きます。
今回の実習から製作した装具は最後に全て「適合評価」が待っています。 製作した装具が治療効果を持ち、患者様に使っていただける精度でモノづくりができたかどうか、最後にフィッティングを確認します。この作業は義肢装具士ならではの大切な仕事です。しっかり学んで行きましょう!" target="_blank">NEW! 1年生 体幹装具が完成しました。 -
反省点は沢山あったものの、患者様と関わる機会をいただいて、「STになりたい!」と
いう思いを強くして帰ってきたようです。
実際に、教員が実習先に訪問に行くと「学院にいるときよりもイキイキしているんじゃない!?」
と突っ込んでしまうくらいの表情の学生もいました(座学よりも実践向き?)。
今回の経験を次の実習に活かして、さらに成長して帰ってくるのを楽しみにしています。 " target="_blank">見学実習Ⅰ反省会
平成28年度 義肢装具学科 入学試験についてご案内します。 一般六次試験の出願を下記の通り受付けます。 受験希望の方はご確認の上、出願手続をお願いします。
◆試験科目 一般入学試験: 一般教養(国語・コミュニケーション英語ⅠⅡ英語) 適性(ペーパークラフト実技)・面接
◆試験日程 一般六次:平成28年3月13日(日) ※募集要項では3月12日(土)となっていますが 都合により日程を変更致しました。 出願期間:平成28年2月22日(月)~平成28年3月7日(月) 必着
義肢装具学科では随時、学校見学および義肢装具製作施設見学ツアーを行っています。大切なあなたの進路決定のために、ぜひご参加ください!ご連絡お待ちしています!
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">平成28年度 一般六次入学試験 出願期間のご案内
" target="_blank">平成28年度 一般六次入学試験 出願期間のご案内-
座位保持装置とは、疾患により四肢、体幹の変形、姿勢異常がみられ、座位がとれない患者様に対し、変形の予防や日常生活動作の改善を目的とし使用する補装具です。義肢装具士が取り扱う補装具のなかでも、より専門性が求められる分野でもあり、臨床で常にこの分野を担当されている先生方のお話はとても貴重です。
 藤田先生には座位保持装置について、基礎知識から製作技術についてご講義いただきました。
「姿勢とは?」から始まり、「身体重心」「脳性麻痺」など運動学、機能解剖学、リハビリテーション医学などで学んだ専門用語が次々と出てきますが、3年生ともなるとそれぞれの意味を理解しながら楽しく講義を聞いていたようです。
藤田先生には座位保持装置について、基礎知識から製作技術についてご講義いただきました。
「姿勢とは?」から始まり、「身体重心」「脳性麻痺」など運動学、機能解剖学、リハビリテーション医学などで学んだ専門用語が次々と出てきますが、3年生ともなるとそれぞれの意味を理解しながら楽しく講義を聞いていたようです。

 小畑先生は車椅子を中心に、子供用から成人用、特殊な機構を持つもの、電動車椅子など、さまざまなタイプの車椅子とその適応について分かり易くご講義いただきました。車椅子と言っても、必要とする患者様の状態によってたくさんの選択肢があることを理解できたのではないでしょうか。
小畑先生は車椅子を中心に、子供用から成人用、特殊な機構を持つもの、電動車椅子など、さまざまなタイプの車椅子とその適応について分かり易くご講義いただきました。車椅子と言っても、必要とする患者様の状態によってたくさんの選択肢があることを理解できたのではないでしょうか。
 続いて、座位保持装置の製作について学びます。座位保持装置の製作方法として、身体各部の寸法を計測する採寸による方法と、適切な座位を再現したうえで身体の型をとる採型による方法があります。今回は写真の専用採型台を用いた採型方法について実習を行いました。
続いて、座位保持装置の製作について学びます。座位保持装置の製作方法として、身体各部の寸法を計測する採寸による方法と、適切な座位を再現したうえで身体の型をとる採型による方法があります。今回は写真の専用採型台を用いた採型方法について実習を行いました。
 採型に使用する機材の準備をします。患者様の負担を減らすためにも、事前準備がとても大切であることを藤田先生から繰り返しお話いただきました。
採型に使用する機材の準備をします。患者様の負担を減らすためにも、事前準備がとても大切であることを藤田先生から繰り返しお話いただきました。
 準備ができたら患者様の事前評価を行います。変形や麻痺の程度を把握しながら、どのように患者様の姿勢を作っていくか、また、採型者が完成品をどれだけイメージできているかが重要であることを教えていただきました。
準備ができたら患者様の事前評価を行います。変形や麻痺の程度を把握しながら、どのように患者様の姿勢を作っていくか、また、採型者が完成品をどれだけイメージできているかが重要であることを教えていただきました。
 事前評価を基に、専用採型台を用いて患者様を安定性良く、かつ楽に座れる姿勢を再現していきます。常に患者様の状態を見ながら素早く作業を進めることが大切ですね!
事前評価を基に、専用採型台を用いて患者様を安定性良く、かつ楽に座れる姿勢を再現していきます。常に患者様の状態を見ながら素早く作業を進めることが大切ですね!
 採型を終えたクッションです。しっかりと身体の形状が再現されています。
採型を終えたクッションです。しっかりと身体の形状が再現されています。

 続いて、ギプスを使ってこのクッションの採型を行います。そして得られたギプスモデルを三次元スキャナでパソコンに読み込ませ、CAD/CAMを用いてスポンジ等の切削加工を行います。
続いて、ギプスを使ってこのクッションの採型を行います。そして得られたギプスモデルを三次元スキャナでパソコンに読み込ませ、CAD/CAMを用いてスポンジ等の切削加工を行います。
 藤田先生に教えていただいたことを踏まえ、いざ、実践です!
藤田先生に教えていただいたことを踏まえ、いざ、実践です!
 夢中になり過ぎて患者様の状態を確認することを忘れないようにしましょうね!
夢中になり過ぎて患者様の状態を確認することを忘れないようにしましょうね!

 続いて、小畑先生から車椅子について実際に試乗しながら説明をしていただきました。講義のために大阪(大東市)からたくさんの車椅子を持って来ていただきました。
続いて、小畑先生から車椅子について実際に試乗しながら説明をしていただきました。講義のために大阪(大東市)からたくさんの車椅子を持って来ていただきました。
 車椅子の構造を理解したら、次は利用者の視点に立って実際に路上を試乗してみましょう!
車椅子の構造を理解したら、次は利用者の視点に立って実際に路上を試乗してみましょう!
 日本の道路は水はけを良くするために、中央が盛り上がった“片流れ路”になっています。車椅子を真っ直ぐ操作しているつもりでも、なかなか直進できませんね。車椅子利用者の本当の不便さを理解することが、何よりも勉強です!
日本の道路は水はけを良くするために、中央が盛り上がった“片流れ路”になっています。車椅子を真っ直ぐ操作しているつもりでも、なかなか直進できませんね。車椅子利用者の本当の不便さを理解することが、何よりも勉強です!
 歩道の走行にも気を使います。何気なく駐輪してある自転車も、立場が変わると思いがけないバリアになってしまいますね。
歩道の走行にも気を使います。何気なく駐輪してある自転車も、立場が変わると思いがけないバリアになってしまいますね。

 駅のエレベーターや発券機は、車椅子を利用している方でも手が届く位置にボタンが配置されています。
駅のエレベーターや発券機は、車椅子を利用している方でも手が届く位置にボタンが配置されています。
 この自動販売機はどうでしょうか・・・
この自動販売機はどうでしょうか・・・
車椅子の介助を体験中。車椅子使用者だけでなく、介助者の視点を学ぶことで見えてくることが大きく変わります。常に双方の視点を忘れずに、モノづくりをして下さいね!
 2日間にわたって座位保持装置、車椅子を徹底的にご講義いただきました。
とても内容の濃い2日間に、学生たちには国家試験勉強の合間の良い刺激となったようです。最後までとても熱心にご指導いただきました小畑先生、藤田先生ありがとうございました。" target="_blank">NEW! 3年生 座位保持装置の特別講義が行われました。
2日間にわたって座位保持装置、車椅子を徹底的にご講義いただきました。
とても内容の濃い2日間に、学生たちには国家試験勉強の合間の良い刺激となったようです。最後までとても熱心にご指導いただきました小畑先生、藤田先生ありがとうございました。" target="_blank">NEW! 3年生 座位保持装置の特別講義が行われました。 -
スキー合宿の3日間とも天候に恵まれ、学生たちはスキーやスノーボードを思う存分楽しんだようです。
 本格的なスキーシーズン前ということもあり、ゲレンデはそれほど混雑していなかったようですね。
本格的なスキーシーズン前ということもあり、ゲレンデはそれほど混雑していなかったようですね。
 3日間の中には、スキー以外にも乗馬体験をする企画があったようですね。このほか信州安曇野名産のわさび田を巡る企画もあったようです。
3日間の中には、スキー以外にも乗馬体験をする企画があったようですね。このほか信州安曇野名産のわさび田を巡る企画もあったようです。

 夜は学生全員で『クリスマス会』を行ったようです。この時間は先輩、後輩の垣根を越えて、みんな楽しく過ごしています。この良き伝統は、先輩たちからずっと受け継がれているようですね!
夜は学生全員で『クリスマス会』を行ったようです。この時間は先輩、後輩の垣根を越えて、みんな楽しく過ごしています。この良き伝統は、先輩たちからずっと受け継がれているようですね!
 澄み切った空気のもとで満点の星空を見ながら、学生たちは少し落ち着いた時間が過ごせたようです。
澄み切った空気のもとで満点の星空を見ながら、学生たちは少し落ち着いた時間が過ごせたようです。


学生会の皆さん、楽しい報告をありがとうございました!" target="_blank">NEW! 白銀の世界でひと休み! -
プレセミナー参加者の質問に答える1年生
今回のコミュニケーションゲームはグループ対抗で「はい・いいえ質問だけで答えを当ててみよう」を 行いましたが、予想以上に早く答えにたどり着きました。積み木を使った検査の体験も盛り上がったようです。
最初は緊張していた参加者でしたが、終わる頃には和やかに打ち解けていました。 少しは言語聴覚士になるために勉強していく内容がイメージできたでしょうか。 1年前の帰りはさっそく一緒に遊びに行った1年生もいるようです。入学前に友達ができるって頼もしいですよね。
来年からは緊張をほぐすゲームから始めようと思っています。
参加者の皆様、春、入学式での再会を楽しみにしています。 " target="_blank">補聴言語学科プレセミナーが行われました -
勝つ!カレー
 勝つ!定食
勝つ!定食
全員が完食できました。これだけ食欲もあれば安心です。 この調子で体調管理に気を付けましょうね。 がんばれ!
がんばれ!
" target="_blank">食べて勝つ!
体験授業では義足で立つ、歩くうえで重要な「アライメント」もついて学び、実習ではホンモノの義足を組み立ててみましょう!適切な継手、足部を選択し指定された長さの義足を組み立てられるか、チャレンジ! オープンキャンパスでは、義肢装具士を体感できる魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています! 入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを再発見してください!
当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩 ◇12:00 体験授業(ホンモノの義足を組み立ててみよう!) ◇13:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
過去のオープンキャンパスの様子はこちら 第5回オープンキャンパス 第6回オープンキャンパス 第7回オープンキャンパス
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
 " target="_blank">2月20日(土) ホンモノの義足を組み立ててみよう!
" target="_blank">2月20日(土) ホンモノの義足を組み立ててみよう!-
福祉機器や用具は「リハビリテーション概論」の授業でも勉強はしていますが、こちらにはなんと1,000点もの展示があります。2グループに分かれて、詳しい説明を聞き、様々な体験をさせていただきました。呼吸を使ってのスイッチでカーテンが閉まった時は感嘆の声が大きかったです。
余談ですが、車椅子用のエアクッションの中身を見せて頂いたら、「有毛細胞」と言っていた学生が いました。ST学生らしい笑いですね。(ちなみに有毛細胞とは、内耳にある音などを感じる細胞のことです。)
昨年同様、一番人気は介護ロボットでした。和みますね~。テスト勉強で疲れた?学生達は 癒されていました。
福祉用具は「特殊なものではなく、生活を便利に豊かにする」ものだと体感し、患者さんの全体像を 捉えるイメージが出来たようです。 " target="_blank">なごや福祉用具プラザ見学 - 見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。
集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院)
*学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。
見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ)
所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。
その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">平成28年度 一般五次入学試験 出願期間のご案内
" target="_blank">平成28年度 一般五次入学試験 出願期間のご案内 -
今日はあぶみの足継手部分の可動域を決定するための切削加工を学習しました。
この部分の角度設定が1°でも変わってしまうと使用者の歩行に大きく影響するため、作業の精度が重要となります。
 義肢装具士は正確に製品を製作する技術だけでなく、一人一人の患者様に製品をフィッティングさせる技術も求められます。一つ一つの作業を妥協することなく、学生たちは真剣に取り組んでいます!" target="_blank">NEW! 2年生 完璧な作業精度を目指して。
義肢装具士は正確に製品を製作する技術だけでなく、一人一人の患者様に製品をフィッティングさせる技術も求められます。一つ一つの作業を妥協することなく、学生たちは真剣に取り組んでいます!" target="_blank">NEW! 2年生 完璧な作業精度を目指して。 - http://wakamiyast.blog25.fc2.com/ 申し込みできます。締め切りは2/10(水)です。 " target="_blank">若宮ST同窓会「ミニセミナー&症例検討会」ご案内
-
”ワクワクしながら“想像を膨らませ考え不可能を可能に変えられるST、目標は遠いですが、
遠くに置く分、ぶれずに目指していきたいと思います。毎回の先生の熱心な授業、少しハードな(!?)緊張感と相まって、たくさんのことを考えることができました。ありがとうございました。
最後が少し笑えますが、「伝わっているんだ」と感じました。STは人間に欠かせない「コミュニケーション」と「食べること」と「感じる・考えること」に関わる職業です。だからこそ、現場は、常に真剣勝負で、本当に患者様のことを考えて悩んだり、喜んだり「人間くさい」体験に満ち溢れています。 私は、それが何より最高のSTの魅力だと考えているので、そこを学生に伝えたいと思いながら授業をしています。
聴能教員P " target="_blank">学生の講義感想(診断学)その2 - 学生の講義感想(診断学)その1
 学院前の道路もいつもとは違う銀世界でした!大雪警報のため午前中の講義は休講となりましたが、午後からは通常通り講義が行われました。
学院前の道路もいつもとは違う銀世界でした!大雪警報のため午前中の講義は休講となりましたが、午後からは通常通り講義が行われました。
 こんな寒い日でも、義肢装具学科の学生たちは元気です!早めに登校してきた学生たちが早速、玄関前で雪だるまを作っていました。サーフォームファイルで丸く丸く仕上げ、彼らなりのこだわり?があるようです。
学生の皆さん、風邪をひかないようにこの冬を乗り切りましょう!" target="_blank">NEW! 名古屋にこの冬初の雪が降りました。
こんな寒い日でも、義肢装具学科の学生たちは元気です!早めに登校してきた学生たちが早速、玄関前で雪だるまを作っていました。サーフォームファイルで丸く丸く仕上げ、彼らなりのこだわり?があるようです。
学生の皆さん、風邪をひかないようにこの冬を乗り切りましょう!" target="_blank">NEW! 名古屋にこの冬初の雪が降りました。-
今回の体験授業では「足部の機能解剖」についての講義、そして、足の採型用の特殊なスポンジ「トリッシャム」を使って自分の足の型を採ってみましょう!

さらに、立位時の足の荷重状況を反映する「フットプリント」を採って、自分の足を分析してみましょう!
入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!
当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩 ◇12:00 体験授業(自分の足を分析してみよう!) ◇13:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
過去のオープンキャンパスの様子はこちら 第5回オープンキャンパス 第6回オープンキャンパス 第7回オープンキャンパス
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
 " target="_blank">1月23日(土)足の構造を分析してみよう!
" target="_blank">1月23日(土)足の構造を分析してみよう! -
今年度は、聴能言語学科(大卒2年課程)・補聴言語学科(高卒3年課程)
ともオープンキャンパスは終了しました。
今後は個別の学校見学で対応させていただきますので、
お気軽にお申込み下さい。日程はご希望に合わせて決定させて
いただきます。
学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、
仕事紹介や学科説明を行います。
専任教員が対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。
 " target="_blank">今年度最後のオープンキャンパスがありました。
" target="_blank">今年度最後のオープンキャンパスがありました。 -
まずは、「あぶみ」という靴に取り付ける部品の金属加工を行います。金属製の下肢装具では、このあぶみが装具の土台となるため最も重要な部分となります。製作実習では実際の製作を始める前に、材料特性や作業工程について理論的に学んで行きます。
 次に、教員が工程ごとにデモンストレーションを行い、工具の使い方や製作上のコツなどを細かく説明して行きます。学生たちもしっかりメモをとっていますね!
次に、教員が工程ごとにデモンストレーションを行い、工具の使い方や製作上のコツなどを細かく説明して行きます。学生たちもしっかりメモをとっていますね!
 講義ではトレースを用いた製作理論を学習していますが、石膏モデル(陽性モデル)による製作方法も講義しています。
講義ではトレースを用いた製作理論を学習していますが、石膏モデル(陽性モデル)による製作方法も講義しています。

 装具を正確に可動させるためには可動する軸位置を正確に設定することが重要となります。数ミリのずれが装具全体の動きを悪くしてしまうため、学生たちも真剣です。製作途中の製作物の出来ばえを教員がすべてチェックし、作業精度を確認して行きます。金属の曲げ加工に苦手意識はあるものの、学生たちの製作スピードは確実に早くなっています。
正確に製作物を作り上げる技術を習得することが何より大切ですが、決められた時間の中で作業を進めることも必要です。
装具の出来上がりを待つ患者様のことを忘れずに次の工程も頑張りましょう!" target="_blank">NEW! 2年生 長下肢装具の製作実習をレポート!
装具を正確に可動させるためには可動する軸位置を正確に設定することが重要となります。数ミリのずれが装具全体の動きを悪くしてしまうため、学生たちも真剣です。製作途中の製作物の出来ばえを教員がすべてチェックし、作業精度を確認して行きます。金属の曲げ加工に苦手意識はあるものの、学生たちの製作スピードは確実に早くなっています。
正確に製作物を作り上げる技術を習得することが何より大切ですが、決められた時間の中で作業を進めることも必要です。
装具の出来上がりを待つ患者様のことを忘れずに次の工程も頑張りましょう!" target="_blank">NEW! 2年生 長下肢装具の製作実習をレポート! -
義肢装具学科では臨床実習中の課題として自らが経験した症例をケースレポートにまとめ、記録することを指導しています。学生たちはこれを学校に持ち帰り、専門書を用いて疾患に対する理解を深め、その後、学生全員の前でプレゼンテーションを行っています。この発表会には卒業生は勿論、臨床実習でご指導いただいた指導者の方々にも大勢ご参加いただきました。
○「症例報告会」の目的 1)対象となる症例の病態を医学的に理解し「症例を診る力」を養う。 2)個人が経験した症例を全員で「情報共有」することで、多くの知識や技術を学習する。 3)症例報告という形式で「プレゼンテーション能力」を養う。
○発表演題 Session1:整形外科疾患Ⅰ 1-1 脊椎圧迫骨折に対する胸腰仙椎装具の製作 成瀬 稜典(2年) 実習施設/㈲奥義肢製作所(福井) 1-2 脛腓骨遠位横断骨折に対するPTB式免荷装具 新美 利紀(2年) 実習施設/㈱愛媛義肢製作所(愛媛) 1-3 骨形成不全に対する足底装具の製作 安江 優作(2年) 実習施設/㈱佐々木義肢製作所弘前支店(青森) 1-4 内転足に対する足底装具の製作 石黒 涼 (2年) 実習施設/㈱松本義肢製作所(愛知) 1-5 特発性側弯症術後に対する胸腰仙椎装具の製作 吉川 拓斗(2年) 実習施設/㈱中礼義肢製作所(鹿児島) Session2:脳血管疾患 2-1 脳卒中片麻痺に対する両側支柱付き短下肢装具の製作 石倉 あや(2年) 実習施設/㈱洛北義肢(京都) 2-2 脳卒中片麻痺に対する湯之児式短下肢装具の製作 高木 敦史(2年) 実習施設/有園義肢製作株式会社(熊本) 2-3 脳卒中片麻痺に対するゲイトソリューションの適応 高見佳那子(2年) 実習施設/川村義肢株式会社(大阪) 2-4 脳卒中片麻痺に対するタマラック足継手付き短下肢装具の製作 林 利和子(3年) 実習施設/㈱小豆澤整形器製作所(大阪) 2-5 脳卒中を発症した変形性膝関節症罹患者に対する長下肢装具の製作 鈴木田典子(3年) 実習施設/㈲ハート義肢(沖縄) 2-6 脳卒中片麻痺に対して上肢装具が処方された1例 高瀬 結衣(3年) 実習施設/東名ブレース株式会社(愛知) Session3:神経疾患・潰瘍 3-1 脳性麻痺児に対するタマラック足継手付き短下肢装具の製作 長谷川丈剛(2年) 実習施設/㈱富山県義肢製作所(富山) 3-2 脳性麻痺児に対する両側支柱付き短下肢装具の製作(半長靴付き)の製作 三嶋 唯楽(2年) 実習施設/㈱かなえ義肢(長崎) 3-3 二分脊椎による足部潰瘍に対する靴型装具の製作 長崎真由美(3年) 実習施設/㈲渡辺義肢製作所(愛知) 3-4 糖尿病性足潰瘍に対する短下肢装具の製作 忠岡 太聖(3年) 実習施設/日本フットケアサービス株式会社(京都) Session4:切断 4-1 糖尿病性足壊疽による両下腿切断に対する下腿義足の製作 神谷 大地(3年) 実習施設/神奈川総合リハビリテーション病院(神奈川) 4-2 大腿切断(短断端)に対する四辺形ソケットの製作 早崎 怜央(3年) 実習施設/㈲長良義肢製作所(岐阜) 4-3 片側骨盤切除例に対する仮義足の製作および適合 坂野 典生(3年) 実習施設/㈱有薗製作所(福岡) 4-4 上腕切断(短断端)に対する肩義手の製作 小塚 啓文(3年) 実習施設/㈱松本義肢製作所(愛知)
以上、19演題です。 この中から参加者全員の投票によって最優秀賞1名、優秀賞3名を選出しました。
 当日は多くの来賓の先生方をお迎えし、貴重なご意見を頂戴しました。
ご参加いただきました先生方、ありがとうございました。
当日は多くの来賓の先生方をお迎えし、貴重なご意見を頂戴しました。
ご参加いただきました先生方、ありがとうございました。
 進行はセッションごとに学生が座長を担当します。学生が座長をすることで症例報告会の進め方や質問のタイミングなどを学ぶことができ、彼らにとっても貴重な経験となりました。
進行はセッションごとに学生が座長を担当します。学生が座長をすることで症例報告会の進め方や質問のタイミングなどを学ぶことができ、彼らにとっても貴重な経験となりました。
 学生たちはみんな自信に満ちた表情で発表をしています!
限られた時間のなかで、相手にいかに分かりやすく情報を伝えるかということはとても難しいことですが、自分が経験した症例だからこそ発表する声にも熱が入ります!
学生たちはみんな自信に満ちた表情で発表をしています!
限られた時間のなかで、相手にいかに分かりやすく情報を伝えるかということはとても難しいことですが、自分が経験した症例だからこそ発表する声にも熱が入ります!
 参加者全員の投票による審査の結果、最優秀賞は林利和子さん(3年)、優秀賞は高瀬結衣
さん(3年)、忠岡太聖さん(3年)、小塚啓文さん(3年)、鈴木田典子さん(3年)が選ばれました!
最優秀賞の林さんには学園より記念のトロフィーと校章入りクリスタルの楯が贈呈されました。
林さん、高瀬さん、忠岡さん、小塚さん、受賞おめでとうございました!
参加者全員の投票による審査の結果、最優秀賞は林利和子さん(3年)、優秀賞は高瀬結衣
さん(3年)、忠岡太聖さん(3年)、小塚啓文さん(3年)、鈴木田典子さん(3年)が選ばれました!
最優秀賞の林さんには学園より記念のトロフィーと校章入りクリスタルの楯が贈呈されました。
林さん、高瀬さん、忠岡さん、小塚さん、受賞おめでとうございました!
 発表を行った学生の皆さん、ご苦労様でした。
また、前日の深夜まで発表の予行演習をご指導いただいた名和先生、唐澤先生ありがとうございました。この症例報告会を通して多くの学生が、臨床実習という機会に何を学習し、何を経験するべきかを改めて理解したことと思います。来年の臨床実習も、より明確な目的意識を持って実習に臨んで下さい。
また、3年生の皆さんはこの経験を活かし、「患者様のために探究する姿勢」を忘れずに、臨床でも活躍して下さい!" target="_blank">NEW! 臨床実習症例報告会が行われました。
発表を行った学生の皆さん、ご苦労様でした。
また、前日の深夜まで発表の予行演習をご指導いただいた名和先生、唐澤先生ありがとうございました。この症例報告会を通して多くの学生が、臨床実習という機会に何を学習し、何を経験するべきかを改めて理解したことと思います。来年の臨床実習も、より明確な目的意識を持って実習に臨んで下さい。
また、3年生の皆さんはこの経験を活かし、「患者様のために探究する姿勢」を忘れずに、臨床でも活躍して下さい!" target="_blank">NEW! 臨床実習症例報告会が行われました。 -
学生の全体発表を前に、教務主任の中川先生より開会のご挨拶がありました。
ここでは、卒業研究を通して義肢装具を定量評価(検証結果を数値化する)することの重要性についてお話がありました。
 グループごとに発表の順番を待つ3年生たちです。
少し緊張しているようですが、凛々しい表情にこの日にかける意気込みが伝わってきます!前日深夜まで指導教員と何度も発表の練習をしていたグループもあったようです。
グループごとに発表の順番を待つ3年生たちです。
少し緊張しているようですが、凛々しい表情にこの日にかける意気込みが伝わってきます!前日深夜まで指導教員と何度も発表の練習をしていたグループもあったようです。
 いざ、本番スタート!
どのグループも発表練習を念入りに行っていて、3年生らしい堂々とした発表ばかりでした!
いざ、本番スタート!
どのグループも発表練習を念入りに行っていて、3年生らしい堂々とした発表ばかりでした!
 なぜその計測方法を選択したのか?
評価方法に問題はなかったか?など、後輩や同級生、先生方からもさまざまな質問が飛び交っています!
なぜその計測方法を選択したのか?
評価方法に問題はなかったか?など、後輩や同級生、先生方からもさまざまな質問が飛び交っています!

 会場内には各研究グループの製作物を展示するブースが設けられていて、休憩時間には実際に学生たちが製作物を手にとって見ることができます。後輩たちは現物を見ると先輩たちの研究に益々興味が湧いてきたようです。
会場内には各研究グループの製作物を展示するブースが設けられていて、休憩時間には実際に学生たちが製作物を手にとって見ることができます。後輩たちは現物を見ると先輩たちの研究に益々興味が湧いてきたようです。

 表彰式の後には、毎年恒例の「国家試験合格祈願セット」が学園より3年生全員に贈られました。
残るは国家試験だけですね!まだまだ気が抜けないと思いますが、あと2ヶ月しっかり走り切って下さい!
発表前の緊張もほぐれて、みんな笑顔がこぼれていますね。
3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">NEW! 卒業研究発表会が行われました。
表彰式の後には、毎年恒例の「国家試験合格祈願セット」が学園より3年生全員に贈られました。
残るは国家試験だけですね!まだまだ気が抜けないと思いますが、あと2ヶ月しっかり走り切って下さい!
発表前の緊張もほぐれて、みんな笑顔がこぼれていますね。
3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">NEW! 卒業研究発表会が行われました。 - 聴能教員P" target="_blank">国家試験合格祈願!

当日ご都合がつかない場合は、 お気軽に学校見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。
なお、学校見学は、聴能(2年課程)・補聴(3年課程)とも それぞれのご希望にあわせて対応いたします。 " target="_blank">聴能言語学科オープンキャンパスのお知らせ
" target="_blank">聴能言語学科オープンキャンパスのお知らせ

 大掃除の日の昼食は、これも恒例となっている「大掃除カレー」を早朝から学生たちが作り、みんなで美味しくいただきました。いつものように他学科の先生方や事務の皆さんにもお裾分けをして喜んでいただけました。美味しいものはみんなで!分け合う心が大切ですね!!
大掃除の日の昼食は、これも恒例となっている「大掃除カレー」を早朝から学生たちが作り、みんなで美味しくいただきました。いつものように他学科の先生方や事務の皆さんにもお裾分けをして喜んでいただけました。美味しいものはみんなで!分け合う心が大切ですね!!
 大掃除では学内を隅々まできれいにするだけでなく、図書室の蔵書整理も行います。
今年も興味深い新書がたくさん入りました!
大掃除では学内を隅々まできれいにするだけでなく、図書室の蔵書整理も行います。
今年も興味深い新書がたくさん入りました!
 大掃除の終了後、中川教務主任より新年を迎えるにあたり、今年一年を振り返り、新しい年への目標を立てる事についてお話がありました。
大掃除の終了後、中川教務主任より新年を迎えるにあたり、今年一年を振り返り、新しい年への目標を立てる事についてお話がありました。
 最後に、今日はクリスマスイブということで中川先生より学生全員にケーキのプレゼントがありました!
思わぬサプライズにみんな笑顔で食べていました。
最後に、今日はクリスマスイブということで中川先生より学生全員にケーキのプレゼントがありました!
思わぬサプライズにみんな笑顔で食べていました。
今年も残すところ、あと僅かとなりました。 3年生にとって、慣れ親しんだ教室を後輩たちと掃除するのもこれが最後となります。 皆さんが受け継いでくれたように、後輩たちもきっと義肢装具学科の数々の伝統を受け継いでくれると信じています!
それでは皆さん、良いお年をお迎え下さい!" target="_blank">NEW! 新しい年を迎える準備ができました!-
1週間で全ての課題を完成させるためには、4つを並行して製作しなければいけません。試験の前までに、しっかりと各課題の製作工程を確認し、どのように作業を行うか計画を立てておくことがとても大切です。なおかつ、実際に始まった時には柔軟に対応することがポイントですね!
 課題を早く提出することも重要ですが、製作物が評価基準を満たしているかどうか、自身で判断する力も必要です。近い将来、自分が製作したものを製品として患者様に渡すことになります!
課題を早く提出することも重要ですが、製作物が評価基準を満たしているかどうか、自身で判断する力も必要です。近い将来、自分が製作したものを製品として患者様に渡すことになります!
 今回の実技試験で、これまでの講義内容を曖昧なまま理解していたことに気づいた学生も多かったようです。計画通りにできた学生、できなかった学生、それぞれの今後の課題が明確になったと思います。
今後の学びにしっかり活かして下さい!" target="_blank">NEW! 1年生 義肢装具基本工作論の実技試験が行われました。
今回の実技試験で、これまでの講義内容を曖昧なまま理解していたことに気づいた学生も多かったようです。計画通りにできた学生、できなかった学生、それぞれの今後の課題が明確になったと思います。
今後の学びにしっかり活かして下さい!" target="_blank">NEW! 1年生 義肢装具基本工作論の実技試験が行われました。 -
まずは、下腿部の切断端の石膏モデル(陽性モデル)を製作し、軟性内ソケットの上から、樹脂注型を行う準備をします。
 液体樹脂を使って、プラスチック製のソケットを製作します。液体樹脂は数分で化学反応により硬化します。
空気が入らないように、そして厚さが均一になるように注意しながら作業することが大切です!
液体樹脂を使って、プラスチック製のソケットを製作します。液体樹脂は数分で化学反応により硬化します。
空気が入らないように、そして厚さが均一になるように注意しながら作業することが大切です!
 次は、陽性モデルを割り出します。ソケット内面の軟性内ソケットを傷つけないよう、慎重に!
次は、陽性モデルを割り出します。ソケット内面の軟性内ソケットを傷つけないよう、慎重に!
 ここからは義足を組み立てる段階に入ります。
義足で安全に歩行できるよう、製作理論に基づいて義足を組み立てます。
義足を作業台の上で理論通りに組み立てる工程をベンチアライメントと言います。
ここからは義足を組み立てる段階に入ります。
義足で安全に歩行できるよう、製作理論に基づいて義足を組み立てます。
義足を作業台の上で理論通りに組み立てる工程をベンチアライメントと言います。
 義足を組み立てる工程では、石膏、プラスチック、木材など、さまざまな材料が使用されます。各材料の特性を理解して、正確に加工する技術が必要となります。
義足を組み立てる工程では、石膏、プラスチック、木材など、さまざまな材料が使用されます。各材料の特性を理解して、正確に加工する技術が必要となります。
 ベンチアライメントが完了すると、次はいよいよ脚の形状に削り出していきます。この工程を“型出し”といいます。
型出しの前に下腿の形状をデッサンしてみると、よりイメージがしやすいですね!
ベンチアライメントが完了すると、次はいよいよ脚の形状に削り出していきます。この工程を“型出し”といいます。
型出しの前に下腿の形状をデッサンしてみると、よりイメージがしやすいですね!
 型出しの完了後、外装に肌色の樹脂を注型して完成です!先生の最終チェックを受けて、良い点や改善すべき点を教えていただきます。
型出しの完了後、外装に肌色の樹脂を注型して完成です!先生の最終チェックを受けて、良い点や改善すべき点を教えていただきます。
今回の実習で義足づくりの基礎を学んだ1年生たち。 来年は実際の切断者をモデルに義足を製作し、適合評価を受けます。 自分が製作した義足で問題なく歩行してもらえるか、楽しみですね! そのためには1年生で学んだ製作理論をしっかりと理解していることが大切ですよ!
< オープンキャンパスのご案内 > 第13回オープンキャンパスを2月20日(土)に開催いたします!

体験授業では今回のレポートでご紹介した下腿義足について、義足で立つ、歩くうえで重要な「アライメント」もついて学び、実習ではホンモノの義足を組み立ててみましょう!適切な継手、足部を選択し指定された長さの義足を組み立てられるか、チャレンジ! オープンキャンパスでは、義肢装具士を体感できる魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています! 入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを再発見してください!
当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩 ◇12:00 体験授業(ホンモノの義足を組み立ててみよう!) ◇13:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">NEW! 1年生 PTB式下腿義足の製作実習をレポート!
" target="_blank">NEW! 1年生 PTB式下腿義足の製作実習をレポート! -
本校では患者様の多様なニーズに応えられる義肢装具士を教育するため、これまで学んだ製靴技術に加えて、オリジナルのアッパーを設計する技術を教育しています。靴型装具の機能面だけを重視するのではなく、ファッション性の面からも新たな提案をすることが義肢装具士として重要なことと考えています。
 アッパーをデザインする前に、まずは歩行評価を行います。
人間の足部には、それぞれ固有のアライメントがあり、複数の運動の組合せによって歩行を可能にしています。義肢装具士は、その患者様の足部のどこに問題があり、どの関節にアプローチするべきかを的確に判断する必要があります。
アッパーをデザインする前に、まずは歩行評価を行います。
人間の足部には、それぞれ固有のアライメントがあり、複数の運動の組合せによって歩行を可能にしています。義肢装具士は、その患者様の足部のどこに問題があり、どの関節にアプローチするべきかを的確に判断する必要があります。
 足部採型のデモンストレーションでは、一つ一つの工程や手技の目的を分かり易く説明していただき、教科書では学ぶことができないテクニックを間近で見られるため、学生たちの表情も真剣です!
足部採型のデモンストレーションでは、一つ一つの工程や手技の目的を分かり易く説明していただき、教科書では学ぶことができないテクニックを間近で見られるため、学生たちの表情も真剣です!
 いよいよラスト(木型)からアッパーのデザインを設計して行きます。靴を製作する中で最も楽しい工程と言えますが、製作者の芸術的センスが問われる難しい工程でもあります。
いよいよラスト(木型)からアッパーのデザインを設計して行きます。靴を製作する中で最も楽しい工程と言えますが、製作者の芸術的センスが問われる難しい工程でもあります。
 アッパーのデザインには、基準となる数値が多く設定されています。この数値を計算しながら、「世界に一つしかない靴」をデザインします!
アッパーのデザインには、基準となる数値が多く設定されています。この数値を計算しながら、「世界に一つしかない靴」をデザインします!
 アッパーのデザインが決まったら画用紙を使って実際にアッパーを製作します。
この学生は、臨床実習で製作した靴型装具と同じデザインのアッパーを設計してみたようです。
それにしても、臨床実習で素敵な靴を作って来ましたね!
アッパーのデザインが決まったら画用紙を使って実際にアッパーを製作します。
この学生は、臨床実習で製作した靴型装具と同じデザインのアッパーを設計してみたようです。
それにしても、臨床実習で素敵な靴を作って来ましたね!
 今年もさまざまなデザインのアッパーが出来上がりました!
学生たちはあまりに夢中になり過ぎて、講義時間をすっかり忘れて作業に没頭していました。
眞殿先生、今年も靴づくりの楽しさを学生たちにお教えいただき、ありがとうございました!
来年もよろしくお願いします!
今年もさまざまなデザインのアッパーが出来上がりました!
学生たちはあまりに夢中になり過ぎて、講義時間をすっかり忘れて作業に没頭していました。
眞殿先生、今年も靴づくりの楽しさを学生たちにお教えいただき、ありがとうございました!
来年もよろしくお願いします!
 3年生の卒業研究で中川先生の靴を製作したチームがあり、1日履いた感想を聞きたいということで学生たちが教務室に来た時の写真です。中川先生も学生たちに靴を作ってもらいとても嬉しそうでした!
さて、一日履いた感想はどうだったでしょうか?
この研究内容は、来年2月に大阪で開催される「第12回日本整形靴技術協会学術大会」のポスターセッションにて発表予定です!" target="_blank">NEW! 2年生 靴づくりのスペシャリストによる特別講義
3年生の卒業研究で中川先生の靴を製作したチームがあり、1日履いた感想を聞きたいということで学生たちが教務室に来た時の写真です。中川先生も学生たちに靴を作ってもらいとても嬉しそうでした!
さて、一日履いた感想はどうだったでしょうか?
この研究内容は、来年2月に大阪で開催される「第12回日本整形靴技術協会学術大会」のポスターセッションにて発表予定です!" target="_blank">NEW! 2年生 靴づくりのスペシャリストによる特別講義 -
装具を製作するための情報収集の手段には下肢の輪郭を紙にトレースする方法や、ギプス包帯で下肢全体を採型する方法があります。ここでも身体に合った装具を作るために学ぶべきポイントがたくさんあります。

 長下肢装具の製作実習は、学生同士がお互いの脚に合わせて製作するため、教員のデモンストレーションをしっかり見た後で、いよいよお互いの脚をトレースしていきます。
長下肢装具の製作実習は、学生同士がお互いの脚に合わせて製作するため、教員のデモンストレーションをしっかり見た後で、いよいよお互いの脚をトレースしていきます。
 次は採型練習です。この装具は、ギプス包帯で採型した石膏モデルを基に製作する場合もあるため、大切な練習です。
2年生もこの時期になると、自信を持って上手に採型出来るようになっています。
次は採型練習です。この装具は、ギプス包帯で採型した石膏モデルを基に製作する場合もあるため、大切な練習です。
2年生もこの時期になると、自信を持って上手に採型出来るようになっています。
次回は来年になりますが、金属支柱の曲げ加工の様子をご紹介します。" target="_blank">NEW! 2年生 両側支柱付き長下肢装具の製作実習が始まりました。 - 見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。
集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院)
*学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。
見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ)
所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。
その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">平成28年度 一般四次入学試験 出願期間のご案内
" target="_blank">平成28年度 一般四次入学試験 出願期間のご案内 -
義肢装具士のモノづくりは、患者さんの体を採型するところから始まります、その採型したモデルをもとに個々に合った義肢や装具を製作します。
体験授業では実際に「短下肢装具の採型」を行っていただきます!
義肢装具士を体感するチャンス!!
入試情報や学生生活などどんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!
当日のスケジュール ◇12:00 受 付 ◇12:30 学科説明 ◇13:15 休 憩 ◇13:30 体験授業(短下肢装具の採型をしてみよう!) ◇15:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇16:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・この春、高校3年生になる方で義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
過去のオープンキャンパスの様子はこちら 第5回オープンキャンパス 第6回オープンキャンパス 第7回オープンキャンパス
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はこちら
 " target="_blank">12月20日(日)短下肢装具を採型してみよう!
" target="_blank">12月20日(日)短下肢装具を採型してみよう! - このような能動的学習は理解が深まります。 本日担当した学生たちは「言語発達障害学」が得意になるといいな、と願っています。 " target="_blank">授業風景
-
会期中は医師、看護師、義肢装具士、理学療法士、教育関係者、靴メーカーなど500名を超える参加者が来場され、たいへん盛況な学会となりました。
学生たちは緊張しながらもホスピタリティの気持ちを忘れずに、参加者の皆さんにしっかり対応していました。
 学会が無事に終わり、会長の 塩之谷 香 先生(前列中央)と一緒に記念撮影。
塩之谷先生から感謝のしるしとして、先生の著書「足のトラブル解消術」を学生全員にプレゼントしていただきました。学会運営という貴重な経験を通して、学生たちの「靴型装具」への関心も益々高まったようです。
3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">NEW! 3年生 学生たちが『日本靴医学会学術集会』をサポート!
学会が無事に終わり、会長の 塩之谷 香 先生(前列中央)と一緒に記念撮影。
塩之谷先生から感謝のしるしとして、先生の著書「足のトラブル解消術」を学生全員にプレゼントしていただきました。学会運営という貴重な経験を通して、学生たちの「靴型装具」への関心も益々高まったようです。
3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">NEW! 3年生 学生たちが『日本靴医学会学術集会』をサポート! - 見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。
集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院)
*学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。
見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ)
所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。
その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">平成28年度 一般三次入学試験 出願期間のご案内
" target="_blank">平成28年度 一般三次入学試験 出願期間のご案内 -
上腕義手と前腕義手それぞれのユーザー様にご協力いただき、操作方法や日常生活の苦労について様々なお話をしていただきました。器用に義手を操作する姿に驚きの声が上がります。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
 デモンストレーションの後は、模擬上腕義手の装着体験です。実際に装着して操作してみると、難しくてなかなか思い通りに操作できません。はじめは操作が難しかったようですが、教員が操作方法を具体的に説明すると、しばらくして操作できるようになりました。義肢装具士は製作するだけではなく、操作方法についての説明(インフォームドコンセント)も必要となり、他のリハビリスタッフと同様に切断者の社会復帰に積極的に関わります。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
デモンストレーションの後は、模擬上腕義手の装着体験です。実際に装着して操作してみると、難しくてなかなか思い通りに操作できません。はじめは操作が難しかったようですが、教員が操作方法を具体的に説明すると、しばらくして操作できるようになりました。義肢装具士は製作するだけではなく、操作方法についての説明(インフォームドコンセント)も必要となり、他のリハビリスタッフと同様に切断者の社会復帰に積極的に関わります。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
 次に、筋電義手のコントロールに必要となる筋電位の導出を行いました。筋肉が収縮すると、体表面では微弱な生体電流が発生します。この生体電流を電極で検知し、入力信号に変換することで電動ハンドのON・OFFに利用する、というのが筋電義手の原理です。実際の講義でもモデル様にご協力いただき、学生全員が筋電位の導出、操作訓練を通して断端を評価し、筋電義手を製作します。今回は採型前に行われる「義手装着前訓練」を体験していただきました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
次に、筋電義手のコントロールに必要となる筋電位の導出を行いました。筋肉が収縮すると、体表面では微弱な生体電流が発生します。この生体電流を電極で検知し、入力信号に変換することで電動ハンドのON・OFFに利用する、というのが筋電義手の原理です。実際の講義でもモデル様にご協力いただき、学生全員が筋電位の導出、操作訓練を通して断端を評価し、筋電義手を製作します。今回は採型前に行われる「義手装着前訓練」を体験していただきました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
 筋電位の導出は、筋電義手をコントロールするために必要とされる筋肉の走行を学習していればそう難しくはありません。解剖学と運動学の知識が大切ですね!
参加者は学生スタッフの前腕を評価し、適切な位置に電極を配置します。初めはなかなか筋の走行を理解できませんでしたが、学生から的確なアドバイスをもらい、理解できるととても楽しそうにチャレンジしていました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
筋電位の導出は、筋電義手をコントロールするために必要とされる筋肉の走行を学習していればそう難しくはありません。解剖学と運動学の知識が大切ですね!
参加者は学生スタッフの前腕を評価し、適切な位置に電極を配置します。初めはなかなか筋の走行を理解できませんでしたが、学生から的確なアドバイスをもらい、理解できるととても楽しそうにチャレンジしていました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
 こちらでは実際に参加者の方が自分で筋電義手の電動ハンドを操作しています。うまくコントロールできていましたよ!
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
こちらでは実際に参加者の方が自分で筋電義手の電動ハンドを操作しています。うまくコントロールできていましたよ!
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
 このように本校ではホントの授業をベースにしたオープンキャンパスを実施しています。オープンキャンパスにご参加いただければ、この学科に入学すると「こんなことが勉強できるんだ!」「難しいけど先生や先輩たちを信頼して頑張ってやってみよう!」という気持ちになっていただけるはずです。本校では理論と実践をバランスよく学ぶことができます。その空気を感じるためにぜひオープンキャンパスにお越しください!" target="_blank">NEW! 第7回オープンキャンパスの様子をご紹介します。
このように本校ではホントの授業をベースにしたオープンキャンパスを実施しています。オープンキャンパスにご参加いただければ、この学科に入学すると「こんなことが勉強できるんだ!」「難しいけど先生や先輩たちを信頼して頑張ってやってみよう!」という気持ちになっていただけるはずです。本校では理論と実践をバランスよく学ぶことができます。その空気を感じるためにぜひオープンキャンパスにお越しください!" target="_blank">NEW! 第7回オープンキャンパスの様子をご紹介します。 -
株式会社松本義肢製作所は国内の義肢装具製作会社の中でも歴史が古く(明治38年創業)、静岡や長野に営業所があります。また、東海地域では最も従業員数が多く、在籍している義肢装具士の多くは本校の卒業生です。
 このほか近年では動物用の義肢装具も手掛けています(アニマルオルソジャパン)。
このほか近年では動物用の義肢装具も手掛けています(アニマルオルソジャパン)。
 学科説明の後、本学科の非常勤講師でもあります佐口先生に会社説明と施設案内をしていただきました。また、義肢装具の歴史から最新のトピックスまで分かり易くご講義していただきました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
学科説明の後、本学科の非常勤講師でもあります佐口先生に会社説明と施設案内をしていただきました。また、義肢装具の歴史から最新のトピックスまで分かり易くご講義していただきました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
 想像以上にたくさんの義肢装具が製作されていく様子を間近で見学し、驚かれた参加者も多かったのではないでしょうか。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
想像以上にたくさんの義肢装具が製作されていく様子を間近で見学し、驚かれた参加者も多かったのではないでしょうか。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。

 その後、模擬義足の体験や足底圧の計測を行いました。貴重な体験を通して、今まで以上に義肢装具士に興味を持っていただけたと思います。
その後、模擬義足の体験や足底圧の計測を行いました。貴重な体験を通して、今まで以上に義肢装具士に興味を持っていただけたと思います。
お知らせ 義肢装具学科では、随時学校見学、義肢装具製作施設見学ツアーを受付けています。あなたのご都合の良い時間を利用して、学校や義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校にお越し頂き、専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">NEW! 第6回オープンキャンパスの様子をご紹介します。
" target="_blank">NEW! 第6回オープンキャンパスの様子をご紹介します。
 実際の授業で行っている専門的な講義の後は、いよいよ歩行観察です!
「アライメント」について学んだ後に実際の義足歩行を見ると、義肢装具士の調整技術がいかに重要か実感した参加者も多かったようです。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
実際の授業で行っている専門的な講義の後は、いよいよ歩行観察です!
「アライメント」について学んだ後に実際の義足歩行を見ると、義肢装具士の調整技術がいかに重要か実感した参加者も多かったようです。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
 切断者固有のアライメントに合わせて義足を調整すると、見違えるほど歩く姿が変化することを理解していただけたと思います。参加者の皆さんも義肢装具士になったつもりで、歩行観察をしていただきました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
切断者固有のアライメントに合わせて義足を調整すると、見違えるほど歩く姿が変化することを理解していただけたと思います。参加者の皆さんも義肢装具士になったつもりで、歩行観察をしていただきました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。

 2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、障害者スポーツが注目されています。本校でもスポーツ用義足を製作しており、今回のオープンキャンパスでもランニングのデモンストレーションを行いました。
義足ユーザーが軽快に疾走する姿を見て、参加者からは「凄い!」という歓声があがっていました。
モデル様の「走れることがこんなに”楽しい”こととは、足を失う前には思いもしなかった」という感想がとても印象的だったのではないでしょうか。
義肢装具士は、失われた機能や身体の一部を義肢や装具によって補うだけではなく、使用者のQOL(生活の質)を高めることもサポートしています。自分の提供した義肢や装具を付けて、目の前で喜んでもらえる、それが義肢装具士という仕事の魅力のひとつですね!
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、障害者スポーツが注目されています。本校でもスポーツ用義足を製作しており、今回のオープンキャンパスでもランニングのデモンストレーションを行いました。
義足ユーザーが軽快に疾走する姿を見て、参加者からは「凄い!」という歓声があがっていました。
モデル様の「走れることがこんなに”楽しい”こととは、足を失う前には思いもしなかった」という感想がとても印象的だったのではないでしょうか。
義肢装具士は、失われた機能や身体の一部を義肢や装具によって補うだけではなく、使用者のQOL(生活の質)を高めることもサポートしています。自分の提供した義肢や装具を付けて、目の前で喜んでもらえる、それが義肢装具士という仕事の魅力のひとつですね!
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
お知らせ 第10回オープンキャンパスを11月28日(土)に開催いたします!

体験授業では今回ご紹介しました、義足で立つ、歩くうえで重要な「アライメント」もついて学び、実習ではホンモノの義足を組み立てることができます!!適切な継手、足部を選択し指定された長さの義足を組み立てられるか、チャレンジ! オープンキャンパスでは、義肢装具士を体感できる魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています! 入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを再発見してください!
当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩((在校生と一緒に軽食をとりながら何でも聞いちゃおう!) ◇12:00 体験授業(ホンモノの義足を組み立ててみよう!) ◇13:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">NEW! 第5回オープンキャンパスの様子をご紹介します。
" target="_blank">NEW! 第5回オープンキャンパスの様子をご紹介します。
 これまで短下肢装具の採型(義肢装具の装着部位の型を採ること)の体験授業を行ってきましたが、今回はさらに工程を先に進めて、製作体験を行いました。成人サイズを製作するのはさすがに難しいので、赤ちゃんの人形にぴったりと合う大きさのミニ短下肢装具です。
これまで短下肢装具の採型(義肢装具の装着部位の型を採ること)の体験授業を行ってきましたが、今回はさらに工程を先に進めて、製作体験を行いました。成人サイズを製作するのはさすがに難しいので、赤ちゃんの人形にぴったりと合う大きさのミニ短下肢装具です。
 プラスチックの熱成型や切り出しなど、すべての工程を体験することは時間的に難しいため、参加者の皆様にはあらかじめある程度まで工程を進めたものをお渡しして、仕上げの切削加工とバンドの取り付けの製作を体験していいただきました。
プラスチックの熱成型や切り出しなど、すべての工程を体験することは時間的に難しいため、参加者の皆様にはあらかじめある程度まで工程を進めたものをお渡しして、仕上げの切削加工とバンドの取り付けの製作を体験していいただきました。
 プラスチックは施設内にある、実際の義肢装具製作現場でも使用されている専用の機械を使って仕上げの切削加工を行います。きれいに削り終えたら、次はベルトの取り付けです。ケガをしないように、必ず学生スタッフと教員がフォローしますので安心して作業ができます。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
プラスチックは施設内にある、実際の義肢装具製作現場でも使用されている専用の機械を使って仕上げの切削加工を行います。きれいに削り終えたら、次はベルトの取り付けです。ケガをしないように、必ず学生スタッフと教員がフォローしますので安心して作業ができます。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
 何気ない作業に見えますが、ベルトの取り付け位置にも力学的に考慮された理由があることを考えながら行います。ハンマーを使って装具本体にベルトを「カシメ」ます。手元をよく見て、装具本体を叩かないように気を付けて!大事な製品にキズがついてしまいますよ!
何気ない作業に見えますが、ベルトの取り付け位置にも力学的に考慮された理由があることを考えながら行います。ハンマーを使って装具本体にベルトを「カシメ」ます。手元をよく見て、装具本体を叩かないように気を付けて!大事な製品にキズがついてしまいますよ!
 うまく取り付けられましたか?
作業を進める中で、学生スタッフに積極的に質問をして、とても楽しい体験になったと思います。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
うまく取り付けられましたか?
作業を進める中で、学生スタッフに積極的に質問をして、とても楽しい体験になったと思います。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
 完成したミニ短下肢装具はお持ち帰りいただけます!
みなさんきれいに製作できたでしょうか?実際の授業と全く同じことを体験できるのは本校のオープンキャンパスだけです!
この後のオープンキャンパスでも楽しい企画をご用意していますのでぜひご参加ください!!" target="_blank">NEW! オープンキャンパス 体験実習のご紹介
完成したミニ短下肢装具はお持ち帰りいただけます!
みなさんきれいに製作できたでしょうか?実際の授業と全く同じことを体験できるのは本校のオープンキャンパスだけです!
この後のオープンキャンパスでも楽しい企画をご用意していますのでぜひご参加ください!!" target="_blank">NEW! オープンキャンパス 体験実習のご紹介-
姉妹校の中部リハビリテーション専門学校から村上忠洋先生(理学療法士)にご協力いただき、モデル様の理学療法評価を踏まえ、臨床でどのような流れで装具が処方されるのか、本学の専任教員を交えて装具処方の様子を再現しました。
 この実習では村上先生の指導のもと、義肢装具士が行わない様々な理学療法評価や身体検査をモデル様に対して行います。座学で学習はしていますが、実践してみると理解できていなかったことがたくさん見えてきます。やはり実際に体験することで理解がより深まるのが実感できたようです。学生たちの表情も真剣そのものです。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
この実習では村上先生の指導のもと、義肢装具士が行わない様々な理学療法評価や身体検査をモデル様に対して行います。座学で学習はしていますが、実践してみると理解できていなかったことがたくさん見えてきます。やはり実際に体験することで理解がより深まるのが実感できたようです。学生たちの表情も真剣そのものです。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
 次は歩行評価です。裸足で歩いた時に起きる問題は何か、それに対して装具にどのような機能が求められるのか、学生同士でディスカッションします。モデル様に長時間歩行していただくことは難しいため、動画を撮影し、歩行時に生じた異常や関節角度の変化を細かく分析します。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
次は歩行評価です。裸足で歩いた時に起きる問題は何か、それに対して装具にどのような機能が求められるのか、学生同士でディスカッションします。モデル様に長時間歩行していただくことは難しいため、動画を撮影し、歩行時に生じた異常や関節角度の変化を細かく分析します。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
 今回得られた評価をもとに、学生ひとり一人が短下肢装具を製作し、適合まで行います。どのような装具が製作されるか今からとても楽しみです。
次回は適合の様子をレポートします!
今回得られた評価をもとに、学生ひとり一人が短下肢装具を製作し、適合まで行います。どのような装具が製作されるか今からとても楽しみです。
次回は適合の様子をレポートします!
お知らせ 12月20日(日)に今回ご紹介したような脳卒中片麻痺患者様に使用される「短下肢装具」の採型が体験できるオープンキャンパスを開催します!義肢装具士のモノづくりは、患者さんの体を採型するところから始まります、その採型したモデルをもとに個々に合った義肢や装具を製作します。 義肢装具士を体感するチャンス!!
先生はもちろん、在校生と話す機会もありますので、入試情報や学生生活などどんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!
当日のスケジュール ◇12:00 受 付 ◇12:30 学科説明 ◇13:15 休 憩(在校生とおしゃべりして情報収集!) ◇13:30 体験授業(短下肢装具の採型をしてみよう!) ◇15:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇16:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
過去のオープンキャンパスの様子はコチラ
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">NEW! 2年生 下肢装具Ⅱの実習が行われました。
" target="_blank">NEW! 2年生 下肢装具Ⅱの実習が行われました。 -
本学科の非常勤講師としてもお世話になっています、佐口先生に会社説明や施設案内をしていただきました。
 片足でこげる車椅子や電動車椅子など、様々タイプの車椅子に試乗させていただきました。
片足でこげる車椅子や電動車椅子など、様々タイプの車椅子に試乗させていただきました。
 模擬義足を装着してみます。想像以上に義足での歩行は難しく、何度も転びそうになりながら体験していました。
模擬義足を装着してみます。想像以上に義足での歩行は難しく、何度も転びそうになりながら体験していました。
 こちらはフットプリントといって、足裏の印象や輪郭を採る体験をしています。足裏のどの部分に高く圧力がかかっているか、インクの濃淡から分析できます。
こちらはフットプリントといって、足裏の印象や輪郭を採る体験をしています。足裏のどの部分に高く圧力がかかっているか、インクの濃淡から分析できます。
 次は施設内を見学させていただきました。たくさんの社員の方々が多くの義肢装具を製作している様子に少々圧倒されている一年生たち。
次は施設内を見学させていただきました。たくさんの社員の方々が多くの義肢装具を製作している様子に少々圧倒されている一年生たち。
 石膏モデルの修正をする部屋を伺ったところ、偶然にも今年3月卒業した先輩が作業する様子を見学させていただくことができました。入社からおよそ半年あまりでテキパキと手順をこなす姿に感心するばかりでした。
石膏モデルの修正をする部屋を伺ったところ、偶然にも今年3月卒業した先輩が作業する様子を見学させていただくことができました。入社からおよそ半年あまりでテキパキと手順をこなす姿に感心するばかりでした。
 明治38年から続く、松本義肢製作所の資料室にはわが国で古くから作られていた義肢装具がたくさん展示されています。プラスチックの無い時代に作られた木・革・金属製の義肢装具に興味津々です。
明治38年から続く、松本義肢製作所の資料室にはわが国で古くから作られていた義肢装具がたくさん展示されています。プラスチックの無い時代に作られた木・革・金属製の義肢装具に興味津々です。
後期に入り、1年生も座学では新たな科目や実習が始まりました。今回の見学を通して学んだことを今後の学業に活かしてもらいたいと思います。 株式会社松本義肢製作所のみなさん、お忙しい所ありがとうございました!
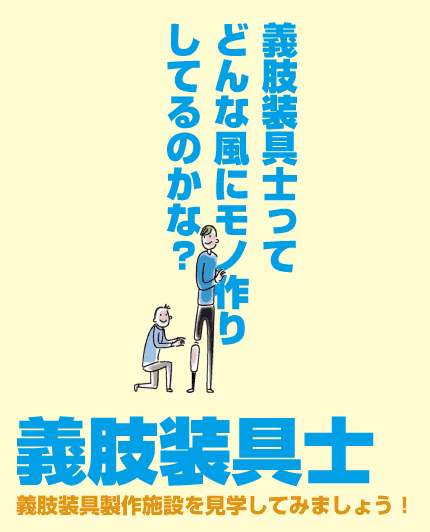
お知らせ 義肢装具学科では、随時学校見学、義肢装具製作施設見学ツアーを受付けています。あなたのご都合の良い時間を利用して、学校や義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校にお越し頂き、専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">NEW! 1年生 (株)松本義肢製作所に見学へ行ってきました。
" target="_blank">NEW! 1年生 (株)松本義肢製作所に見学へ行ってきました。
南海トラフ巨大地震が発生したときに、自分や家族の命を守るために必要な備えは何か、どのように行動するべきなのか具体的にお話いただきました。 南海トラフ巨大地震が発生すると、中村区では震度7が予想され、津波や液状化現象などの被害が想定されています。想像するだけでとても怖いですが、被害を想定し、身の安全を守る備えをしていれば建物や人名などの被害を1/3~1/2に減らすことができるそうです。 身近なところから対策することの大切さを学ぶことができました。 名古屋市消防局のみなさん、大変ありがとうございました。 " target="_blank">NEW! 防災講話が行われました。
国家資格取得後、そのほとんどが民間企業で働いていますが、義肢装具士が企業で働くとはどういうことか、義肢装具士の社会的な役割とはなにか、義肢装具士のこれからについて、など広い範囲にわたってお話いただきました。 今回の講義を通して、“ビジネス”という視点を持つことができたのではないかと思います。講義後には先生にたくさん質問をしている学生の姿が印象的でした。
松本先生、お忙しい中ご講義いただき、ありがとうございました!" target="_blank">NEW! 1年生 松本芳樹先生の特別講義が行われました。
体験授業では義足で立つ、歩くうえで重要な「アライメント」もついて学び、実習ではホンモノの義足を組み立ててみましょう!適切な継手、足部を選択し指定された長さの義足を組み立てられるか、チャレンジ! オープンキャンパスでは、義肢装具士を体感できる魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています! 入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを再発見してください!
当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩((在校生と一緒に軽食をとりながら何でも聞いちゃおう!) ◇12:00 体験授業(ホンモノの義足を組み立ててみよう!) ◇13:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
過去のオープンキャンパスの様子はコチラ
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">11月28日(土) ホンモノの義足を組み立ててみよう!
" target="_blank">11月28日(土) ホンモノの義足を組み立ててみよう!- 見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。
集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院)
*学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。
見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ)
所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。
その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">平成28年度 推薦二次・一般二次入学試験 出願期間のご案内
" target="_blank">平成28年度 推薦二次・一般二次入学試験 出願期間のご案内 -
美代子先生は「日本失語症協議会 第30回全国大会 愛知大会」を
手伝っておられます。
http://japc.info/index.html
失語症患者さんが集まって、支え合って、話をしたり 旅行に行ったりする「友の会」が全国各地にあります。 この全国の「友の会」が一堂に会し、交流を深める会が 10月11日(日曜日)に名古屋で行われます。 この愛知大会の会場を飾るお花を美代子先生と補聴1年生で 一緒に作りました。「こういうボランティアも知ってほしくて・・・」と 美代子先生はおっしゃいます。 直接的なボランティアばかりに目が行きますが、 このような間接的なボランティアもあるのです。
そんな美代子先生の思いは伝わったのでしょうか。 最初から手伝いをしていた学生たちは、 まわりの学生も巻き込んで、ワイワイガヤガヤ 楽しそうにお花をたくさん作ってくれました。 " target="_blank">これもボランティアです
-
カンファレンス場面の見学では、多職種同士で
意見を出し合い、また、スタッフ同士のコミュニケーションが
とても多いことが印象的なようです。
ST訓練場面の見学では、言いたいことを言えない 患者さんの気持ちが学生にも伝わるようです。 失語症の方とうまくコミュニケーションが取れる 先輩STに感動しています。 また、患者さんが楽しそうに訓練をされているのを見て、 「訓練」のイメージが変わったようです。
最後に、STの先生による質疑応答ですが、 相手の気持ちを第一優先に、訓練ばかりを押し 付けないのなど、よいお話をたくさんして いただきました。
学生にとって、得るものの多い刺激的な 半日だったことと思います。 " target="_blank">補聴1年生 鵜飼リハビリテーション病院見学 - 恒例??のサイン会です。先生の周りには黄色い声が飛び交っていました " target="_blank">柴田先生の集中講義が行われました
-
今回の体験授業では「足部の機能解剖」についての講義、そして、足の採型用の特殊なスポンジ「トリッシャム」を使って自分の足の型を採ってみましょう!

さらに、立位時の足の荷重状況を反映する「フットプリント」を採って、自分の足を分析してみましょう!
入試情報や学生生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!
当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 休 憩(在校生と軽食をとりながら情報収集!) ◇12:00 体験授業(自分の足を分析してみよう!) ◇13:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇13:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇14:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
第3回オープンキャンパスの様子はコチラ
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">10月17日(土)足の構造を分析してみよう!
" target="_blank">10月17日(土)足の構造を分析してみよう! -
そして、この研究会は毎夏行っており、そこには2つの特色があります。
まず1つは、 外部から講師を招く講演会とは異なり、卒業生の研究発表を行う点。
全国の学院卒業生たちは、研究活動にも精力的に取り組んでいます。 もちろん、学会発表も活発に行っているのですが、 学会発表というと、発表時間は10分もないことがほとんど。 たくさんの苦労を積み重ねてまとめた発表を、 この研究会では60分かけて披露してもらうことで、 より詳細な内容が学べます。
次に、卒後1年目の新卒者たちで会を運営する点。
講師の先生との事前やり取りや当日の司会などの経験は、 STとして社会人1年生の新卒業生たちにとっ、てきっと今後の役に立つことと思います。 また、先輩が研究発表する姿を間近に見て、それぞれに何かを感じてほしい、とも思っています。
「学ぶ」ことはもちろんなのですが、 先輩のすばらしさを知ったり、自分も頑張ろうと思えたり・・・。
同窓会のイベント、 少しでも卒業生のみんなに役立てば、と願ってやみません。
" target="_blank">若宮ST同窓会研究会盛況でした。 - こちらの参加申し込み用紙に必要事項をご記入の上、FAXにて本学院までご返送下さい。
なお、企業説明会についてご不明な点がございましたら、担当(教務:芥川)までご連絡いただければ幸いに存じます。
□開催日 平成27年10月24日(土)午前9時~午後12時(予定) □会場 専門学校 日本聴能言語福祉学院 5階多目的ホール 〒453-0023 愛知県名古屋市中村区若宮町2丁目14番地 TEL(052)482-8788 FAX(052)471-8703 ※こちらの地図をご参照下さい。 □備考 ※開始15分前には会場内のブースにご着席下さい。 ※本学院の企業説明会は他校の学生も自由に参加できるようになっていますので、予めご了承下さい。 ※ブース形式(長机1800×450 2卓)とさせていただき、企業様ごとのプレゼンテーションの時間は設けておりません。
" target="_blank">平成27年度 企業説明会のご案内 -
いよいよ「平成28年度 推薦一次・一般一次 入学試験」が10月10日(土)と近づいてまいりました!受験生の皆さん、準備は進んでいますか?
今回のオープンキャンパスでは「入試直前対策講座」と題し、いよいよ間近に迫った入学試験の「ポイント」について詳細にお話しします!
入試に備えてしっかりと情報収集をしてください!!
筆記試験の出題傾向と学習の要点、面接試験の重要ポイントなどについて具体的に説明を行います。ポイントをおさえて、ぜひ入学試験のご参考にしてくださいね!!
当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:30 入試直前対策講座(入試に備えてしっかりと情報収集!) ◇12:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇12:30 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇13:00 終 了(予定)
筆記試験の出題傾向と学習の要点、面接試験の重要ポイントなどについて具体的に説明を行います!
まだ進路決定に悩んでいる方も、義肢装具士の仕事、本校の特色についても詳しくお話ししますのでぜひ参加してみてください!!
第3回オープンキャンパスの様子はコチラ
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">9月12日(土)入試直前対策講座!
" target="_blank">9月12日(土)入試直前対策講座! -
体験授業では「筋電義手」の仕組みを学び、電動ハンドを自身の電気信号でコントロールする体験ができます!
また、実際の義手ユーザーにお越しいただき、義手の装着や操作方法について見学することもできます。
義肢装具士を体感するチャンス!!
先生はもちろん、在校生と話す機会もありますので、入試情報や学生生活など、どんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!
当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:15 休 憩(在校生とおしゃべりして情報収集!) ◇11:30 学生企画(在校生による学校生活のプレゼンテーション!) ◇12:00 昼 食(在校生と軽食をとりながら、気軽に何でも聞いちゃおう!) ◇12:30 体験授業(筋電義手に触れてみよう!) ◇15:00 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:00 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇15:30 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
第3回オープンキャンパスの様子はコチラ
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">8月22日(土)筋電義手に触れてみよう!
" target="_blank">8月22日(土)筋電義手に触れてみよう! - " target="_blank">保育実習、頑張ってます!
- http://wakamiyast.blog25.fc2.com/
<申込> 件名を「H27研究会申し込み」とし、メールまたは FAXにて「卒学科・卒期・氏名・所属」を明記し、 お申し込みください。 下記からも申し込みできます。 http://form1.fc2.com/form/?id=595041 締め切りは8/21(金)です。
若宮ST同窓会 FAX 052-471-8703 メール st@kzan.jp " target="_blank">若宮ST同窓会・研究会のお知らせ -
今年4月からスタートした聴能言語学科の学内実習。 早いもので半分の4か月がたちました。 すでに臨床実習1か所目を終えて、学内実習に戻ってきた学生もいます。 病院での臨床実習で学んだことを学内実習でいかす、 そんな学生たちの成長や変化を追えるのも、 私たちにとっては嬉しいことです。
ちょうど中間点の今、自らを振り返り、 残りの実習期間をより実り多いものにしてほしいと思います。
" target="_blank">学内実習真っ最中です。 -
電車に揺られること約2時間で鳥羽駅に到着。
まずは鳥羽水族館に行きました。
 三重と言ったら伊勢うどん!?
三重と言ったら伊勢うどん!?
 水族館ではしゃぐ学生
水族館ではしゃぐ学生
 その後はホテルで夕ご飯
その後はホテルで夕ご飯
夜は恒例のレクリエーション大会 今年は伝言ゲーム、ハンカチ落とし、だるまさんが転んだ、など等・・・
 伝言ゲームではしゃぐ教員と冷静な学生
伝言ゲームではしゃぐ教員と冷静な学生
当日は偶然にも第60回鳥羽みなとまつりが開かれ、花火鑑賞もしました その後はみんなで花火大会!!
その後はみんなで花火大会!!
次の日はミキモト真珠島に行って、名古屋へ。
 帰りの電車の中では数日後のテスト対策・・・
帰りの電車の中では数日後のテスト対策・・・
いよいよ来週からは1週間の見学実習がはじまります。 今回発揮されたチームワークで、みんなで乗り切っていきましょう。 " target="_blank">学外授業に行ってきました!! -
体験授業では実際の義足ユーザーをお招きし「義足の歩行観察」を行います!
スポーツ用義足によるデモンストレーションも行います!
義肢装具士を体感するチャンス!!
先生はもちろん、在校生と話す機会もありますので、入試情報や学生生活など、どんどん質問して、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!
当日のスケジュール ◇10:00 受 付 ◇10:30 学科説明 ◇11:15 休 憩(在校生とおしゃべりして情報収集!) ◇11:30 学生企画(在校生による学校生活のプレゼンテーション!) ◇12:00 昼 食(在校生と軽食をとりながら、気軽に何でも聞いちゃおう!) ◇12:30 体験授業(義足ユーザーの歩行を観察してみよう!) ◇15:00 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇15:00 個別相談(入試のこと、一人暮らしのことなど何でも相談!) ◇15:30 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます。 ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
過去のオープンキャンパスの様子はコチラ
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">7月25日(土)義足ユーザーの歩行を観察してみよう!
" target="_blank">7月25日(土)義足ユーザーの歩行を観察してみよう! -
ある日、補聴言語学科の学生達が 「先生!これ、小児の訓練で使えるかな?」と牛乳パックで 作った竹とんぼ、ブーメランを持ってきてくれました。 訓練教材として作成したのではなく、他の機会にたまたま作成を して、「教材で使えるかも!」と思って持ってきてくれたそうです。
後日、別件でその学生のレポートを読んでいると 「日常生活の中で、『これ、訓練で使えるかな』と意識することが 増えました。」という言葉がありました。
私自身も言語聴覚士になって、生活のあらゆる場面で 「これ、この患者さんに使えるかも!」と考えるようになりました。 いわゆる『職業病』です。
学生の頃から、訓練を見据えて生活が出来るなんて本当に素晴らしい! 患者様の為に頑張れる言語聴覚士になれると信じています。 実習頑張って下さいね! " target="_blank">訓練材料をもらいました -
学生会のリーダーの号令とともに、元気よく大掃除が始まりました!この日は早朝から土砂降りの雨でしたが、大掃除が始まる直前に雨も止み、大掃除日よりとなりした。
 昼食は学生会スタッフと先生たちが早朝から集まって作ってくれたカレーを学生全員で食べました!
昼食は学生会スタッフと先生たちが早朝から集まって作ってくれたカレーを学生全員で食べました!
 蒸し暑い中、頑張って大掃除した後のカレーは、格別に美味しかったですね!
学生の中には4杯もおかわりした学生がいたようです。
蒸し暑い中、頑張って大掃除した後のカレーは、格別に美味しかったですね!
学生の中には4杯もおかわりした学生がいたようです。
夏休みに入ると1、2年生は海合宿へ。 2年生はいよいよ初めての臨床実習が始まります。 学生それぞれに目標を持った夏休みが始まります!" target="_blank">NEW! 夏休み前の大掃除が行われました。 -
採型時の膝関節角度を基にソケットと足部を適切な位置に設定します。差金や重錘を用いて理論通りに義足が組み立てられているか確認します。
 義足の組み立てにはmm単位の調整が必要となります。何度も先生に確認してもらい、問題があった場合はその理由を考えます。問題の原因を解明し、繰り返し修正を重ねながら義足を組立てて行きます。
義足の組み立てにはmm単位の調整が必要となります。何度も先生に確認してもらい、問題があった場合はその理由を考えます。問題の原因を解明し、繰り返し修正を重ねながら義足を組立てて行きます。
 次に義足の仮合わせとなります。
仮合わせでは、実際に義足を装着してもらい、静止立位時あるいは歩行時の義足の不具合を調整します。
※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。
次に義足の仮合わせとなります。
仮合わせでは、実際に義足を装着してもらい、静止立位時あるいは歩行時の義足の不具合を調整します。
※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。
 まずはスタティックアライメントです。
両足で立った状態で、不安定感やソケット内部の痛みなどが無く、安定的に立てるように調整を行います。原因と対処方法が理論的に解っていても、これを実際に判断し、的確に対処することは非常に難しいです。
まずはスタティックアライメントです。
両足で立った状態で、不安定感やソケット内部の痛みなどが無く、安定的に立てるように調整を行います。原因と対処方法が理論的に解っていても、これを実際に判断し、的確に対処することは非常に難しいです。
 さあ、いよいよ学生の仮合わせです。
自身の目で問題点を判断することも大切ですが、モデル様との対話から情報を引き出すことも重要です。ソケット内部の痛みは外から観察していても判断できません。義肢装具士にコミュニケーション能力が必要不可欠な理由はここにあります。
※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。
さあ、いよいよ学生の仮合わせです。
自身の目で問題点を判断することも大切ですが、モデル様との対話から情報を引き出すことも重要です。ソケット内部の痛みは外から観察していても判断できません。義肢装具士にコミュニケーション能力が必要不可欠な理由はここにあります。
※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。
 この実習を最後に2年生はいよいよ8月から初めての臨床実習となります。
今回学習した患者様への応対方法や義足の調整方法、そして約1年半学んだ知識や製作技術を十分に発揮し有意義な臨床実習にして下さいね!" target="_blank">NEW! 2年生 下腿義足の適合評価が行われました。
この実習を最後に2年生はいよいよ8月から初めての臨床実習となります。
今回学習した患者様への応対方法や義足の調整方法、そして約1年半学んだ知識や製作技術を十分に発揮し有意義な臨床実習にして下さいね!" target="_blank">NEW! 2年生 下腿義足の適合評価が行われました。 -
まずは香川先生より、大腿義足の仮合わせをする際の流れ、注意事項について細かく説明がありました。
※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。
 今回製作した大腿義足は吸着式という懸垂方法のため、ソケットの中に切断端を直接挿入して義足を使用します。そのため、ソケット内面に皮膚を傷つけるような突起がないこと、義足を構成する各パーツのネジに緩みがないことを確認するよう説明がありました。
今回製作した大腿義足は吸着式という懸垂方法のため、ソケットの中に切断端を直接挿入して義足を使用します。そのため、ソケット内面に皮膚を傷つけるような突起がないこと、義足を構成する各パーツのネジに緩みがないことを確認するよう説明がありました。
 これは、大腿部と下腿部の長さを確認しています。義足長が健側の下肢長と同じでも、それぞれの長さが異なっていると座った時に膝の高さが揃わないことがあります。義足の目的は歩行だけでなく、外観の復元も忘れてはいけません。
※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。
これは、大腿部と下腿部の長さを確認しています。義足長が健側の下肢長と同じでも、それぞれの長さが異なっていると座った時に膝の高さが揃わないことがあります。義足の目的は歩行だけでなく、外観の復元も忘れてはいけません。
※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。
 義足膝継手を上手く調整できない時は、先生が最適な調整をアドバイスしてくれます!
この学生は疑問点を整理して、的確な専門用語を使って質問していました。現在起きている義足の問題点を把握し、専門用語を用いて他者に解り易く説明することは、義足調整を理解する上で重要なスキルです!
義足膝継手を上手く調整できない時は、先生が最適な調整をアドバイスしてくれます!
この学生は疑問点を整理して、的確な専門用語を使って質問していました。現在起きている義足の問題点を把握し、専門用語を用いて他者に解り易く説明することは、義足調整を理解する上で重要なスキルです!
 常にモデル様の状態に気を配りながら仮合わせを行います。
大腿義足使用者は残存している切断端と股関節の筋力で膝継手をコントロールしているため、あまり長い時間歩いてもらうことができません。仮合わせでは迅速な対応と正確な調整が必要となります。
常にモデル様の状態に気を配りながら仮合わせを行います。
大腿義足使用者は残存している切断端と股関節の筋力で膝継手をコントロールしているため、あまり長い時間歩いてもらうことができません。仮合わせでは迅速な対応と正確な調整が必要となります。
3年生の前期の大腿義足の実習は、これで最後となります。 次回は、夏休み明けの9月から坐骨収納型(IRC)ソケットの製作実習が始まります。" target="_blank">NEW! 3年生 大腿義足の適合評価が行われました。 -
講師は川村義肢株式会社「工房アルテ」の福島有佳子先生です。
福島先生は日本におけるこの分野の第一人者。「人工ボディ」の製作工程について分かり易くご講義いただきました。
 技術面だけでなく、技術者として、社会人として、仕事に対する取り組み方や患者様への対応など幅広い講義内容に学生たちも興味津々です!
技術面だけでなく、技術者として、社会人として、仕事に対する取り組み方や患者様への対応など幅広い講義内容に学生たちも興味津々です!
 続いては実習の様子です。これは耳(義耳)の採型を行っているところです。「人工ボディ」の採型には、義肢装具士が通常使用しているギプス包帯ではなく、歯科などで歯型の採型に用いる印象材を使用します。
続いては実習の様子です。これは耳(義耳)の採型を行っているところです。「人工ボディ」の採型には、義肢装具士が通常使用しているギプス包帯ではなく、歯科などで歯型の採型に用いる印象材を使用します。
 これは顔面の採型をしているところです。印象材で顔全体を覆うため、採型中でも呼吸ができるようにストローを咥えています。
さあ、きれいな採型ができるでしょうか?
これは顔面の採型をしているところです。印象材で顔全体を覆うため、採型中でも呼吸ができるようにストローを咥えています。
さあ、きれいな採型ができるでしょうか?
 印象材を顔面から取り外すと、眉毛やまつ毛、皮膚のシワまで鮮明に採型されています。
印象材を顔面から取り外すと、眉毛やまつ毛、皮膚のシワまで鮮明に採型されています。
 完全硬化した印象材に石膏を流し入れ、陽性モデルを取り出します。爪や指のシワ、血管など細かく採型されていますね。実際にはここからシリコン材料を用いて「人工ボディ」を製作して行きます。
完全硬化した印象材に石膏を流し入れ、陽性モデルを取り出します。爪や指のシワ、血管など細かく採型されていますね。実際にはここからシリコン材料を用いて「人工ボディ」を製作して行きます。
 福島先生がご専門とされている「人工ボディ」は義肢装具の中でも特殊な専門性の高い分野となるため、例年、特別講義を楽しみにしている学生が沢山います。
福島先生、お忙しいところ今年もご講義いただき、誠にありがとうございました!" target="_blank">NEW! 2年生 「人工ボディ」の特別講義が行われました。
福島先生がご専門とされている「人工ボディ」は義肢装具の中でも特殊な専門性の高い分野となるため、例年、特別講義を楽しみにしている学生が沢山います。
福島先生、お忙しいところ今年もご講義いただき、誠にありがとうございました!" target="_blank">NEW! 2年生 「人工ボディ」の特別講義が行われました。 -
10:00 受付
「おはようございます!」正門前で学生スタッフが元気に参加者をお迎えしています。元気な挨拶はPO学科学生のトレードマーク!
気持ちの良い挨拶から、いよいよオープンキャンパスの始まりです!
 会場では開始前から学生スタッフが参加者と楽しそうに歓談をしていました。とてもリラックスした雰囲気に、参加者からも自然に笑みがこぼれていました!
会場では開始前から学生スタッフが参加者と楽しそうに歓談をしていました。とてもリラックスした雰囲気に、参加者からも自然に笑みがこぼれていました!
 10:25 開会
教務主任より、開会のご挨拶がありました。
この日は、東海地域はもちろん、全国から大勢の皆さんにご参加いただきました。2020年の東京パラリンピックの開催決定をきっかけに、義肢装具士に興味を持たれる方が増え、オープンキャンパスへの参加者も段々と増えてきました!
10:25 開会
教務主任より、開会のご挨拶がありました。
この日は、東海地域はもちろん、全国から大勢の皆さんにご参加いただきました。2020年の東京パラリンピックの開催決定をきっかけに、義肢装具士に興味を持たれる方が増え、オープンキャンパスへの参加者も段々と増えてきました!
 10:30 学科説明
義肢とは?装具とは?義肢装具士の業務とは?そして、義肢装具学科について教員から詳しい説明がありました。また、「専門学校で義肢装具を学ぶこと」のメリットについても説明があり、進路決定の大きなヒントになったのではないでしょうか?
10:30 学科説明
義肢とは?装具とは?義肢装具士の業務とは?そして、義肢装具学科について教員から詳しい説明がありました。また、「専門学校で義肢装具を学ぶこと」のメリットについても説明があり、進路決定の大きなヒントになったのではないでしょうか?
 11:15 休憩
進路について悩んでいること、学校生活について気になっていること、入試に向けての具体的な準備など、学生スタッフが少しだけ先輩の立場で相談に乗ってくれます!とにかく、オープンキャンパスに参加して、先輩たちにいろいろ聞いて下さいね!
11:15 休憩
進路について悩んでいること、学校生活について気になっていること、入試に向けての具体的な準備など、学生スタッフが少しだけ先輩の立場で相談に乗ってくれます!とにかく、オープンキャンパスに参加して、先輩たちにいろいろ聞いて下さいね!

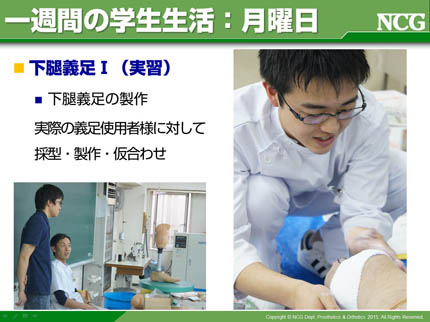 11:30 学生企画 『一週間の学生生活』
今回は学生を代表して、2年生の成瀬君が学校生活や義肢装具を学ぶことの楽しさについてプレゼンテーションしてくれました。
成瀬君、講義の合間のプレゼン準備、お疲れ様でした!
11:30 学生企画 『一週間の学生生活』
今回は学生を代表して、2年生の成瀬君が学校生活や義肢装具を学ぶことの楽しさについてプレゼンテーションしてくれました。
成瀬君、講義の合間のプレゼン準備、お疲れ様でした!
 12:00 ランチタイム
参加者の皆さんと学生スタッフとのランチタイムです。ここでも参加者の皆さんからいろいろな質問が出ていました!特に、保護者の方からは「学生さんから学校に関する率直なお話が聞けて、たいへん参考になりました!」と、ランチタイムは好評です!
12:00 ランチタイム
参加者の皆さんと学生スタッフとのランチタイムです。ここでも参加者の皆さんからいろいろな質問が出ていました!特に、保護者の方からは「学生さんから学校に関する率直なお話が聞けて、たいへん参考になりました!」と、ランチタイムは好評です!
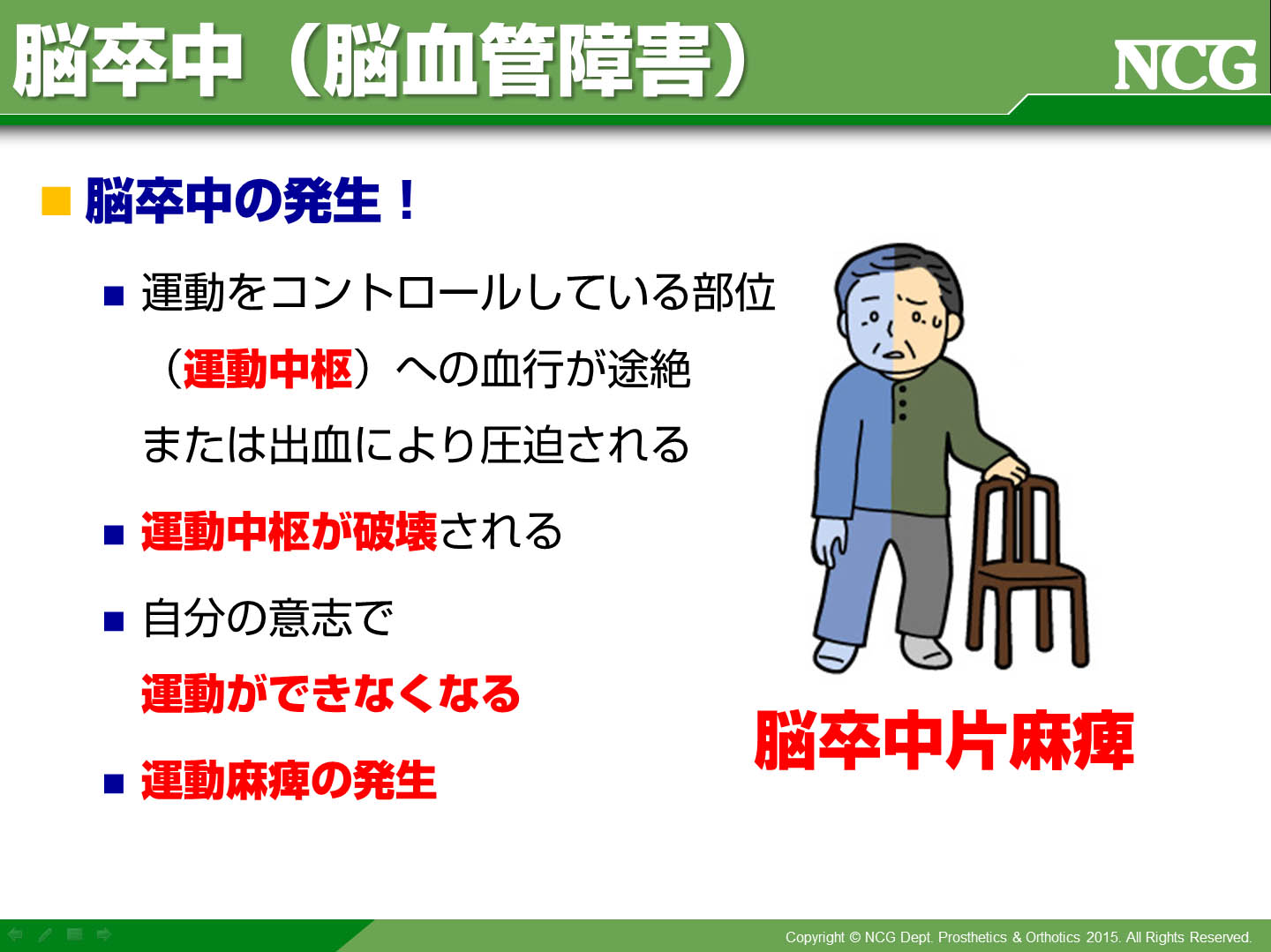 12:30 体験授業
今回の体験授業のテーマは短下肢装具の採型ということで、まずは短下肢装具が適応となる疾患について講義が行われました。病態の説明の後は、脳卒中方麻痺患者様の装具なしと装具ありの歩行を動画で観察します。装具装着による歩容の変化に参加者の皆さんも驚いていました。
12:30 体験授業
今回の体験授業のテーマは短下肢装具の採型ということで、まずは短下肢装具が適応となる疾患について講義が行われました。病態の説明の後は、脳卒中方麻痺患者様の装具なしと装具ありの歩行を動画で観察します。装具装着による歩容の変化に参加者の皆さんも驚いていました。
 参加者の皆さんに体験していただく、「短下肢装具」の採型のデモンストレーションです。教員が手際よくギプス包帯を巻く様子に、参加者の皆さんは興味津々で見入っていました!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
参加者の皆さんに体験していただく、「短下肢装具」の採型のデモンストレーションです。教員が手際よくギプス包帯を巻く様子に、参加者の皆さんは興味津々で見入っていました!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
 さあ、今度は参加者の皆さんが採型にチャレンジします!
一人ずつ学生スタッフがサポートしながら、義肢装具士の仕事を実体験してもらいます。ギプス包帯は時間が経つにつれて固まって行きます。見ていると簡単そうな作業でも、やってみると意外に難しく奥が深いことが解っていただけましたか?
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
さあ、今度は参加者の皆さんが採型にチャレンジします!
一人ずつ学生スタッフがサポートしながら、義肢装具士の仕事を実体験してもらいます。ギプス包帯は時間が経つにつれて固まって行きます。見ていると簡単そうな作業でも、やってみると意外に難しく奥が深いことが解っていただけましたか?
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
 採型という工程の中に、いくつもの手順があることを理解していただけたようです。しかし、皆さんとっても綺麗に採型していますね!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
採型という工程の中に、いくつもの手順があることを理解していただけたようです。しかし、皆さんとっても綺麗に採型していますね!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
 一番難しいのは、ギプス包帯を切開する工程です。切開するためのガイドとなるヒモを切ってしまい、悪戦苦闘する場面も見られましたが、参加者の皆さんは諦めずに何回も挑戦してくれました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
一番難しいのは、ギプス包帯を切開する工程です。切開するためのガイドとなるヒモを切ってしまい、悪戦苦闘する場面も見られましたが、参加者の皆さんは諦めずに何回も挑戦してくれました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
 さあ、出来上がったモデルを比べてみましょう!何回か挑戦するうちに、皆さんみるみる上達して綺麗な陰性モデルを採型することができました。
記念に陰性モデルを持ち帰った参加者の方もいて、体験授業を楽しんでいただけたのではないかと思います。
参加者の皆さん、お疲れ様でした!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
さあ、出来上がったモデルを比べてみましょう!何回か挑戦するうちに、皆さんみるみる上達して綺麗な陰性モデルを採型することができました。
記念に陰性モデルを持ち帰った参加者の方もいて、体験授業を楽しんでいただけたのではないかと思います。
参加者の皆さん、お疲れ様でした!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
参加者(保護者)の声 初めて採型を体験してみて、最初は焦ってしまいましたが、回数を重ねるたびに慣れて、3回目にはとても綺麗にできました。誉めてもらうことが出来てうれしかったです。また、同学年の参加者とも話が出来てうれしかったです。 (高校3年生)
ここに来ないとできない貴重な体験ばかりでした。分からなかったことが知れて、より義肢装具士になりたいと思いました。 (高校3年生)
先輩がとても優しくて、話しやすくて良い方々だった。絶対ここに入学して、もっと先輩と話をしたいと思いました。 (高校3年生)
義肢装具士の仕事を少しでも体験できて楽しかったです。とても勉強になりました。 (高校3年生)
採型はとても難しかったですが、とても親切に教えていただき、入学したい気持ちが高まりました。 (高校2年生)
採型がとても楽しかった。回数を重ねるごとに綺麗に作れて、完成した時の達成感がすごかったです。 (高校2年生)
在学生のお話しが直接聞けたことがとても良かったです。採型も3回も体験させてもらい、勉強になりました。 (保護者)
とても良い体験ができました。在校生や先生方の雰囲気もアットホームな感じで、子供を預けることの心配がなくなりました。 (保護者)
このほかにも、たくさんの感想をいただきました。ありがとうございました。 義肢装具士の業務内容について少しでもご理解いただき、進路決定のヒントにしてくださいね! 次回もぜひ、ご参加ください!" target="_blank">NEW! 第3回オープンキャンパスの様子をご紹介します! -
東海地区唯一の義肢装具士養成校。
実学を通して義肢装具の採型・製作・適合の理論と技術を習得し、臨床で活躍できる人材を目指します。高い国家試験合格率と就職実績で、卒業生は全国で活躍しています。 自分の仕事が、必要としている方に目の前で喜ばれる、それが義肢装具士です。
モノづくりで医療を支えるプロフェッショナルを育成します。
当日のスケジュール ◇18:00 受 付 ◇18:30 学科説明(義肢装具士や学科の特色など詳しくご説明!) ◇19:15 休 憩 ◇19:30 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!) ◇19:30 個別相談(授業、入試、就職のことなど何でも相談!) ◇20:00 終 了(予定)
義肢装具士という資格やその仕事について詳しくご説明します! ホントの授業に参加して、義肢装具士を体感するチャンス!
土曜日開催のオープンキャンパスに参加できない社会人の方、お仕事の帰りに気軽に参加してみませんか? ・義肢装具士を目指そうとしている方、興味のある方なら、どなたでも参加できます! ・保護者の方やご友人とご一緒に参加して、今後の進路をじっくりと検討してください。
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください!
過去のオープンキャンパスの様子はコチラ
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">7月15日(水)18時~ 学校見学会のお知らせ
" target="_blank">7月15日(水)18時~ 学校見学会のお知らせ -
実習前に検査の練習、練習、練習
さて先週の土曜日に、1週目の実習を終えた学生が何人か学校に 来ていました。 ある子は実習先で出された課題を調べに・・・。 ある子は症例の相談をしに・・・。 ある子は弱音を吐きに・・・。 弱音を吐きに来た子も、まだ始まったばかりでよく分かっていない 様子でした。
これから週を重ねるにつれ、課題量や患者さんに実施することが 増えていきます。 大変なことも増えてきますが、その分言語聴覚士としてのやりがいを 発見することになるでしょう。
毎年実習から帰ってきた学生を見るたびに、「大きく成長したなぁ」と 感じます。 多くのことを学んで、また元気な姿で学校に帰ってきてくださいね。 " target="_blank">臨床実習開始です!! -
企画・運営を担う2年生は、早々から調理実習室にこもり、 炊き込みご飯を作るもの、豚汁の野菜を切るもの、から揚げを揚げる ものと、みんなワイワイ、がやがや、楽しみながら作りました。 から揚げ(下ごしらえ、味付けは日置先生)はまかせておけ~
から揚げ(下ごしらえ、味付けは日置先生)はまかせておけ~
洗い物はまかせておけ~
そんな心のこもった料理を頂きながら、各テーブルでは会話が 弾みます。 その後、下級生と教員からの応援・激励の言葉があり、実習に赴く 3年生が抱負を語り、会は終了しました。 抱負を語る3年生
抱負を語る3年生
実習では楽しいことも、大変なこともあると思いますが、 また2か月後に元気な顔をみせて下さいね。

 大人気! 炊き込みご飯。 すぐに売り切れでした。
おかわりしたかった~(by 日置先生)
大人気! 炊き込みご飯。 すぐに売り切れでした。
おかわりしたかった~(by 日置先生)
 なんと味噌から手作りです!杉浦先生の豚汁。
なんと味噌から手作りです!杉浦先生の豚汁。
 2年生から3年生へプレゼント贈呈
2年生から3年生へプレゼント贈呈
 栄養ドリンクとクッキー メッセージ付き!
栄養ドリンクとクッキー メッセージ付き!
 2年生、企画・運営おつかれさまでした!
" target="_blank">実習がんばって下さい会
2年生、企画・運営おつかれさまでした!
" target="_blank">実習がんばって下さい会 -
前回製作したプラスチック製の短下肢装具とは材質が異なり、今回は金属製の短下肢装具を製作して行きます。金属材料の性質をよく理解し、それぞれの加工法を一つずつ習得して行って下さいね!
 まずは、装具の土台となる“あぶみ”の加工をします。
数ミリのズレも許されないので、加工前の設定がとっても大切です!
まずは、装具の土台となる“あぶみ”の加工をします。
数ミリのズレも許されないので、加工前の設定がとっても大切です!
 金属の曲げ加工には、ハッカーという特殊な工具を使用します。このハッカーが正しく使われていないと金属支柱に捻れが生じるため、学生たちの表情も真剣です!
金属の曲げ加工には、ハッカーという特殊な工具を使用します。このハッカーが正しく使われていないと金属支柱に捻れが生じるため、学生たちの表情も真剣です!
 両方の支柱が平行な位置関係にあるか、捻じれはないか、確認をしているところです。ここの微調整がなかなか難しいのですが、頑張って習得して下さいね!
両方の支柱が平行な位置関係にあるか、捻じれはないか、確認をしているところです。ここの微調整がなかなか難しいのですが、頑張って習得して下さいね!
 支柱の曲げ加工が終わったら、次は“半月(はんげつ)”の加工です。装具全体をいわゆる閉じた構造にするため、ここでの接合部の曲げ加工がポイントとなります!
支柱の曲げ加工が終わったら、次は“半月(はんげつ)”の加工です。装具全体をいわゆる閉じた構造にするため、ここでの接合部の曲げ加工がポイントとなります!
金属の曲げ加工は、コツを掴むまで学生たちの試行錯誤が続きます。 まずは作業の目的を理論的に理解し、次に自身の手を通して工程を体感することが重要ですね!" target="_blank">NEW! 1年生 両側支柱短下肢装具の製作が始まりました。 -
前回仮合わせを行ったチェックシューズを基に、樹脂製のラスト(木型)を起こし、これに甲革(アッパー)を吊り込んで靴に仕上げていきます!
この学生は、靴のトップを左右対称にデザインしているところです。
 甲革(アッパー)の吊り込みを始めると、途中で手を止めることができません。
1回だけの失敗が許されない作業のため、学生たちは教員のデモンストレーションを食い入るように観察しています。
甲革(アッパー)の吊り込みを始めると、途中で手を止めることができません。
1回だけの失敗が許されない作業のため、学生たちは教員のデモンストレーションを食い入るように観察しています。
 さあ、いよいよ実践です!学生たちは製靴専用の支持プライヤ(通称:ワニぐちプライヤ)を使って甲革(アッパー)を吊り込んでいます。靴の外観や強度に関わる大事な工程ですので、しわが無いよう美しく吊り込んで下さいね!
さあ、いよいよ実践です!学生たちは製靴専用の支持プライヤ(通称:ワニぐちプライヤ)を使って甲革(アッパー)を吊り込んでいます。靴の外観や強度に関わる大事な工程ですので、しわが無いよう美しく吊り込んで下さいね!
 吊り込み作業が終わりました。だんだん靴の形になってきましたね!
吊り込み作業が終わりました。だんだん靴の形になってきましたね!
 残るは靴底の加工です。
靴底のデザインを決める重要な工程ですので、最後まで慎重に作業しましょう!
残るは靴底の加工です。
靴底のデザインを決める重要な工程ですので、最後まで慎重に作業しましょう!
 最後にヒールを取り付けます。左右のデザインや高さが同じになるように設定します。
最後にヒールを取り付けます。左右のデザインや高さが同じになるように設定します。
 靴底とヒールの段差を整えます。せっかく美しく吊り込んだ甲革(アッパー)を傷つけないよう丁寧に仕上げます。
靴底とヒールの段差を整えます。せっかく美しく吊り込んだ甲革(アッパー)を傷つけないよう丁寧に仕上げます。
 これで全ての工程が終わり、ようやく靴型装具が完成しました!
さて、自分の足に合わせて作った靴の履き心地はどうでしょうか?
これで全ての工程が終わり、ようやく靴型装具が完成しました!
さて、自分の足に合わせて作った靴の履き心地はどうでしょうか?
 最後はクラスメイトの前で歩行評価を行います。陽性モデルの修正箇所やヒールの設定によって歩行に大きく影響が出るため、装着時の歩行を細かく観察することが重要です。
最後はクラスメイトの前で歩行評価を行います。陽性モデルの修正箇所やヒールの設定によって歩行に大きく影響が出るため、装着時の歩行を細かく観察することが重要です。
 2年生は8月中旬から、初めての臨床実習が始まります。
彼らは臨床実習の期間中は自身が製作した靴を必ず履いていますので、ぜひ彼らの足元に注目して下さい!
2年生は8月中旬から、初めての臨床実習が始まります。
彼らは臨床実習の期間中は自身が製作した靴を必ず履いていますので、ぜひ彼らの足元に注目して下さい!
義肢装具学科では、“靴づくりのできる義肢装具士”の実践教育を行っています。靴づくりに興味のある方は、ぜひ今後のオープンキャンパスにお越し下さい!" target="_blank">NEW! 2年生 靴型装具が完成しました。 -
この日までの研究の進捗状況を熱心に発表する3年生。
研究テーマの背景、目的、研究手法を後輩たちに分かり易く発表していました。
 それぞれの研究グループに対して、1、2年生からたくさんの質問が出ていました!
それぞれの研究グループに対して、1、2年生からたくさんの質問が出ていました!
 全ての研究グループの発表が終わった後、義肢装具学科顧問の髙見先生より総評を頂きました。
全ての研究グループの発表が終わった後、義肢装具学科顧問の髙見先生より総評を頂きました。
教務の先生方や同級生、後輩たちから様々な質問や意見をもらい、是非とも今後の研究の参考にして行って下さい!
さて、3年生はいよいよ8週間の臨床実習が始まります。 最高学年の学生として、昨年とは違う視点で義肢装具や患者様に向き合ってくれると期待しています!
大きな成果を持って学院に帰ってくることを楽しみにしています! ガンバレ3年生!" target="_blank">NEW! 3年生 卒業研究中間報告会が行われました。 -
奥村社長様と西井部長様に会社の概要をご説明いただき、いよいよ見学がスタートです。
 まずは、広い社内を部署ごとにご案内いただきました。
患者様が使われる製品についてどのような工程で製作されているのか、分かり易くご説明いただきました。
また、開発中のリハビリテーション機器についてもご紹介いただき、製作されている製品の多さに学生たちも興味津々でした!
まずは、広い社内を部署ごとにご案内いただきました。
患者様が使われる製品についてどのような工程で製作されているのか、分かり易くご説明いただきました。
また、開発中のリハビリテーション機器についてもご紹介いただき、製作されている製品の多さに学生たちも興味津々でした!
 続いて、本社工場に併設されている「CAD/CAMセンター」に移動し、CAD/CAMシステムを用いた装具製作について説明をしていただきました。
続いて、本社工場に併設されている「CAD/CAMセンター」に移動し、CAD/CAMシステムを用いた装具製作について説明をしていただきました。
 ここでは学生たちの体を実際にスキャンニングしてもらい、パソコン上で陽性モデル修正、トリミングライン設定などをデモンストレーションしていただきました。
ここでは学生たちの体を実際にスキャンニングしてもらい、パソコン上で陽性モデル修正、トリミングライン設定などをデモンストレーションしていただきました。
 試しに、顔面のスキャンニングもさせてもらいました。
瞬時に顔の輪郭や表情がそのまま再現されていく様子に、学生たちからは驚きの声が上がっていました!
試しに、顔面のスキャンニングもさせてもらいました。
瞬時に顔の輪郭や表情がそのまま再現されていく様子に、学生たちからは驚きの声が上がっていました!
 このCAD/CAMセンターにも、やはり義肢装具士の存在は欠かせないようです。ここでも本校の卒業生が、オペレーターとして大活躍していました。
長尾先輩、後輩たちに熱心にご説明いただき、ありがとうございました!
このCAD/CAMセンターにも、やはり義肢装具士の存在は欠かせないようです。ここでも本校の卒業生が、オペレーターとして大活躍していました。
長尾先輩、後輩たちに熱心にご説明いただき、ありがとうございました!
 ミーリングマシンに発泡ウレタンのベースをセットし、約15分で陽性モデルが削り終わります。手作業であれば通常1時間以上かかる作業が、みるみるうちに出来上がって行きます!
ミーリングマシンに発泡ウレタンのベースをセットし、約15分で陽性モデルが削り終わります。手作業であれば通常1時間以上かかる作業が、みるみるうちに出来上がって行きます!
 見学の最後に、新しくできた「CAD/CAMセンター」の前で記念撮影。
この日は梅雨のあいにくのお天気でしたが、奥村社長様、西井部長様には長時間にわたってご対応いただき、ありがとうございました!
学生たちはこれを機会に、学内の勉強だけでなく、現在、臨床でどのようなことが行われているのかについても興味を持ってもらえればと思います。" target="_blank">NEW! 1年生 東名ブレース株式会社へ見学に行きました。
見学の最後に、新しくできた「CAD/CAMセンター」の前で記念撮影。
この日は梅雨のあいにくのお天気でしたが、奥村社長様、西井部長様には長時間にわたってご対応いただき、ありがとうございました!
学生たちはこれを機会に、学内の勉強だけでなく、現在、臨床でどのようなことが行われているのかについても興味を持ってもらえればと思います。" target="_blank">NEW! 1年生 東名ブレース株式会社へ見学に行きました。 - 前回レポートをした陽性モデル修正の後、切断端を収納するソケットの製作を行いました。今回は、ソケット・膝継手・足部をひとつに組み立て、いよいよ大腿義足として完成させます。
「組み立て」といっても、単純に各構成要素を連結するだけではなく、人それぞれが持つ固有の「アライメント※」を正確に再現する必要があります。この固有のアライメントを1本のラインで表したものを“基準線”と言います。基準線が正しく設定されていることが、義足の組み立てではとても重要です。
2年次の下腿義足製作に続き、大腿義足のアライメント理論もしっかりと習得しましょう!
※アライメント:足部に対する膝継手およびソケットの相対的位置関係。作業台の上で義足を組み立てる工程をベンチアライメントといいます。
 まずは足部と膝継手を連結します。義足歩行では、足部に対する膝継手の位置が立位や歩行時の安定性に影響してきます。
まずは足部と膝継手を連結します。義足歩行では、足部に対する膝継手の位置が立位や歩行時の安定性に影響してきます。
 基準線は、膝継手軸の15mm前方を通過させなければいけません。手元の1度のズレはさほど影響が無いように見えますが、距離が離れるとこれが大きな誤差となります。少しのズレも無い、正確な作業が要求されます。
基準線は、膝継手軸の15mm前方を通過させなければいけません。手元の1度のズレはさほど影響が無いように見えますが、距離が離れるとこれが大きな誤差となります。少しのズレも無い、正確な作業が要求されます。
 次に、組み立てた膝継手以下とソケットを連結します。いよいよ大腿義足のカタチができあがってきました!モノづくりの過程の中で、最もワクワクする瞬間ではないでしょうか?
次に、組み立てた膝継手以下とソケットを連結します。いよいよ大腿義足のカタチができあがってきました!モノづくりの過程の中で、最もワクワクする瞬間ではないでしょうか?
 それぞれのパーツに設定した基準線が、床面に対して垂直になるように調整します。ここまでの作業が一つ一つ正確に行われていないと、固有のアライメントを再現できません。
問題があれば原因を特定し、これについて考察し、解決する手順を把握することが大切ですね!
それぞれのパーツに設定した基準線が、床面に対して垂直になるように調整します。ここまでの作業が一つ一つ正確に行われていないと、固有のアライメントを再現できません。
問題があれば原因を特定し、これについて考察し、解決する手順を把握することが大切ですね!
 組み立てが完了し、先生から最終的チェックを受けます。ドキドキする瞬間ですね・・・・・・
自分では正しく組立てているつもりでも、微妙なズレが生じているようです。基準線を引く時は、物体に対して常に正面から見ることを心掛けましょう!
組み立てが完了し、先生から最終的チェックを受けます。ドキドキする瞬間ですね・・・・・・
自分では正しく組立てているつもりでも、微妙なズレが生じているようです。基準線を引く時は、物体に対して常に正面から見ることを心掛けましょう!
 採型、陽性モデル修正、ソケット製作を経て、いよいよベンチアライメントが完了しました。これで実際に義足を装着していただく「仮合わせ」の準備ができましたね!
「大腿義足のアライメント」「大腿義足の異常歩行」について、しっかり予習をして仮合わせに臨みましょう!" target="_blank">NEW! 3年生 大腿義足の組み立て実習が行われました。
採型、陽性モデル修正、ソケット製作を経て、いよいよベンチアライメントが完了しました。これで実際に義足を装着していただく「仮合わせ」の準備ができましたね!
「大腿義足のアライメント」「大腿義足の異常歩行」について、しっかり予習をして仮合わせに臨みましょう!" target="_blank">NEW! 3年生 大腿義足の組み立て実習が行われました。 -
言語聴覚士は、理学療法士さんや作業療法士さんに比べてトランス
ファーが苦手です。
今回はお向かいの中部リハビリテーション専門学校の演習室を
お借りして練習しました。
両学科とも、1年の時に中部リハビリテーション学校の先生に直接
教えて頂いていますので、最初は患者さん役の学生と一緒に倒れこんだ
りしていましたが、だんだん思い出したのか、それなりになってきま
した。
実習先でもがんばって下さいね。ちょっとへっぴり腰?
よいっしょっと! 力技ではダメですよ。 " target="_blank">いよいよ来週から臨床実習です!
-
仮合わせで採寸したベルトの長さを基に、完成品を製作していきます。
皮革の切り出し方からベルトの縫製まで、細かな説明とデモンストレーションが続きます。
 義肢装具製作では工業用ミシンを使用し、縫製作業を行います。この日はミシンの機能だけでなく、上糸の通し方、下糸の巻き方、ステッチ幅の変更など、ミシンの微妙な調整を数多く学びました。
義肢装具製作では工業用ミシンを使用し、縫製作業を行います。この日はミシンの機能だけでなく、上糸の通し方、下糸の巻き方、ステッチ幅の変更など、ミシンの微妙な調整を数多く学びました。
 最後に装具本体に縫製したベルトを取り付けて完成です。
取り付ける位置や角度など、仮合わせで得た情報を反映させていきます!
最後に装具本体に縫製したベルトを取り付けて完成です。
取り付ける位置や角度など、仮合わせで得た情報を反映させていきます!
 いよいよ装具が完成し、適合評価です!
圧痛箇所はないか、決められた寸法通りであるか、ベルトの長さは適切か、適合時のチェックポイントを一つずつ確認していきます。
いよいよ装具が完成し、適合評価です!
圧痛箇所はないか、決められた寸法通りであるか、ベルトの長さは適切か、適合時のチェックポイントを一つずつ確認していきます。
明日は全員が完成した装具を1日装着する体験実習を行います。 装具を製作するだけでなく、装着することで見えてくる問題点や課題が多くあります。 患者様、義肢装具士の両方の立場になって、しっかり考察しましょう!" target="_blank">NEW! 1年生 シューホーンブレイスが完成しました。 -
始めに、「フットプリント」による足底圧の計測を行います。その後、足部の周径を計測し、靴づくりに反映させていきます。患者様の身体を正確に採寸することは、靴を作る上で重要となります。
 次に先生の採型のデモンストレーションです!
ここでの採形は、これから製作するラスト(靴の木型)の元となる陽性モデル製作に大切な工程ですから、しっかりデモンストレーションを観察しましょう!
次に先生の採型のデモンストレーションです!
ここでの採形は、これから製作するラスト(靴の木型)の元となる陽性モデル製作に大切な工程ですから、しっかりデモンストレーションを観察しましょう!
 採型は「トリシャム」という特殊なスポンジ状の素材とギプス包帯を使用して足部の形を採型します。義肢装具の採型はこのように様々な素材や採型手法を用いて行います。
採型は「トリシャム」という特殊なスポンジ状の素材とギプス包帯を使用して足部の形を採型します。義肢装具の採型はこのように様々な素材や採型手法を用いて行います。
 フットプリントを基に、自身の足部に合わせて靴のデザインをします。その後、デザインした靴の形状に合わせて陽性モデルを修正していきます。
フットプリントを基に、自身の足部に合わせて靴のデザインをします。その後、デザインした靴の形状に合わせて陽性モデルを修正していきます。
 この陽性モデルが靴を製作する木型の基となります。
納得のいく『かっこいい靴』 に仕上げてくださいね!
この陽性モデルが靴を製作する木型の基となります。
納得のいく『かっこいい靴』 に仕上げてくださいね!
 修正した陽性モデルにプラスチック材を熱成形し、チェックシューズを製作します。
修正した陽性モデルにプラスチック材を熱成形し、チェックシューズを製作します。
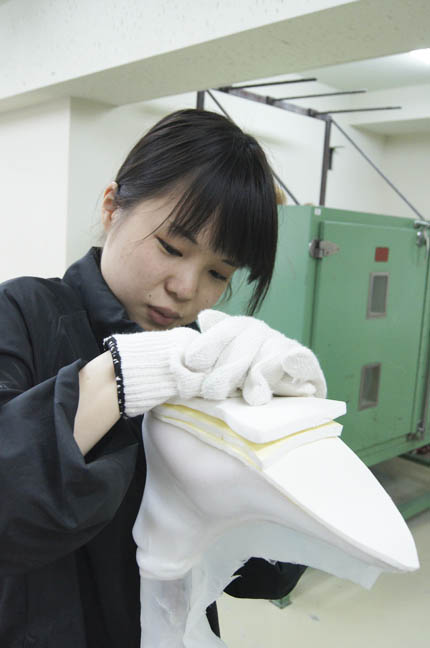 次に、熱成形したプラスチックに靴底を貼りつけ、靴を完成させる前に適合状態を確認するためのチェックシューズが完成します。
次に、熱成形したプラスチックに靴底を貼りつけ、靴を完成させる前に適合状態を確認するためのチェックシューズが完成します。
 靴底(踵の高さ)を整えてチェックシューズが完成します。
2年生はこの授業で製作した靴を履いて8月からの臨床実習に行きます。
臨床実習でご指導いただく先生方、彼らの足元に注目して下さい!そして、いろいろなご意見をいただきたいと思います。" target="_blank">NEW! 2年生 靴型装具の製作実習が行われました。
靴底(踵の高さ)を整えてチェックシューズが完成します。
2年生はこの授業で製作した靴を履いて8月からの臨床実習に行きます。
臨床実習でご指導いただく先生方、彼らの足元に注目して下さい!そして、いろいろなご意見をいただきたいと思います。" target="_blank">NEW! 2年生 靴型装具の製作実習が行われました。 - http://ncg.kzan.jp/blog/2015/05/post_412.html
今回の就職ガイダンスでは、社会経験の少ない補聴学生のために 求人票の見方の詳細な説明もあります。 基本給、調整手当、賞与、昇給など給与面や、 履歴書、卒業証明書、成績証明書などの書類の整え方などの 話がありました。
学生からは 「お給料は総額しか気にしてなかった」 「免許証の写しって、運転免許証じゃないんですね」 「添え状の存在を知ってよかった」 など、教員としてはビックリの感想が出ました。
後半では模擬集団面接が行われましたが、 仲の良い3年生、あまり緊張せずに終始ニコニコ(にやにや?) していました。 ニコニコ
ニコニコ
それでも予想外の質問に頭が真っ白になったのか、 言葉に詰まったり、笑ってごまかしたり・・・。
印象の良さはなかなかでしたが、質問に対して、 もう少ししっかり答えられるように練習しましょうね。 ニコニコニコ
" target="_blank">補聴言語学科だけの就職ガイダンス
ニコニコニコ
" target="_blank">補聴言語学科だけの就職ガイダンス - " target="_blank">NEW! 東京パラリンピックを目指して!
-
アンケートを見てみると参加して下さった方は 学校のカリキュラムや国家試験、就職・・・だけでなく、 在校生とお話をして実際の学校生活についても知って頂けたようです。
 ホームページ、ブログなどで学院の様子を分かりやすく伝えたいと
思っていますが、
『百聞は一見にしかず』
オープンキャンパスに来て体験してみるからこそ分かることが
たくさんあるようです。
ホームページ、ブログなどで学院の様子を分かりやすく伝えたいと
思っていますが、
『百聞は一見にしかず』
オープンキャンパスに来て体験してみるからこそ分かることが
たくさんあるようです。
次回のオープンキャンパスは7月18日(土)です。 ご都合が合わなかった方、是非ご参加ください! " target="_blank">聴能・補聴オープンキャンパスご報告 -
まず最初に、鵜飼リハビリテーション病院のリハビリテーション医師、言語聴覚士、看護師の先生方より「専門職種間連携の必要性」、「専門職の役割と連携の注意点」、「連携の実践例」についてそれぞれご講義いただきました。
 次は、提示された症例についてグループディスカッションです。関連職種は義肢装具士(PO)、理学療法士(PT)、言語聴覚士(ST)、看護師(Ns)の4職種です。それぞれの立場から「問題の整理」「目標の設定」「アプローチ」について議論を深めます!
次は、提示された症例についてグループディスカッションです。関連職種は義肢装具士(PO)、理学療法士(PT)、言語聴覚士(ST)、看護師(Ns)の4職種です。それぞれの立場から「問題の整理」「目標の設定」「アプローチ」について議論を深めます!
 学生同士が互いの専門性をベースに議論をすることで、症例に対する知見が広がるだけでなく、チーム医療の必要性について再認識できた学生が多かったようです。
学生同士が互いの専門性をベースに議論をすることで、症例に対する知見が広がるだけでなく、チーム医療の必要性について再認識できた学生が多かったようです。
 二週にわたって行われたこの合同授業では、多くの学生が専門知識の重要性やチーム医療の必要性について改めて深く考える機会になったと思います。
ご講義いただきました鵜飼リハビリテーション病院の先生方、各学科の先生方、ありがとうございました!" target="_blank">NEW! 3年生 『専門職種間連携教育』の授業が行われました。
二週にわたって行われたこの合同授業では、多くの学生が専門知識の重要性やチーム医療の必要性について改めて深く考える機会になったと思います。
ご講義いただきました鵜飼リハビリテーション病院の先生方、各学科の先生方、ありがとうございました!" target="_blank">NEW! 3年生 『専門職種間連携教育』の授業が行われました。 -
その関連3校・4職種の最上級生が、臨床実習直前の2日間、
一堂に会して、「専門職種間連携教育」の授業が行われました!
内容は、初日は鵜飼リハビリテーション病院スタッフによる講義と症例提示で わからなかった専門用語を説明し合い、2日目はグループワークで 各専門職それぞれのアプローチについて話し合った後、 模擬カンファレンス・チームとしてのアプローチをまとめました。
リハビリテーションにはチームアプローチが大切です。 しかし、連携と言っても、例えば、各職種にはそれぞれの見方・考え方や 専門用語があり、就職してすぐにそれが簡単ではないことに気づきます。
 今回の授業で各専門職の見方が違うことがわかり、チームで目標を
共有するという体験ができたことは大きいと思います。
チームにはコミュニケーションが大切です。
STはその専門家のはず!
今後も多職種理解を深めていってほしいものです。
" target="_blank">3校合同授業「専門職種間連携教育」を行いました
今回の授業で各専門職の見方が違うことがわかり、チームで目標を
共有するという体験ができたことは大きいと思います。
チームにはコミュニケーションが大切です。
STはその専門家のはず!
今後も多職種理解を深めていってほしいものです。
" target="_blank">3校合同授業「専門職種間連携教育」を行いました -
今の医学では、「こうすれば認知症にならない」という方法は
残念ながらありません。しかしながらライフスタイルによって
「認知症の発症を遅らせる」ことが分かってきました。
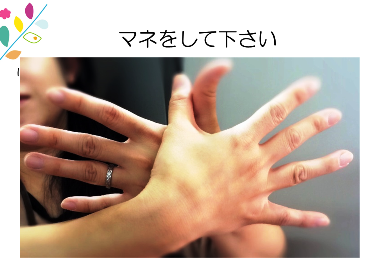 そのライフスタイルとはどんなものなのか、食事方法、
脳のトレーニングなどをお伝えしました。
会場からは質問も多く、なごやかな雰囲気となりました。
コミュニケーションや社会的接触は、それが乏しい人たちに比べて
認知症を8倍も予防してくれるそうです。
このような教室に参加しよう!という積極的に行動をされる方は
すでに認知症の予防をされているんですね。
そのライフスタイルとはどんなものなのか、食事方法、
脳のトレーニングなどをお伝えしました。
会場からは質問も多く、なごやかな雰囲気となりました。
コミュニケーションや社会的接触は、それが乏しい人たちに比べて
認知症を8倍も予防してくれるそうです。
このような教室に参加しよう!という積極的に行動をされる方は
すでに認知症の予防をされているんですね。
 第二部では、希望者に簡単な聴力検査を行いました。
難聴によって認知症のリスクが上がることが知られています。
(耳から情報が入ってこないと脳はついついお休みがちになります)
こちらもたくさんの方が参加下さいました。
" target="_blank">中部リハビリテーション教室で講演しました
第二部では、希望者に簡単な聴力検査を行いました。
難聴によって認知症のリスクが上がることが知られています。
(耳から情報が入ってこないと脳はついついお休みがちになります)
こちらもたくさんの方が参加下さいました。
" target="_blank">中部リハビリテーション教室で講演しました -
本年は、まずまず!
繰り返し練習してきた成果が発揮できたようでした。 評価を行い、1年で学んだ症状がなぜ出るのかについても、 理解が深まってくれると信じています。 " target="_blank">SLTA実技テスト終了! - 前回の授業で製作した陽性モデルにプラスチックシートを熱成形し、仮合わせ用に装具のトリミングを行いました。初めての作業に戸惑いながらも、徐々に装具の形になってゆくと学生たちも楽しそうです!
 陽性モデルに熱成形したプラスチックを装具として必要なトリミングラインに合わせて切り出していきます。プラスチックのカットラインを面取りし、身体に傷などができないように加工します。
陽性モデルに熱成形したプラスチックを装具として必要なトリミングラインに合わせて切り出していきます。プラスチックのカットラインを面取りし、身体に傷などができないように加工します。
 いよいよ仮合わせです。
製作した装具を装着し、適合感や不具合がないかを確認していきます。
いよいよ仮合わせです。
製作した装具を装着し、適合感や不具合がないかを確認していきます。
 装具を外した後も身体に傷が出来ていないか、細かくチェックしていきます。
装具を外した後も身体に傷が出来ていないか、細かくチェックしていきます。
 さて、初めて製作した装具の適合状態はどうだったでしょうか?
次回は仕上げ加工をして、ついに装具が完成となります。新しく習ったことを少しずつ、自分の知識にしていきましょう!
さて、初めて製作した装具の適合状態はどうだったでしょうか?
次回は仕上げ加工をして、ついに装具が完成となります。新しく習ったことを少しずつ、自分の知識にしていきましょう!
6月20日(土)のオープンキャンパスでは、紹介している短下肢装具(シューホーンブレイス)の採型を参加者の皆様に体験して頂けます。 義肢装具士の仕事を体感するチャンス!ぜひご参加ください!!
 義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
 " target="_blank">NEW! 1年生 シューホーンブレイスの製作
" target="_blank">NEW! 1年生 シューホーンブレイスの製作 -
3年生は4月から本格的に国家試験対策が始まっています!
学生たちは国家試験対策の講義はもちろん、講義開始前の早朝と放課後にグループ学習を毎日行っています。
過去の国家試験問題を1問ずつ解いて、選択肢一つ一つに解説を記述します。その選択肢のどこが誤りなのか、正しくはどうなのかを理解することは、国家試験対策を行う上でとても大切なことです。
 「継続は力なり!」毎日の積み重ねが実力をつけていくことに繋がります。全員合格を目指して、地道にコツコツ頑張りましょう!" target="_blank">NEW! 3年生 休み時間も国家試験勉強中!
「継続は力なり!」毎日の積み重ねが実力をつけていくことに繋がります。全員合格を目指して、地道にコツコツ頑張りましょう!" target="_blank">NEW! 3年生 休み時間も国家試験勉強中! - 前回の採型実習に引き続き、今日は陽性モデル修正を行いました。
PTB式は下腿義足ソケットの中でも比較的に多く使用されているタイプのソケットです。学生たちは事前にソケットの体重支持原理を学習していますので、今日から製作方法を実習していきます。
 まずは先生のデモンストレーションを見て、その工程を学習します。先生の手の動きをしっかりと観察し、真似することが大切ですね!
まずは先生のデモンストレーションを見て、その工程を学習します。先生の手の動きをしっかりと観察し、真似することが大切ですね!

 学生たちは徐々にきれいな陽性モデルが作れるようになってきました。採寸値に合わせて正確な削りや盛り修正をすることはもちろん、なめらかな形状に仕上げることもソケット適合に大きく影響します。
また、義肢ソケットでは皮膚がソケット内面に直接触れることもあるため、細かな凹凸も繊細に修正する必要があります。
学生たちは徐々にきれいな陽性モデルが作れるようになってきました。採寸値に合わせて正確な削りや盛り修正をすることはもちろん、なめらかな形状に仕上げることもソケット適合に大きく影響します。
また、義肢ソケットでは皮膚がソケット内面に直接触れることもあるため、細かな凹凸も繊細に修正する必要があります。
次回は、ソフトインサート製作とソケット樹脂注型の工程をお伝えします!" target="_blank">NEW! 2年生 下腿義足の陽性モデル修正が行われました。 - 前回の採型実習に引き続き、四辺形ソケットの陽性モデル修正を行いました。
 まずは採型時に採寸した切断端の周径値を基に、コンプレッション値を設定していきます。コンプレッション値は断端長や皮下組織の厚さなどによってその数値が個々に決定されます。
まずは採型時に採寸した切断端の周径値を基に、コンプレッション値を設定していきます。コンプレッション値は断端長や皮下組織の厚さなどによってその数値が個々に決定されます。
 一般的な切断例だけでなく、様々な症例に応じた陽性モデルの修正ポイントを分かり易く教えていただきました。見る見るうちに陽性モデルが完成する工程に、学生たちも興味津々です。
一般的な切断例だけでなく、様々な症例に応じた陽性モデルの修正ポイントを分かり易く教えていただきました。見る見るうちに陽性モデルが完成する工程に、学生たちも興味津々です。
 大腿義足ソケットの陽性モデル修正ではミリ単位の誤差がソケットの適合に大きく影響するため、学生たちは何度もコンプレッション値を計算し、念入りに確認をしていました。
大腿義足ソケットの陽性モデル修正ではミリ単位の誤差がソケットの適合に大きく影響するため、学生たちは何度もコンプレッション値を計算し、念入りに確認をしていました。
 徐々に四辺形ソケットの形状に近づいてきました。
陽性モデル修正では周径調整と同時に、筋の走路や骨形状など解剖学的に理解をしていないと形状を整えることができません。
徐々に四辺形ソケットの形状に近づいてきました。
陽性モデル修正では周径調整と同時に、筋の走路や骨形状など解剖学的に理解をしていないと形状を整えることができません。
 3年生は6月から約2ヵ月間の臨床実習が始まります。
実習施設では今日学んだことをしっかりと実践して下さいね!
3年生は6月から約2ヵ月間の臨床実習が始まります。
実習施設では今日学んだことをしっかりと実践して下さいね!
次回はソケット熱成形作業とベンチアライメント設定までの様子をレポートします!" target="_blank">NEW! 3年生 大腿義足の陽性モデル修正が行われました。 -
前半は、教員より昨年の求人件数や地域などの説明がされました。 当学院に、昨年度頂いた求人件数は650、求人数は1500を 超え、過去最高となっており、STはここ数年、かなりの売り手市場に なっています。 そんな状況下での、条件の絞り方、情報収集の仕方、施設見学に ついてなどなどレクチャーがありました。
後半は5人の先輩をお招きし、急性期、回復期、生活期、小児領域の それぞれの病院の特色、よかったこと、大変なこと、またどのように就職 活動をしたのか等をお話し頂きました。 それぞれの期について、「思っていた印象と違った」「やはり小児に
こだわりたい」と言う感想の他、
「苦手な分野だからこそ、あえて足を踏み入れた」
「興味のある分野と向いている分野は違う」という先輩方の話に感銘を
うけて、自分の将来について気持ちをあらたにしたようでした。
それぞれの期について、「思っていた印象と違った」「やはり小児に
こだわりたい」と言う感想の他、
「苦手な分野だからこそ、あえて足を踏み入れた」
「興味のある分野と向いている分野は違う」という先輩方の話に感銘を
うけて、自分の将来について気持ちをあらたにしたようでした。

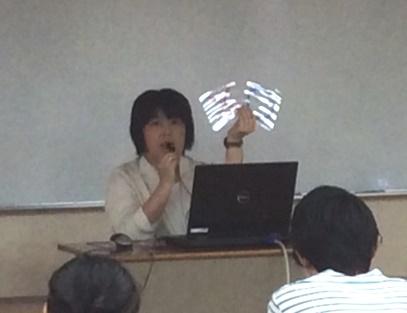 その後にグループになり、先輩を囲んで茶話会が行われ、就職の話
だけではなく、臨床実習に向けて準備したほうがいいもの、使用した
参考書、レジュメ、さらには国試対策についてまで、盛り上がった
ようでした。
その後にグループになり、先輩を囲んで茶話会が行われ、就職の話
だけではなく、臨床実習に向けて準備したほうがいいもの、使用した
参考書、レジュメ、さらには国試対策についてまで、盛り上がった
ようでした。
 盛り上がる茶話会
同じ学校の先輩、後輩、気の置けない間柄ですもんね.
盛り上がる茶話会
同じ学校の先輩、後輩、気の置けない間柄ですもんね.
" target="_blank">就職ガイダンスが行われました -
田宮先生ありがとうございました
講演を聞いた感想として、非常に学生の事を考えて実習して くださっていることが伝わってきました。 学生の体調や能力に配慮しつつ、プロの臨床家としてのノウハウを きめ細やかに指導していただいていることを感じました。
実習前は不安ばかり言っていた学生が、実習後は「楽しかった」と 言って帰ってくることが多くあります。 実習指導の先生方が学生に配慮してくださり、臨床の魅力を伝えて くださっているからだと思います。

 指導者と面談中
指導者と面談中
今年も多くの学生がそのような体験をして帰ってくると思います。 学生の皆さんは、実習指導の先生方に少しでも追いつけるように、 充実した実習を過ごせるよう頑張ってくださいね。 " target="_blank">臨床実習 実習指導者会議を行いました -
最初は採型(さいけい)から学びます。先生のデモンストレーションをしっかり観察し、採型の手順や材料特性を理解します。
モノづくりだけでなく、患者様への対応も学んで行きます。
 いよいよ実践です!
先生のデモンストレーションではとても簡単そうに見えても、実際にやってみると難しい作業です!
いよいよ実践です!
先生のデモンストレーションではとても簡単そうに見えても、実際にやってみると難しい作業です!
 ギプス包帯は時間が経つにつれて、その扱いが難しくなります。
決められた時間の中で手際よく作業を終えなくてならず、学生たちはこの日一日、悪戦苦闘していました!
ギプス包帯は時間が経つにつれて、その扱いが難しくなります。
決められた時間の中で手際よく作業を終えなくてならず、学生たちはこの日一日、悪戦苦闘していました!
 次に、採型した陰性モデルから陽性モデルを製作し、医学的根拠に基づいた修正を加えていきます。
陽性モデル修正は、患者様の病態から必要な修正をモデルに加え、装具に治療効果を持たせる重要な作業工程です。
次に、採型した陰性モデルから陽性モデルを製作し、医学的根拠に基づいた修正を加えていきます。
陽性モデル修正は、患者様の病態から必要な修正をモデルに加え、装具に治療効果を持たせる重要な作業工程です。
 製作理論や材料特性、工具や機械の使い方など、義肢装具を製作する上で必要な基礎知識を1つ1つ学んでいきましょう!" target="_blank">1年生 入学して初めての採型実習が行われました。
製作理論や材料特性、工具や機械の使い方など、義肢装具を製作する上で必要な基礎知識を1つ1つ学んでいきましょう!" target="_blank">1年生 入学して初めての採型実習が行われました。 -
聴能言語学科1年生の男子2名。いざというとき頼りになりそうです。
 聴能言語学科2年生の女子2名。使用の仕方をしっかりと学びました。
" target="_blank">防災訓練
聴能言語学科2年生の女子2名。使用の仕方をしっかりと学びました。
" target="_blank">防災訓練 -
*聴能学科は手作り感あふれています
聴能言語学科の新入生歓迎会は5Fの講堂で手作りの飾り付けをして、 お寿司とオードブルでのおもてなしです。 内部教員はもちろん、外来講師の先生も5名ご参加され、 温かい言葉をたくさんいただきました。
 *方言とジェスチャーでわかるかな?
*方言とジェスチャーでわかるかな?
上級生と新入生の親睦を深めるゲームなどもあり、 盛り上がっていました。
新入生からの「今からしておいた方がよいことは何ですか?」 などの質問に対して、自らの反省の意味もこめてでしょうか、 真摯に答えていた先輩の姿が印象的でした。補聴言語学科の会は2年生・3年生もほぼ参加して、 総勢90名の大所帯、お店の1フロアを貸切って行われました。  *我が学院の癒し、島田学科長
*我が学院の癒し、島田学科長
こちらも外来講師の先生も3名参加され、 チーム対抗のゲームも行われました。 *盛り上がっております!
*盛り上がっております!
あの先生がかっこいいと盛り上がる学生達、 「この科目は大変だよ」などと話しかける先輩もいて、 新入生もかなり打ち解けた様子でした。
 *3年生と1年生、誰と話しているのでしょうか
*3年生と1年生、誰と話しているのでしょうか
どちらも、楽しい時はあっという間に過ぎました。 幹事の聴能2年生、補聴3年生の皆さん、 お疲れ様、お忙しい中ありがとうございました! " target="_blank">新入生歓迎会 -
ナブテスコ株式会社 福祉事業推進部の 坂田晃生 先生に自社製品の高機能義足膝継手を中心にその他義足パーツについてご講義いただきました。
 講義では最新の高機能膝継手をはじめ、多くの義足パーツを展示していただき、学生たちは講義が始まる前から興味津々でした。
講義では最新の高機能膝継手をはじめ、多くの義足パーツを展示していただき、学生たちは講義が始まる前から興味津々でした。
 3年生はこれまで何回か学会にも参加しているため、製品自体は見たことがある学生も多かったようです。しかし、改めて製品の機能や適応などを学ぶことができ、学生たちは知識の整理ができたようです。
3年生はこれまで何回か学会にも参加しているため、製品自体は見たことがある学生も多かったようです。しかし、改めて製品の機能や適応などを学ぶことができ、学生たちは知識の整理ができたようです。
 講義の後は、実際に製品に触れて調整してみましょう!
講義の後は、実際に製品に触れて調整してみましょう!
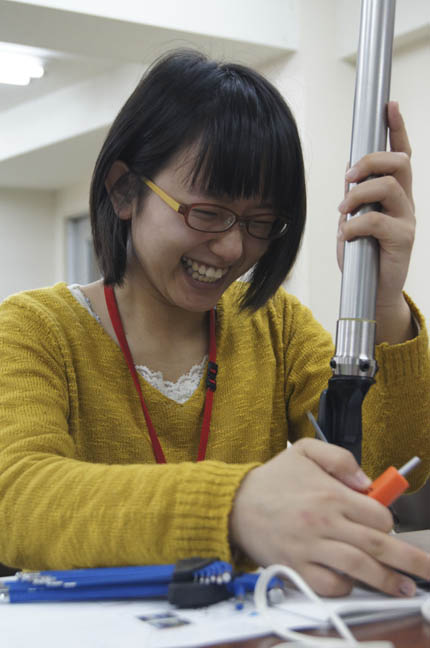 製品の機能や適応を理解しているだけでなく、実際にパーツを調整できることが大切ですね!
上手く調整ができると、自然に笑顔になりますね!
製品の機能や適応を理解しているだけでなく、実際にパーツを調整できることが大切ですね!
上手く調整ができると、自然に笑顔になりますね!
 こちらのグループは義足足部に実際に体重をかけて、足部の動きを確認していますね。義足パーツについて患者様に的確な説明ができることも義肢装具士の重要な役割です。
こちらのグループは義足足部に実際に体重をかけて、足部の動きを確認していますね。義足パーツについて患者様に的確な説明ができることも義肢装具士の重要な役割です。
 この学生は足部の振り出しのスピードを上手く調整できたでしょうか?
6月からの臨床実習では、皆さんが実際に義足の調整をする場面が持っています。その時に安心して作業を任せてもらえるよう、しっかり復習しておきましょう!
この学生は足部の振り出しのスピードを上手く調整できたでしょうか?
6月からの臨床実習では、皆さんが実際に義足の調整をする場面が持っています。その時に安心して作業を任せてもらえるよう、しっかり復習しておきましょう!
坂田先生、お忙しいところご講義いただき、ありがとうございました。義肢装具士として臨床で製作、適合に携わられていた経験からのお話は、学生たちにとって何より参考になったと思います。来年もよろしくお願いします!
お知らせ 義肢装具学科では、随時学校見学を受付けています。あなたのご都合の良い時間を利用して、学校を見学してみませんか?タイミングが合えば、今回ご紹介したような実習風景も見学できます!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
 " target="_blank">3年生 義足膝継手の特別講義が行われました。
" target="_blank">3年生 義足膝継手の特別講義が行われました。 -
まずは先生による採型のデモンストレーションです。
義足製作に必要となる切断端の解剖学的あるいは運動学的な所見や、切断原因、切断者の職業、生活習慣など様々な情報を問診、視診、触診によって確認して行きます。学生たちは採寸や採型の技術だけでなく、切断者への心配りやコミュニケーションの大切さも実感したようです。
 義足ソケットで体重を支える部分を明確にするため、骨突起部などにマーキングを行います。ここでは骨の形状や配列、筋の走路などが解剖学的に理解されていることが重要です。
義足ソケットで体重を支える部分を明確にするため、骨突起部などにマーキングを行います。ここでは骨の形状や配列、筋の走路などが解剖学的に理解されていることが重要です。
 それでは実際に採型をしてみましょう!
学生たちは初めて実際の切断端に触れましたが、なかなか上手くギプス包帯を巻いているようですね。ギプス包帯を強く巻きすぎると切断端の形状が変わってしまうため、テンションの掛け方もしっかり把握して下さいね!
それでは実際に採型をしてみましょう!
学生たちは初めて実際の切断端に触れましたが、なかなか上手くギプス包帯を巻いているようですね。ギプス包帯を強く巻きすぎると切断端の形状が変わってしまうため、テンションの掛け方もしっかり把握して下さいね!
 ギプス包帯を巻き終えたら、ギプスが完全硬化する前に体重を支える箇所を明確にする手技を行います。ギプス包帯を巻いた上から手技を行うため、切断端の形状が把握できず、学生たちはここで悪戦苦闘していました!
ギプス包帯を巻き終えたら、ギプスが完全硬化する前に体重を支える箇所を明確にする手技を行います。ギプス包帯を巻いた上から手技を行うため、切断端の形状が把握できず、学生たちはここで悪戦苦闘していました!
次回は、陽性モデル修正の様子をお伝えします!
お知らせ 義肢装具学科では、随時学校見学を受付けています。あなたのご都合の良い時間を利用して、学校を見学してみませんか?タイミングが合えば、今回ご紹介したような実習風景も見学できます!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
 " target="_blank">2年生 下腿義足の採型実習が行われました。
" target="_blank">2年生 下腿義足の採型実習が行われました。 -
大腿義足の製作実習は、臨床で活躍する義肢装具士から直接講義を受けることができます。
香川貴宏先生(㈱松本義肢製作所)、今年度もよろしくお願いいたします!
 この学生は切断肢の股関節の角度を計測する基準線を引いています。大腿切断では股関節の角度によって切断端の周径や長さが変化するため、この角度設定が重要です。このほか断端の皮膚状況や骨形状などの触診を行います。
この学生は切断肢の股関節の角度を計測する基準線を引いています。大腿切断では股関節の角度によって切断端の周径や長さが変化するため、この角度設定が重要です。このほか断端の皮膚状況や骨形状などの触診を行います。


 大腿義足の採型は切断者に健側肢で立位をとってもらいながら行います。切断者の身体的、心理的負担を考慮し、限られて時間のなかで全ての工程を正確に行う必要があります。そのためには、採型前のシミュレーションが重要ですね!
大腿義足の採型は切断者に健側肢で立位をとってもらいながら行います。切断者の身体的、心理的負担を考慮し、限られて時間のなかで全ての工程を正確に行う必要があります。そのためには、採型前のシミュレーションが重要ですね!
 採型したギプスモデル(陰性モデル)は全て香川先生にチェックしてもらいます。股関節の角度や採型手技など、次の採型に向けてそれぞれの課題を見つけて行きます。
採型したギプスモデル(陰性モデル)は全て香川先生にチェックしてもらいます。股関節の角度や採型手技など、次の採型に向けてそれぞれの課題を見つけて行きます。
 この日は1年生が3年生の実習を見学に来ました!
義肢装具学科では、新入生に2、3年生の専門科目の授業を積極的に見学させ、早い時期から専門分野への関心を高める取り組みを行っています。
この日は1年生が3年生の実習を見学に来ました!
義肢装具学科では、新入生に2、3年生の専門科目の授業を積極的に見学させ、早い時期から専門分野への関心を高める取り組みを行っています。
次回は、ギプスモデル(陽性モデル)修正の様子をレポートします!" target="_blank">3年生 大腿義足の採型実習が行われました。 -
平成27年度の義肢装具学科オープンキャンパス日程を公開しました。
オープンキャンパスでは実際に義肢装具学科の授業が体験できます!毎日行われているホントの授業を聞いて、義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを体感してみませんか?装具の採型、義足の歩行観察、筋電義手、ホンモノの義足の組み立て、自分の足の分析などなど、魅力的なコンテンツをたくさんご用意しています!!
義肢装具学科の先生はもちろん、在校生と話す機会もたくさんありますので、入試情報や学校生活など、どんどん質問して義肢装具士のつくる楽しさと、学ぶ楽しさを発見してください!!
みなさんの参加をお待ちしています!
義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ
" target="_blank">平成27年度義肢装具学科オープンキャンパス日程を公開しました。 -
3年生の前期では大腿切断者が装着する「四辺形ソケット」について学習をします。大腿義足ではこれまで学習した解剖学や運動学の知識が重要となり、さらにソケット適合の難易度も高くなります。学生の中には、「大腿義足を作りたい!」という目標を持って入学してきた学生も多いため、どの学生もやる気に満ちた表情で講義に臨んでいます!
 まずは大腿切断の解剖学的特徴やソケットの体重支持原理など、大腿義足の基礎的な知識を講義形式で学習します。これまでに学んだ専門知識を応用しながら講義が進みます。
まずは大腿切断の解剖学的特徴やソケットの体重支持原理など、大腿義足の基礎的な知識を講義形式で学習します。これまでに学んだ専門知識を応用しながら講義が進みます。
 学生たちは真剣な表情で講義を聞いています。講義の中では学生から積極的に質問する場面も多く見られ、実際の製作に向けて段々と準備が整って行きます。
学生たちは真剣な表情で講義を聞いています。講義の中では学生から積極的に質問する場面も多く見られ、実際の製作に向けて段々と準備が整って行きます。
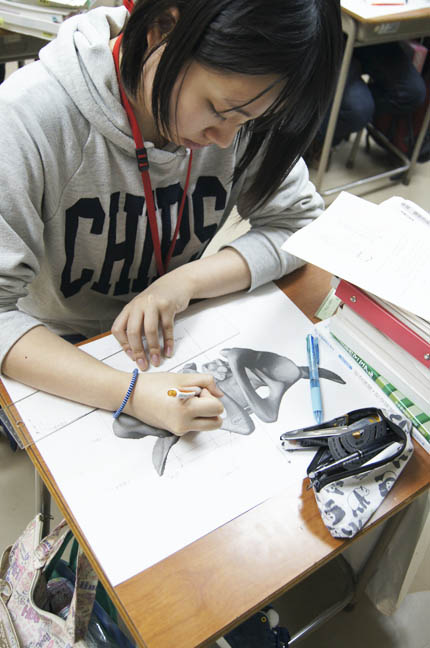 講義が終わると、次はソケットを具体的に設計することを紙面上で学習して行きます。こうしてソケット設計の理論を理解し、これを実際の製作に繋げて行くことが大切です。
講義が終わると、次はソケットを具体的に設計することを紙面上で学習して行きます。こうしてソケット設計の理論を理解し、これを実際の製作に繋げて行くことが大切です。
 今回製作するチェックソケット(仮合わせの為の透明ソケット)を細かく観察しているようですね。ソケット形状が持つ意味をしっかり理解し、次の製作実習に活かしてください。
次回は採型実習の様子をお伝えします!!" target="_blank">3年生 大腿義足の製作実習が始まりました。
今回製作するチェックソケット(仮合わせの為の透明ソケット)を細かく観察しているようですね。ソケット形状が持つ意味をしっかり理解し、次の製作実習に活かしてください。
次回は採型実習の様子をお伝えします!!" target="_blank">3年生 大腿義足の製作実習が始まりました。 -
自分たちの研究テーマについて担当教員に説明し、今後の研究計画について具体的な指導を受けます。
どうやら指導教員から指摘を受けているようですが、研究の骨子はしっかり組立てられているでしょうか?
 このグループは研究のタイムスケジュールについて打ち合わせしているようですね。3年生は6月から臨床実習が始まるため、それまでには基礎的な研究が終えられるように進めて行きましょう!
このグループは研究のタイムスケジュールについて打ち合わせしているようですね。3年生は6月から臨床実習が始まるため、それまでには基礎的な研究が終えられるように進めて行きましょう!
 このグループも研究の進め方について活発なディスカッションが行われていました。卒業研究は過去の文献調査や研究の主旨、具体的な計測方法などグループの中で情報を共有し、常に共通認識
を持つことが重要です。実はこのディスカッションこそが研究を上手く進めるコツだと思います。
このグループも研究の進め方について活発なディスカッションが行われていました。卒業研究は過去の文献調査や研究の主旨、具体的な計測方法などグループの中で情報を共有し、常に共通認識
を持つことが重要です。実はこのディスカッションこそが研究を上手く進めるコツだと思います。
12月の「卒業研究発表会」には納得の行く研究成果が報告できるよう、各グループとも気合いを入れて頑張りましょう!" target="_blank">3年生 卒業研究が始まりました。 -
2人とも4月からSTとして働きはじめ、新しい環境の中で覚えること、
考えることもたくさんあるようです。
「(覚えることがたくさんあって)いっぱいいっぱいです。」と 言いながらも元気そうな顔を見せてくれて、ほっとしました。
卒業生が顔を出してくれると教員もとてもうれしいです。
2人ともSTとしてスタートを切ったばかり! 大変なこともたくさんあるでしょうが、人から元気をもらうこと、 こちらが元気をあげれること等など 「STになってよかった!!」と思えることがたくさんあるはずです。 さあ、また来週から頑張っていきましょう!!
さあ、また来週から頑張っていきましょう!!
" target="_blank">卒業生がきてくれました -
最初はなかなか上手くは行かないものです。 繰り返し練習とフィードバックを受けて 着実に力をつけていってくれるよう、 教員もしっかりと指導していきたいと思います。

" target="_blank">新学期が始まりました! -
卒業生より就職活動の体験談を聞く、 貴重な機会です。
6名の先輩から、活動期間や就職先を選んだ理由、 選考試験の内容などを、また、就職活動で感じたことや 反省点は後輩へのアドバイスを含めて話してくれました。
地元で就職したい、回復期に行きたいなど一番譲れない 希望・条件に優先順位をつけることが必要ですが、 なかなか一人では決めきれないようです。 友人や教員に相談したという話も聞かれました。
新学年は始まったばかりですが、 新年度の求人票もちらほら届いています。 実習までもあっという間です。 先輩からのアドバイス通り、「早めの準備」を始める きっかけになったことと思います。 「授業」 「実習」 「就活」 「国試勉強」 最上級生はバランスよくがんばりましょう!
" target="_blank">聴能・補聴合同就職活動報告会 -
中でも・・・ 担当各教員からのおすすめは。 「症状経過観察に役立つ脳卒中画像のみかた」 「深く深く知る脳からわかる摂食・嚥下障害」 「標準理学療法学・作業療法学 人間発達学」 「認知症のコミュニケーション障害 その評価と支援」
一般向けの書籍ですが、新入生が取り掛かり易そうな 「史上最強 カラー図鑑 臨床心理学のすべてがわかる本」
我ら先輩(聴能5期)春原則子先生が「学習障害」を 執筆されました。 「標準言語聴覚障害学 言語発達障害学 第2版」
などなど。 また図書室でチェックしてみてくださいね。 DVDも入りましたよ。
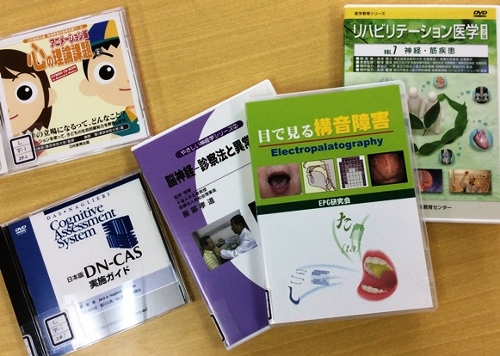
" target="_blank">新刊 (とは限りませんが・・・) 入りました! -
Q:まずは自己紹介をお願いします。
A:松岡 将平(21歳)、愛知県立稲沢東高等学校 出身です。
Q:義肢装具士を目指したきっかけを教えてください。 A:小学生の時に装具を装着した経験から、義肢装具士という存在を知りました。また、地元の先輩が義肢装具学科に入学していたため、その先輩から義肢装具の教科書を見せてもらい、興味を持つようになりました。また、オープンキャンパスや見学ツアーなどに参加する中で、この学科の雰囲気がとても好きになったことがきっかけです。
 Q:3年間の学校生活を振り返って、感想を聞かせてください!
A:3年間を振り返ると、正直大変でした。医学を学ぶことや義肢装具士としてのスキルを身につけることなど、簡単に乗り越えられるものは1つもありませんでした。
ただ、両親や熱心な先生方、多くのクラスメイトに支えられ、無事卒業することができました。今は感謝の気持ちでいっぱいです。
Q:3年間の学校生活を振り返って、感想を聞かせてください!
A:3年間を振り返ると、正直大変でした。医学を学ぶことや義肢装具士としてのスキルを身につけることなど、簡単に乗り越えられるものは1つもありませんでした。
ただ、両親や熱心な先生方、多くのクラスメイトに支えられ、無事卒業することができました。今は感謝の気持ちでいっぱいです。
 Q:義肢装具を勉強して、自分のなかで大きく変化したことはありますか?
A:私はある病気が原因で21年間、片方の踵が浮いた状態で生活しています。今まで何も不便を感じていませんでしたが、臨床実習に行った際、先輩の義肢装具士から「これから患者様の病気を診るのであれば、まず自分の障がいをしっかり分析できるようになりなさい」と言われ、そこから自身の障害とも向き合うようになりました。
Q:義肢装具を勉強して、自分のなかで大きく変化したことはありますか?
A:私はある病気が原因で21年間、片方の踵が浮いた状態で生活しています。今まで何も不便を感じていませんでしたが、臨床実習に行った際、先輩の義肢装具士から「これから患者様の病気を診るのであれば、まず自分の障がいをしっかり分析できるようになりなさい」と言われ、そこから自身の障害とも向き合うようになりました。
 Q:これから、義肢装具士として働く意気込みを聞かせてください!
A:これまで21年間過ごした愛知を離れ、春から岡山の企業で働くことになりました。私は幼い頃から義肢装具士の姿を見て育ち、この職に就きたいと思い、ここまできました。今度は、私の働く姿を見て、「義肢装具士になりたい!」と思ってもらえるよう、日々精進して行きたいと思います。
3年間ご指導いただいた先生方、本当にありがとうございました!
Q:これから、義肢装具士として働く意気込みを聞かせてください!
A:これまで21年間過ごした愛知を離れ、春から岡山の企業で働くことになりました。私は幼い頃から義肢装具士の姿を見て育ち、この職に就きたいと思い、ここまできました。今度は、私の働く姿を見て、「義肢装具士になりたい!」と思ってもらえるよう、日々精進して行きたいと思います。
3年間ご指導いただいた先生方、本当にありがとうございました!
3月27日に第28回義肢装具士国家試験の合格発表があり、松岡くんもみごと合格しました! 松岡くん、本当におめでとうございました! これからの活躍に期待しています!! " target="_blank">NEW! 義肢装具学科 学生インタビュー! Part2 -
入学式当日は朝から雨が心配されていましたが、午前中は晴れ間も見え、新入生の皆さんを祝福しているような清々しい天気となりました!
義肢装具学科の入学生は第29期生となります。 皆さん希望とやる気に満ちた表情で入学式に臨んでいました!
 棚橋学院長からお祝いの式辞をいただき、新入生たちは医学を学ぶ専門学校生になることの重みを改めて実感したようです。
棚橋学院長からお祝いの式辞をいただき、新入生たちは医学を学ぶ専門学校生になることの重みを改めて実感したようです。
新入生たちはこれから膨大な医学や工学の知識を学ばなくていけません。初心を忘れることなく、学びの日々を積み重ねて行ってください!" target="_blank">NEW! 平成27年度入学式が行われました。 -
女子学生Bさんより
「私は勉強が苦手で国家試験がとても不安でしたが、
先生方の手厚いご指導を受け、クラスメイトと励まし合い
無事に国家試験に合格することができました。
この学院で得たことを春からの臨床に役立てていきたいと
思います。」
本当におめでとう! 皆さんの成長を楽しみにしています。 学院にはいつでも遊びに来てくださいね。 " target="_blank">合格した学生の喜びの言葉です -
第28回義肢装具士国家試験の合格発表がありました(壮行会・受験の様子はコチラ)。
合格率 96.4%(全国平均90.2%) (厚生労働省 第28回義肢装具士国家の合格発表について)
本年度も全国平均を大きく上回る、素晴らしい結果となりました! 第26期生をご指導いただきました、講師の先生方、臨床実習施設の皆様、モデル被験者の皆様、本当にありがとうございました。
国家試験の受験勉強と真摯に向き合い、コツコツと知識を積み重ねてきた成果が出ましたね!これで晴れて義肢装具士としてのスタートラインに立ちました。 臨床現場では、たくさんの困難にぶつかることがあると思いますが、職場の先輩、一緒に勉強した同期生に相談し、ひとつひとつ壁を乗り越えて立派な義肢装具士になることを期待しています。
つまずいて悩んだとき、嬉しいことがあったとき、そして何もなくても、気軽に学校に立ち寄って近況を聞かせてくださいね! 第26期生のみなさん、本当におめでとうございました!" target="_blank">NEW! 速報!PO国家試験合格発表 -
ダルマに目を入れる学生たち
 入りました!
入りました!
のちほど、合格した卒業生の声をアップしますね! " target="_blank">速報!ST国家試験合格発表結果! -
吃音の症状は様々で、場面によって出たり出なかったりも しますし、また、症状を抑えるコツも把握されていることも多いです。
言語聴覚士を目指す学生に、言語聴覚士に期待することなども お話いただいたのでしょうか。 全体では質問しにくいことも、小グループになると聞きやすいのか どのグループも活発にお話できたようです。

会終了後の学生の声です。 「症状などは人それぞれ違うのだとわかった」 「貴重なお話を聞く機会ができてよかった」
今週から始まる都筑澄夫先生の「吃音」集中講義が より楽しみになった学生たちでした。
 最後に全員で集合写真
" target="_blank">名古屋きつおんサポートのみなさんとの交流会報告です
最後に全員で集合写真
" target="_blank">名古屋きつおんサポートのみなさんとの交流会報告です -
見学&訓練が終わると報告書の作成→提出→フィードバック… 理解が出来るまで、とことんフィードバックと再提出の繰り返し。
4月から患者さんの為に頑張れるSTを目指して、 卒後も頑張っています!
" target="_blank">就職に向けた学内実習(卒後教育)しています。 -
・机上で学んだ知識と目の前で起こっていることが結びつかない。
・課題が追いつかない。
・患者様と接してみて、どのように会話を展開していってよいか
分からない。
さまざまな課題に直面したようです。
その反面、 ・今まで机上で学んできた知識が整理され、曖昧だった障害像が 明確になった。 ・指導者の先生がどのように患者様に接しているのか、関わり方を 学ぶことができた。 など、学べることも多かったようです。
そして学生の多くは「(たくさん刺激を受け)楽しかった。 行ってよかった。」と言っています。
次は、2年生の臨床実習!!それまでまだまだハードな日々が 続きますが、一緒に頑張りましょう!! " target="_blank">聴能言語学科の見学実習が終わりました! -
コミュニケーション機器は学校には無い物もあり、
実際に触れて感動していました。
そして一番人気はロボット!
アザラシのパロは人工知能、聴覚・触覚センサー等が
ついていて、動きも滑らか、充電器がおしゃぶり型なのも
ロボットを感じさせないところです。
テストでお疲れの皆さんにアニマルセラピー?
ほぼ全員名前を呼んで、喜んで撫でていました。
今日学んだことは来年の実習先や就職先で 活かされることでしょう。 " target="_blank">補聴言語学科1年 なごや福祉用具プラザ見学 -
卒業式直前の様子です。今日は一段と活き活きしていますね!
 棚橋学院長より義肢装具学科総代が卒業証書を受け取りました。
棚橋学院長より義肢装具学科総代が卒業証書を受け取りました。
 義肢装具学科の学生として名前を呼ばれるのはこれが最後ですね。一人ひとりが卒業の喜びを噛みしめているようでした。
義肢装具学科の学生として名前を呼ばれるのはこれが最後ですね。一人ひとりが卒業の喜びを噛みしめているようでした。
 卒業式の終了後は学科に戻り、『卒業証書授与式』が行われました。緊張も解けて、みんなリラックスしていますね!
卒業式の終了後は学科に戻り、『卒業証書授与式』が行われました。緊張も解けて、みんなリラックスしていますね!
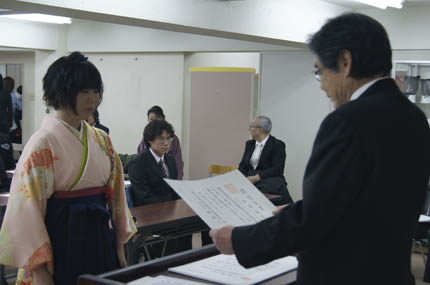 義肢装具学科顧問の高見健二先生より、一人ひとりに卒業証書が授与されました。
義肢装具学科顧問の高見健二先生より、一人ひとりに卒業証書が授与されました。
 (一社)日本義肢装具士協会『優秀学生賞』が、宮川理事より授与されました。
(一社)日本義肢装具士協会『優秀学生賞』が、宮川理事より授与されました。
 義肢装具学科OB会『薫風会』、香川会長より『薫風会賞』が授与されました。
義肢装具学科OB会『薫風会』、香川会長より『薫風会賞』が授与されました。
 卒業生より、在校生に卒業記念品が贈呈されました。
卒業生より、在校生に卒業記念品が贈呈されました。
 最後に、校舎前で恒例の記念撮影を行いました。
三年間ご指導いただきました先生方、ありがとうございました!
最後に、校舎前で恒例の記念撮影を行いました。
三年間ご指導いただきました先生方、ありがとうございました!
26期生の皆さん、ご卒業おめでとうございました。 全国各地で皆さんが活躍されることを教職員一同、期待しています!" target="_blank">NEW! 第26期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 -
卒業式のあと、夕方からは謝恩会。 これは卒業生たちがお世話になった先生方に 感謝の気持ちを込めて招待するパーティで、 その役割を中心になって演じる卒業生たちにとっては 学生時代最後の晴れ舞台といえるでしょう。

聴能言語学科と補聴言語学科の謝恩会担当の卒業生たちは 会場の受付、花束、記念品の準備、企画、会場案内と忙しく動いており、 そんな彼らはひときわ大きく輝いてみえました。
謝恩会といえば、 かつては毎年のように動的なアトラクションが企画されていましたが、 ここ数年は参加者同士の歓談を中心に、 学生時代の思い出を綴ったスライドショーの上映、 そして教員からのメッセージが主流になっています。 今回もとても穏やかな雰囲気で、和やかな会になりました。

各テーブルから講師の先生方と卒業生たちの楽しい会話が聞こえてきました。
最後は、教員からの熱いメッセージ。 卒業生たちは真剣な表情で耳を傾けてくれていました。 とにかく、みんな元気で頑張ってほしい、 そんな気持ちを込めてメッセージを送りました。
" target="_blank">卒業式~謝恩会編~ -
学院長からの卒業証書授与
みんな一緒に新しい人生学校へと羽ばたいていくんですね。 学院は、これから応援者として、いつまでもみなさんを見守る親鳥?のようなものでしょうか。 時々は顔を見せに学院という「巣」へ戻ってきてくださいね。 " target="_blank">卒業式終わりました。 -
Q:まずは自己紹介からお願いします。
A:義肢装具学科第1学年 成瀬稜典です (私立岡崎城西高等学校出身)。趣味は音楽鑑賞と卓球です。
Q:義肢装具士を目指したきっかけを教えてください。 A:身内が病気で装具を装着していたこともあり、高校に入学した頃から義肢装具士に興味を持っていました。また、将来はモノづくりで人の役に立つ仕事がしたいと考えていたので、義肢装具士は僕の理想にピッタリ合っていると思い入学しました。
Q:今回の実習で製作した『装具』について教えてください。 A:腰仙椎装具モールド型とナイト型を製作しました。モールド型はクラスメイトのモデルを基に、ナイト型は自分のモデルを基に製作をしました。 腰仙椎装具ナイト型は腰椎の伸展、屈曲、側屈運動の制限や腰椎前弯の軽減などを目的としていて、腰部椎間板ヘルニア、変形性脊椎症などの腰仙椎疾患に処方されます。また、モールド型は腰椎の動きを制限する装具で、腰椎分離症や脊椎固定術後などに処方されています。
 Q:今回の実習を通して感じたことを教えてください。
A:体幹装具の実習は基本工作論とは違い、実際に装着者に装具を適合させることを目的とした実習でした。特に難しかった点は、陽性モデルの周径を変えずに左右対称に修正しなければならないことでした。私のモデルは採型時に体幹が回旋してしまったため、多くの修正が必要でした。陽性モデルの出来ばえが装具の適合を左右してしまうので、モデル修正はとても重要だと感じました。
Q:今回の実習を通して感じたことを教えてください。
A:体幹装具の実習は基本工作論とは違い、実際に装着者に装具を適合させることを目的とした実習でした。特に難しかった点は、陽性モデルの周径を変えずに左右対称に修正しなければならないことでした。私のモデルは採型時に体幹が回旋してしまったため、多くの修正が必要でした。陽性モデルの出来ばえが装具の適合を左右してしまうので、モデル修正はとても重要だと感じました。
 Q:製作した装具を適合してみてどうでしたか?
A:適合では採型時に行ったマーキング箇所を基に、設定したトリミングライン通りに製作されているか、装具が正しく装着されているかを評価しました。
モールド型の適合は、装具の丈が長く座位時に装具の下縁が大腿部にあたってしまいました。採型時のマーキングの位置や手技が間違っていたことが原因ではないかと思います。
ナイト型は自分で装着して適合評価をしました。私が作った装具は背部の支柱が体に沿っておらず、少し浮いていました。装着者の身体に合わせて作るのは難しいと思いました。装具を装着することは日常なかなかないことなので、とても良い経験になりました。
Q:製作した装具を適合してみてどうでしたか?
A:適合では採型時に行ったマーキング箇所を基に、設定したトリミングライン通りに製作されているか、装具が正しく装着されているかを評価しました。
モールド型の適合は、装具の丈が長く座位時に装具の下縁が大腿部にあたってしまいました。採型時のマーキングの位置や手技が間違っていたことが原因ではないかと思います。
ナイト型は自分で装着して適合評価をしました。私が作った装具は背部の支柱が体に沿っておらず、少し浮いていました。装着者の身体に合わせて作るのは難しいと思いました。装具を装着することは日常なかなかないことなので、とても良い経験になりました。
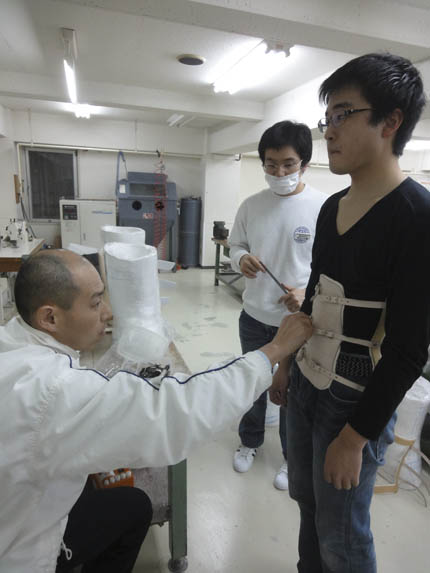 Q:では、最後に、成瀬君のこれからの目標を教えてください!
A:義肢や装具を必要としている人はたくさんいると思います。義肢装具士として働くようになったら、患者様に喜んでもらえる義肢や装具が作れるようにこれからも頑張ります!
Q:では、最後に、成瀬君のこれからの目標を教えてください!
A:義肢や装具を必要としている人はたくさんいると思います。義肢装具士として働くようになったら、患者様に喜んでもらえる義肢や装具が作れるようにこれからも頑張ります!
成瀬君、ありがとうございました! 1年間義肢装具を勉強し、知識、技術ともにだんだんと深みが増してきたようですね!4月からは2年生として、後輩の指導もしっかりお願いしますね!
お知らせ 義肢装具学科では、随時学校見学を受付けています。あなたのご都合の良い時間を利用して、学校を見学してみませんか?タイミングが合えば、今回ご紹介したような実習風景も見学できます!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
 " target="_blank">義肢装具学科 学生インタビュー!
" target="_blank">義肢装具学科 学生インタビュー! -
そして後半は、卒業生による症例検討会。 今回は卒後1~2年の若手卒業生による2症例。 悩みながらの臨床経過を報告。 参加者のみなさんから多くのアドバイスをいただきました。 さらには、今回の発表にあたって指導をいただいた ベテランのスーパーバイザーからのコメントは、 本当に勉強になりました。
在校生たちも多数参加してました。 前日に実習が終わったばかりの補聴2年生も多くて感心。 実習に行ったことでより一層勉強への士気が高まったようです。
今年度の同窓会イベントはこれにて終了です。 来年度も卒業生の皆さんのためになる企画を、 たくさん考えていきます!
" target="_blank">若宮ST同窓会イベント大盛況でした! 10:00 受 付 10:30 学科説明 11:15 学校見学(教室や実習室をのぞいてみよう!)
個別相談(授業のこと、入試のことなど何でも相談!)12:00 終 了(予定)
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ)
当日の学科説明のスライドを一部ご紹介。 義肢装具士の仕事についてから始まり、学科の特色をご説明します。





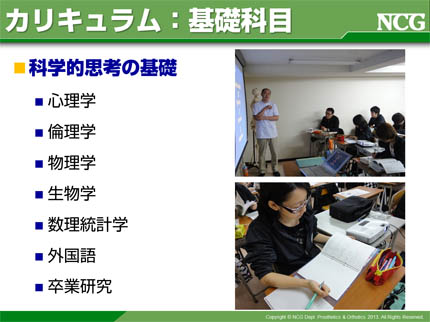
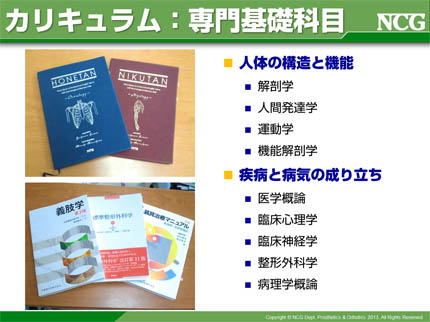
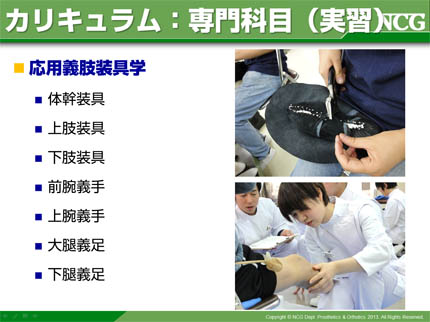

これ以外に当日しか聞くことのできない、国家試験対策や入試のポイントなど、重要な情報を得るチャンスです!ぜひ参加してください!!

 " target="_blank">3月15日(日)オープンキャンパス この春3年生になる皆さんへ
" target="_blank">3月15日(日)オープンキャンパス この春3年生になる皆さんへ
平成27年度 義肢装具学科 入学試験についてご案内します。 一般六次試験の出願を下記の通り受付けます。 受験希望の方はご確認の上、出願手続をお願いします。
◆試験科目 一般入学試験:一般教養(国語・英語)・適性(ペーパークラフト実技)・面接
◆試験日程 一般六次:平成27年3月14日(土) 出願期間:平成27年2月23日(月)~3月9日(月) 必着
義肢装具学科では随時、学校見学および義肢装具製作施設見学ツアーを行っています。大切なあなたの進路決定のために、ぜひご参加ください!ご連絡お待ちしています!
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">平成27年度 一般六次入学試験 出願期間のご案内
" target="_blank">平成27年度 一般六次入学試験 出願期間のご案内お知らせ 義肢装具学科では、随時学校見学、義肢装具製作施設見学ツアーを受付けています。あなたのご都合の良い時間を利用して、学校や義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校にお越し頂き、専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具学科 学校見学・施設見学ツアーのご案内
" target="_blank">義肢装具学科 学校見学・施設見学ツアーのご案内 出発当日、棚橋学院長より温かな激励のお言葉を頂きました。
3年間、共に頑張ってきたクラスメイトと笑顔で卒業できるよう、全力を尽くして来て下さい!
出発当日、棚橋学院長より温かな激励のお言葉を頂きました。
3年間、共に頑張ってきたクラスメイトと笑顔で卒業できるよう、全力を尽くして来て下さい! 1年生がこの日のために応援団を結成し、壮行会を開いてくれました!
毎日、試験勉強を頑張っている先輩の後ろ姿を見てきたからこそ、応援にも力が入っていますね!
1年生がこの日のために応援団を結成し、壮行会を開いてくれました!
毎日、試験勉強を頑張っている先輩の後ろ姿を見てきたからこそ、応援にも力が入っていますね! 後輩たちの熱いエールに、3年生たちも励まされたようです!
今まで学生生活を支えてきてくれた家族や友人、後輩たちが応援してくれていることは、とても心強いです!
後輩たちの熱いエールに、3年生たちも励まされたようです!
今まで学生生活を支えてきてくれた家族や友人、後輩たちが応援してくれていることは、とても心強いです! 後輩たちに見送られながら、いよいよ東京に向けて出発です!
後輩たちに見送られながら、いよいよ東京に向けて出発です!
 名古屋駅ホームでの様子。とってもリラックスしていますね。
名古屋駅ホームでの様子。とってもリラックスしていますね。 国家試験場の TOC ARIAKE です。
当日はとても良い天気に恵まれました。
3年間コツコツと積み重ねてきた成果を、ついに発揮する時がやってきました。普段の実力で落ち着いて臨めば、必ず合格できますよ!
国家試験場の TOC ARIAKE です。
当日はとても良い天気に恵まれました。
3年間コツコツと積み重ねてきた成果を、ついに発揮する時がやってきました。普段の実力で落ち着いて臨めば、必ず合格できますよ!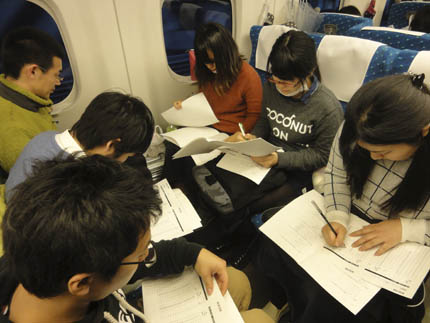 東京から名古屋へ戻る新幹線の車内の様子。
東京へ向かう時よりも緊張した面持ちで、解答を自己採点用紙に書き込んでいます。
東京から名古屋へ戻る新幹線の車内の様子。
東京へ向かう時よりも緊張した面持ちで、解答を自己採点用紙に書き込んでいます。国家試験の結果は、3月末に発表されます。 それまでは、ゆっくり休んで下さいね!3年生の皆さん、お疲れさまでした!" target="_blank">3年生 義肢装具士国家試験が終わりました。
これは、厚生労働省から認可を受けた学校のみに適用される制度で、 資格取得すれば最大で96万円の給付、 さらに在学中にも給付金支給を受けることが可能という、 充実の学費サポート制度です。
詳細については本学院ホームページ、 もしくはハローワークのこちらのページでご確認ください。
今年度の入試は、あと1回、2月21日のみとなりました。 学費のことなどでお悩みの方、ぜひご検討ください!
なお、すでに入学が決まっている方は早急な手続きが必要となります。 あわせてご確認ください!
" target="_blank">最大96万円+α 給付!『専門実践教育訓練給付金制度』が受けられます!
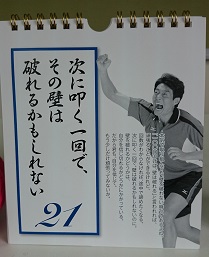 その隣に↑。
「熱い気持ちであきらめずに!」って乗り切ろうってことでね(笑)
その隣に↑。
「熱い気持ちであきらめずに!」って乗り切ろうってことでね(笑)
" target="_blank">いよいよ!国家試験まであと少しとなりました!
学院生活のイメージのためのオリエンテーションでは、 4月から始まる1年間の流れと学校近くのおいしいお店のお話 などをしました。
講座①では脳の健康について、前頭葉機能を鍛える体操の実演や クイズで学習しました。 昼食は1年生(先輩)とお話しをしながらサンドイッチをいただきました。 先輩が感じていることを聞いて参考になったでしょうか?
 講座②では脳トレ?高次脳機能障害の検査を体験しようということで、
3種類の検査を実際に行いました。
速くできたところと苦戦していたところがあるようでした。
講座②では脳トレ?高次脳機能障害の検査を体験しようということで、
3種類の検査を実際に行いました。
速くできたところと苦戦していたところがあるようでした。
終了後の感想では、「楽しかった」「脳に興味が持てた!」 「早く入学して勉強したいと思いました!」と 有意義な時間となったようです。
また4月に元気な皆さんにお会いできることを 教員一同楽しみにしています。 " target="_blank">補聴言語学科・プレセミナーが行われました!
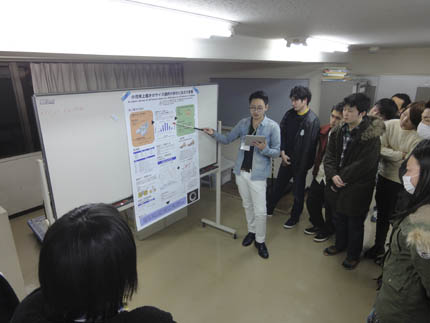 学会前夜、発表に向けてリハーサルに余念がありませんでした。後輩たちも先輩の予行演習に真剣に耳を傾けていました。
学会前夜、発表に向けてリハーサルに余念がありませんでした。後輩たちも先輩の予行演習に真剣に耳を傾けていました。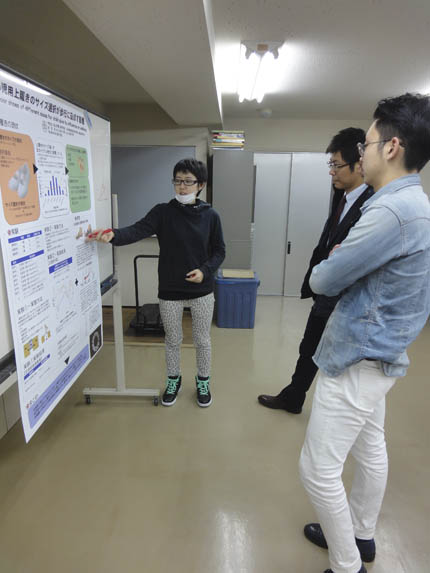 限られた発表時間のなかで研究の内容を正確に、分かりやすく伝えられるよう、夜遅くまで発表原稿を何度も練り直していました。
限られた発表時間のなかで研究の内容を正確に、分かりやすく伝えられるよう、夜遅くまで発表原稿を何度も練り直していました。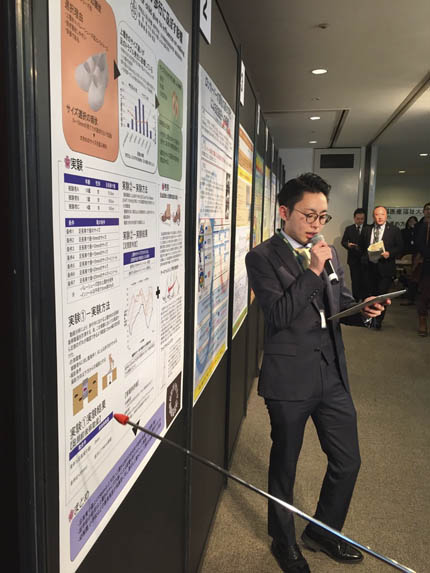 翌日、早朝に東京へ移動し、いよいよ学会本番です!
入念なリハーサルの甲斐もあり、本番はリラックスして医師、義肢装具士、整形靴製作技術者、看護師、理学療法士など、多くの参加者の前で堂々と発表をしていました!
翌日、早朝に東京へ移動し、いよいよ学会本番です!
入念なリハーサルの甲斐もあり、本番はリラックスして医師、義肢装具士、整形靴製作技術者、看護師、理学療法士など、多くの参加者の前で堂々と発表をしていました!
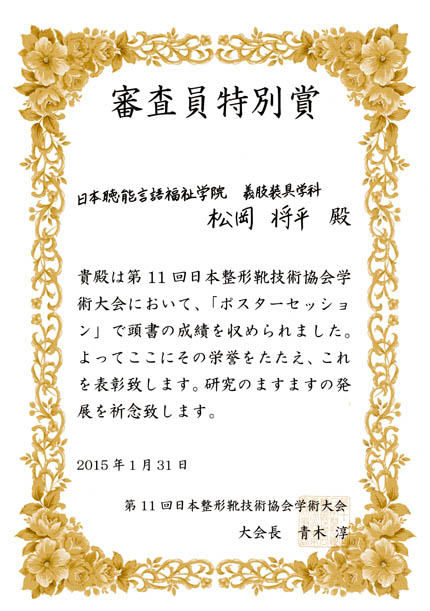 審査の結果、「審査員特別賞」の栄冠に輝きました!
審査員の先生方をはじめ、多くの参加者の皆様に研究成果を評価していただき、本校は8回連続の受賞となりました!
日々の講義や国家試験勉強の傍らで発表の準備をしていましたが、今回の受賞は発表をした学生だけではなく、後に続く後輩たちにとっても、大きな目標、自信に繋がったことと思います。
卒業研究 第2班 の松岡将平君、小川卓司君、片野ふくみさん、受賞おめでとうございました!" target="_blank">3年生 卒業研究論文が「審査員特別賞」を受賞しました!
審査の結果、「審査員特別賞」の栄冠に輝きました!
審査員の先生方をはじめ、多くの参加者の皆様に研究成果を評価していただき、本校は8回連続の受賞となりました!
日々の講義や国家試験勉強の傍らで発表の準備をしていましたが、今回の受賞は発表をした学生だけではなく、後に続く後輩たちにとっても、大きな目標、自信に繋がったことと思います。
卒業研究 第2班 の松岡将平君、小川卓司君、片野ふくみさん、受賞おめでとうございました!" target="_blank">3年生 卒業研究論文が「審査員特別賞」を受賞しました! 生涯学習委員の宇野秋人先生より『義肢装具士の生涯学習の重要性』について、研修副委員長の宮川拓也先生より『関係法規~義肢装具士法~』について、会則検討委員長の鈴木昭宏先生より『協会倫理綱領』について、㈱松本義肢製作所の佐口明先生より『義肢装具の支給体系』についてご講義頂きました。
生涯学習委員の宇野秋人先生より『義肢装具士の生涯学習の重要性』について、研修副委員長の宮川拓也先生より『関係法規~義肢装具士法~』について、会則検討委員長の鈴木昭宏先生より『協会倫理綱領』について、㈱松本義肢製作所の佐口明先生より『義肢装具の支給体系』についてご講義頂きました。 就職を目前にして、緊張した面持ちで講義を受ける3年生。
自分が義肢装具士として社会に出るということは、どのような責任や義務を持つことになるのか。そして、医療職に就く社会人として必要な職業倫理を改めて考える機会になったことと思います。
就職を目前にして、緊張した面持ちで講義を受ける3年生。
自分が義肢装具士として社会に出るということは、どのような責任や義務を持つことになるのか。そして、医療職に就く社会人として必要な職業倫理を改めて考える機会になったことと思います。 セミナーの後半は、本校の卒業生である磯村明さん((株)洛北義肢)、山本卓さん(東名ブレース株式会社)、伊藤文彦さん((有)稲垣義肢)をお招きし、座談会形式で受講者を交えてのディスカッションが行われました。
セミナーの後半は、本校の卒業生である磯村明さん((株)洛北義肢)、山本卓さん(東名ブレース株式会社)、伊藤文彦さん((有)稲垣義肢)をお招きし、座談会形式で受講者を交えてのディスカッションが行われました。 始めは3年生は緊張した様子でしたが、司会の千田弦先生(研修委員)の楽しい司会で次第にリラックスでき、和やかな雰囲気で座談会が進んで行きました。
始めは3年生は緊張した様子でしたが、司会の千田弦先生(研修委員)の楽しい司会で次第にリラックスでき、和やかな雰囲気で座談会が進んで行きました。 OBの先輩方に質問する3年生。
義肢装具士になって良かったと思うこと、失敗した時の対処法など、沢山の質問が出ていました、
春からの新生活を目前に、不安に思う気持ちは先輩方も通ってきた道です。後輩たちの質問にとても親身になって答えて頂き、3年生はたいへん勇気づけられた様子でした!
OBの先輩方に質問する3年生。
義肢装具士になって良かったと思うこと、失敗した時の対処法など、沢山の質問が出ていました、
春からの新生活を目前に、不安に思う気持ちは先輩方も通ってきた道です。後輩たちの質問にとても親身になって答えて頂き、3年生はたいへん勇気づけられた様子でした!3年生はいよいよ2月27日に「第28回義肢装具士国家試験」に臨みます。先輩方のエールを糧に、あと少しラストスパートをかけて下さいね!" target="_blank">3年生卒前新人セミナーが開催されました。
 まずは、「あぶみ」と呼ばれる靴に装具を取り付ける部分の金属加工を行います。下肢装具には様々な種類がありますが、金属製の支柱を用いる場合は地面に接するこのあぶみが装具の最も重要な土台となります。
まずは、「あぶみ」と呼ばれる靴に装具を取り付ける部分の金属加工を行います。下肢装具には様々な種類がありますが、金属製の支柱を用いる場合は地面に接するこのあぶみが装具の最も重要な土台となります。 この学生はあぶみの高さを決める重要な工程をしています。
数ミリのずれが装具の動きを悪くしてしまうため、学生たちも真剣です。
この学生はあぶみの高さを決める重要な工程をしています。
数ミリのずれが装具の動きを悪くしてしまうため、学生たちも真剣です。 義肢装具学科では、すべての学生が一つずつ義肢や装具を仕上げる製作実習を行っています!
義肢装具学科では、すべての学生が一つずつ義肢や装具を仕上げる製作実習を行っています!
この学生は支柱に半月を取り付けているところです。 装具の継ぎ手部分が正しく可動するには、支柱が捻れていないことが重要です。
金属の曲げ加工に苦手意識はあるものの、一年生の時から比べると製作スピードが確実に早くなっていますね! 正確に製作物を作る技術を習得することが何より大切ですが、決められた時間の中で作業が終えられることも必要です。常に装具の完成を待っている患者様のことを忘れずにいて下さい!" target="_blank">2年生 より良い適合を目指して!「長下肢装具」
 中川教務主任の一年間を締めくくるお話を学生全員で聞いた後、いよいよ大掃除がスタートです。学生たちが学内を隅々まできれいにして休みを迎えるのは義肢装具学科の伝統です!
中川教務主任の一年間を締めくくるお話を学生全員で聞いた後、いよいよ大掃除がスタートです。学生たちが学内を隅々まできれいにして休みを迎えるのは義肢装具学科の伝統です! 汚れているところがあれば、進んできれいにする!それが義肢装具学科の学生です!
汚れているところがあれば、進んできれいにする!それが義肢装具学科の学生です! さあ、いよいよお昼休み。お待ちかねのカレーの時間がやってきました!
さあ、いよいよお昼休み。お待ちかねのカレーの時間がやってきました! みんなで顔をあわせて、一年間の出来事をいろいろ話しているようですね!
みんなで顔をあわせて、一年間の出来事をいろいろ話しているようですね! 臨床実習でお世話になっている株式会社青森日東義肢様(青森市)より、今年も美味しいリンゴをたくさん送って頂きました!
時吉社長様、ありがとうございました!
臨床実習でお世話になっている株式会社青森日東義肢様(青森市)より、今年も美味しいリンゴをたくさん送って頂きました!
時吉社長様、ありがとうございました! 学生たちはみんな、美味しそうにリンゴを頬張っていました。
これで午後からの掃除も頑張れますね!
学生たちはみんな、美味しそうにリンゴを頬張っていました。
これで午後からの掃除も頑張れますね!3年生にとっては今日が学生生活最後の大掃除となりました。慣れ親しんだ教室を大掃除するのもこれが最後。お昼のカレーも3年生は少し感慨深げに食べているようでした・・・。 冬休み明け、元気に登校してくるのを待っています!" target="_blank">X'mas Eveに大掃除を行いました。
 この学生は“トースカン”という工具を使って、義足の高さを設定する作業をしています。
この学生は“トースカン”という工具を使って、義足の高さを設定する作業をしています。 こちらの学生は短下肢装具の石膏モデル(陽性モデル)の修正を行っています。1mmの違いが装具のアライメントに大きく影響することを学生たちは学習しています。
こちらの学生は短下肢装具の石膏モデル(陽性モデル)の修正を行っています。1mmの違いが装具のアライメントに大きく影響することを学生たちは学習しています。 こちらの学生は下腿義足の外装仕上げ作業をしています。患者様が装着することを意識して、細部まで丁寧に仕上げることが大切ですね!
こちらの学生は下腿義足の外装仕上げ作業をしています。患者様が装着することを意識して、細部まで丁寧に仕上げることが大切ですね!1年生はこの講義を通して工具・機械の使い方や、様々な材料を加工して義肢装具を製作する基礎を学びます。今回の実技試験で思い通りに製作できた学生も、なかなか上手く出来なかった学生も、自分なりにしっかり自己分析して明日に繋げましょう!" target="_blank">1年生 義肢装具基本工作論の実技試験が行われました。
実習指導者の先生に指導をして頂きながら、知識の無い自分、 技術の無い自分を間の当たりにし、今の自分に出来ることを必死に やってきた様子が目に浮かびました。 就職をしてからも、成長し続けてくれることと思います。
さて、実習も終わり2年生は国家試験勉強一色の日々に!! 体調に気を付けて頑張りましょう!!
1年生はタイトなスケジュールの中、準備お疲れさまでした。 1年生の奮闘についてはまた後日のブログで・・・ " target="_blank">実習お疲れ様会
 講義では各部疾患に対する装具の適応や機能、治療効果などについてこれまでの臨床データを基に説明をしていただきました。
講義では各部疾患に対する装具の適応や機能、治療効果などについてこれまでの臨床データを基に説明をしていただきました。 特に膝関節の靱帯損傷に対する膝装具の適応について興味を持った学生は多かったようです。整形外科学の講義で学んだ知識と今回の講義内容を重ね合わせて、しっかり復習して行きましょう!
特に膝関節の靱帯損傷に対する膝装具の適応について興味を持った学生は多かったようです。整形外科学の講義で学んだ知識と今回の講義内容を重ね合わせて、しっかり復習して行きましょう! それでは、実際に装具を装着してみましょう!
臨床現場では義肢装具士は装具の適合状態を確認するだけでなく、患者様に適切な装着方法も説明しなくてはいけません。装着の手順やベルトの向きなどもしっかり覚えて下さいね!
それでは、実際に装具を装着してみましょう!
臨床現場では義肢装具士は装具の適合状態を確認するだけでなく、患者様に適切な装着方法も説明しなくてはいけません。装着の手順やベルトの向きなどもしっかり覚えて下さいね! しっかり装着できていますか?患者様に説明するように丁寧な対応を心掛けましょう!
しっかり装着できていますか?患者様に説明するように丁寧な対応を心掛けましょう! 実際に装具を装着してみると、装具の装着感や患者様にご説明する際のポイントがより理解できます。
実際に装具を装着してみると、装具の装着感や患者様にご説明する際のポイントがより理解できます。今回、アルケア株式会社の先生方にご講義いただいた装具は臨床現場で多く用いられているものばかりです。来年の臨床実習では、また違った視点でこれらの装具を考えられるようになったのではないでしょうか。
アルケア株式会社名古屋営業所の皆様、ご講義いただきありがとうございました!" target="_blank">2年生 アルケア株式会社の特別講義が行われました。
1)対象となる症例の病態を医学的に理解し「症例を診る力」を養う。 2)ひとりの学生が経験した症例を学生全員で「情報共有」することで、多くの知識、技術を学習する。 3)症例報告という形式で「プレゼンテーション能力」を養う。
学生たちは臨床実習終了後、3ヶ月以上の準備期間を経て発表当日を迎えました。
[発表演題] Session1:整形外科疾患Ⅰ 1-1 先天性膝関節拘縮症に対する術後の膝装具製作について 第3学年 舟戸なつみ 1-2 アキレス腱延長術に対する装具の処方について 第2学年 神谷大地 1-3 電撃症に対する長下肢装具の製作 第3学年 高木友弥 1-4 進行性筋ジストロフィー症に対する体幹装具付長下肢装具の製作 第2学年 小木曽慎
Session2:整形外科疾患Ⅱ 2-1 CADシステムを用いた体幹装具の製作 第3学年 堀さやか 2-2 股関節人工骨頭置換術によって脚長差を呈した1症例 第2学年 小塚啓文 2-3 エーラスダンロス症候群によって生じた足部変形に対する靴型装具の製作 第2学年 坂野典生 2-4 足部痛患者に対する足底装具の製作 第3学年 小川卓司
Session3:脳血管疾患・神経疾患 3-1 脳血管障害に対するオクラホマ継手付プラスチック短下肢装具について 第2学年 辻元彰海 3-2 左視床出血に対する装具の検討と製作 第3学年 渡久地政樹 3-3 対麻痺に対するプラスチック製短下肢装具の製作 第2学年 鈴木田典子 3-4 第1腰椎圧迫骨折による脊髄損傷患者に対する長下肢装具の製作 第2学年 忠岡太聖 3-5 脳血管障害による片麻痺に対して長対立装具が処方された一例 第3学年 片野ふくみ 3-6 先天性の体幹機能障害により脊柱側弯症を呈した症例 第2学年 高瀬結衣 3-7 頸髄損傷に対する上肢装具の製作 第3学年 藤澤佳代子
Session4:切断 4-1 右手関節離断に対する筋電義手の製作 第3学年 藤田祐実 4-2 中足骨切断に対する足袋式足根中足義足の製作 第3学年 田中照己 4-3 下腿切断に対するライナー付TSB式下腿義足の製作 第2学年 林利和子 4-4 小児切断後の経過と足部変更に伴う歩容変化について 第3学年 岡本敬之
以上、19演題です。 この中から参加者全員の投票によって最優秀賞、優秀賞を選出しました。
 参加者は総勢90名でした。11名の来賓の先生方をお迎えし、貴重なご意見を頂戴しました。ご参加いただきました先生方、ありがとうございました。
参加者は総勢90名でした。11名の来賓の先生方をお迎えし、貴重なご意見を頂戴しました。ご参加いただきました先生方、ありがとうございました。 セッションごとに学生2名が座長を担当しました。学生が座長を経験することで会の進行や質問のタイミングなどを学ぶことができ、彼らにとっても貴重な学びの場となったようです。
セッションごとに学生2名が座長を担当しました。学生が座長を経験することで会の進行や質問のタイミングなどを学ぶことができ、彼らにとっても貴重な学びの場となったようです。次は発表者の様子です。一部のみご紹介させていただきます。
 学生たちはみんな自信に満ちた表情で発表をしていました。限られた時間のなかで、相手にいかに分かりやすく情報を伝えるかということはとても難しいことですが、自身が経験した症例だからこそ発表する内容やその姿勢に熱が感じられました!
学生たちはみんな自信に満ちた表情で発表をしていました。限られた時間のなかで、相手にいかに分かりやすく情報を伝えるかということはとても難しいことですが、自身が経験した症例だからこそ発表する内容やその姿勢に熱が感じられました! 当日は姉妹校である中部リハビリテーション専門学校の村上先生や、㈱松本義肢製作所の溝手先生など、日ごろから非常勤講師としてご指導いただいている先生方にお越しいただき、学生たちと活発なディスカッションをしていただきました。
当日は姉妹校である中部リハビリテーション専門学校の村上先生や、㈱松本義肢製作所の溝手先生など、日ごろから非常勤講師としてご指導いただいている先生方にお越しいただき、学生たちと活発なディスカッションをしていただきました。 フロアの学生からも活発な質問が出ていました。どんな些細なことにも疑問を持ち、恥ずかしがらずに質問する姿勢はPO学科の学生の伝統です。
フロアの学生からも活発な質問が出ていました。どんな些細なことにも疑問を持ち、恥ずかしがらずに質問する姿勢はPO学科の学生の伝統です。 参加者全員の投票による審査の結果、最優秀賞は岡本敬之君(第3学年)、優秀賞は田中照巳さん(第3学年)、藤田祐実さん(第3学年)、舟戸なつみさん(第3学年)が選ばれました。
受賞者の皆さんには学園より記念のトロフィーと校章入りクリスタルの楯が贈呈されました。
岡本君、田中さん、藤田さん、舟戸さん、受賞おめでとうございました!
参加者全員の投票による審査の結果、最優秀賞は岡本敬之君(第3学年)、優秀賞は田中照巳さん(第3学年)、藤田祐実さん(第3学年)、舟戸なつみさん(第3学年)が選ばれました。
受賞者の皆さんには学園より記念のトロフィーと校章入りクリスタルの楯が贈呈されました。
岡本君、田中さん、藤田さん、舟戸さん、受賞おめでとうございました! 発表された学生の皆さん、ご苦労様でした。また、前日深夜まで発表の予行演習をご指導いただいた名和先生、唐澤先生、ありがとうございました。
この症例報告会を通して多くの学生が、臨床実習という機会に何を学習し、何を経験するべきかを改めて理解したことと思います。来年の臨床実習でも、より明確な目的意識を持って臨んで下さい。
また、3年生の皆さんはこの経験を活かし、「患者様のために探究する姿勢」を忘れずに、臨床でも活躍して下さい!" target="_blank">臨床実習症例報告会が行われました。
発表された学生の皆さん、ご苦労様でした。また、前日深夜まで発表の予行演習をご指導いただいた名和先生、唐澤先生、ありがとうございました。
この症例報告会を通して多くの学生が、臨床実習という機会に何を学習し、何を経験するべきかを改めて理解したことと思います。来年の臨床実習でも、より明確な目的意識を持って臨んで下さい。
また、3年生の皆さんはこの経験を活かし、「患者様のために探究する姿勢」を忘れずに、臨床でも活躍して下さい!" target="_blank">臨床実習症例報告会が行われました。 長下肢装具の製作実習は、教員のデモンストレーションでしっかり学んだ後に、学生同士が互いの下肢をトレースします。
長下肢装具の製作実習は、教員のデモンストレーションでしっかり学んだ後に、学生同士が互いの下肢をトレースします。
 次は採型実習です。
この装具は、ギプス包帯で採型した石膏モデルを基に製作する場合もあるため、その状況を想定して採型練習も行います。
2年生もこの時期になると、自信を持って採型ができるようになっていますね!
次は採型実習です。
この装具は、ギプス包帯で採型した石膏モデルを基に製作する場合もあるため、その状況を想定して採型練習も行います。
2年生もこの時期になると、自信を持って採型ができるようになっていますね!次回は金属支柱の曲げ加工の様子をお伝えします。" target="_blank">2年生 長下肢装具の製作実習がスタートしました。
 表彰式での大村愛知県知事との記念撮影。
表彰式での大村愛知県知事との記念撮影。本校では香川先生が2016年にフランス共和国(ボルドー市)で開催される「第9回国際アビリンピック」で義肢競技の日本代表選手として活躍されることを期待しています! 香川先生、義肢装具学科の学生たちが応援しています!ぜひ頑張ってください!!
 大会前日(11月21日)の読売新聞 愛知県内版 に香川先生の記事が掲載されました。
母校である本校のことも少し掲載されています!
" target="_blank">香川先生、金賞受賞おめでとうございます!
大会前日(11月21日)の読売新聞 愛知県内版 に香川先生の記事が掲載されました。
母校である本校のことも少し掲載されています!
" target="_blank">香川先生、金賞受賞おめでとうございます! 次に足の評価を学びます。
足はそれぞれに特有のアライメントがあり、複数の運動の組み合わせによって歩行を可能にしています。義肢装具士はその患者様の足のどこに問題があり、どの関節にアプローチするべきかを的確に判断する必要があります。
次に足の評価を学びます。
足はそれぞれに特有のアライメントがあり、複数の運動の組み合わせによって歩行を可能にしています。義肢装具士はその患者様の足のどこに問題があり、どの関節にアプローチするべきかを的確に判断する必要があります。 いよいよラスト(木型)からアッパーのデザインを設計します。靴を製作するなかで最も楽しい工程と言えますが、製作者の美的センスが問われる難しい工程でもあります。
いよいよラスト(木型)からアッパーのデザインを設計します。靴を製作するなかで最も楽しい工程と言えますが、製作者の美的センスが問われる難しい工程でもあります。 アッパーのデザインには、基準となる数値が多く設定されています。この数値を計算しながら、世界に一つしかない靴をデザインします。
アッパーのデザインには、基準となる数値が多く設定されています。この数値を計算しながら、世界に一つしかない靴をデザインします。 アッパーのデザインが決まったら画用紙を使って実際にアッパーを作ってみましょう!これはどこかで見たようなデザインですね?
アッパーのデザインが決まったら画用紙を使って実際にアッパーを作ってみましょう!これはどこかで見たようなデザインですね? この学生は自分が履いているスニーカーを改めてデザインしてみたようです。
既製品の靴と同じデザインになっているでしょうか?
この学生は自分が履いているスニーカーを改めてデザインしてみたようです。
既製品の靴と同じデザインになっているでしょうか? 今年もさまざまなデザインのアッパーが出来上がりました。
学生たちはあまりに夢中になり過ぎて、講義時間をすっかり忘れてアッパーのデザイン設計に没頭していました。
眞殿先生、今年も靴づくりの楽しさを学生たちにお教えいただき、
ありがとうございました!
来年度もよろしくお願いします!
今年もさまざまなデザインのアッパーが出来上がりました。
学生たちはあまりに夢中になり過ぎて、講義時間をすっかり忘れてアッパーのデザイン設計に没頭していました。
眞殿先生、今年も靴づくりの楽しさを学生たちにお教えいただき、
ありがとうございました!
来年度もよろしくお願いします!" target="_blank">2年生 靴型装具の特別講義が行われました。
 いざ本番開始!
資料やプレゼンの準備を綿密に行ってきた甲斐もあり、どのグループも3年生らしく堂々と発表していました。
いざ本番開始!
資料やプレゼンの準備を綿密に行ってきた甲斐もあり、どのグループも3年生らしく堂々と発表していました。 どんな計測をしたのか?評価の方法は?後輩・同級生・先生方からたくさんの質問が活発に飛び交います。
どんな計測をしたのか?評価の方法は?後輩・同級生・先生方からたくさんの質問が活発に飛び交います。 どんな質問にも自信を持って答える3年生。
中には質問のために特別にスライドを準備している学生もいました。限られた時間の中で分かりやすく研究内容を伝えるため、プレゼンに工夫を凝らしている様子がとても印象的でした。
どんな質問にも自信を持って答える3年生。
中には質問のために特別にスライドを準備している学生もいました。限られた時間の中で分かりやすく研究内容を伝えるため、プレゼンに工夫を凝らしている様子がとても印象的でした。 座長を務めてもらった2年生。
来年には発表者として演台に上がる番ですね!
座長を務めてもらった2年生。
来年には発表者として演台に上がる番ですね! 1、2年生も先輩たちのプレゼンを真剣に聞いていました。研究することの楽しさを少しずつ感じ取っている様子でした!
1、2年生も先輩たちのプレゼンを真剣に聞いていました。研究することの楽しさを少しずつ感じ取っている様子でした!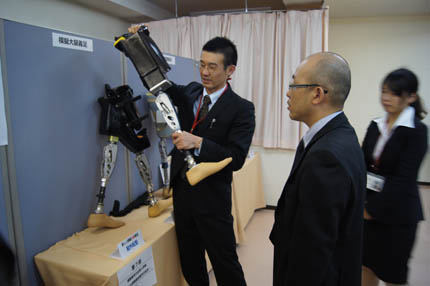 研究テーマの製作物の展示ブースを設けました。
製作物についてディスカッションできるのも研究発表会の醍醐味ですね!
研究テーマの製作物の展示ブースを設けました。
製作物についてディスカッションできるのも研究発表会の醍醐味ですね!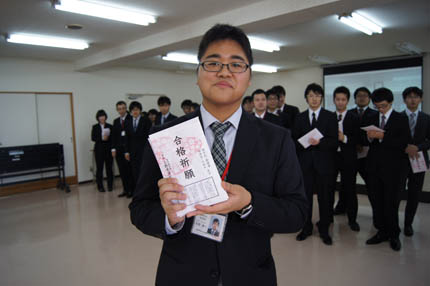 発表会の後には、毎年恒例の「国家試験合格祈願セット」の授与式が行われました。
残すは就職活動と国家試験ですね!まだまだ気が抜けない3年生ですが、あと4ヶ月、しっかり走り切って下さい!
発表会の後には、毎年恒例の「国家試験合格祈願セット」の授与式が行われました。
残すは就職活動と国家試験ですね!まだまだ気が抜けない3年生ですが、あと4ヶ月、しっかり走り切って下さい! その後、学生会の皆さんが、「卒業研究お疲れ様会」を催してくれました!
その後、学生会の皆さんが、「卒業研究お疲れ様会」を催してくれました! 2年生は先輩とたくさんディスカッションをして、この後はじまる研究テーマ決めに活かしましょう!
2年生は先輩とたくさんディスカッションをして、この後はじまる研究テーマ決めに活かしましょう! 発表前の緊張もほぐれて、笑顔がこぼれていますね。
3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">卒業研究発表会が行われました。
発表前の緊張もほぐれて、笑顔がこぼれていますね。
3年生の皆さん、お疲れ様でした!" target="_blank">卒業研究発表会が行われました。 人工ボディを実際に手にとってみるとその精巧な作りに驚きます。学生たちは講義中もとにかく熱心に質問をしていました!
人工ボディを実際に手にとってみるとその精巧な作りに驚きます。学生たちは講義中もとにかく熱心に質問をしていました! 講義の後は、「細密印象材」で採型の実習をしました。
福島先生の繊細な採型に、学生たちは興味津々です!
講義の後は、「細密印象材」で採型の実習をしました。
福島先生の繊細な採型に、学生たちは興味津々です! 次にグループに分かれて、実際に採型実習を行いました。
このグループは「鼻」の型を採っていますね。
次にグループに分かれて、実際に採型実習を行いました。
このグループは「鼻」の型を採っていますね。 こちらは「耳」の型を採っているグループ。
採型に使用している細密印象材は皮膚の凹凸、シワまではっきり移すことができるので、日ごろじっくり見ることのない部分まで手に取って観察することができました。
こちらは「耳」の型を採っているグループ。
採型に使用している細密印象材は皮膚の凹凸、シワまではっきり移すことができるので、日ごろじっくり見ることのない部分まで手に取って観察することができました。 「顔面」全体の型にチャレンジしているグループ。
息ができるよう口にストローを咥えているのでご安心下さい!
「顔面」全体の型にチャレンジしているグループ。
息ができるよう口にストローを咥えているのでご安心下さい!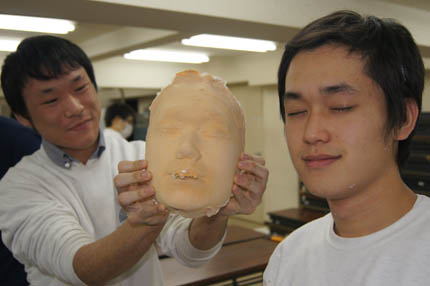 今回使用した石膏は超硬石膏、硬石膏、普通石膏の3種類です。
超硬石膏は何十年経っても劣化しないので、今の自分を記録するには最適な材料です!
今回使用した石膏は超硬石膏、硬石膏、普通石膏の3種類です。
超硬石膏は何十年経っても劣化しないので、今の自分を記録するには最適な材料です! 最後に、両先生と学生全員で記念写真を撮りました!
お忙しいところ今年もご講義いただきました、福島先生、木下先生、ありがとうございました!" target="_blank">NEW! 2年生 人工ボディの特別講義が行われました。
最後に、両先生と学生全員で記念写真を撮りました!
お忙しいところ今年もご講義いただきました、福島先生、木下先生、ありがとうございました!" target="_blank">NEW! 2年生 人工ボディの特別講義が行われました。参加された方からは毎回好評を頂いております。 教員も詳しくご説明いたします!
この機会に、ぜひ学院をのぞいてみませんか? みなさんのお越しをお待ちしております!
" target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ
 次は、社内「青山ホール」の中で様々な車椅子を試乗させていただきました。改めて車椅子の重要性を認識した学生も多かったようです。
次は、社内「青山ホール」の中で様々な車椅子を試乗させていただきました。改めて車椅子の重要性を認識した学生も多かったようです。 次は、いよいよ工場内を見学しました。分業制による製作の流れを初めて見学し、学生たちは様々な感想を持ったようです。
次は、いよいよ工場内を見学しました。分業制による製作の流れを初めて見学し、学生たちは様々な感想を持ったようです。 「資料室」に展示されている昔の義肢装具を見学させていただきました。日清、日露戦争当時の恩賜の義足やセルロイド製のコルセットなど歴史的価値のある展示品が数多くあり、学生たちも熱心に質問をしていました。
「資料室」に展示されている昔の義肢装具を見学させていただきました。日清、日露戦争当時の恩賜の義足やセルロイド製のコルセットなど歴史的価値のある展示品が数多くあり、学生たちも熱心に質問をしていました。1年生は4月に入学してから約半年間、義肢装具について勉強してきました。現在、必死に医学用語を覚え、義肢装具の製作を経験するなかで、実際の製作現場はどのように目に映ったでしょうか。今回の見学で得た知識を活かして、さらに学んで行くための糧にして下さいね!
長時間にわたり会社見学をご担当いただきました佐口先生にお礼申し上げます。誠にありがとうございました。
お知らせ 義肢装具学科では、今回ご紹介した松本義肢製作所への施設見学ツアーを受付けています。あなたのご都合の良い時間を利用して、学校や義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員がご案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校にお越し頂き、専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : (株)松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">NEW! 1年生 (株)松本義肢製作所へ会社見学に行ってきました。
" target="_blank">NEW! 1年生 (株)松本義肢製作所へ会社見学に行ってきました。" target="_blank">聴能言語学科1年生の 『学内実習』 見学
奥村先生、お忙しいところご講義いただき、ありがとうございました。" target="_blank">1年生 奥村先生の特別講義が行われました。
 義肢装具士は多種多様な義肢パーツの特徴をよく知っている必要があります。膝継手や足部の機能が義足使用者の生活にどのように影響するのか、しっかり勉強して下さいね!
義肢装具士は多種多様な義肢パーツの特徴をよく知っている必要があります。膝継手や足部の機能が義足使用者の生活にどのように影響するのか、しっかり勉強して下さいね! 義足の膝継手を分解した状態から組み立てる実習をしました。このような作業を日常的に義肢装具士が行うことはありませんが、機械的な機構を理解する上で貴重な経験になったと思います。
義足の膝継手を分解した状態から組み立てる実習をしました。このような作業を日常的に義肢装具士が行うことはありませんが、機械的な機構を理解する上で貴重な経験になったと思います。 最後に、「体験用模擬義足」を使って義足足部の感触を一つ一つ体験しました。ご紹介いただいた足部のなかには、小走りができる高機能なものから、ゆっくり歩きで安全性を重視した低活動者向けのものまで幅広くあり、学生たちもその感触の違いに驚いていたようです。
最後に、「体験用模擬義足」を使って義足足部の感触を一つ一つ体験しました。ご紹介いただいた足部のなかには、小走りができる高機能なものから、ゆっくり歩きで安全性を重視した低活動者向けのものまで幅広くあり、学生たちもその感触の違いに驚いていたようです。深谷先生、藤田先生は本学院の卒業生であり、義肢パーツメーカーに勤務する義肢装具士として現在どのように患者様と関わっているのか、仕事の楽しさや魅力などを交えながらご講義いただきました。 深谷先生、藤田先生本当にありがとうございました!" target="_blank">3年生 義足膝継手の特別講義が行われました!
 10:30~ 学科説明
専任教員より「義肢装具とは?」「義肢装具士の仕事とは?」「義肢装具士に求められるスキルは?」など、義肢装具士という資格の魅力についてご説明しました.
カリキュラムの説明では、「“難しい”を“楽しい”に変える!」という学科の教育方針をご説明させていただきました!
10:30~ 学科説明
専任教員より「義肢装具とは?」「義肢装具士の仕事とは?」「義肢装具士に求められるスキルは?」など、義肢装具士という資格の魅力についてご説明しました.
カリキュラムの説明では、「“難しい”を“楽しい”に変える!」という学科の教育方針をご説明させていただきました!11:30~ 入試直前対策講座 教務主任より、本学科の入学試験について説明が行われました。筆記試験の出題傾向と学習の要点、面接試験の重要ポイントなどについて具体的に説明を行い、皆さん熱心にメモを取っていました。特に、面接試験に向けて「義肢装具士という仕事を理解していること」が重要です!オープンキャンパス、施設見学ツアー、学校見学に参加した皆さんには、この点をしっかりと理解していただいたと思います。
当日のスライドの一部をご紹介します!
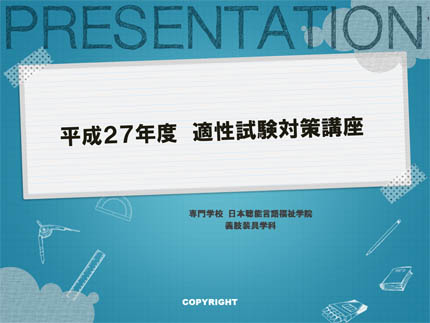
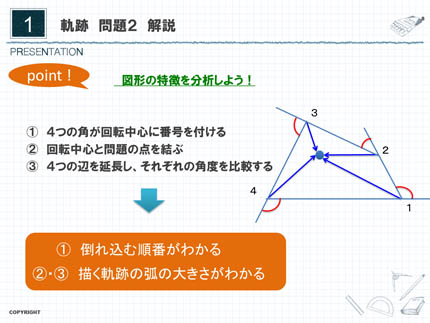
参加者(保護者)の声 入試対策になって良かったです。 (高校3年) 入試についての説明が良かった。 (高校3年) 本日は2回目の参加だったのですが、貴校の入試に向けての対策などが聞けて良かったです。 (高校3年) 入試について詳しく知ることができて良かったです。 (高校3年) 今日の入試対策を活かして残り一ヶ月、勉強して合格できるようにしたいです。ありがとうございました。 (高校3年) 入試のヒントがいろいろ聞けて参考になりました。 (高校3年) 入試内容が非常に分かりやすかったです。 (高校3年) 入試について詳しく聞くことができてとても良かったです。 (高校3年) 義肢装具士について、インターネットなどでは知ることのできないことを詳しく説明していただいて、将来のことについてとても参考になりました。 (高校1年) 学校の伝統や実績が分かり、とても素晴らしい学校だと分かりましたので、今後、進路のひとつとして考えながら家族で相談していきたいと思います。義肢装具士の仕事のことも、重要さもよく分かりました。女性の患者さんにとっては、女性の義肢装具士が求められるのかもしれませんね。ありがとうございました。 (保護者) 入試問題の説明が良かったです。 (保護者)
この他にもたくさんのご感想をいただきました。ありがとうございました。入学試験に向けての心構え、対策ポイントをしっかりと把握していただけたでしょうか。筆記試験、志望動機、義肢装具士の理解、学習の意欲、モノ作りへの興味など、今からしっかりと準備をして10月の入試に臨んでください! 試験会場で皆さんとお会いすることを楽しみにしています!
ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました!
(義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (第4回オープンキャンパスの様子はコチラ) (第3回オープンキャンパスの様子はコチラ) (第2回オープンキャンパスの様子はコチラ) (第1回オープンキャンパスの様子はコチラ)
今後も引き続きオープンキャンパスを開催します。社会人や大学生で、日中なかなか時間を作れず参加できなかった方、情報を得るチャンスです!ぜひご参加ください!!

 " target="_blank">第5回オープンキャンパスが行われました!
" target="_blank">第5回オープンキャンパスが行われました! IRCソケットは、坐骨周辺の形状を正確に採型するため、二人一組で行います。四辺形ソケットに比べて坐骨周辺の適合をより厳密に行う必要があるため、骨盤の形状が解剖学的によく理解されていないと採型はできません。しっかり、復習しておきましょう!
IRCソケットは、坐骨周辺の形状を正確に採型するため、二人一組で行います。四辺形ソケットに比べて坐骨周辺の適合をより厳密に行う必要があるため、骨盤の形状が解剖学的によく理解されていないと採型はできません。しっかり、復習しておきましょう! では、いよいよ採型です!
採型の前には、まず患者様のデータをカルテに記録して行きます。
3年生ともなると上手にコミュニケーションがとれていますね!
必要な情報をしっかり聞き取り、義足製作にきちんと反映させて下さい!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
では、いよいよ採型です!
採型の前には、まず患者様のデータをカルテに記録して行きます。
3年生ともなると上手にコミュニケーションがとれていますね!
必要な情報をしっかり聞き取り、義足製作にきちんと反映させて下さい!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
 採型の手順も段取り良く行えていますね!
メインで採型する学生も自分のスタイルが少しずつ出来上がっていて、サポートする学生も的確な補助がされていました。着々と臨床現場に出る準備が出来てきました!
採型の手順も段取り良く行えていますね!
メインで採型する学生も自分のスタイルが少しずつ出来上がっていて、サポートする学生も的確な補助がされていました。着々と臨床現場に出る準備が出来てきました!次回は、陽性モデル修正の様子をレポートします! 10月から後期の授業が始まりますので、引き続き講義の様子をどんどんお伝えして行きます!
お知らせ 義肢装具学科では、随時学校見学、義肢装具製作施設見学ツアーを受付けています。あなたのご都合の良い時間を利用して、学校や義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校にお越し頂き、専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">3年生 大腿義足の採型実習が行われました!
" target="_blank">3年生 大腿義足の採型実習が行われました!これから受験を考えるうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひご参加ください! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ)
当日の学科説明のスライドを一部ご紹介。 義肢装具士の仕事についてから始まり、学科の特色をご説明します。




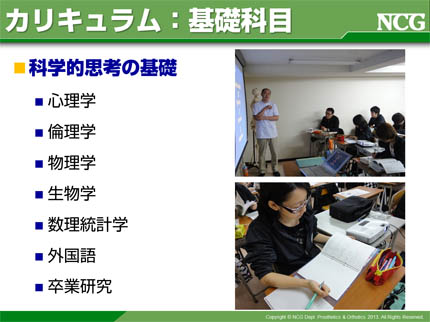
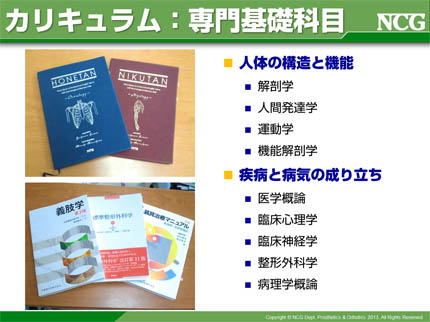
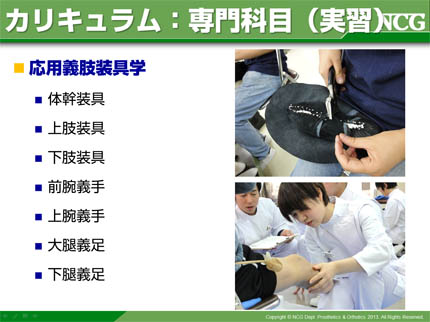

国家試験対策や入試のポイントなど、重要な情報を得るチャンスです!ぜひご参加ください!!

 " target="_blank">9月6日(土)義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ!
" target="_blank">9月6日(土)義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ!学院では卒業論文がないので、 研究の仕方がわからないなどの疑問の助けになればと、 年1回は「研究」色の強いイベントを開催しています。
今年は卒業生の学会発表を中心に、 その背景となる知識や仮説についてもレクチャーをしてもらい、 どうやって研究を進めているのか学習しました。 また、二村先生は大学の研究生として、 伊藤先生はイギリス留学と大学院博士課程での学びに ついても合わせてお話しいただきました。
 座長の渡邉先生は二村先生・伊藤先生の学生時代には
教員をされていたので大変お世話になっており、
十数年を経て壇上で質問を受けるなんて、
学会発表よりも緊張したのではないでしょうか?
座長の渡邉先生は二村先生・伊藤先生の学生時代には
教員をされていたので大変お世話になっており、
十数年を経て壇上で質問を受けるなんて、
学会発表よりも緊張したのではないでしょうか?
若い卒業生を中心に、在校生には ちょっと難しかったかもしれません。 でもみんな熱心に聞き入っていました。 次は誰がその立場になるのか、楽しみですね! " target="_blank">同窓会総会&研究会開催報告
10:30~学科説明 専任教員より義肢装具学科についての紹介、最新の入試情報などの説明を行いました。
 11:30~学生企画
学生企画「学生の一日」を3年生の片野さんが元気にプレゼンしてくれました。3年生は2ヶ月間という長い臨床実習を終えたばかり。「勉強は大変だけど、患者様が喜ぶ顔が見られることが楽しい。」という言葉がとても印象的でした!
11:30~学生企画
学生企画「学生の一日」を3年生の片野さんが元気にプレゼンしてくれました。3年生は2ヶ月間という長い臨床実習を終えたばかり。「勉強は大変だけど、患者様が喜ぶ顔が見られることが楽しい。」という言葉がとても印象的でした! 12:00~ランチタイム
在校生と一緒に軽食を取りながら学校生活について、授業の様子やどんな勉強をしているのかなど、楽しく会話がはずんでいました!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
12:00~ランチタイム
在校生と一緒に軽食を取りながら学校生活について、授業の様子やどんな勉強をしているのかなど、楽しく会話がはずんでいました!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 12:45~体験授業
今回は「筋電義手に触れてみよう!」というテーマで体験授業を行いました。
筋電義手は筋肉が運動によって収縮する際に発生する微弱な電気信号を利用して電動ハンドをコントロールするタイプの義手です。前回に引き続き専門用語が多く難しい内容でしたが、丁寧な説明に皆さん熱心にメモをとっていました!
12:45~体験授業
今回は「筋電義手に触れてみよう!」というテーマで体験授業を行いました。
筋電義手は筋肉が運動によって収縮する際に発生する微弱な電気信号を利用して電動ハンドをコントロールするタイプの義手です。前回に引き続き専門用語が多く難しい内容でしたが、丁寧な説明に皆さん熱心にメモをとっていました! 講義が終わった後は筋電義手ユーザーにご協力いただき、義手操作訓練のデモンストレーションが行われました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
講義が終わった後は筋電義手ユーザーにご協力いただき、義手操作訓練のデモンストレーションが行われました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
 さあ、いよいよ参加者の皆さんの体験実習です!
実際に参加者の皆様に筋電義手に触れていただき、学生に手伝ってもらいながらハンドの操作を体験しました。皆さんとても上手に操作していましたね!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
さあ、いよいよ参加者の皆さんの体験実習です!
実際に参加者の皆様に筋電義手に触れていただき、学生に手伝ってもらいながらハンドの操作を体験しました。皆さんとても上手に操作していましたね!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 次は、実際の授業でも使っている「摸擬上腕義手」の装着体験をしていただきました!どのような仕組みで義手が動いているのかを参加者全員に考えてもらいました。その仕組みが解った瞬間、皆さんから一斉に「すごい!」という声が上がりました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
次は、実際の授業でも使っている「摸擬上腕義手」の装着体験をしていただきました!どのような仕組みで義手が動いているのかを参加者全員に考えてもらいました。その仕組みが解った瞬間、皆さんから一斉に「すごい!」という声が上がりました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。学生全員が筋電義手の採型・製作・適合を学習するカリキュラムが組まれているPO養成校は全国で本校だけです。 近年、筋電義手の処方数は増加傾向にあるため、本校では全国のPO養成校に先駆けてその取り組みを始めています。
参加者(保護者)の声 筋電義手を動かすのは難しかったけど、良かった。義手にもいろいろな種類があることが分かった。 (高校3年)
改めて義肢装具士という仕事について興味がわきました。 (高校3年)
筋電義手を体験してボールを掴んだりすることができて、とても興味深かった。 (社会人)
実際に義手ユーザーの方々のお話を聞けて良かったです。 (高校3年)
実際オープンキャンパスに参加して、この学校や義肢装具士に対するイメージが大きく変わり、参考になりました。生徒さんも先生方も生き生きとしていて、とても良い雰囲気でした。 (高校2年)
大変良いオープンキャンパスで参考になりました。先生方のお話に加え、昼食時に学生さんから色々とお話が伺えたことが良かったです。 (保護者)
この他にもたくさんのご感想を頂きました。ありがとうございました。義肢装具学科での授業内容は勿論ですが、義肢装具士の仕事の面白さや素晴らしさを感じていただけたのではないでしょうか。 ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました!
(義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (第3回オープンキャンパスの様子はコチラ) (第2回オープンキャンパスの様子はコチラ) (第1回オープンキャンパスの様子はコチラ)
今後も引き続きオープンキャンパスを開催します。社会人や大学生で、日中なかなか時間を作れず参加できなかった方、情報を得るチャンスです!ぜひご参加ください!!

 " target="_blank">第4回オープンキャンパスの様子をご紹介します!
" target="_blank">第4回オープンキャンパスの様子をご紹介します!これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (第3回オープンキャンパスの様子はコチラ) (第2回オープンキャンパスの様子はコチラ) (第1回オープンキャンパスの様子はコチラ)
当日しか聞くことのできない、国家試験対策や入試のポイントなど、重要な情報を得るチャンスです!ぜひご参加ください!!

 " target="_blank">8月23日(土)義肢装具学科オープンキャンパスのご案内
" target="_blank">8月23日(土)義肢装具学科オープンキャンパスのご案内 次は、グループに分かれてレクリエーション活動です。このグループは自家製バームクーヘン作りを選んだようですね。
次は、グループに分かれてレクリエーション活動です。このグループは自家製バームクーヘン作りを選んだようですね。 別のグループでは飛騨高山の古い町並みを散策したようですね。見知らぬ町で、何か新しい発見はありましたか?
別のグループでは飛騨高山の古い町並みを散策したようですね。見知らぬ町で、何か新しい発見はありましたか? 次はみんなで宿泊するペンションに移動です。長い山道を登って行くと、ようやくペンションが見えて来ました!
次はみんなで宿泊するペンションに移動です。長い山道を登って行くと、ようやくペンションが見えて来ました! 山頂のペンションから見る飛騨高山の景色は絶景でした!
山頂のペンションから見る飛騨高山の景色は絶景でした! 夜はみんなお待ちかねのBBQです!日ごろの学校生活や勉強の悩み、臨床実習に向けての心構えなど、夜遅くまで学生同士の話し合いは尽きなかったようです。
夜はみんなお待ちかねのBBQです!日ごろの学校生活や勉強の悩み、臨床実習に向けての心構えなど、夜遅くまで学生同士の話し合いは尽きなかったようです。 学生会幹事の皆さん、事前準備から当日の運営まで本当にご苦労さまでした!
この伝統を後輩たちにもしっかり伝えて行って下さいね!
学生会幹事の皆さん、事前準備から当日の運営まで本当にご苦労さまでした!
この伝統を後輩たちにもしっかり伝えて行って下さいね! 学生たちは、それぞれに楽しい夏の思い出ができたようです。
この夏、お盆明けから2年生はいよいよ臨床実習が始まります。
日聴の学生らしさを忘れずに、しっかり実習に励んで下さい!
学生たちは、それぞれに楽しい夏の思い出ができたようです。
この夏、お盆明けから2年生はいよいよ臨床実習が始まります。
日聴の学生らしさを忘れずに、しっかり実習に励んで下さい!オープンキャンパスで学生の一週間の生活をのぞいてみませんか? 義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています!
(義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (第2回オープンキャンパスの様子はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">今年も夏合宿が行われました!
" target="_blank">今年も夏合宿が行われました! 決められた競技課題を制限時間内に製作し、規定通りの製品に仕上がっているかを審査員が評価します。本年度は「義肢」種目が公開競技となっていたため、多くの方が会場へ見学に来られていました。
決められた競技課題を制限時間内に製作し、規定通りの製品に仕上がっているかを審査員が評価します。本年度は「義肢」種目が公開競技となっていたため、多くの方が会場へ見学に来られていました。 競技終了後の表彰式の様子です。武内君、松岡君とも大村愛知県知事(写真中央)の前で賞状とメダルを授与していただきました!
大勢の県関係者や競技選手の前での表彰式ということで、2人とも少し緊張気味でした。
競技終了後の表彰式の様子です。武内君、松岡君とも大村愛知県知事(写真中央)の前で賞状とメダルを授与していただきました!
大勢の県関係者や競技選手の前での表彰式ということで、2人とも少し緊張気味でした。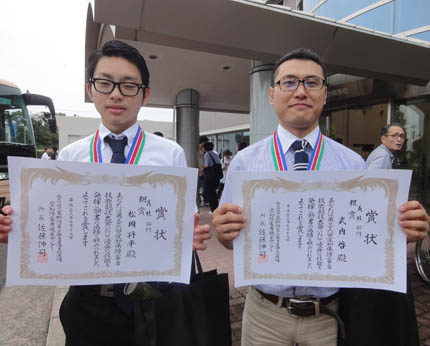 武内君、松岡君、おめでとうございました!
この受賞を励みに、今後も知識と技術の研鑽に励んで下さい!
武内君、松岡君、おめでとうございました!
この受賞を励みに、今後も知識と技術の研鑽に励んで下さい! 最後に、アビリンピックあいち2014のイメージキャラクター「アイチータ」と一緒に記念撮影。
最後に、アビリンピックあいち2014のイメージキャラクター「アイチータ」と一緒に記念撮影。第35回全国障害者技能競技大会(アビリンピックあいち2014) 障害者技能競技の全国大会である「アビリンピックあいち2014」が今年、愛知県で開催されます。(平成26年11月21日~23日) もちろん「義肢」種目も行われますので、ぜひ会場のポートメッセなごやにお越し下さい! 大会ホームページ:技能五輪・アビリンピックあいち大会2014" target="_blank">武内啓君・松岡将平君 入賞おめでとうございます!
その後は音戯の郷(おとぎのさと) 「日本でも珍しい音をテーマにした体験型ミュージアム」で いろんな音を聴きました。 言語聴覚士を目指しているんですもの、音は大事ですね。
民宿でおいしい夕食の後は、花火!
普段の勉強のことは忘れてみんなで大はしゃぎしました! 8月に行われる見学実習に向け、リフレッシュできた2日間でした。
" target="_blank">学外授業へGO!
☆学内ツアー : 学校内の見どころを学生の解説付きで見て回って頂きました。 実際に使用している訓練室、貴重な蔵書の数々がある図書館 …などなどを案内しました。 でも、私の一押しは・・・ やはり、今年度に入ってまだ4か月ほどですが、 大量に来ている求人票コーナー! 言語聴覚士は本当に売り手市場だと感じます。
☆STが実際に仕事の中で使用している機器展示 学生が実際に使用しているテキスト・ノートの展示 言語聴覚士が訓練の中で使用している検査器具、道具の数々を 展示しました。 説明しているのはもちろん、学生達。それぞれが、 学んだばかりの知識を来場された方々に分かりやすく説明していました。
学生たちの手作りによる郷土料理、教員たちの手作りによる豚汁、 から揚げ、ポテトサラダなどオードブルを囲んで 楽しく充実した時間が流れてゆきました。
 「出陣式」ということで最後に、
各実習施設へと出陣していく学生たちに
決意表明をしてもらいました。
「出陣式」ということで最後に、
各実習施設へと出陣していく学生たちに
決意表明をしてもらいました。
ひとりひとりの学生たちが実習に望む熱い気持ちが 伝わってくるようでした。
そんな先輩たちに後輩たちは激励の言葉を贈っていました。 ほのぼのとした空気が流れ盛況のうちに終わることができました。" target="_blank">補聴言語学科 実習出陣式行いました!
10:30~学科説明 専任教員より義肢装具学科についての紹介、最新の入試情報などの説明を行いました。
 11:30~学生企画
前回に引き続き、在校生の神谷君(2年生)から日ごろの学校生活の様子を身振り手振りをまじえて、楽しくプレゼンしてもらいました!
11:30~学生企画
前回に引き続き、在校生の神谷君(2年生)から日ごろの学校生活の様子を身振り手振りをまじえて、楽しくプレゼンしてもらいました!  12:00~ランチタイム
在校生と一緒にランチをとりながら学校生活について、授業の様子や入学して楽しいこと、大変なことなどを学生の視点からアドバイスをしています。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
12:00~ランチタイム
在校生と一緒にランチをとりながら学校生活について、授業の様子や入学して楽しいこと、大変なことなどを学生の視点からアドバイスをしています。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 12:45~体験授業
今回は「義足のアライメントの概念」について講義が行われました。聞きなれない専門用語がたくさん出てきたと思いますが、皆さん熱心にメモをとっていました!
12:45~体験授業
今回は「義足のアライメントの概念」について講義が行われました。聞きなれない専門用語がたくさん出てきたと思いますが、皆さん熱心にメモをとっていました!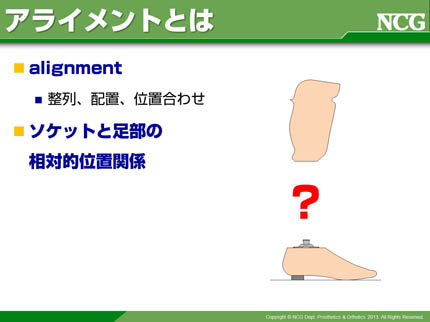
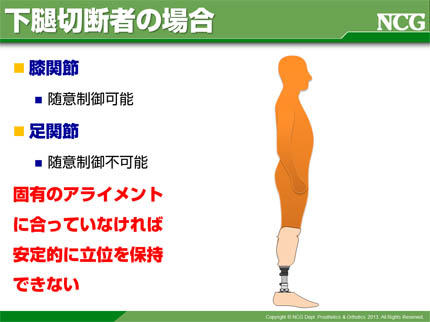 体験授業の講義スライドをご紹介します!
切断によって失った部分をただ補完(ほかん)するだけでは、立ったり、歩いたりすることはできない、ということがお解りいただけたと思います。
義肢装具士はモノづくりだけではなく、それを必要とする方にフィッティングさせる技術も必要です。
体験授業の講義スライドをご紹介します!
切断によって失った部分をただ補完(ほかん)するだけでは、立ったり、歩いたりすることはできない、ということがお解りいただけたと思います。
義肢装具士はモノづくりだけではなく、それを必要とする方にフィッティングさせる技術も必要です。 いよいよ下腿義足ユーザーの歩行観察です!
義足のアライメントの違いによる歩行の異常を観察しました。義肢装具士が現場で行っているアライメント調整も見ていただき、少しの調整で歩容がどんどん変わって行く様子に参加者は興味津々でした!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
いよいよ下腿義足ユーザーの歩行観察です!
義足のアライメントの違いによる歩行の異常を観察しました。義肢装具士が現場で行っているアライメント調整も見ていただき、少しの調整で歩容がどんどん変わって行く様子に参加者は興味津々でした!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 続いて大腿義足ユーザーの歩行観察です。
ロボットのような人工の膝関節「義足膝継手(ひざつぎて)」の動きと、それを器用に操るベテラン義足ユーザーの身体能力に参加者は感心するばかりでした!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
続いて大腿義足ユーザーの歩行観察です。
ロボットのような人工の膝関節「義足膝継手(ひざつぎて)」の動きと、それを器用に操るベテラン義足ユーザーの身体能力に参加者は感心するばかりでした!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
 歩行観察の後は、義足ユーザーへの質問タイムです。
義足ユーザーに接する機会が無く、日ごろなかなか聞けない質問にも気さくに答えていただきました。義足ユーザーの生き生きとした姿を見て、障がいを持たれた方への義肢装具の必要性を実感していただけたのではないでしょうか。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
歩行観察の後は、義足ユーザーへの質問タイムです。
義足ユーザーに接する機会が無く、日ごろなかなか聞けない質問にも気さくに答えていただきました。義足ユーザーの生き生きとした姿を見て、障がいを持たれた方への義肢装具の必要性を実感していただけたのではないでしょうか。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。参加者(保護者)の声 実際に足を失った人が、義足をつけて歩いたり走ったりする姿を間近に見られたので、大変貴重な体験ができました。ありがとうございました。 (高校3年)
午後からの参加でも手厚く対応して下さり、ありがとうございました。義肢装具士になりたいと思いました。 (高校3年)
体験授業が難しかったけど、楽しかったです。次回も参加したいと思います。 (高校3年)
前回と同じように体験実習ができて非常に良かった。また次回も参加したい。 (高校3年)
参加して良かったと思いました。ありがとうございました。 (高校3年)
義足を使用されている方を初めて見ましたが、とても楽しそうに走っている姿に、私も作りたいと感じ、義肢装具士になりたいと強く思いました。先輩にもたくさん話を聞くことができたので、よかったです。 (高校3年)
在校生の方とたくさん話ができたのでよかった。体験授業が楽しかった。 (高校3年)
先輩方と、学校生活や休日などどのような事をしているか話ができ、とても楽しかった。 (高校3年)
前回も参加しましたが、体験授業がより面白かったです。 (社会人)
体験授業の時に担当になってくれた先輩の説明がとても分かり易かったです。 (高校2年)
初めて義足ユーザーの方を見ることができました。良い体験ができて良かったです! (高校2年)
本日は大変お世話になりまして誠にありがとうございました。 ハンディを抱えておられる人々の非常に役立つとてもやりがいのある素晴らしいお仕事と実感いたしました。とてもしっかりされた学生さんと昼食の時にお話ができ、幸せでした。 (保護者)
学校全体の良い雰囲気が感じられ大変良かったです。ありがとうございました。 (保護者)
義足を使用されている方の声が聞けてよかったです。義足ユーザーの方のとても嬉しそうな顔が印象的でした。満足のいく義肢装具を作るために、多くの知識、技術、コミュニケーション能力が必要であり、容易な事ではないことが理解できました。 (保護者)
学生の方々の熱心さや、充実した学生生活を送られているのが伺えて良かったです。 (保護者)
この他にもたくさんのご感想をいただきました。ありがとうございました。ご参加いただきました皆様に、義肢装具士の業務内容や義肢装具学科の魅力についてご理解いただければ幸いです。
8月23日(土)の第4回オープンキャンパスの体験授業では、筋電義手についての講義の後、実際に筋電義手ユーザーによる操作デモンストレーションを行います。
義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています!
(義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (第2回オープンキャンパスの様子はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">第3回オープンキャンパスの様子をご紹介します!
" target="_blank">第3回オープンキャンパスの様子をご紹介します! モデル被検者さんのご要望に合わせて、ソケットの外装にイラストをデザインしてみました。モノづくりだけでなく、このような“デザイン”に興味をお持ちの方、詳しくはオープンキャンパスでご説明させていただきます!
モデル被検者さんのご要望に合わせて、ソケットの外装にイラストをデザインしてみました。モノづくりだけでなく、このような“デザイン”に興味をお持ちの方、詳しくはオープンキャンパスでご説明させていただきます!
 スポーツ用義足が完成しました!この義足は世界中の陸上選手が競技用としてパラリンピックなどでも使用しています。
7月19日(土)、ぜひこの走行用義足を見に来てくださいね!
スポーツ用義足が完成しました!この義足は世界中の陸上選手が競技用としてパラリンピックなどでも使用しています。
7月19日(土)、ぜひこの走行用義足を見に来てくださいね!7月19日(土)の第3回オープンキャンパスの体験授業では、先生から義足アライメントについての講義の後、実際に下腿義足・大腿義足の歩行観察を行います。パラリンピックでも注目される「スポーツ用義足の走行デモンストレーション」も行われますよ!
義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (第1回オープンキャンパスの様子はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">スポーツ用下腿義足を製作しました!
" target="_blank">スポーツ用下腿義足を製作しました!これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (第2回オープンキャンパスの様子はコチラ) (第1回オープンキャンパスの様子はコチラ)
当日の学科説明のスライドを一部ご紹介。



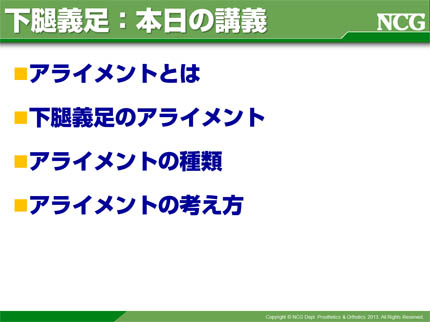
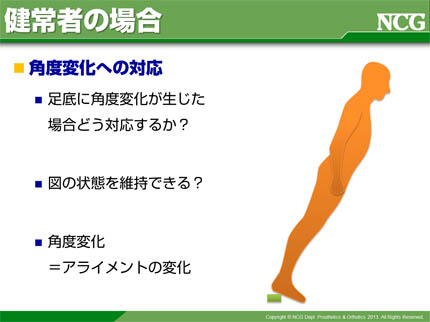
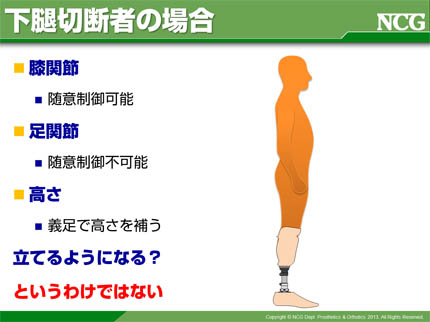
これ以外に当日しか聞くことのできない、国家試験対策や入試のポイントなど、重要な情報を得るチャンスです!ぜひ参加してください!!

 " target="_blank">7月19日(土)義肢装具学科オープンキャンパスのご案内
" target="_blank">7月19日(土)義肢装具学科オープンキャンパスのご案内 10:30(開会式)
今回もやはり圧倒的に高校3年生の参加者が多く、中川教務主任より入学試験について簡単な説明がありました。
10:30(開会式)
今回もやはり圧倒的に高校3年生の参加者が多く、中川教務主任より入学試験について簡単な説明がありました。 10:30(学科説明)
専任教員より義肢装具学科の紹介、最新の入試情報などの詳しい説明がありました。
10:30(学科説明)
専任教員より義肢装具学科の紹介、最新の入試情報などの詳しい説明がありました。 11:15(休憩)
学生スタッフと楽しくティータイム。
学校に入学する前後でどのように印象が変わったか、学生の目線から参加者の皆さんの疑問に一生懸命お答えしています!
11:15(休憩)
学生スタッフと楽しくティータイム。
学校に入学する前後でどのように印象が変わったか、学生の目線から参加者の皆さんの疑問に一生懸命お答えしています! 11:30~ 学生企画「学生の一週間」
今回は学生を代表し、2年生の神谷君が学校生活や義肢装具を学ぶことの楽しさについてプレゼンしてくれました。
とても一生懸命で楽しいプレゼン内容に、参加者の皆さんからも笑いが起こっていました。これも義肢装具士に求められるコミュニケーション能力のひとつですね!
神谷君、楽しいプレゼンをありがとうございました!
11:30~ 学生企画「学生の一週間」
今回は学生を代表し、2年生の神谷君が学校生活や義肢装具を学ぶことの楽しさについてプレゼンしてくれました。
とても一生懸命で楽しいプレゼン内容に、参加者の皆さんからも笑いが起こっていました。これも義肢装具士に求められるコミュニケーション能力のひとつですね!
神谷君、楽しいプレゼンをありがとうございました! 12:00(昼食)
学生スタッフと一緒にサンドイッチを食べながら学校生活、授業の様子、入学して楽しいことや大変なことなど学生の視点から分かりやすくお話します。学生スタッフには、保護者の皆さんからたくさんの質問をいただいていましたね!
12:00(昼食)
学生スタッフと一緒にサンドイッチを食べながら学校生活、授業の様子、入学して楽しいことや大変なことなど学生の視点から分かりやすくお話します。学生スタッフには、保護者の皆さんからたくさんの質問をいただいていましたね! 学生生活の楽しさや勉強の大変さを分かりやすくお話してくれた学生スタッフ。義肢装具学科の魅力は、学生スタッフの笑顔からも参加者の皆さんに十分伝わったのではないでしょうか。
学生生活の楽しさや勉強の大変さを分かりやすくお話してくれた学生スタッフ。義肢装具学科の魅力は、学生スタッフの笑顔からも参加者の皆さんに十分伝わったのではないでしょうか。 展示コーナーでは、教員が義肢装具の機能について分かりやすく説明します。参加者の皆さんの興味は、益々高まっているようでした!
展示コーナーでは、教員が義肢装具の機能について分かりやすく説明します。参加者の皆さんの興味は、益々高まっているようでした! 12:45(体験授業)
午後からは体験授業です。
まずは、日ごろ実際に学生が受けている内容の講義を受講していただきます。内容は「脳卒中片麻痺」を例に、短下肢装具の目的や製作工程について、わかりやすく説明されます。
患者さまの病気や症状について詳しく理解することが、義肢装具を製作する際にとても大切です。
12:45(体験授業)
午後からは体験授業です。
まずは、日ごろ実際に学生が受けている内容の講義を受講していただきます。内容は「脳卒中片麻痺」を例に、短下肢装具の目的や製作工程について、わかりやすく説明されます。
患者さまの病気や症状について詳しく理解することが、義肢装具を製作する際にとても大切です。 講義の後は、製作実習室で参加者の皆さんに短下肢装具の採型(さいけい)を体験していただきました!採型は患者様に直接触れることができる義肢装具士にしかできない、大切な業務のひとつです。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
講義の後は、製作実習室で参加者の皆さんに短下肢装具の採型(さいけい)を体験していただきました!採型は患者様に直接触れることができる義肢装具士にしかできない、大切な業務のひとつです。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 さあ、いよいよ採型の実体験です!
実際の患者さまに使用するギプス包帯を使い、下腿部の石膏モデルで採型をします。学生スタッフが一人一人をサポートし、採型のポイントをアドバイスしました。
初めて巻くギプス包帯の感触はいかがでしたか?
実はただ単にギプス包帯をくるくると巻いている訳ではないことが、よくお分かりいただけたとことと思います。参加者の皆さんには、ひとつの作業の中にたくさんの知識と技術の集積が必要なことを実体験していただきました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
さあ、いよいよ採型の実体験です!
実際の患者さまに使用するギプス包帯を使い、下腿部の石膏モデルで採型をします。学生スタッフが一人一人をサポートし、採型のポイントをアドバイスしました。
初めて巻くギプス包帯の感触はいかがでしたか?
実はただ単にギプス包帯をくるくると巻いている訳ではないことが、よくお分かりいただけたとことと思います。参加者の皆さんには、ひとつの作業の中にたくさんの知識と技術の集積が必要なことを実体験していただきました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。参加者(保護者)の声 実際に採型の体験をすることができて良かった。先輩方から学校生活についてたくさん話を聞くことができてよかった。次回も必ず参加したい。 (高校3年)
体験授業や学生さんとの交流を通して、知りたかった情報を得ることができた。参加してよかった。 (高校3年)
体験授業は難しかったけれど、1回目より2回目のほうが上手くできてうれしかった。大変だったけど楽しかったです。ありがとうございました。 (高校3年)
難しかったけど、すごく楽しかったです。生徒の皆さんが明るくて、学校が楽しいんだなと感じました。 (高校3年)
2回目の参加でしたが、学生さんにとても親切にしていただいて良かったです。 (高校3年)
先輩方が気さくに丁寧にいろいろなことを教えてくださって、今回来て本当に良かったです。 (高校2年)
先輩のお話で「やってみようかな」「できるかも」と思えるほど身近に感じることができた。うちの子どもだったらと、いろいろとシミュレーションすることができた。 (保護者)
学生の皆さんが一生懸命話をしてくれて、とても楽しかったです。学校の日常がよく分かりました。 (保護者)
この他にもたくさんのご感想をいただきました。ありがとうございました。 義肢装具士の業務内容や義肢装具学科の魅力についてご理解いただければ幸いです。
7月19日(土)の第3回オープンキャンパスの体験授業では、先生から義足アライメントについての講義の後、実際に下腿義足・大腿義足の歩行観察を行います。パラリンピックでも注目される「スポーツ用義足の走行デモンストレーション」も行われますよ!
義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (第1回オープンキャンパスの様子はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">第2回オープンキャンパスの様子をご紹介します!
" target="_blank">第2回オープンキャンパスの様子をご紹介します!言語聴覚士に興味がある方はもちろん、 「ことばやコミュニケーションって面白そう」と思っている方、 「医療系のお仕事ってどんなのかなあ」と漠然と考えている方・・・ まずは一度学院にお越し下さい!
本学院のオープンキャンパスでは、 「学生と話そう!」「学生による学内ツアー」が あります。 在校生の生の声を聞くこともでき、 学校生活についても詳しく説明しますので、 参加された方からは毎回好評を頂いております。 もちろん、教員も詳しくご説明いたします! この機会に、ぜひ学院をのぞいてみませんか? みなさんのお越しをお待ちしております!
" target="_blank">オープンキャンパスにいらっしゃいませんか?
 義足の完成度を決める仕上げの作業ですから、講義を聞く学生たちの表情も真剣そのものです!
義足の完成度を決める仕上げの作業ですから、講義を聞く学生たちの表情も真剣そのものです! 講義の後は、いよいよ実習です。初めて削るスポンジ材の感触に最初は戸惑っていたようですが、段々慣れてきたようです。
講義の後は、いよいよ実習です。初めて削るスポンジ材の感触に最初は戸惑っていたようですが、段々慣れてきたようです。 削り終わったら仕上げの義足専用ストッキングを被せ、接着剤を表面に塗り込みます。義足の外観を左右する美的センスが求められる作業ですから、最後まで気が抜けません。
削り終わったら仕上げの義足専用ストッキングを被せ、接着剤を表面に塗り込みます。義足の外観を左右する美的センスが求められる作業ですから、最後まで気が抜けません。 実習の最後は高山先生と学生全員で出来栄えを評価します。どこから見ても美しい義足に仕上がっていることが重要です。2年生の皆さん、8月からの臨床実習ではぜひこの作業にチャレンジして下さい!
高山先生、2日間ご講義いただき、ありがとうございました。
実習の最後は高山先生と学生全員で出来栄えを評価します。どこから見ても美しい義足に仕上がっていることが重要です。2年生の皆さん、8月からの臨床実習ではぜひこの作業にチャレンジして下さい!
高山先生、2日間ご講義いただき、ありがとうございました。 今年度の最優秀賞は中林君に決定です。素晴らしくきれいに削れています、なんと過去最高の出来栄えだと高山先生も驚いていましたよ!
今年度の最優秀賞は中林君に決定です。素晴らしくきれいに削れています、なんと過去最高の出来栄えだと高山先生も驚いていましたよ!次回はTSB式下腿義足の製作実習の様子を夏休み明けにお送りします!
" target="_blank">2年生下腿義足外装加工の実習が行われました。
 吊り込みの作業は、一度始めたら途中で手を止めることができません。初めての作業に学生たちも少し戸惑い気味ですが、一つひとつ丁寧に仕上げていました。
吊り込みの作業は、一度始めたら途中で手を止めることができません。初めての作業に学生たちも少し戸惑い気味ですが、一つひとつ丁寧に仕上げていました。 甲革にシワができないように吊り込むのは、繊細かつ根気のいる作業です。
甲革にシワができないように吊り込むのは、繊細かつ根気のいる作業です。 甲革の吊り込みが終わったら、靴底に補強材を入れます。日ごろ履いている靴の構造が分かって、面白いですね。
甲革の吊り込みが終わったら、靴底に補強材を入れます。日ごろ履いている靴の構造が分かって、面白いですね。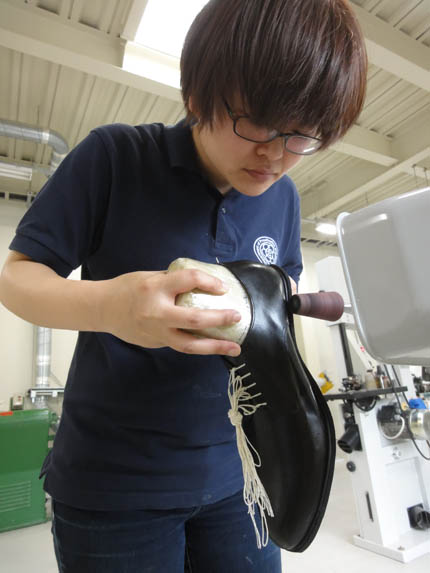 靴底を付けて出来上がりです。
だんだん靴の形になって行くと、学生たちも楽しそうです。もう少しで完成ですが、最後まで気を抜かず頑張りましょう!
靴底を付けて出来上がりです。
だんだん靴の形になって行くと、学生たちも楽しそうです。もう少しで完成ですが、最後まで気を抜かず頑張りましょう! 靴が完成したところで、早速歩いてみましょう。
靴が完成したところで、早速歩いてみましょう。 クラス全員で歩行観察をします。靴の外観はもちろん、歩容もしっかりチェックし、製作上の問題点をディスカッションして行きます。
クラス全員で歩行観察をします。靴の外観はもちろん、歩容もしっかりチェックし、製作上の問題点をディスカッションして行きます。 学生同士で採型し、製作した靴の履き心地はどうですか?
よく履き込んで、既成靴との違いを実感してください。
2年生は8月から始まる臨床実習に今回製作した靴を履いて行きます。ぜひ、学生たちの足元に注目してみてください!
" target="_blank">2年生 靴型装具が完成しました。
学生同士で採型し、製作した靴の履き心地はどうですか?
よく履き込んで、既成靴との違いを実感してください。
2年生は8月から始まる臨床実習に今回製作した靴を履いて行きます。ぜひ、学生たちの足元に注目してみてください!
" target="_blank">2年生 靴型装具が完成しました。 修正し終わった陽性モデルに熱で軟化させたプラスチック板を熱成形し、装具の本体となる部分を製作します。
修正し終わった陽性モデルに熱で軟化させたプラスチック板を熱成形し、装具の本体となる部分を製作します。 半完成品の状態で装具を一度装着し、適合状態を確認する「仮合わせ」を行います。試歩行なども行いトリミングラインの変更やや装具の効果をチェックします。
半完成品の状態で装具を一度装着し、適合状態を確認する「仮合わせ」を行います。試歩行なども行いトリミングラインの変更やや装具の効果をチェックします。 装具を装着し静止立位で適合状態を確認しているところです。
採型角度の設定、正確に陽性モデル修正が行えているか、トリミングラインの設定は適切か、など細かくチェックし装具を完成させます。
装具を装着し静止立位で適合状態を確認しているところです。
採型角度の設定、正確に陽性モデル修正が行えているか、トリミングラインの設定は適切か、など細かくチェックし装具を完成させます。1年生は翌日、完成した装具を一日装着体験しました。装具を使用する患者様の生活を体験することも貴重な経験となります。 今回の反省点をしっかり考察しレポートにまとめて下さい!" target="_blank">1年生 シューホーンブレースが完成しました。
在校生にとっては、「就職」が一気に現実的となった1日だったでしょう。 でも、「STになりたい!」という思いでここまで勉学・実習に励んできたのですから、是非、自分の納得のいく就職活動をしほしいと願っています。
目の前の課題やこの後の実習で頭がいっぱい・・・ でしょうが、就職活動はスタートしましたよ! 「STになりたい!」という思いでここまで突き進んできたのですから、 是非、自分の納得のいく就職活動をしてほしいと願っています。
" target="_blank">就職活動スタートです!
 これは大腿義足ソケットの側面に引いた線を、差金をあてながら確認しているところです。どうでしょう?直線に見えますか?
これは大腿義足ソケットの側面に引いた線を、差金をあてながら確認しているところです。どうでしょう?直線に見えますか? これは義足を組み立てるうえで、全ての基準となる「基準線」を陽性モデル上に引いているところです。3年生になると、直尺を使って曲面に上手に線が引けるようになっていますね。
これは義足を組み立てるうえで、全ての基準となる「基準線」を陽性モデル上に引いているところです。3年生になると、直尺を使って曲面に上手に線が引けるようになっていますね。 義肢装具を製作する上で、「曲面に線を引く」という作業はとても大切です。このような、ちょっとした作業でも確実に行えることがモノづくりの基礎となります。
皆さんも身の周りの「曲面」を使って一度、直線を引いてみましょう!途切れたり、曲がったりしないように慎重に・・・!" target="_blank">3年生 大腿義足「曲面に線を引く!?」
義肢装具を製作する上で、「曲面に線を引く」という作業はとても大切です。このような、ちょっとした作業でも確実に行えることがモノづくりの基礎となります。
皆さんも身の周りの「曲面」を使って一度、直線を引いてみましょう!途切れたり、曲がったりしないように慎重に・・・!" target="_blank">3年生 大腿義足「曲面に線を引く!?」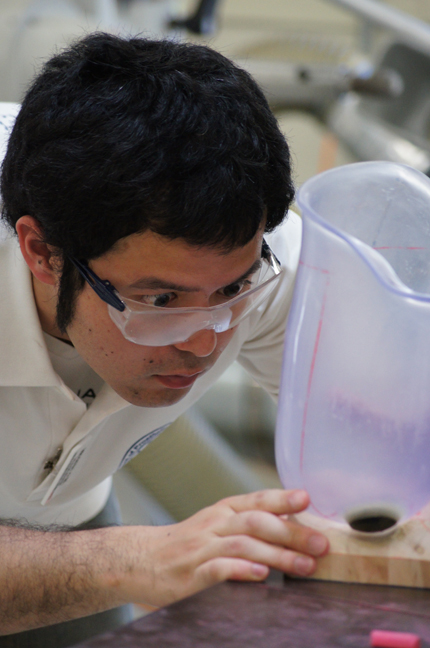 次にソケットを基準となる線が床に対して垂直となる様に木材に接着していきます。正しいアライメントからソケットが傾いてしまわないよう慎重な作業が必要ですね。
次にソケットを基準となる線が床に対して垂直となる様に木材に接着していきます。正しいアライメントからソケットが傾いてしまわないよう慎重な作業が必要ですね。 差金(さしがね)を使ってソケットに引いた基準線が床面に垂直になっているかを確認しています。数ミリのずれも許されない慎重な作業が続きます。
差金(さしがね)を使ってソケットに引いた基準線が床面に垂直になっているかを確認しています。数ミリのずれも許されない慎重な作業が続きます。 次は、ソケット以下の組み立てを行います。
ソケットを正確に埋め込んでいても、膝継手から下のパーツが傾いていると義足は真っ直ぐに組み立てられません。水準器を使って、ここでもミリ単位の調整が続きます。
次は、ソケット以下の組み立てを行います。
ソケットを正確に埋め込んでいても、膝継手から下のパーツが傾いていると義足は真っ直ぐに組み立てられません。水準器を使って、ここでもミリ単位の調整が続きます。 膝継手以下のパーツが組み上がれば、ソケット部分と連結して義足の完成です。それぞれのパーツに引いた基準線が、床面に対して垂直に立ちあがるように調整をしていきます。
膝継手以下のパーツが組み上がれば、ソケット部分と連結して義足の完成です。それぞれのパーツに引いた基準線が、床面に対して垂直に立ちあがるように調整をしていきます。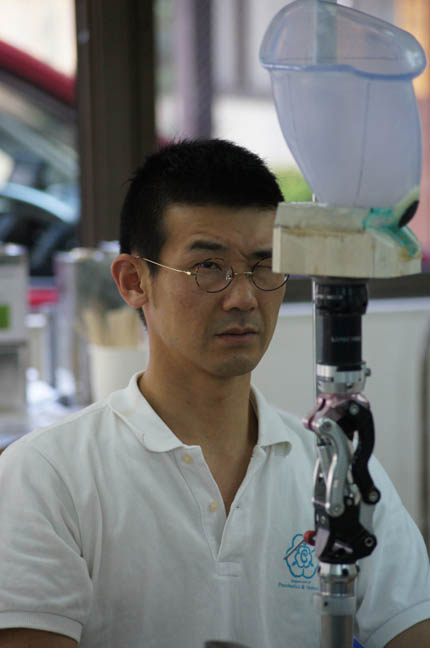 一つ一つの作業が的確に行われていなければ、理論通りの義足の組み立ては実現できません。自らの作業の問題点をしっかり考察し、次へのステップにして下さい!
一つ一つの作業が的確に行われていなければ、理論通りの義足の組み立ては実現できません。自らの作業の問題点をしっかり考察し、次へのステップにして下さい! ベンチアライメントとは、義足を組み上げる際の基準です。
ただ、理論通りに組み上げた義足では直ぐに歩くことができません。義足使用者にきれいに歩いてもらうためには、ご本人の歩容に合わせて義足を調整することが重要です。つまり、義足の完成度だけでなく、それらを適切に調整する技術も義肢装具士には必要です!
ベンチアライメントとは、義足を組み上げる際の基準です。
ただ、理論通りに組み上げた義足では直ぐに歩くことができません。義足使用者にきれいに歩いてもらうためには、ご本人の歩容に合わせて義足を調整することが重要です。つまり、義足の完成度だけでなく、それらを適切に調整する技術も義肢装具士には必要です!6月21日(土)の第2回オープンキャンパスの体験授業では、義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">3年生 大腿義足のベンチアライメント実習が行われました。
" target="_blank">3年生 大腿義足のベンチアライメント実習が行われました。 陽性モデルを修正する際に、義足の進行方向となる基準面の設定が重要となります。まずはこの面を正確に設定することが、陽性モデル修正の第一歩となります。
陽性モデルを修正する際に、義足の進行方向となる基準面の設定が重要となります。まずはこの面を正確に設定することが、陽性モデル修正の第一歩となります。 次に切断端の骨突起部に盛り修正を行います。
義足装着時、この箇所が痛みの原因とならないように除圧(じょあつ)する目的があります。
次に切断端の骨突起部に盛り修正を行います。
義足装着時、この箇所が痛みの原因とならないように除圧(じょあつ)する目的があります。 少しずつきれいな陽性モデルを作ることができるようになってきましたね!義肢ソケットの場合、断端皮膚が直接ソケットに触れることもあるため、小さな凹凸も傷の原因となることがあります。義肢装具士としての細かい気配りが大切ですね!
少しずつきれいな陽性モデルを作ることができるようになってきましたね!義肢ソケットの場合、断端皮膚が直接ソケットに触れることもあるため、小さな凹凸も傷の原因となることがあります。義肢装具士としての細かい気配りが大切ですね!次回はソケット樹脂注型(ラミネーション)からベンチアライメント設定までの様子をレポートします!" target="_blank">2年生 PTB式ソケットの陽性モデル修正が行われました。
 本年度も株式会社松本義肢製作所の香川貴宏先生にご担当いただき、四辺形ソケットの陽性モデル修正実習が行われました。今日は陽性モデル修正の製作理論だけでなく、臨床現場での話を交えながら興味深いお話を聞かせていただき、学生たちも興味津々です!
本年度も株式会社松本義肢製作所の香川貴宏先生にご担当いただき、四辺形ソケットの陽性モデル修正実習が行われました。今日は陽性モデル修正の製作理論だけでなく、臨床現場での話を交えながら興味深いお話を聞かせていただき、学生たちも興味津々です! 香川先生のデモンストレーションだけでは細かなニュアンスは伝わりにくいため、自分の手で触って、感覚を得ることがとても重要です。上手く同じ形状を再現することができるでしょうか?学生同士でディスカッションしている場面が見られます。
香川先生のデモンストレーションだけでは細かなニュアンスは伝わりにくいため、自分の手で触って、感覚を得ることがとても重要です。上手く同じ形状を再現することができるでしょうか?学生同士でディスカッションしている場面が見られます。 学生が香川先生に質問をしていたようですが、上手く専門用語を使って的確な質問ができていました。納得がいくまで探究する姿勢は、とても頼もしく見えますね!
学生が香川先生に質問をしていたようですが、上手く専門用語を使って的確な質問ができていました。納得がいくまで探究する姿勢は、とても頼もしく見えますね!
 3年生ともなると工具の使い方も上手になってくるため、だんだん義肢装具士らしい手つきになってきました。少しずつ、臨床現場に出る準備が整ってきているようです。
3年生ともなると工具の使い方も上手になってくるため、だんだん義肢装具士らしい手つきになってきました。少しずつ、臨床現場に出る準備が整ってきているようです。 講義の間、学生たちは必死に一言一句聞き逃さないようにメモをしています。
製作実習では座学の講義と異なり、メモをとる以外にも先生の手元を見逃さないようにすることが重要ですね!
講義の間、学生たちは必死に一言一句聞き逃さないようにメモをしています。
製作実習では座学の講義と異なり、メモをとる以外にも先生の手元を見逃さないようにすることが重要ですね!次回はソケットの製作からベンチアライメント設定までの様子をレポートします!" target="_blank">3年生 大腿義足の陽性モデル修正が行われました。
 学生たちは先生のデモンストレーションを食い入るように観察していますね!
学生たちは先生のデモンストレーションを食い入るように観察していますね! さぁ、いよいよ実践です!ギプス包帯は時間が経つにつれて扱いが難しくなっていきます。まずはしっかり作業の目的を理解して、手際よくギプス包帯を巻いていきましょう!
さぁ、いよいよ実践です!ギプス包帯は時間が経つにつれて扱いが難しくなっていきます。まずはしっかり作業の目的を理解して、手際よくギプス包帯を巻いていきましょう! 採型作業の精度によって、これから製作する装具の出来ばえに大きく影響してきます。一つ一つの失敗をしっかり自己分析して、技術を自分のものにして行きましょう!
採型作業の精度によって、これから製作する装具の出来ばえに大きく影響してきます。一つ一つの失敗をしっかり自己分析して、技術を自分のものにして行きましょう!6月21日(土)の第2回オープンキャンパスでは、今回ご紹介した短下肢装具の採型実習を体験できます!。義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">1年生 シューホーンブレースの採型実習が行われました。
" target="_blank">1年生 シューホーンブレースの採型実習が行われました。 次に、ギプス包帯の硬化時間を考慮しながら採型をします。
円錐状の切断端にギプス包帯を巻きつけることはとても難しいのですが、上手く巻いていますね!
次に、ギプス包帯の硬化時間を考慮しながら採型をします。
円錐状の切断端にギプス包帯を巻きつけることはとても難しいのですが、上手く巻いていますね! これはPTB式ソケットを採型するうえで最も重要な手技(しゅぎ)です。
この手技の精度によってソケット適合に影響する場合があるため、学生たちの表情も真剣です!
これはPTB式ソケットを採型するうえで最も重要な手技(しゅぎ)です。
この手技の精度によってソケット適合に影響する場合があるため、学生たちの表情も真剣です! 患者様とのコミュニケーションも義肢装具士にとって必要なスキルです。今日は学生たちも笑顔を絶やさないで上手に会話していました!
患者様とのコミュニケーションも義肢装具士にとって必要なスキルです。今日は学生たちも笑顔を絶やさないで上手に会話していました!次回は、陽性モデル修正の様子をレポートします。
6月21日(土)の第2回オープンキャンパスの体験授業では、今回ご紹介した下腿義足の採型実習が体験できます!。義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">2年生 PTB式下腿義足の採型実習が行われました。
" target="_blank">2年生 PTB式下腿義足の採型実習が行われました。 次に、「歩行観察」を行い、歩容から特徴と問題点を判断します。
次に、「歩行観察」を行い、歩容から特徴と問題点を判断します。 次に、静止立位時の重心位置を知るため、「フットプリント」による足底圧の計測を行います。様々な計測、評価を用いて患者様の情報を収集し、靴づくりに反映していきます。これも義肢装具を製作するために必要な、義肢装具士の大切な仕事の一つです。
次に、静止立位時の重心位置を知るため、「フットプリント」による足底圧の計測を行います。様々な計測、評価を用いて患者様の情報を収集し、靴づくりに反映していきます。これも義肢装具を製作するために必要な、義肢装具士の大切な仕事の一つです。 いよいよ採型です!ここでも、医学的根拠に基づいた靴づくりの基礎を学んでいきます。採型は、これから製作するラスト(靴の木型)の元となる大切な工程ですから、しっかりとデモンストレーションを観察しましょう!
採型は「トリシャム」というスポンジ状の素材とギプス包帯を用いて足の形を採型します。義肢装具の採型には、このように様々な素材や採型手法を用いています。
いよいよ採型です!ここでも、医学的根拠に基づいた靴づくりの基礎を学んでいきます。採型は、これから製作するラスト(靴の木型)の元となる大切な工程ですから、しっかりとデモンストレーションを観察しましょう!
採型は「トリシャム」というスポンジ状の素材とギプス包帯を用いて足の形を採型します。義肢装具の採型には、このように様々な素材や採型手法を用いています。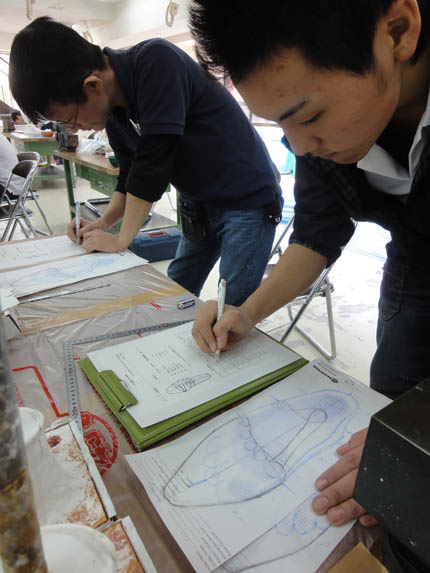 フットプリントの情報を元にモデルの修正箇所や修正値(量)を設定し、具体的な靴の形を設計していきます。
フットプリントの情報を元にモデルの修正箇所や修正値(量)を設定し、具体的な靴の形を設計していきます。 自分のデザインした靴の形状に合わせて、陽性モデルを修正します。
自分のデザインした靴の形状に合わせて、陽性モデルを修正します。 ここからは、「チェックシューズ」製作の工程に入ります。修正した陽性モデルにインソールを加工し、その上からプラスチック板を熱成形していきます。
ここからは、「チェックシューズ」製作の工程に入ります。修正した陽性モデルにインソールを加工し、その上からプラスチック板を熱成形していきます。 次に、熱成形したプラスチックに靴底を貼りつけ、最終的な靴の形にする前に適合状態を確認するチェックシューズが完成します。
次に、熱成形したプラスチックに靴底を貼りつけ、最終的な靴の形にする前に適合状態を確認するチェックシューズが完成します。 早速履いてみましょう!履き心地はどうでしょうか?自分の足から型をとって製作しているため、いつも履いているスニーカーとは全く違う感覚だと思います。ここで痛みのある箇所やフィッティングがあまい箇所などを細かくチェックし、最終的な木型製作に反映させていきます。
早速履いてみましょう!履き心地はどうでしょうか?自分の足から型をとって製作しているため、いつも履いているスニーカーとは全く違う感覚だと思います。ここで痛みのある箇所やフィッティングがあまい箇所などを細かくチェックし、最終的な木型製作に反映させていきます。2年生はこのプロジェクトで完成させた靴を履いて、8月からの臨床実習に出て行きます。 かっこいい靴を完成させて、臨床実習に臨んで下さいね!" target="_blank">2年生 靴型装具の製作実習が始まりました。
【当日のスケジュール】 受 付 10:00~ 学科説明 10:30~11:15 学校見学 11:15~ 終 了 12:00
 義肢装具士の業務や国家資格について、本学の講義内容や入試科目などについて専任教員から詳しくご説明しています!
義肢装具士の業務や国家資格について、本学の講義内容や入試科目などについて専任教員から詳しくご説明しています!《参加者(保護者)の声》 『学科の特徴、義肢装具士の役割について理解することができた。』(高3)
『義肢装具士の仕事について、今まで知らなかったことも詳しく知ることができてとてもよかったです。オープンキャンパスで分かったことを踏まえ、これからの進路についてじっくり考えてみたいと思います。』(高3)
『知らなかったことが沢山あったので、参加してよかったです。』(高3)
『疑問に思っていたことが分かって、勉強になりました。』(高3)
『普段の生活の中では見ることができないが、参加して実際に見たり、触れることができてよかった。先生方の接し方や雰囲気もとても温かだった。』(保護者)
『学校見学の時は少人数の中でゆっくり話を聞かせて頂くことができ、聞きたいと思っていた内容もよく分かりました。』(保護者)
『義肢装具士について知らなかったことも多く、参加して良かったです。学校側の教育サポートもしっかりしていることが分かりました。』(保護者)
今回参加して頂いた高校3年生の皆さんや保護者の皆さんから沢山の感想を頂き、ありがとうございました! 進路について悩んでいる方、義肢装具士に興味のある高校生、大学生の皆さん、保護者の方も是非、これから始まるオープンキャンパスや学校見学にご参加下さい! 次回、第2回オープンキャンパスは6月21日(土)となりますが、その前に社会人、大学4年生を対象とした夕方からのオープンキャンパスを企画しています!詳細はまたこのブログ内で告知をしますので、お楽しみに!
6月21日(土)の第2回オープンキャンパスの体験授業では、先生から短下肢装具と下腿義足についての講義の後、実際に短下肢装具と下腿義足の採型実習を行います。義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">第1回オープンキャンパスの様子をご紹介します!
" target="_blank">第1回オープンキャンパスの様子をご紹介します!個別相談(授業のこと、入試のことなど何でも相談!)
これから進路を選択するうえで、きっと参考になると思います!この機会にぜひ参加してみてください! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)
当日の学科説明のスライドを一部ご紹介。 義肢装具士の仕事についてから始まり、学科の特色をご説明します。





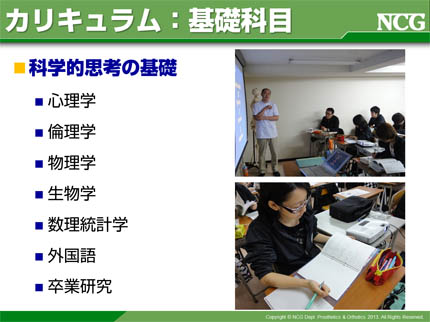
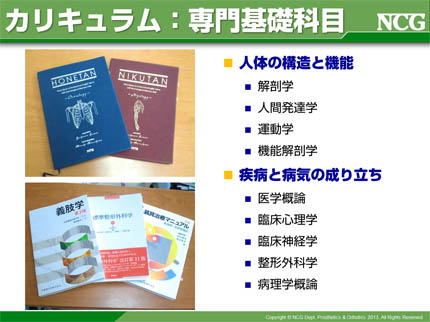
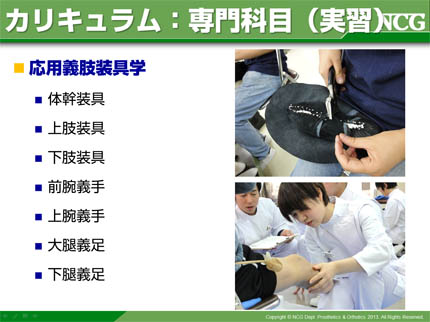

これ以外に当日しか聞くことのできない、国家試験対策や入試のポイントなど、重要な情報を得るチャンスです!ぜひ参加してください!!

 " target="_blank">4月19日(土)オープンキャンパス 高校3年生の皆さん集合!!
" target="_blank">4月19日(土)オープンキャンパス 高校3年生の皆さん集合!! まずは切断端の骨突起部にマーキングをします。切断端は厚い軟部組織で覆われていますが、しっかり触診すると大腿骨を確認できます。痛みのない快適なソケットを製作するためにも、切断端の情報をできるだけ細かく記録しておくことが大切です。
まずは切断端の骨突起部にマーキングをします。切断端は厚い軟部組織で覆われていますが、しっかり触診すると大腿骨を確認できます。痛みのない快適なソケットを製作するためにも、切断端の情報をできるだけ細かく記録しておくことが大切です。
 採型をする場合、モデルさんは約10分間片足で立ったままの状態になります。採型だけに集中するのではなく、モデルさんの表情や体調などを観察しながら作業を進めてゆくことが大切ですね!
※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。
採型をする場合、モデルさんは約10分間片足で立ったままの状態になります。採型だけに集中するのではなく、モデルさんの表情や体調などを観察しながら作業を進めてゆくことが大切ですね!
※プライバシー保護のため画像を一部加工しています。 この授業では四辺形ソケットという大腿義足ソケットの製作を学習します。採型時にソケットの形状をかたち作るための特別な手技を行い、ギプス包帯を硬化させます。この採型手技を的確に行うことが、適合感のよいソケットを作る第一歩となります。
この授業では四辺形ソケットという大腿義足ソケットの製作を学習します。採型時にソケットの形状をかたち作るための特別な手技を行い、ギプス包帯を硬化させます。この採型手技を的確に行うことが、適合感のよいソケットを作る第一歩となります。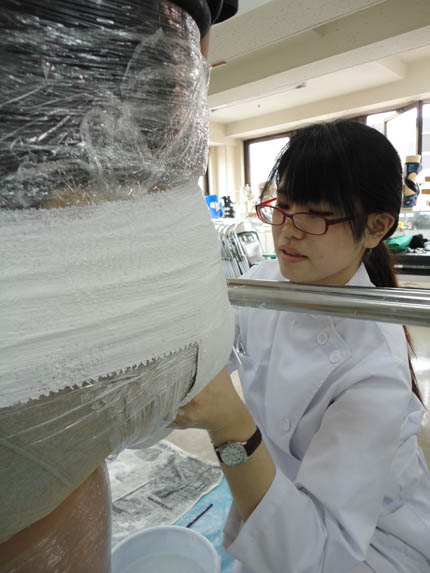 理論的に理解していても実際に採型してみると、なかなか難しいようですね。ギプス包帯を巻く順序、スピード、手技のタイミングなど、ここでマスターしなければいけないことが沢山あります。
理論的に理解していても実際に採型してみると、なかなか難しいようですね。ギプス包帯を巻く順序、スピード、手技のタイミングなど、ここでマスターしなければいけないことが沢山あります。 授業が終わった後も、学生同士で採型手技についてディスカッションをしていました。自分の技術だけでなく、クラスメイトの技術を観察することも大切ですね!
授業が終わった後も、学生同士で採型手技についてディスカッションをしていました。自分の技術だけでなく、クラスメイトの技術を観察することも大切ですね!次回は陽性モデル修正の様子をレポートします! " target="_blank">3年生 大腿義足の製作実習がスタートしました。
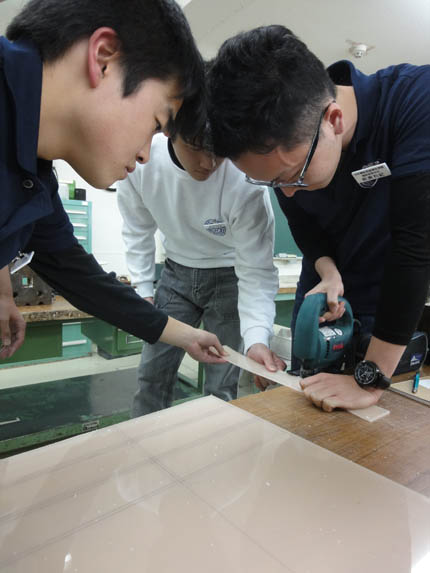 ジグソー(電動鋸)を使ってプラスチック板を寸法通りに正確に切り出していきます。
ジグソー(電動鋸)を使ってプラスチック板を寸法通りに正確に切り出していきます。 次に、カービングマシンという機械を使って、プラスチック板の面取り作業を行います。規則性のある形に仕上げるには、実はいろんなポイントがあるんですね!先生の手元をしっかり観察することが大切ですよ!
次に、カービングマシンという機械を使って、プラスチック板の面取り作業を行います。規則性のある形に仕上げるには、実はいろんなポイントがあるんですね!先生の手元をしっかり観察することが大切ですよ! 最後に、銅鋲でプラスチックをリベットする作業でパイプホルダーが完成します。ハンマを握る手の位置が変わるだけで、作業のしやすさが変わることを実感した学生が多かったようです。
患者様が身体に装着する大切な義肢装具ですから、一つ一つの作業を正確かつ丁寧に行えるよう頑張って行きましょう!" target="_blank">1年生 基本工作論の授業が始まりました。
最後に、銅鋲でプラスチックをリベットする作業でパイプホルダーが完成します。ハンマを握る手の位置が変わるだけで、作業のしやすさが変わることを実感した学生が多かったようです。
患者様が身体に装着する大切な義肢装具ですから、一つ一つの作業を正確かつ丁寧に行えるよう頑張って行きましょう!" target="_blank">1年生 基本工作論の授業が始まりました。 新入生、保護者の皆さんの受付けや式場へのご案内は、義肢装具学科の2年生が担当しました。彼らも一年前は緊張した面持ちでこの日を迎えていたことを思い出していたのではないでしょうか?
新入生、保護者の皆さんの受付けや式場へのご案内は、義肢装具学科の2年生が担当しました。彼らも一年前は緊張した面持ちでこの日を迎えていたことを思い出していたのではないでしょうか? 「新入生誓いのことば」では、新入生を代表して義肢装具学科の吉川拓斗くん(第28期生)が誓いの言葉を述べてくれました。とてもはっきりとした口調で元気がよく、清々しい誓いの言葉でした!
「新入生誓いのことば」では、新入生を代表して義肢装具学科の吉川拓斗くん(第28期生)が誓いの言葉を述べてくれました。とてもはっきりとした口調で元気がよく、清々しい誓いの言葉でした! 入学式後は本年度の保護者後援会総会が行われ、多数の保護者の皆様にご出席をいただきました。在校生、新入生の保護者の皆様、ありがとうございました。
入学式後は本年度の保護者後援会総会が行われ、多数の保護者の皆様にご出席をいただきました。在校生、新入生の保護者の皆様、ありがとうございました。これで3学年が全員揃い、いよいよ新年度のスタートです! 今年度も授業の様子を詳細にレポートしていきますので、ぜひご覧ください!" target="_blank">平成26年度入学式が行われました。
補聴言語学科 94.7 %
全国平均 74.1%
今回も全国合格率に比べ、 聴能・補聴とも高い合格率となりました!
苦しい国家試験勉強を乗り切って、 見事STへの入り口に立てた聴能28期・補聴20期のみなさん、 本当におめでとう!
これまでの道のりは、決してラクなものではなかったと思います。 本当に良く頑張りました。
学生達を支え導いてくださった実習指導の先生方、 講師の先生方、本当にありがとうございました。
そして、いよいよ、新しいスタートをきる時がきましたね。 たくさんの皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに、 これから始まるST人生、 対象者のみなさんにより良い臨床を提供できる専門家・臨床家として、 日々努力を重ねてがんばってくださいね。 いつまでも応援しています。
教員一同
" target="_blank">第16回 言語聴覚士国家試験結果
 来年の国家試験まで、もう一年もありません。「備えあれば憂いなし」準備が早すぎて困ることはありませんので、今からコツコツ準備して行きましょう!
3年生は日ごろの授業に加えて、臨床実習、卒業研究、就職活動と一年間で乗り越えなくてはいけない課題がたくさんあります。
来年の今ごろ、義肢装具士として第一歩が踏み出せるよう、一つ一つ確実にクリアして行って下さいね!" target="_blank">春休みも図書室は学生でいっぱいです!
来年の国家試験まで、もう一年もありません。「備えあれば憂いなし」準備が早すぎて困ることはありませんので、今からコツコツ準備して行きましょう!
3年生は日ごろの授業に加えて、臨床実習、卒業研究、就職活動と一年間で乗り越えなくてはいけない課題がたくさんあります。
来年の今ごろ、義肢装具士として第一歩が踏み出せるよう、一つ一つ確実にクリアして行って下さいね!" target="_blank">春休みも図書室は学生でいっぱいです! ロッカーの名札もすべて新しいものに貼り変えます。3年生が今まで使用してきたロッカーを片付け、新入生の名札を貼っていきます。新入生の皆さん!先輩たちは皆さんが入学する前からいろいろな準備をしてくれています!
ロッカーの名札もすべて新しいものに貼り変えます。3年生が今まで使用してきたロッカーを片付け、新入生の名札を貼っていきます。新入生の皆さん!先輩たちは皆さんが入学する前からいろいろな準備をしてくれています! 窓も一枚一枚、丁寧に拭き掃除しています。花粉やPM2.5の影響もあるのでしょうか?外気に触れている窓は見えない汚れがたくさんありますね。
窓も一枚一枚、丁寧に拭き掃除しています。花粉やPM2.5の影響もあるのでしょうか?外気に触れている窓は見えない汚れがたくさんありますね。 実習で使用する機械も日ごろ掃除しないところまで細かく掃除していきます。新年度からの授業に支障がないように機械のメンテナンスも行います。
実習で使用する機械も日ごろ掃除しないところまで細かく掃除していきます。新年度からの授業に支障がないように機械のメンテナンスも行います。 製作実習室の床も机を移動させ、日ごろの掃除では取りきれない石膏や樹脂などの汚れも水を流してきれいにして行きます。
製作実習室の床も机を移動させ、日ごろの掃除では取りきれない石膏や樹脂などの汚れも水を流してきれいにして行きます。 大掃除恒例のカレーです!今回も学生会と教務で朝7時から約100食分を調理しました。
学生会の皆さん、朝早くからご苦労さまでした!
大掃除恒例のカレーです!今回も学生会と教務で朝7時から約100食分を調理しました。
学生会の皆さん、朝早くからご苦労さまでした!

 今日のカレーは少し辛かったようですね?いつものことながら、学生たちは美味しそうに何度もおかわりをしていました!
今日のカレーは少し辛かったようですね?いつものことながら、学生たちは美味しそうに何度もおかわりをしていました!学生の皆さん、一年間ご苦労さまでした!これで学生たちは明日から春季休業に入ります。新年度に向けてしっかり休んで英気を養って下さい!
本年度も「義肢装具学科ブログ」をご覧いただき、ありがとうございました。4月からも学科内の楽しい情報を発信して行きますので、どうぞ引き続きご覧下さい!" target="_blank">春休み前の大掃除が行われました。
 この授業では、患者様に装着指導するポイントや不適合だった場合の修正方法などを学習します。金属支柱が体に接触していないか、継ぎ手の位置が適切か、ベルトの長さが適切かなど、細部まで確認します。
この授業では、患者様に装着指導するポイントや不適合だった場合の修正方法などを学習します。金属支柱が体に接触していないか、継ぎ手の位置が適切か、ベルトの長さが適切かなど、細部まで確認します。 先生が一人ずつ静止立位時の適合状態をチェックしています。
装具が身体に正しく適合していることは勿論ですが、ベルトの縫製の美しさや金属の曲げ加工の美しさなど、製作物としての出来ばえも評価します。また、製作物について学生に簡単なプレゼンテーションをしてもらい、義肢装具士として人前で話すことを学習します。
先生が一人ずつ静止立位時の適合状態をチェックしています。
装具が身体に正しく適合していることは勿論ですが、ベルトの縫製の美しさや金属の曲げ加工の美しさなど、製作物としての出来ばえも評価します。また、製作物について学生に簡単なプレゼンテーションをしてもらい、義肢装具士として人前で話すことを学習します。 つぎに、実際に歩行しながら装具の適合状態を評価します。装具の足、膝継ぎ手の位置がずれている場合や歩行時のアライメント(各関節の角度)が変化する場合、金属支柱が身体にあたる場合などがあります。これは採寸する段階で予測できるとよいのですが、実際に装具を装着し歩行してみないと判断できないことが多くあります。
つぎに、実際に歩行しながら装具の適合状態を評価します。装具の足、膝継ぎ手の位置がずれている場合や歩行時のアライメント(各関節の角度)が変化する場合、金属支柱が身体にあたる場合などがあります。これは採寸する段階で予測できるとよいのですが、実際に装具を装着し歩行してみないと判断できないことが多くあります。 近年、長下肢装具は脳卒中の急性期のリハビリテーションで重要視されており、処方されることが多い装具でもあります。製作だけでなく、脳卒中の病態についてもしっかり学習して下さい!
近年、長下肢装具は脳卒中の急性期のリハビリテーションで重要視されており、処方されることが多い装具でもあります。製作だけでなく、脳卒中の病態についてもしっかり学習して下さい!2年生の専門科目の授業はこれで終了です。 3年生ではさらに高度な製作技術の習得が課題となります。2年生同様、一つずつ確実に積み上げて行って下さい!" target="_blank">2年生 長下肢装具の適合評価が行われました。
 " target="_blank">義肢装具製作施設見学および学校見学のお知らせ
" target="_blank">義肢装具製作施設見学および学校見学のお知らせ 卒業証書授与の様子。
義肢装具学科総代が棚橋学院長より証書を受け取りました。
卒業証書授与の様子。
義肢装具学科総代が棚橋学院長より証書を受け取りました。 薫風会(義肢装具学科OB会)の香川会長より「薫風会賞」が授与されました。
薫風会(義肢装具学科OB会)の香川会長より「薫風会賞」が授与されました。 卒業生より、在校生全員へ記念品が贈呈されました。
卒業生より、在校生全員へ記念品が贈呈されました。 最後に恒例の校舎前での記念撮影です!
最後に恒例の校舎前での記念撮影です! 第25期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!
3年間この学び舎で多くのことを学び、いよいよ義肢装具士として第一歩を踏み出すことができますね!「モノづくりを通して人の役に立ちたい」という初心を忘れることなく、患者様のため、障がいを持つ方のために、その力を惜しみなく発揮して下さい!皆さんのこれからの活躍に期待しています!" target="_blank">第25期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!
第25期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます!
3年間この学び舎で多くのことを学び、いよいよ義肢装具士として第一歩を踏み出すことができますね!「モノづくりを通して人の役に立ちたい」という初心を忘れることなく、患者様のため、障がいを持つ方のために、その力を惜しみなく発揮して下さい!皆さんのこれからの活躍に期待しています!" target="_blank">第25期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます! 試験直前の3年生たちの様子です。緊張しているなかにも笑顔が見えます。3年間一緒に学んできた仲間がいるのは、やっぱり心強いですね!
試験直前の3年生たちの様子です。緊張しているなかにも笑顔が見えます。3年間一緒に学んできた仲間がいるのは、やっぱり心強いですね!3年生はこの日のうちに名古屋に戻り、学校で自己採点を済ませました。 そして、明日はいよいよ卒業式です!国家試験受験の興奮が冷めやらぬうちに“お別れの日”となります。
3年生の皆さん、これまで本当にお疲れさまでした!" target="_blank">第27回義肢装具士国家試験が行われました。
 1年生はこの日のために、2週間前からクラス全員で準備をしてくれていたようです。彼らの熱心な応援に、3年生の士気が一気に上がりました!
1年生はこの日のために、2週間前からクラス全員で準備をしてくれていたようです。彼らの熱心な応援に、3年生の士気が一気に上がりました! 後輩たちが3年生全員に手づくりのお守りをプレゼントしてくれました! さぁ、いよいよ東京に向けて出発です!
後輩たちが3年生全員に手づくりのお守りをプレゼントしてくれました! さぁ、いよいよ東京に向けて出発です! 学院正門前では後輩たちが待ち構える「必勝アーチ」をくぐって、3年生いざ出陣です!
学院正門前では後輩たちが待ち構える「必勝アーチ」をくぐって、3年生いざ出陣です!3年生の皆さん、これまでお世話になった多くの方々の顔を思い浮かべながら、明日はしっかり実力を発揮してきて下さいね!" target="_blank">義肢装具士国家試験 壮行会が行われました。
 上腕義手ではハーネスと呼ばれるリュックサック型のベルトを介して、肘継手の固定解除・肘継手の曲げ・手先具の開閉動作を行います。各部品の位置が数mmずれるだけでも使用者が義手を操作しにくくなってしまうので、仮合わせ時の微調整が重要となってきます。
上腕義手ではハーネスと呼ばれるリュックサック型のベルトを介して、肘継手の固定解除・肘継手の曲げ・手先具の開閉動作を行います。各部品の位置が数mmずれるだけでも使用者が義手を操作しにくくなってしまうので、仮合わせ時の微調整が重要となってきます。 手先具を開くために必要な力を、バネばかりで計測し問題がないか確認しています。コントロールケーブルと呼ばれるワイヤーの走路に問題があると、効率よく手先具を開閉することができません。
上腕切断者は切断側の肩関節と健側の肩関節の動きを利用して義手を操作しています。そのため、できるだけ少ない力で無理なく義手が操作できるように調整することが大切です。
手先具を開くために必要な力を、バネばかりで計測し問題がないか確認しています。コントロールケーブルと呼ばれるワイヤーの走路に問題があると、効率よく手先具を開閉することができません。
上腕切断者は切断側の肩関節と健側の肩関節の動きを利用して義手を操作しています。そのため、できるだけ少ない力で無理なく義手が操作できるように調整することが大切です。 ハーネスの走路やコントロールケーブルが問題なく調整できていると、口もとで手先具を大きく開くことができます。この義手はしっかり調節ができていますね!
ハーネスの走路やコントロールケーブルが問題なく調整できていると、口もとで手先具を大きく開くことができます。この義手はしっかり調節ができていますね! 授業にご協力いただいているモデルさんの中には、学科設立以来ずっとお世話になっている方もおられます。今年も学生たちがお世話になりました。
授業にご協力いただいているモデルさんの中には、学科設立以来ずっとお世話になっている方もおられます。今年も学生たちがお世話になりました。また、溝手雅之先生(㈱松本義肢製作所)には前腕義手に引き続いて学生をご指導いただき、ありがとうございました。" target="_blank">2年生 上腕義手の適合評価が行われました。
 あぶみの高さを決める重要な工程です。数ミリのずれが装具の動きを悪くしてしまうため、学生たちも真剣です。
あぶみの高さを決める重要な工程です。数ミリのずれが装具の動きを悪くしてしまうため、学生たちも真剣です。 膝下までの装具はすでに1年生で学習していますので、ここまではスムーズに作業が進められていますね!
膝下までの装具はすでに1年生で学習していますので、ここまではスムーズに作業が進められていますね! 支柱の捻じれを定盤と呼ばれる台の上で確認しています。装具の継ぎ手部分が上手く可動するためには、支柱が捻れていないことが大切でしたね!
支柱の捻じれを定盤と呼ばれる台の上で確認しています。装具の継ぎ手部分が上手く可動するためには、支柱が捻れていないことが大切でしたね!金属加工に苦手意識はあるものの、製作するスピードは確実に早くなっていますね!正確に製作物を作り上げる技術を習得することが何より大切ですが、決められた時間の中で作業を進めることも必要です。装具を待つ患者様のことを忘れずに!" target="_blank">2年生 長下肢装具の金属加工が行われました。
 講義①:本協会のあり方
講師:坂井一浩 先生(日本義肢装具士協会 会長)
坂井会長にご来校いただき、日本義肢装具士協会のあり方についてご講義いただきました。「義肢装具士のこれから」として、専門性の強化、職域の拡大、技術革新が課題であること、今後は協会としてこれらの活動を主軸に会員をバックアップして行きたい!という心強いご講義がありました。
講義①:本協会のあり方
講師:坂井一浩 先生(日本義肢装具士協会 会長)
坂井会長にご来校いただき、日本義肢装具士協会のあり方についてご講義いただきました。「義肢装具士のこれから」として、専門性の強化、職域の拡大、技術革新が課題であること、今後は協会としてこれらの活動を主軸に会員をバックアップして行きたい!という心強いご講義がありました。 講義②:関係法規~義肢装具士法~
講師:宮川拓也 先生(理事・研修副委員長)
義肢装具士になること、つまり資格を取得するということが法的に、また社会的にどのような責任や義務を持つことになるのか、分かりやすくご講義いただきました。国家試験を目前に控え、義肢装具士法について再確認できる良い機会となりました。
講義②:関係法規~義肢装具士法~
講師:宮川拓也 先生(理事・研修副委員長)
義肢装具士になること、つまり資格を取得するということが法的に、また社会的にどのような責任や義務を持つことになるのか、分かりやすくご講義いただきました。国家試験を目前に控え、義肢装具士法について再確認できる良い機会となりました。 講義③:協会倫理綱領
講師:鈴木昭宏 先生(理事・会則検討委員長)
関係法規では、法律という明文化された誰もが守らなければいけない規則、また、法律に明文化されていなくても社会通念や一般的モラルとして判断される社会倫理について、義肢装具士の視点から分かり易くご講義いただきました。学生を卒業する彼らにとって社会人としての倫理、そして義肢装具士としての倫理を改めて考える良いきっかけになったと思います。
講義③:協会倫理綱領
講師:鈴木昭宏 先生(理事・会則検討委員長)
関係法規では、法律という明文化された誰もが守らなければいけない規則、また、法律に明文化されていなくても社会通念や一般的モラルとして判断される社会倫理について、義肢装具士の視点から分かり易くご講義いただきました。学生を卒業する彼らにとって社会人としての倫理、そして義肢装具士としての倫理を改めて考える良いきっかけになったと思います。 講義④:義肢装具の支給体系
講師:佐口明 先生(日本義肢装具士協会会員)
3年生の授業でもご講義いただいている佐口先生から、改めて義肢装具の支給体系についてご講義いただきました。講義のなかで聞いたことのある内容が多かったと思いますが、改めて質問をされると・・・・・・?国家試験の問題にも出題される範囲の講義なので、受験前の良い復習ができたのではないでしょうか。
講義④:義肢装具の支給体系
講師:佐口明 先生(日本義肢装具士協会会員)
3年生の授業でもご講義いただいている佐口先生から、改めて義肢装具の支給体系についてご講義いただきました。講義のなかで聞いたことのある内容が多かったと思いますが、改めて質問をされると・・・・・・?国家試験の問題にも出題される範囲の講義なので、受験前の良い復習ができたのではないでしょうか。 座談会:先輩からのメッセージ
司会:千田弦 先生(日本義肢装具士協会 研修委員)
このセミナーでは、昨年から「先輩からのメッセージ」と題して、卒後1 年目から4 年目までの先輩をお招きし、一緒に昼食をとりながら座談会形式で体験談を話していただく企画を行っています。昨年の学生からもたいへん好評だったため、今年は他の地域でも同じ企画が行われているようです。
座談会:先輩からのメッセージ
司会:千田弦 先生(日本義肢装具士協会 研修委員)
このセミナーでは、昨年から「先輩からのメッセージ」と題して、卒後1 年目から4 年目までの先輩をお招きし、一緒に昼食をとりながら座談会形式で体験談を話していただく企画を行っています。昨年の学生からもたいへん好評だったため、今年は他の地域でも同じ企画が行われているようです。 左から
1年目:福島一公 さん(有限会社渡辺義肢製作所)
2年目:岩田崇宏 さん(有限会社アルテックブレース)
3年目:羽根慎太郎 さん(株式会社松本義肢製作所)
4年目:近藤菜津子 さん(東名ブレース株式会社)
最初は先輩方も学生も緊張した様子でしたが・・・・・・。
左から
1年目:福島一公 さん(有限会社渡辺義肢製作所)
2年目:岩田崇宏 さん(有限会社アルテックブレース)
3年目:羽根慎太郎 さん(株式会社松本義肢製作所)
4年目:近藤菜津子 さん(東名ブレース株式会社)
最初は先輩方も学生も緊張した様子でしたが・・・・・・。 千田委員の楽しい司会もあり、次第にリラックスした雰囲気で座談会が進んで行きました。一貫制と分業制という業務形態の違い、働き出してから困ったことについて、それぞれお話をしていただきました。
学生からは、義肢装具士になってよかったと思ったこと、失敗したときの対処法、学生時代にもっと勉強しておけばよかったことなど、たくさん質問が出ましたが、皆さん的確にお答えいただき、たいへん盛り上がりました。
先輩方もこのセミナーの趣旨である「自己研鑽の大切さ」を触れられ、3年生も心に感じるところがあったようです。
千田委員の楽しい司会もあり、次第にリラックスした雰囲気で座談会が進んで行きました。一貫制と分業制という業務形態の違い、働き出してから困ったことについて、それぞれお話をしていただきました。
学生からは、義肢装具士になってよかったと思ったこと、失敗したときの対処法、学生時代にもっと勉強しておけばよかったことなど、たくさん質問が出ましたが、皆さん的確にお答えいただき、たいへん盛り上がりました。
先輩方もこのセミナーの趣旨である「自己研鑽の大切さ」を触れられ、3年生も心に感じるところがあったようです。 セミナーの締めくくりとして、日本義肢装具士協会理事であり、中部日本支部支部長でもある中川教務主任から職能団体としての日本義肢装具士協会で活動することの意義についてお話がありました。
セミナーの締めくくりとして、日本義肢装具士協会理事であり、中部日本支部支部長でもある中川教務主任から職能団体としての日本義肢装具士協会で活動することの意義についてお話がありました。 中川先生のお話を聞いて、社会人としての心構えを改めて再確認できた様子でした。
中川先生のお話を聞いて、社会人としての心構えを改めて再確認できた様子でした。3年生の皆さん、いよいよ国家試験まであと僅かとなりました。ラストスパートですね! 卒業後は皆さんが学院だけでなく、日本義肢装具士協会などさまざまな場所で情報交換してくれることを期待しています。" target="_blank">3年生 卒前新人セミナーが行われました。
 実際にお互いの体を採型してみましょう!
患者様に負担をかけないように手際よくギプス包帯を巻き、素早くカットして陰性モデルを取り外します。お互いに患者役をすると患者様の大変さが実感できますね。常に患者様の立場になって考えられる優しい心配りが必要です。
実際にお互いの体を採型してみましょう!
患者様に負担をかけないように手際よくギプス包帯を巻き、素早くカットして陰性モデルを取り外します。お互いに患者役をすると患者様の大変さが実感できますね。常に患者様の立場になって考えられる優しい心配りが必要です。 陽性モデルを起こしたら左右対称にミリ単位で修正していきます。
正確な採型が行われていないと、この修正でいくつもの手直しが必要になります。
陽性モデルを起こしたら左右対称にミリ単位で修正していきます。
正確な採型が行われていないと、この修正でいくつもの手直しが必要になります。 みんな一言も喋らず黙々と作業しています。
人体に義肢装具を適合させる難しさを、実感し始めたのではないでしょうか?
みんな一言も喋らず黙々と作業しています。
人体に義肢装具を適合させる難しさを、実感し始めたのではないでしょうか? きれいな陽性モデルが出来上がりましたね!
モデル表面の凹凸を指で確認しながら、丁寧に仕上げていますね。
きれいな陽性モデルが出来上がりましたね!
モデル表面の凹凸を指で確認しながら、丁寧に仕上げていますね。 次はいよいよ装具本体の製作です。仕上げたモデルの上に、熱で軟化させたプラスチック材を巻き付けていきます。
次はいよいよ装具本体の製作です。仕上げたモデルの上に、熱で軟化させたプラスチック材を巻き付けていきます。今回はモールドジャケットというプラスチック製の体幹装具を製作していますが、次回は金属製の体幹装具を製作します。同じ体幹装具でも材質や種類によって適応となる疾患や機能も変わってきます。それぞれの装具についてしっかり勉強していきましょう!" target="_blank">1年生 体幹装具の製作実習が始まりました。

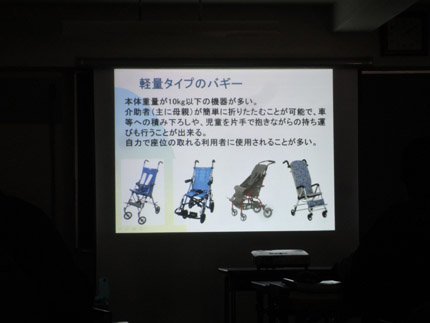 小畑先生は車椅子を中心に、子供用から成人用、特殊な機構を持つもの、電動車椅子など、さまざまなタイプの車椅子とその適応について分かり易くご講義いただきました。車椅子と言っても、必要とする患者様の状態によってたくさんの選択肢があることを理解できたのではないでしょうか?
小畑先生は車椅子を中心に、子供用から成人用、特殊な機構を持つもの、電動車椅子など、さまざまなタイプの車椅子とその適応について分かり易くご講義いただきました。車椅子と言っても、必要とする患者様の状態によってたくさんの選択肢があることを理解できたのではないでしょうか? 続いて、座位保持装置の製作について学びます。座位保持装置の製作方法として、身体各部の寸法を計測する採寸による方法と、適切な座位を再現したうえで身体の型をとる採型による方法があります。今回は写真の専用採型台を用いた採型方法について実習を行いました。
続いて、座位保持装置の製作について学びます。座位保持装置の製作方法として、身体各部の寸法を計測する採寸による方法と、適切な座位を再現したうえで身体の型をとる採型による方法があります。今回は写真の専用採型台を用いた採型方法について実習を行いました。 採型に使用する器具の準備をします。患者様の負担を減らすためにも、事前準備がとても大切であることを藤田先生から繰り返しお話いただきました。
採型に使用する器具の準備をします。患者様の負担を減らすためにも、事前準備がとても大切であることを藤田先生から繰り返しお話いただきました。 準備ができたら患者様の事前評価を行います。変形や麻痺の程度を把握しながら、どのように患者様の姿勢を作っていくか、また、採型者が完成品をどれだけイメージできているかが重要であることを教えていただきました。
準備ができたら患者様の事前評価を行います。変形や麻痺の程度を把握しながら、どのように患者様の姿勢を作っていくか、また、採型者が完成品をどれだけイメージできているかが重要であることを教えていただきました。

 事前評価を基に、専用採型台を用いて患者様を安定性良く、かつ楽に座れる姿勢を再現していきます。常に患者様の状態を見ながら素早く作業を進めることが大切ですね!
事前評価を基に、専用採型台を用いて患者様を安定性良く、かつ楽に座れる姿勢を再現していきます。常に患者様の状態を見ながら素早く作業を進めることが大切ですね! 採型を終えたクッションです。しっかりと身体の形状が再現されています。
この後、ギプスを用いてさらにこのクッションの採型を行います。そして得られたギプスモデルを三次元スキャナでパソコンに読み込ませ、CAD/CAMを用いてスポンジ等の切削加工を行います。
採型を終えたクッションです。しっかりと身体の形状が再現されています。
この後、ギプスを用いてさらにこのクッションの採型を行います。そして得られたギプスモデルを三次元スキャナでパソコンに読み込ませ、CAD/CAMを用いてスポンジ等の切削加工を行います。 藤田先生に教えていただいたことを踏まえ、いざ、実践です!
藤田先生に教えていただいたことを踏まえ、いざ、実践です! 夢中になり過ぎて患者様の状態を確認することを忘れないようにしましょうね!
夢中になり過ぎて患者様の状態を確認することを忘れないようにしましょうね! 続いて、小畑先生から種車椅子について実際に試乗しながら説明をしていただきました。講義のために大阪(大東市)から10台以上の車椅子を持って来ていただきました。
続いて、小畑先生から種車椅子について実際に試乗しながら説明をしていただきました。講義のために大阪(大東市)から10台以上の車椅子を持って来ていただきました。 車椅子の構造を理解したら、次は利用者の視点に立って実際に路上を試乗してみましょう!
車椅子の構造を理解したら、次は利用者の視点に立って実際に路上を試乗してみましょう! 日本の道路は水はけを良くするために、中央が盛り上がった“片流れ路”になっています。車椅子を真っ直ぐ操作しているつもりでも、なかなか直進できませんね。車椅子利用者の本当の不便さを理解することが、何よりも勉強です!
日本の道路は水はけを良くするために、中央が盛り上がった“片流れ路”になっています。車椅子を真っ直ぐ操作しているつもりでも、なかなか直進できませんね。車椅子利用者の本当の不便さを理解することが、何よりも勉強です! 狭い路地の走行にも気を使いますね。後ろのほうでは電柱にぶつかっているようですが大丈夫ですか?
狭い路地の走行にも気を使いますね。後ろのほうでは電柱にぶつかっているようですが大丈夫ですか? 車椅子の介助を体験中。車椅子使用者だけでなく、介助者の視点を学ぶことで見えてくることが大きく変わります。常に双方の視点を忘れずに、モノづくりをして下さいね!
車椅子の介助を体験中。車椅子使用者だけでなく、介助者の視点を学ぶことで見えてくることが大きく変わります。常に双方の視点を忘れずに、モノづくりをして下さいね!以上、2日間にわたって座位保持装置、車椅子を徹底的にご講義いただきました。とても内容の濃い2日間に学生たちはやや疲れぎみのようでしたが、何より最後までとても熱心にご指導いただきました小畑先生、藤田先生ありがとうございました。" target="_blank">3年生 座位保持装置の特別講義が行われました。
 切断端にギプス包帯を巻く手際も良くなってきました。頭の中でしっかり作業手順が理解できているようです。先生たちも安心して作業を見ていることができます。
切断端にギプス包帯を巻く手際も良くなってきました。頭の中でしっかり作業手順が理解できているようです。先生たちも安心して作業を見ていることができます。 奇麗な陰性モデルが採れましたね!
モデルさんとのコミュニケーションも、ぎこちなさが抜けて自然に会話ができるようになりました。皆さん、ゆっくりで良いので少しずつ義肢装具士に近づいて行って下さい!
奇麗な陰性モデルが採れましたね!
モデルさんとのコミュニケーションも、ぎこちなさが抜けて自然に会話ができるようになりました。皆さん、ゆっくりで良いので少しずつ義肢装具士に近づいて行って下さい!昔から、「義肢装具の適合は、採型(さいけい)の良し悪しで全て決まる」と言われているほど、採型は義肢装具士のモノづくりにとって重要な工程です。学生たちもその大切さをようやく実感できるようになってきました。
次回は、陽性モデル修正から義足組み立てまでの工程をまとめてご紹介します!" target="_blank">2年生 下腿義足の採型実習が行われました。
 次に「歩行観察」です。ヒトがどのように歩いているかを前後、左右からポイントを定めて観察をします。義肢装具士にとって、“歩行を観察する目”を持つことはとても重要です。これがしっかり身に付いていると、義肢装具がどのようにヒトに影響しているかを判断することができます。
次に「歩行観察」です。ヒトがどのように歩いているかを前後、左右からポイントを定めて観察をします。義肢装具士にとって、“歩行を観察する目”を持つことはとても重要です。これがしっかり身に付いていると、義肢装具がどのようにヒトに影響しているかを判断することができます。 次に、装具を製作する上で必要な脚の輪郭を用紙にトレースしていきます。ここでも学ぶべきポイントはたくさんあります。患者様への負担が少なく、効率的に作業を進めなくてはいけないため、学生たちは先生の説明を食入るように聞いています。
次に、装具を製作する上で必要な脚の輪郭を用紙にトレースしていきます。ここでも学ぶべきポイントはたくさんあります。患者様への負担が少なく、効率的に作業を進めなくてはいけないため、学生たちは先生の説明を食入るように聞いています。 次は採型練習です。この装具は脚のトレースから製作する場合と、ギプス包帯で採型して石膏モデルを基に製作する場合の2つの製作方法があります。
2年生もこの時期になると、自信を持って上手に採型できるようになっていますね!
次は採型練習です。この装具は脚のトレースから製作する場合と、ギプス包帯で採型して石膏モデルを基に製作する場合の2つの製作方法があります。
2年生もこの時期になると、自信を持って上手に採型できるようになっていますね!次回は金属支柱の曲げ加工の様子をご紹介します。 " target="_blank">2年生 長下肢装具の製作実習がスタートしました。
" target="_blank">評価実習指導者会議を行いました(補聴2年生)
 長野県の姨捨サービスエリアでお昼休憩です。遠くの山並みが雪景色に変わり、だんだん空気も冷たくなってきました。
長野県の姨捨サービスエリアでお昼休憩です。遠くの山並みが雪景色に変わり、だんだん空気も冷たくなってきました。ようやく、斑尾高原スキー場に到着しました! 一日目の様子です。
 学生たちはソリ大会やかまくら作りに奮闘していました。日ごろは交流が少ない1年生と3年生も楽しく関わりを持つことができました。また、かまくらはかなりの完成度で、スキー場に来たスキーヤーからも好評でした。いざ作るとなれば妥協はしない!さすがPO学科の学生ですね!細かな部分までこだわって製作していました。
学生たちはソリ大会やかまくら作りに奮闘していました。日ごろは交流が少ない1年生と3年生も楽しく関わりを持つことができました。また、かまくらはかなりの完成度で、スキー場に来たスキーヤーからも好評でした。いざ作るとなれば妥協はしない!さすがPO学科の学生ですね!細かな部分までこだわって製作していました。 この日は12月25日、クリスマスです。夕食のあとは中川先生より学生全員にクリスマスケーキのプレゼントがありました!
この日は12月25日、クリスマスです。夕食のあとは中川先生より学生全員にクリスマスケーキのプレゼントがありました!2日目の様子です。
 この日はスキーやスノーボードをするグループと、善光寺参りと小布施の町並みを散策するグループに分かれて行動しました。
天候にも恵まれ、山頂からの眺めは最高でした。初めてスキーやスノーボードをする学生もいましたが、学生同士教え合いながら楽しそうでした。また、善光寺では玉照院で座禅体験や小布施グルメを満喫したようです。さて、座禅の効果はあったでしょうか?
この日はスキーやスノーボードをするグループと、善光寺参りと小布施の町並みを散策するグループに分かれて行動しました。
天候にも恵まれ、山頂からの眺めは最高でした。初めてスキーやスノーボードをする学生もいましたが、学生同士教え合いながら楽しそうでした。また、善光寺では玉照院で座禅体験や小布施グルメを満喫したようです。さて、座禅の効果はあったでしょうか? 日ごろの学校生活では見ない学生たちの無邪気な姿に、先生たちも癒されました。
来年もみんなこのパワーで頑張って行きましょう!" target="_blank">斑尾高原へスキー合宿に行ってきました。
日ごろの学校生活では見ない学生たちの無邪気な姿に、先生たちも癒されました。
来年もみんなこのパワーで頑張って行きましょう!" target="_blank">斑尾高原へスキー合宿に行ってきました。 毎日の製作実習で使う機械に感謝をこめて、綺麗にしています!
毎日の製作実習で使う機械に感謝をこめて、綺麗にしています! いつも使っている教室も隅々までピカピカに!最後は先輩たちがチェックをします!
いつも使っている教室も隅々までピカピカに!最後は先輩たちがチェックをします! 昼食はPO学科伝統のカレーライスが待っています。早朝から学生会が丹精こめて作ったカレーライスを学生全員でいただきます!
昼食はPO学科伝統のカレーライスが待っています。早朝から学生会が丹精こめて作ったカレーライスを学生全員でいただきます! 頑張ってお掃除したから美味しいですね!おかわりもいっぱいありますよ!
頑張ってお掃除したから美味しいですね!おかわりもいっぱいありますよ! デザートは青森の臨床実習施設から送っていただいたリンゴをみんなでいただきました!
デザートは青森の臨床実習施設から送っていただいたリンゴをみんなでいただきました! 蜜が入った美味しいリンゴをありがとうございました!ご馳走さまでした!
蜜が入った美味しいリンゴをありがとうございました!ご馳走さまでした!学生全員の協力で、学校中がピカピカになりました。これで気持ちの良い新年を迎えることが出来そうです!
年が明けると3年生はいよいよ国家試験受験に向けてカウントダウンが始まります。2年生は来年度の臨床実習、卒業研究に向けて準備段階に入り、1年生は専門科目の実習が基礎から各論へと進んで行きます。各学年とも実り多き年となりますよう期待しています!
今年一年お世話になりました皆様へ、心より感謝申し上げます。" target="_blank">年末恒例の大掃除を行いました。
 学生たちのなかには、臨床実習で膝関節周囲の疾患についてすでに学習している学生も多くいますが、より臨床的な講義内容に興味津々です。
学生たちのなかには、臨床実習で膝関節周囲の疾患についてすでに学習している学生も多くいますが、より臨床的な講義内容に興味津々です。 講義のあとは、実際に装具を着けてみましょう!
装着手順、ベルトの走路など、膝装具の機能についてじっくり説明を受けながら一つ一つ理解を深めて行きます。
講義のあとは、実際に装具を着けてみましょう!
装着手順、ベルトの走路など、膝装具の機能についてじっくり説明を受けながら一つ一つ理解を深めて行きます。 学生たちは真剣な表情で装着方法を聞いています。
どんなに優れた機能を持つ装具でも、正しく装着していなければその効果は期待できません。いつも患者様の身になって考えられる義肢装具士になって下さいね!
学生たちは真剣な表情で装着方法を聞いています。
どんなに優れた機能を持つ装具でも、正しく装着していなければその効果は期待できません。いつも患者様の身になって考えられる義肢装具士になって下さいね! お互いに装具の位置、ベルトの走路などを一つ一つ確認しながら実際に装着体験して行きます。うまく装着できるでしょうか?
お互いに装具の位置、ベルトの走路などを一つ一つ確認しながら実際に装着体験して行きます。うまく装着できるでしょうか? 実際に装着してみると、装具がどのように身体に作用しているかがよく分かります。ここでは学生同士のディスカッションが始まりました。プロの視点になって疑問点を話し合う姿がたくましく見えます!
実際に装着してみると、装具がどのように身体に作用しているかがよく分かります。ここでは学生同士のディスカッションが始まりました。プロの視点になって疑問点を話し合う姿がたくましく見えます! 義肢装具士は補装具全般を取り扱うことができるスペシャリストです。
専門領域のさまざまな講義を通して幅広い専門性を身につけて行って下さい!" target="_blank">膝装具(アルケア株式会社)の特別講義が行われました。
義肢装具士は補装具全般を取り扱うことができるスペシャリストです。
専門領域のさまざまな講義を通して幅広い専門性を身につけて行って下さい!" target="_blank">膝装具(アルケア株式会社)の特別講義が行われました。 授業で学んだことを正確に、なおかつ迅速に行えるかが重要です。
授業で学んだことを正確に、なおかつ迅速に行えるかが重要です。 この試験では、機械や工具を正しく安全に使っているかも審査しています。
この試験では、機械や工具を正しく安全に使っているかも審査しています。 義足を脚の形に削り出しているところです。理論的に組み上げた部品を、最後は美しい脚の形に仕上げなくてはいけません。最も芸術的なセンスが求められる工程です!
義足を脚の形に削り出しているところです。理論的に組み上げた部品を、最後は美しい脚の形に仕上げなくてはいけません。最も芸術的なセンスが求められる工程です!この実技試験が終わると、「義肢装具基本工作論」の授業も終了です。ここからは、いよいよ義肢装具士になるための専門科目の授業が本格的にスタートします。そのためにも、この実技試験を全員がクリアして、次のステップに進んで下さい!" target="_blank">1年生 義肢装具基本工作論実技試験が行われました。
 学生にはセッションごとに2名ずつ座長を担当してもらいました。1年にとっては初めての体験でしたが、3年生の先輩にサポートしてもらいながら、落ち着いてセッションを進めていました。
学生にはセッションごとに2名ずつ座長を担当してもらいました。1年にとっては初めての体験でしたが、3年生の先輩にサポートしてもらいながら、落ち着いてセッションを進めていました。次は発表者の様子です。一部のみご紹介させていただきます。
 学生たちはみんな自信に満ちた表情で発表しています。5分間という限られた時間のなかで、いかに分かりやすく相手に情報を伝えるかはとても難しいことですね。学生たちは前日も深夜まで学校に残り、教務の先生たちと試行錯誤しながら発表の準備をしていました。
学生たちはみんな自信に満ちた表情で発表しています。5分間という限られた時間のなかで、いかに分かりやすく相手に情報を伝えるかはとても難しいことですね。学生たちは前日も深夜まで学校に残り、教務の先生たちと試行錯誤しながら発表の準備をしていました。 来賓の先生方から多くのご質問、ご意見をいただきました!
来賓の先生方から多くのご質問、ご意見をいただきました!
 来賓の先生やOBからの質問にも、学生たちはしっかり対応していました。
来年の臨床実習の課題が見つかった学生もおり、会場内は白熱した雰囲気でした!
来賓の先生やOBからの質問にも、学生たちはしっかり対応していました。
来年の臨床実習の課題が見つかった学生もおり、会場内は白熱した雰囲気でした! 発表した学生のなかには、休憩時間に疑問点などを積極的に来賓の先生方に聞きに行く場面が見られました。「自ら進んで学ぶことの楽しさ」を実感してもらえると嬉しいです!
発表した学生のなかには、休憩時間に疑問点などを積極的に来賓の先生方に聞きに行く場面が見られました。「自ら進んで学ぶことの楽しさ」を実感してもらえると嬉しいです! 参加した学生も一生懸命、メモをとっているようです。症例報告会の実施目的でもある「情報共有」の大切さが実感できる1コマです。
参加した学生も一生懸命、メモをとっているようです。症例報告会の実施目的でもある「情報共有」の大切さが実感できる1コマです。

 参加者全員の投票の結果、最優秀賞は山本あゆかさん(第3学年)、優秀賞は西村正暁君(第3学年)と、岡本敬之君(第2学年)が選ばれました。
受賞者には、中川教務主任より記念の校章入りクリスタルガラスの楯が贈呈されました。
参加者全員の投票の結果、最優秀賞は山本あゆかさん(第3学年)、優秀賞は西村正暁君(第3学年)と、岡本敬之君(第2学年)が選ばれました。
受賞者には、中川教務主任より記念の校章入りクリスタルガラスの楯が贈呈されました。 山本あゆかさん、西村正暁君、岡本敬之君、受賞おめでとうございました!
山本あゆかさん、西村正暁君、岡本敬之君、受賞おめでとうございました! 発表者の皆さん、ご苦労様でした!
この症例報告会を通して多くの学生が、臨床実習という機会に何を学び、何を経験しなくてはいけないのかを、改めて理解できたのではないかと思います。来年の臨床実習でも、より具体的な目的意識を持って臨んで下さい。
また、3年生の皆さんは今回の経験を活かし、「患者様のために探究する姿勢」を忘れずに、臨床でも活躍して下さい!" target="_blank">平成25年度 臨床実習症例報告会が開催されました。
発表者の皆さん、ご苦労様でした!
この症例報告会を通して多くの学生が、臨床実習という機会に何を学び、何を経験しなくてはいけないのかを、改めて理解できたのではないかと思います。来年の臨床実習でも、より具体的な目的意識を持って臨んで下さい。
また、3年生の皆さんは今回の経験を活かし、「患者様のために探究する姿勢」を忘れずに、臨床でも活躍して下さい!" target="_blank">平成25年度 臨床実習症例報告会が開催されました。またはメール→ st@kzan.jp にてどうぞ。
お気軽にお申し込みください! お待ちしています。
" target="_blank">夜間学校説明会のお知らせ
当日は在学生たちも参加していました。
在学中はもちろんですが、 卒業後の学びなくしていい臨床家にはなれません。 在学生たちが見た先輩の真剣なまなざし、 これを今後ずっと忘れることなくいてほしいものです。
" target="_blank">同窓会イベント 『吃音』のセミナーを行いました。
 モデルさんは開学以来ご協力いただいている義手使用の大ベテランです。初めての上腕義手の採型で学生たちも緊張していましたが、モデルさんのほうから義手について実体験を交えたお話をしていただき、和やかな雰囲気のなかで採型が行われていました。
※プライバシー保護の為、画像を一部加工しています。
モデルさんは開学以来ご協力いただいている義手使用の大ベテランです。初めての上腕義手の採型で学生たちも緊張していましたが、モデルさんのほうから義手について実体験を交えたお話をしていただき、和やかな雰囲気のなかで採型が行われていました。
※プライバシー保護の為、画像を一部加工しています。 上腕切断者の切断端は軟部組織がとても柔らかく、学生たちにはこれまでの採型実習では体験したことのない感触だったと思います。
上腕切断者の切断端は軟部組織がとても柔らかく、学生たちにはこれまでの採型実習では体験したことのない感触だったと思います。 さあ、いよいよ採型です!講義で学習した通りにできるでしょうか?
学生の緊張がモデルさんにも伝わっているようですが・・・。
※プライバシー保護の為、画像を一部加工しています。
さあ、いよいよ採型です!講義で学習した通りにできるでしょうか?
学生の緊張がモデルさんにも伝わっているようですが・・・。
※プライバシー保護の為、画像を一部加工しています。 採型が終わったら、その場でギプスソケットを製作し適合状態をチェックします。
採型が終わったら、その場でギプスソケットを製作し適合状態をチェックします。 モデルさんから現在使用している義手の状況や、切断原因、切断端のどこに痛みがあるかなど、様々な情報を聞き出すことが義手を製作するうえで大切なポイントとなります。
モデルさんから現在使用している義手の状況や、切断原因、切断端のどこに痛みがあるかなど、様々な情報を聞き出すことが義手を製作するうえで大切なポイントとなります。次回は、陽性モデル修正とソケット樹脂注型の様子をレポートします!" target="_blank">2年生 上腕義手の採型実習が行われました。
 先生のデモンストレーションを見ながら、このあと自分が製作する陽性モデルにどのように反映させるかを考えていきます。学生たちは先生の手元をよく観察し、作業のポイントを見落とさないように真剣です!
先生のデモンストレーションを見ながら、このあと自分が製作する陽性モデルにどのように反映させるかを考えていきます。学生たちは先生の手元をよく観察し、作業のポイントを見落とさないように真剣です!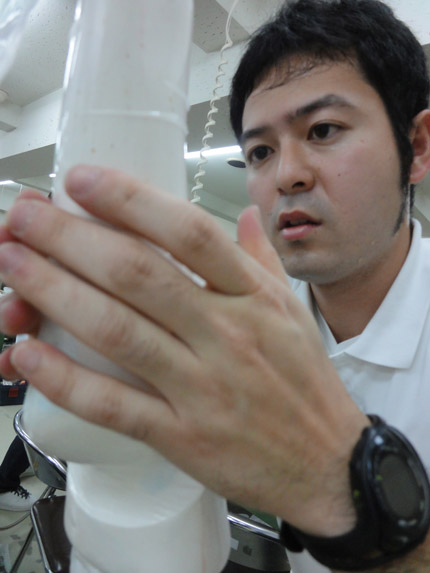 仮合わせで確認した情報を最終的に製作するソケットに反映させ、液体の樹脂を流し込んでいよいよ義手の形に成形していきます。
仮合わせで確認した情報を最終的に製作するソケットに反映させ、液体の樹脂を流し込んでいよいよ義手の形に成形していきます。 液体の樹脂を流し込み、切断後の残存している部分を挿入するソケットを製作しています。学生たちは授業のなかで何度もこの作業を経験していますが、いつも緊張するようです。
液体の樹脂を流し込み、切断後の残存している部分を挿入するソケットを製作しています。学生たちは授業のなかで何度もこの作業を経験していますが、いつも緊張するようです。 学生たちのソケットが完成しました!
次は、電動ハンドを取り付ける前腕部の製作です。このソケット先端に石膏を盛り付け、使用者の手の長さに合わせて前腕部を形作っていきます。
学生たちのソケットが完成しました!
次は、電動ハンドを取り付ける前腕部の製作です。このソケット先端に石膏を盛り付け、使用者の手の長さに合わせて前腕部を形作っていきます。 徐々に形になってきましたね。筋電義手では電動ハンドを動かすためのバッテリーを取り付けます。どこに付けると使用者が最も使い易いかを考えるのも大切なことです。
徐々に形になってきましたね。筋電義手では電動ハンドを動かすためのバッテリーを取り付けます。どこに付けると使用者が最も使い易いかを考えるのも大切なことです。 製作途中で学生同士のディスカッションが始まりました。単なるモノづくりではなく、使用者の「生活」や「条件」を考えたモノづくりを学んで下さいね!
製作途中で学生同士のディスカッションが始まりました。単なるモノづくりではなく、使用者の「生活」や「条件」を考えたモノづくりを学んで下さいね!次は適合評価の様子をご紹介します。
 仮合わせ後に問題点を修正し、ソケット適合に問題がなければバッテリーを取り付けていよいよ義手を動かしてみましょう!まずは体の前です。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
仮合わせ後に問題点を修正し、ソケット適合に問題がなければバッテリーを取り付けていよいよ義手を動かしてみましょう!まずは体の前です。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。 次に口元です。口元で電動ハンドがしっかり開閉できるかチェックしています。義肢装具士として使用者に分かり易い説明ができているでしょうか?
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
次に口元です。口元で電動ハンドがしっかり開閉できるかチェックしています。義肢装具士として使用者に分かり易い説明ができているでしょうか?
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。 次は靴ひもを結ぶ位置で電動ハンドの開閉が可能かチェックします。この筋電義手は問題なく操作できるようですね。モデルさんも思わず笑みがこぼれています!
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
次は靴ひもを結ぶ位置で電動ハンドの開閉が可能かチェックします。この筋電義手は問題なく操作できるようですね。モデルさんも思わず笑みがこぼれています!
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。 義肢装具士として、筋電義手の使い方を分かり易く説明することも大切な役割です。モデルさんの目を見てしっかりとコミュニケーションがとれていますか?
義肢装具士として、筋電義手の使い方を分かり易く説明することも大切な役割です。モデルさんの目を見てしっかりとコミュニケーションがとれていますか?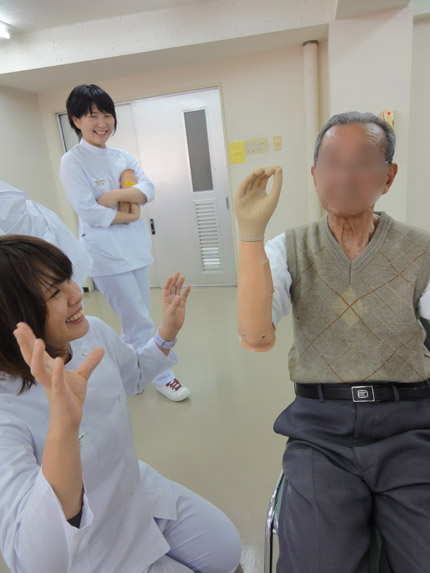 筋電義手の適合評価が完了し、これで前腕義手の製作実習は終了です。
一生懸命製作してモデルさんに喜んでもらえると、頑張った甲斐がありますね!この楽しさを忘れずに、次の上腕義手の製作実習も頑張りましょう!
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。" target="_blank">2年生 筋電義手の適合実習が行われました。
筋電義手の適合評価が完了し、これで前腕義手の製作実習は終了です。
一生懸命製作してモデルさんに喜んでもらえると、頑張った甲斐がありますね!この楽しさを忘れずに、次の上腕義手の製作実習も頑張りましょう!
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。" target="_blank">2年生 筋電義手の適合実習が行われました。またはメール→ st@kzan.jp にてどうぞ。
お気軽にお申し込みください! お待ちしています。 " target="_blank">『夜間学校説明会』のお知らせ
義肢装具学科では『義肢装具士』への進路を検討中の方への情報提供として、個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています。 義肢装具士をもっと知りたい!と興味をもった方はぜひご参加ください!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具製作施設見学ツアーのご案内!
" target="_blank">義肢装具製作施設見学ツアーのご案内! すべての部品に引いたラインが1本につながるように義足を組み立てていきます。
ブロックが組み上がったところでそれぞれを接着し、いよいよ型出しの工程へと進みます。
すべての部品に引いたラインが1本につながるように義足を組み立てていきます。
ブロックが組み上がったところでそれぞれを接着し、いよいよ型出しの工程へと進みます。 先生が実際の脚をモデルに、解剖学的に見た下肢の形状について細かく説明をしています。
先生が実際の脚をモデルに、解剖学的に見た下肢の形状について細かく説明をしています。 いざ、実践!削っては何度もデッサンを繰り返し、脚のイメージを明確に表現できるようにしていきます。
いざ、実践!削っては何度もデッサンを繰り返し、脚のイメージを明確に表現できるようにしていきます。  おおよそ満足のいく形に仕上がった時点で、クラスメイトに客観的に評価してもらいます。クライスメイトに評価してもらうと、自分では気が付かなかった点が見えてきますね。
おおよそ満足のいく形に仕上がった時点で、クラスメイトに客観的に評価してもらいます。クライスメイトに評価してもらうと、自分では気が付かなかった点が見えてきますね。 右脚、左脚、間違えないように!
頭でイメージした形状を実際に機会を使って削り出していく作業はなかなか難しいようですね。
右脚、左脚、間違えないように!
頭でイメージした形状を実際に機会を使って削り出していく作業はなかなか難しいようですね。 ようやく脚の形になってきましたね!
患者様が装着したくなるような仕上がりを目指しましょう!" target="_blank">1年生 PTB式下腿義足(殻構造)の「型出し」を行いました。
ようやく脚の形になってきましたね!
患者様が装着したくなるような仕上がりを目指しましょう!" target="_blank">1年生 PTB式下腿義足(殻構造)の「型出し」を行いました。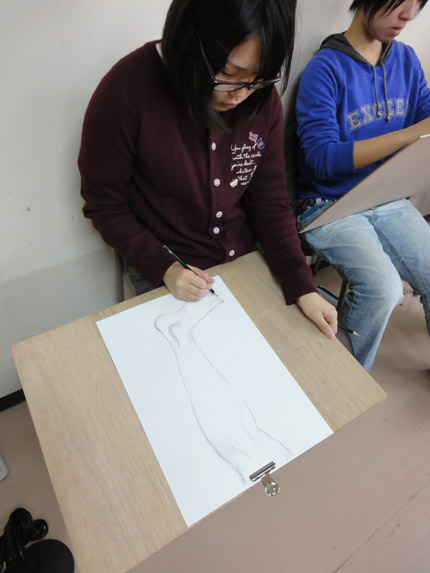 解剖学で学んだ知識もデッサンに盛り込んでいきます。
筋腹の位置、曲線の頂点、陰影の表現方法など学ぶことが沢山あります。
解剖学で学んだ知識もデッサンに盛り込んでいきます。
筋腹の位置、曲線の頂点、陰影の表現方法など学ぶことが沢山あります。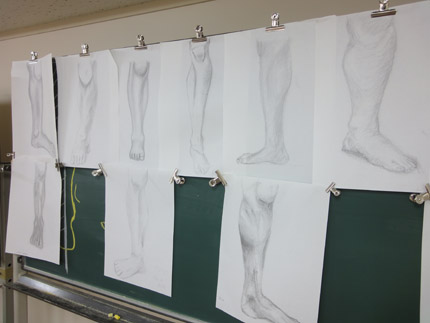 デッサンが完成しました!脚をしっかりイメージすることができたでしょうか?
デッサンが完成しました!脚をしっかりイメージすることができたでしょうか? 次は粘土で実際に脚を造形してみます。
デッサンでしっかり脚のイメージができれば、立体的に造形することもできるようになります!
次は粘土で実際に脚を造形してみます。
デッサンでしっかり脚のイメージができれば、立体的に造形することもできるようになります! 完成したミニチュアの脚です。
完成したミニチュアの脚です。次回は、いよいよ義足を実際の脚の形に仕上げていく作業が始まります。患者様にとって義足の外観は義足を装着するための大きなモチベーションにつながります。「型出し」の作業を通して自分の美的感性をしっかり磨いていきましょう!" target="_blank">1年生 芸術の秋 自分の感性と向き合う講義?
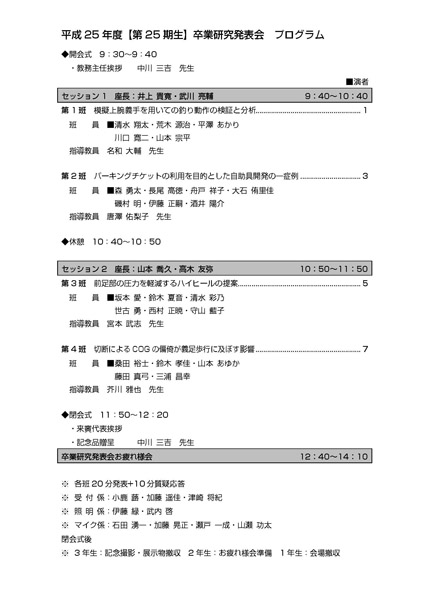 第1班「模擬上腕義手を用いての釣り動作の検証と分析」
第2班「パーキングチケットの利用を目的とした自助具開発の一症例」
第3班「前足部の圧力を軽減するハイヒールの提案」
第4班「切断によるCOGの偏倚が義足歩行に及ぼす影響」
以上、全4班による発表となりました。
発表時間は各班20分で、質疑応答は10分間です。
第1班「模擬上腕義手を用いての釣り動作の検証と分析」
第2班「パーキングチケットの利用を目的とした自助具開発の一症例」
第3班「前足部の圧力を軽減するハイヒールの提案」
第4班「切断によるCOGの偏倚が義足歩行に及ぼす影響」
以上、全4班による発表となりました。
発表時間は各班20分で、質疑応答は10分間です。 1・2年生も真剣な面持ちで発表を聞いています。
1・2年生も真剣な面持ちで発表を聞いています。 座長を務めるのは2年生です。こちらも緊張した様子でしたが、うまく進行できたでしょうか?来年は自分たちが発表をする立場になります。1・2年生の皆さん、3年生の勇姿をしっかり見ておいてくださいね!
座長を務めるのは2年生です。こちらも緊張した様子でしたが、うまく進行できたでしょうか?来年は自分たちが発表をする立場になります。1・2年生の皆さん、3年生の勇姿をしっかり見ておいてくださいね! 初めて聞く相手に、いかに分かりやすく説明できるか、本学科の教育課題の1つである「プレゼンテーション能力」が重要になってきます。
初めて聞く相手に、いかに分かりやすく説明できるか、本学科の教育課題の1つである「プレゼンテーション能力」が重要になってきます。 質疑応答では1・2年生や来賓の先生方、教務からも活発な質問がされました。やや時間を超過して学生が研究成果を説明する場面もあり、とても熱いディスカッションが繰り広げられていました!
質疑応答では1・2年生や来賓の先生方、教務からも活発な質問がされました。やや時間を超過して学生が研究成果を説明する場面もあり、とても熱いディスカッションが繰り広げられていました! 第3班が実際に製作した靴です。市販されている既製靴と比べてもまったく遜色のない仕上がりとなっており、多くの参加者の注目を集めていました。なお、この研究は来年2月に開催される第10回日本整形靴技術協会学術大会(東京)IVO JAPANにエントリーする予定です。
学生たちは日々の講義の限られた時間のなかで、どの班も上手く役割分担をして研究に取り組んでいました。
第3班が実際に製作した靴です。市販されている既製靴と比べてもまったく遜色のない仕上がりとなっており、多くの参加者の注目を集めていました。なお、この研究は来年2月に開催される第10回日本整形靴技術協会学術大会(東京)IVO JAPANにエントリーする予定です。
学生たちは日々の講義の限られた時間のなかで、どの班も上手く役割分担をして研究に取り組んでいました。
 本学科顧問の髙見健二先生(写真:上)と元教務主任の松本芳樹先生(写真:下)からそれぞれ総評をいただき、お褒めの言葉だけでなく、今後の具体的な研究課題などについてもアドバイスをいただきました。
本学科顧問の髙見健二先生(写真:上)と元教務主任の松本芳樹先生(写真:下)からそれぞれ総評をいただき、お褒めの言葉だけでなく、今後の具体的な研究課題などについてもアドバイスをいただきました。 終了後の集合写真です。3年生全員が晴れやかな顔をしていました。
終了後の集合写真です。3年生全員が晴れやかな顔をしていました。

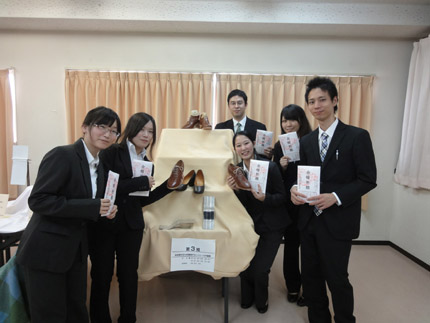
 閉会式では中川教務主任から国家試験合格祈願セットが3年生全員に贈呈されました!この達成感を胸に、第25期生全員合格を目指して、これからの試験勉強に取り組んで行きましょう!
閉会式では中川教務主任から国家試験合格祈願セットが3年生全員に贈呈されました!この達成感を胸に、第25期生全員合格を目指して、これからの試験勉強に取り組んで行きましょう!閉会式後、学生会企画の卒業研究お疲れ様会が開かれました。 3年生の皆さん、一年間お疲れ様でした!
ここからはお疲れ様会の様子を写真でご紹介します。




 お疲れ様会の会場でも、引き続き後輩たちから卒業研究のテーマ決めや、研究の進め方について質問がされていました。" target="_blank">3年生 卒業研究発表会が行われました。
お疲れ様会の会場でも、引き続き後輩たちから卒業研究のテーマ決めや、研究の進め方について質問がされていました。" target="_blank">3年生 卒業研究発表会が行われました。 筋電位がうまく感知できるでしょうか。専用の電極を取り付けて確認しています。実際の医療現場では作業療法士との連携が重要となる作業です。
筋電位がうまく感知できるでしょうか。専用の電極を取り付けて確認しています。実際の医療現場では作業療法士との連携が重要となる作業です。 ギプス包帯を使って断端の採型を行ないます。肘関節周辺の形状を出すために特殊な手技を行います。
ギプス包帯を使って断端の採型を行ないます。肘関節周辺の形状を出すために特殊な手技を行います。 問題なく採型できたでしょうか?次の仮合わせが楽しみですね。
問題なく採型できたでしょうか?次の仮合わせが楽しみですね。 仮合わせでは、ソケットの適合状態を確認するために透明なプラスチックを用いてソケットを製作します。また、ハンドの位置関係を調整できるようにするために義手全体が仮合わせに適した形をしています。
仮合わせでは、ソケットの適合状態を確認するために透明なプラスチックを用いてソケットを製作します。また、ハンドの位置関係を調整できるようにするために義手全体が仮合わせに適した形をしています。
 この製作実習は、株式会社松本義肢製作所の溝手雅之先生にご指導いただいています。まずはソケットの適合状態を確認します。様々な方向から力を加えて痛みが無いか確認しています。
この製作実習は、株式会社松本義肢製作所の溝手雅之先生にご指導いただいています。まずはソケットの適合状態を確認します。様々な方向から力を加えて痛みが無いか確認しています。 電極を取り付けてハンドを動かしてみましょう。先生の製作した義手は問題なく動いています。さあ、学生たちはどうでしょうか?
電極を取り付けてハンドを動かしてみましょう。先生の製作した義手は問題なく動いています。さあ、学生たちはどうでしょうか? 学生のソケットも問題なく、ハンドもうまく動いているようですね!
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
学生のソケットも問題なく、ハンドもうまく動いているようですね!
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。 筋電義手の操作に習熟すれば、紙コップのような柔らかい素材もこのように把持することができます。
筋電義手の操作に習熟すれば、紙コップのような柔らかい素材もこのように把持することができます。次回は仮合わせの情報をもとに、日常生活で使用できる形に仕上げていく工程をご紹介します!" target="_blank">2年生 筋電義手の製作実習がスタートしました。
 今回の会場となった佐賀市文化会館です。佐賀はもう紅葉が始まっていました。
今回の会場となった佐賀市文化会館です。佐賀はもう紅葉が始まっていました。 来年、金沢で行われる第21回日本義肢装具士協会学術大会の展示ブースです。金沢では、本校の学生たちが運営スタッフを務めます。ぜひ、金沢へもご参加ください!
来年、金沢で行われる第21回日本義肢装具士協会学術大会の展示ブースです。金沢では、本校の学生たちが運営スタッフを務めます。ぜひ、金沢へもご参加ください!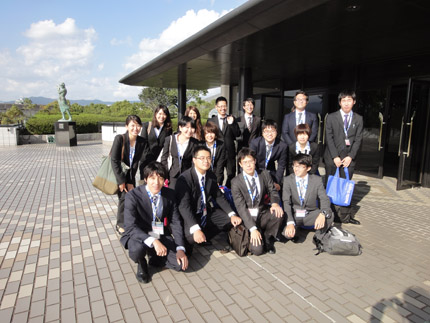 学会も終わり、会場前で記念の集合写真。今回有志で参加した学生の皆さん、おつかれさまでした!
学会も終わり、会場前で記念の集合写真。今回有志で参加した学生の皆さん、おつかれさまでした!今回の学会は演題数も多く、各会場では活発に意見交換が行われていました。参加した学生たちはEBM(医学的根拠)に基づいた義肢装具製作の奥深さを感じるよい機会になったことと思います。" target="_blank">第29回日本義肢装具学会学術大会に参加しました!
 企業の方々から会社の魅力、義肢装具士の仕事の醍醐味について沢山お話していただきました。
企業の方々から会社の魅力、義肢装具士の仕事の醍醐味について沢山お話していただきました。 学生の中には10社もお話を聞いた学生もいました。短い時間でしたが、全国の義肢装具製作会社の特色を知ることができたようですね。
学生の中には10社もお話を聞いた学生もいました。短い時間でしたが、全国の義肢装具製作会社の特色を知ることができたようですね。 学生たちも積極的に質問しており、どの企業ブースもたいへん盛況でした。
学生たちも積極的に質問しており、どの企業ブースもたいへん盛況でした。本学では1年生から企業説明会に参加し、就職について早い時期から意識して学校生活を送るように指導しています。年に一度、全国各地の企業の皆様とお話しすることのできる貴重な機会を学生の皆さんは有意義に過ごすことができたでしょうか?3年間で自分の将来を決めることができるよう、今からしっかり準備をして行きましょう!
遠方よりご参加いただきました企業の皆様、長時間にわたり自社の魅力を多くの学生にお伝えいただき、誠にありがとうございました!また来年のご参加を教務一同、お待ちしております。" target="_blank">平成25年度 義肢装具学科企業説明会が行なわれました。
平成26年度 義肢装具学科 入学試験についてご案内します。 推薦一次・一般一次試験の出願を下記の通り受付けます。 受験希望の方はご確認の上、出願手続をお願いします。
◆試験科目 推薦入学試験:一般教養(国語・英語・適性(空間把握))・面接 一般入学試験:一般教養(国語・英語)・適性(ペーパークラフト実技)・面接
◆試験日程 推薦二次:平成25年11月9日(土) 出願期間:平成25年10月21日(月)~平成25年11月5日(火) 必着
一般二次:平成25年11月16日(土) 出願期間:平成25年10月28日(月)~平成25年11月11日(月) 必着
義肢装具学科では随時、学校見学および義肢装具製作施設見学ツアーを行っています。大切なあなたの進路決定のために、ぜひご参加ください!ご連絡お待ちしています!
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">平成26年度 推薦二次・一般二次 入学試験 出願期間のご案内
" target="_blank">平成26年度 推薦二次・一般二次 入学試験 出願期間のご案内当日ご都合がつかない場合は、 お気軽に学校見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。
なお、学校見学は、聴能・補聴 ご希望にあわせて対応いたしますし、 今年度は夜間開催も予定しております。 詳しくはコチラをご覧ください。
 " target="_blank">10/26(土)聴能・補聴オープンキャンパス行ないます!
" target="_blank">10/26(土)聴能・補聴オープンキャンパス行ないます! 義肢装具の歴史から、義肢装具士が臨床の現場でどのように働いているか、義肢装具士に必要な知識などを分かり易くご講義して頂きました。
義肢装具の歴史から、義肢装具士が臨床の現場でどのように働いているか、義肢装具士に必要な知識などを分かり易くご講義して頂きました。 足部に問題を抱える患者様に対し、足底圧を確認するフットプリントの採り方を教えていただきました。
足部に問題を抱える患者様に対し、足底圧を確認するフットプリントの採り方を教えていただきました。 実際にフットプリントを体験している様子です。
実際にフットプリントを体験している様子です。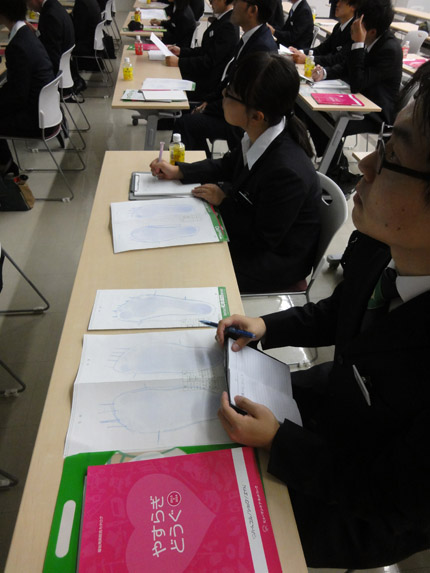 フットプリントは足に起きている問題を定性的に評価することができます。
フットプリントは足に起きている問題を定性的に評価することができます。 フットプリントの評価方法を詳しく教えて頂き、自分の足を診断しました。
フットプリントの評価方法を詳しく教えて頂き、自分の足を診断しました。 様々な種類の車椅子を紹介して頂きました。
車椅子によってデザインも操作方法も違うことを体験することができました。
様々な種類の車椅子を紹介して頂きました。
車椅子によってデザインも操作方法も違うことを体験することができました。 次は工場内の見学です。モデル修正の部署では各疾患、様々なモデルを修正している現場を見学しました。
次は工場内の見学です。モデル修正の部署では各疾患、様々なモデルを修正している現場を見学しました。 体幹装具をCAD/CAMシステムでモデルを修正している様子です。
CAD/CAMシステムを用いることで、少しでも早く、一定の品質で製品を製作することができるそうです。
*Computer-Aided-Design / Computer Aided Manufactureing
体幹装具をCAD/CAMシステムでモデルを修正している様子です。
CAD/CAMシステムを用いることで、少しでも早く、一定の品質で製品を製作することができるそうです。
*Computer-Aided-Design / Computer Aided Manufactureing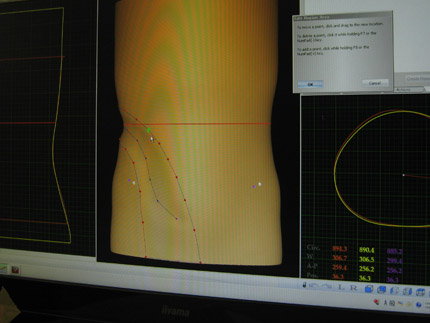 パソコン上でのモデルです。これもまた、手作業であるため、深い知識と経験が必要な作業です。
パソコン上でのモデルです。これもまた、手作業であるため、深い知識と経験が必要な作業です。 シーティングを専門にしている部署です。患者様一人ひとりの体に合ったシートを製作しています。車いすのシートだけでなくベットのシートも製作しています。
シーティングを専門にしている部署です。患者様一人ひとりの体に合ったシートを製作しています。車いすのシートだけでなくベットのシートも製作しています。 最後に社内の資料室です。昔の義肢や装具が展示されています。
昔はクジラのひげが装具の材料に使われていたそうです。
最後に社内の資料室です。昔の義肢や装具が展示されています。
昔はクジラのひげが装具の材料に使われていたそうです。
1年生の皆さん、半年間、義肢装具の勉強をしてきたからこそ製品が製作されている様子や義肢装具士の業務を、より身近な視点で見ることができたのではないでしょうか。 今回の見学で感じたことをしっかり持ち帰り、後期も有意義に過ごしてくださいね! 最後に、お忙しいところ見学をご担当頂きました佐口先生ありがとうございました。
本校が行っている『義肢装具製作施設見学ツアー』では、今回1年生が見学した㈱松本義肢製作所へご案内し、同じように社内をご覧頂くことができます。 義肢装具士の仕事をもっと知りたい方、興味を持った方、義肢装具士への進路を検討中の方は是非ご参加ください!
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">1年生 松本義肢製作所へ会社見学に行ってきました。
" target="_blank">1年生 松本義肢製作所へ会社見学に行ってきました。平成26年度 義肢装具学科 入学試験についてご案内します。 推薦一次・一般一次試験の出願を下記の通り受付けます。 受験希望の方はご確認の上、出願手続をお願いします。
◆試験科目 推薦入学試験:一般教養(国語・英語・適性(空間把握))・面接 一般入学試験:一般教養(国語・英語)・適性(ペーパークラフト実技)・面接
◆試験日程 推薦一次:平成25年10月5日(土) 出願期間:平成25年10月1日(火)~平成25年10月3日(木) 必着
一般一次:平成25年10月12日(土) 出願期間:平成25年10月1日(火)~平成25年10月10日(木) 必着
義肢装具学科では随時、学校見学および義肢装具製作施設見学ツアーを行っています。大切なあなたの進路決定のために、ぜひご参加ください!ご連絡お待ちしています!
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">平成26年度 推薦一次・一般一次入学試験 出願期間のご案内
" target="_blank">平成26年度 推薦一次・一般一次入学試験 出願期間のご案内平成26年度 義肢装具学科 入学試験についてご案内します。
◆試験科目 推薦入学試験:一般教養(国語・英語・適性(空間把握))・面接 一般入学試験:一般教養(国語・英語)・適性(ペーパークラフト実技)・面接
◆試験日程 推薦一次:平成25年10月5日(土) 出願期間:平成25年10月1日(火)~平成25年10月3日(木) 必着
一般一次:平成25年10月12日(土) 出願期間:平成25年10月1日(火)~平成25年10月10日(木) 必着
推薦二次:平成25年11月9日(土) 出願期間:平成25年10月21日(月)~平成25年11月5日(火) 必着
一般二次:平成25年11月16日(土) 出願期間:平成25年10月28日(月)~平成25年11月11日(月) 必着
一般三次:平成25年12月7日(土) 出願期間:平成25年11月18日(月)~平成25年12月2日(月) 必着
一般四次:平成26年1月18日(土) 出願期間:平成25年12月30日(月)~平成26年1月14日(火) 必着
一般五次:平成26年2月15日(土) 出願期間:平成26年1月27日(月)~平成26年2月10日(月) 必着
一般六次:平成26年3月15日(土) 出願期間:平成26年3月1日(土)~平成26年3月13日(木) 必着
義肢装具学科では『義肢装具士』への進路を検討中の方への情報提供として、学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています。 義肢装具士をもっと知りたい!と興味をもった方はぜひご参加ください!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">平成26年度 義肢装具学科 入学試験のご案内
" target="_blank">平成26年度 義肢装具学科 入学試験のご案内 " target="_blank">学校説明・学校見学会のお知らせ(夜間もあります!)
" target="_blank">学校説明・学校見学会のお知らせ(夜間もあります!)当日ご都合がつかない場合は、 お気軽に学校見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。 (学校見学は、聴能・補聴 ご希望にあわせて対応いたします。)
 " target="_blank">9月14日(土)午後はオープンキャンパスです!
" target="_blank">9月14日(土)午後はオープンキャンパスです!義肢装具学科では『義肢装具士』への進路を検討中の方への情報提供としてオープンキャンパス(*詳細リンク)に加えて、個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています。 義肢装具士をもっと知りたい!と興味をもった方はぜひご参加ください!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具製作施設見学ツアーのご案内!
" target="_blank">義肢装具製作施設見学ツアーのご案内!参加者(保護者)の声 今回で3回目の参加ですが、学科説明が分かり易く、知りたい情報がまとまっており、とても参考になりました。 (保護者)
 11:15(休憩時間)
この時間は在学生とリラックスしてお話していただけます。
入学して感じたことなどを、在校生から気軽に聞くことができます。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
11:15(休憩時間)
この時間は在学生とリラックスしてお話していただけます。
入学して感じたことなどを、在校生から気軽に聞くことができます。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 11:30(学生企画)
今回は臨床実習から戻ってきたばかりの3年生の学生さんに学校生活の様子をプレゼンテーションしてもらいました。
臨床実習へ行って学んだことや悩んだことなどを交え、国家試験対策や卒業研究など、3年生ならではのお話が盛りだくさんでした。
11:30(学生企画)
今回は臨床実習から戻ってきたばかりの3年生の学生さんに学校生活の様子をプレゼンテーションしてもらいました。
臨床実習へ行って学んだことや悩んだことなどを交え、国家試験対策や卒業研究など、3年生ならではのお話が盛りだくさんでした。 12:00(昼食)
学生と一緒に昼食を食べながら、お話をしていただきました。
入学前の話や学校生活について何でも聞くことができます。
学校の雰囲気を少しでも感じていただけたのではないでしょうか。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
12:00(昼食)
学生と一緒に昼食を食べながら、お話をしていただきました。
入学前の話や学校生活について何でも聞くことができます。
学校の雰囲気を少しでも感じていただけたのではないでしょうか。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。参加者(保護者)の声 目標達成のために生徒さん同志が助け合っているというお話を聞き、団結力の強さを感じました。 (保護者)
 12:45(体験授業)
午後からは体験授業です。
専門用語を用い、普段学生が受けている授業を体験していただきました。学校に入ってどんな勉強が待っているのか、ここで解っていただけると思います。
12:45(体験授業)
午後からは体験授業です。
専門用語を用い、普段学生が受けている授業を体験していただきました。学校に入ってどんな勉強が待っているのか、ここで解っていただけると思います。参加者(保護者)の声 実際の授業を受けることが出来てよかった。 (高3女子)
 大腿義足ユーザーに、義足の装着方法をデモンストレーションをしていただきました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
大腿義足ユーザーに、義足の装着方法をデモンストレーションをしていただきました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。 今回は膝より上部の切断をされた方の歩行観察を行いました。
電子制御による膝継手を取り付けた義足を装着し、どのように歩くことが出来るのか、観察してもらいました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
今回は膝より上部の切断をされた方の歩行観察を行いました。
電子制御による膝継手を取り付けた義足を装着し、どのように歩くことが出来るのか、観察してもらいました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。 専任教員が、アライメント調整を行います。
体験授業の内容を踏まえ、調整によって歩容が変化する様子を見ていただきます。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
専任教員が、アライメント調整を行います。
体験授業の内容を踏まえ、調整によって歩容が変化する様子を見ていただきます。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。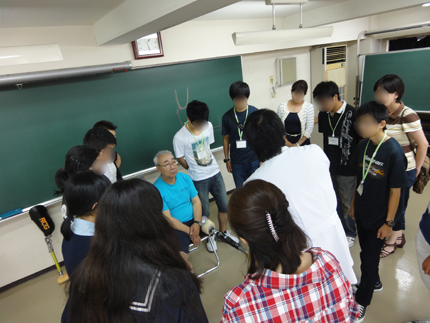 最後に義足を使用している立場から色んなお話をしていただき、参加者からの疑問にも分かり易くお答えいただきました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。
最後に義足を使用している立場から色んなお話をしていただき、参加者からの疑問にも分かり易くお答えいただきました。
※プライバシー保護のため、画像を一部加工しています。参加者(保護者)の声 とても勉強になりました。入学してもっと勉強したいと思いました。 (高1男子)
参加された皆さん、暑い中お越しいただき、ありがとうございました。 義肢装具学科では『義肢装具士』への進路を検討中の方への情報提供として個別での学校見学、義肢装具製作施設見学ツアーを実施しています。義肢装具士をもっと知りたい!と興味をもった方、お休みが合わずオープンキャンパスに参加できなかった方など、ぜひご参加ください!本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">第3回オープンキャンパスの様子をご紹介します!
" target="_blank">第3回オープンキャンパスの様子をご紹介します!
 " target="_blank">8月17日(土)開催 オープンキャンパスのご案内!
" target="_blank">8月17日(土)開催 オープンキャンパスのご案内! 10:30(学科説明)
専任教員より義肢装具学科についての紹介、最新の入試情報などの説明がありました。
10:30(学科説明)
専任教員より義肢装具学科についての紹介、最新の入試情報などの説明がありました。 11:30(学生企画)
在校生から普段の学校生活の様子をプレゼンしてもらいました。専任教員から実際の学生生活についてインタビューを受けている様子です。
11:30(学生企画)
在校生から普段の学校生活の様子をプレゼンしてもらいました。専任教員から実際の学生生活についてインタビューを受けている様子です。 12:00(昼食)
在校生と一緒にサンドイッチを食べながら学校生活について、学校の授業の様子、入学して楽しいことや大変なことなど学生の視点から分かり易くお伝えします。
12:00(昼食)
在校生と一緒にサンドイッチを食べながら学校生活について、学校の授業の様子、入学して楽しいことや大変なことなど学生の視点から分かり易くお伝えします。 2年生からは専門知識も増え、勉強していく楽しさをお伝えします!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
2年生からは専門知識も増え、勉強していく楽しさをお伝えします!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 入学して4ヶ月の1年生からは義肢装具を一から学ぶ難しさや、楽しさをフレッシュにお伝えします!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
入学して4ヶ月の1年生からは義肢装具を一から学ぶ難しさや、楽しさをフレッシュにお伝えします!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。参加者(保護者)の声 在校生の方と色々話し聞くことができて良かった。気軽に話しかけてくれたので楽しかった。自分もこんなコミュニケーションがとれるようになりたいと思った。 (高2女子)
在校生の方々の会話はとてもためになりました。オープンキャンパスに参加して良かったと思います。 (社会人)
学生さんのリアルな話が聞けてとても参考になりました。 (社会人)
2回目の参加でしたが、今回も学生さんが熱心にお話して下さり、とても雰囲気の良い学校だなと実感しました。 (保護者)
 12:45(体験授業)
いよいよ下腿義足ユーザーの歩行観察です!
義足のアライメントの違いによる歩行の異常を観察しました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
12:45(体験授業)
いよいよ下腿義足ユーザーの歩行観察です!
義足のアライメントの違いによる歩行の異常を観察しました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 また、義肢装具士が現場で行っているアライメントの調整も見ていただきました。専任教員の素早い調整作業に参加者も興味津々でした。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
また、義肢装具士が現場で行っているアライメントの調整も見ていただきました。専任教員の素早い調整作業に参加者も興味津々でした。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 次に、体験用模擬義足を装着し、義足の使用感を体験していただきました。足関節が自由に動かない状態での歩行、立位バランスをとる難しさを実感していただけたでしょうか?
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
次に、体験用模擬義足を装着し、義足の使用感を体験していただきました。足関節が自由に動かない状態での歩行、立位バランスをとる難しさを実感していただけたでしょうか?
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。参加者(保護者)の声 すごく為になりました。入学したいと思いました。 (高2女子)
アライメントのわずかな調整で歩行に大きく影響することがわかりました。 (高3男子)
専任教員の姿勢、積極性が素晴らしかった。 (社会人)
親切丁寧な対応ありがとうございました。 (社会人)
来てよかったです。モノづくりだけではなく、奥深い素敵なお仕事であることがわかりました。ありがとうございました。 (保護者)
 次回のオープンキャンパスは8月17日(土)です!
体験授業では、先生から大腿義足についての講義の後、実際に大腿義足のモデルさんをお招きして、大腿義足の歩行観察を行います。義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています!
(義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ)
(第1回オープンキャンパスの様子はコチラ)
(昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)
次回のオープンキャンパスは8月17日(土)です!
体験授業では、先生から大腿義足についての講義の後、実際に大腿義足のモデルさんをお招きして、大腿義足の歩行観察を行います。義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています!
(義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ)
(第1回オープンキャンパスの様子はコチラ)
(昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">第2回オープンキャンパスの様子をご紹介します!
" target="_blank">第2回オープンキャンパスの様子をご紹介します!
 " target="_blank">7月20日(土)開催 オープンキャンパスのご案内!
" target="_blank">7月20日(土)開催 オープンキャンパスのご案内! 展示ブースでは義肢装具学科もしっかりPRをしてきました!
展示ブースでは義肢装具学科もしっかりPRをしてきました! 最後に、本校の先輩である砂田大会長と学生全員で記念撮影です。
砂田先輩ありがとうございました。
最後に、本校の先輩である砂田大会長と学生全員で記念撮影です。
砂田先輩ありがとうございました。2日間とも好天に恵まれ、講演内容、天候共にあつい学会となりました。最先端の研究や、疾患に関する専門的な講演など、盛りだくさんな内容を聴講して、学生は改めて義肢装具の奥深さを実感したようです。 ぜひ、名古屋に戻ってもう一度しっかりまとめ、今後の学業にフィードバックしてください!" target="_blank">第20回日本義肢装具士協会学術大会に参加しました!
 今日も猛暑の名古屋、モリモリ食べて、午後からもお掃除頑張ります!
今日も猛暑の名古屋、モリモリ食べて、午後からもお掃除頑張ります! 1・2年生は今週末に沖縄で行われる第20回義肢装具士協会学術大会に参加します!全国の義肢装具士が一同に集まり、研究発表や様々な講演が行われます。たくさん講演を聞いて、義肢装具の見識を広めてくださいね!" target="_blank">いよいよ夏休み!恒例の大掃除が行われました!
1・2年生は今週末に沖縄で行われる第20回義肢装具士協会学術大会に参加します!全国の義肢装具士が一同に集まり、研究発表や様々な講演が行われます。たくさん講演を聞いて、義肢装具の見識を広めてくださいね!" target="_blank">いよいよ夏休み!恒例の大掃除が行われました! 10:00
受付では学生スタッフがお出迎え。
オープンキャンパスの資料をお渡しします。
10:00
受付では学生スタッフがお出迎え。
オープンキャンパスの資料をお渡しします。 10:30
まず、最初に専任教員による学科説明があります。
ここでは、義肢装具士の仕事について、義肢装具士になるまでの流れや、学科のカリキュラム内容について説明がありました。
10:30
まず、最初に専任教員による学科説明があります。
ここでは、義肢装具士の仕事について、義肢装具士になるまでの流れや、学科のカリキュラム内容について説明がありました。 11:15
休憩時間は学生スタッフと飲み物やお菓子を食べながら、学生スタッフが積極的に参加者とお話をし、緊張した空気をほぐしてくれます。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
11:15
休憩時間は学生スタッフと飲み物やお菓子を食べながら、学生スタッフが積極的に参加者とお話をし、緊張した空気をほぐしてくれます。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。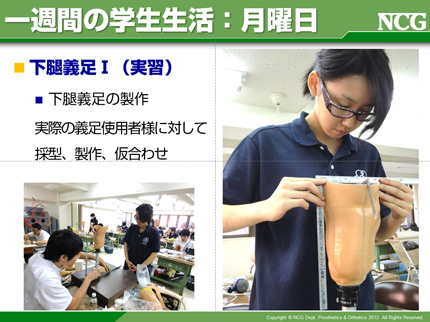 11:30
ここからは在校生による学生企画。1週間の学生生活についてのプレゼンテーションです。
在校生がどんな学生生活を送っているのか、登校から下校までの過ごし方や、授業の難しさ、楽しさを盛りだくさんにお話ししてくれました。
11:30
ここからは在校生による学生企画。1週間の学生生活についてのプレゼンテーションです。
在校生がどんな学生生活を送っているのか、登校から下校までの過ごし方や、授業の難しさ、楽しさを盛りだくさんにお話ししてくれました。 12:00
昼食は学生スタッフと一緒にサンドイッチを食べながら、入学したきっかけや、学生生活などをお話していました。学生スタッフも入学前にオープンキャンパスに参加していたこともあり、楽しく会話も弾んでいました!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
12:00
昼食は学生スタッフと一緒にサンドイッチを食べながら、入学したきっかけや、学生生活などをお話していました。学生スタッフも入学前にオープンキャンパスに参加していたこともあり、楽しく会話も弾んでいました!
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。参加者(保護者)の声 在校生の方に入試の話が聞くことができてよかったです。 (社会人)
在学している生徒さんのお話を聞けて参考になりました。 (社会人)
学生さんが熱心にお話してくださって、皆さんが頑張っている良い学校だということがわかりました。ありがとうございました。 (保護者)
生徒の方がとても明るく、とても気持ちよく過ごせました。素敵でした。 (保護者)
 12:45
午後からは体験授業です。
まずは、日ごろ実際に学生が受けている内容の講義を受講します。内容は「脳卒中片麻痺」を例に、短下肢装具の目的や製作工程について説明がされます。
患者さまの病気や症状について詳しく理解することが、義肢装具を製作する際にとても大切です。
12:45
午後からは体験授業です。
まずは、日ごろ実際に学生が受けている内容の講義を受講します。内容は「脳卒中片麻痺」を例に、短下肢装具の目的や製作工程について説明がされます。
患者さまの病気や症状について詳しく理解することが、義肢装具を製作する際にとても大切です。 専任教員による採型のデモンストレーションです。
講義の内容を踏まえ、短下肢装具の採型方法を見ていただきます。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
専任教員による採型のデモンストレーションです。
講義の内容を踏まえ、短下肢装具の採型方法を見ていただきます。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 参加者の皆さん一人一人に採型を体験していただきました!
実際の患者さまに使用するギプス包帯を使い、下腿部の石膏モデルで採型をします。学生スタッフが一人一人をサポートし、採型のポイントをアドバイスしました。
参加者の皆さん一人一人に採型を体験していただきました!
実際の患者さまに使用するギプス包帯を使い、下腿部の石膏モデルで採型をします。学生スタッフが一人一人をサポートし、採型のポイントをアドバイスしました。 簡単そうに見えて、やってみると意外と難しいのですが、参加者も一生懸命チャレンジしてくれました!
参加者の皆さん、初めて触るギプス包帯の感覚はどうでしたか?
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
簡単そうに見えて、やってみると意外と難しいのですが、参加者も一生懸命チャレンジしてくれました!
参加者の皆さん、初めて触るギプス包帯の感覚はどうでしたか?
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。 最後に、下腿義足の採型デモンストレーションを見ていただきました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。
最後に、下腿義足の採型デモンストレーションを見ていただきました。
※プライバシー保護のため、一部画像を加工しています。参加者(保護者)の声 体験実習は難しかったけど、楽しかったです。 (高3女子)
義肢装具についての体験ができてよかったです。 (高3男子)
体験授業は難しくて大変な作業だと思ったけど、とてもわかりやすく教えていただいてとても楽しく体験できました。 (高3男子)
担当の学生さんが話しやすく、わかりやすかったです。ありがとうございました。 (高3男子)
学生の方が丁寧に対応してくださり、また学校生活についてもいろいろとお話を聞くことができて大変満足しました。 (社会人)
装具製作における実習体験をさせてもらってモノづくりの楽しさがありました。次はうまく作れるようにという思いがでてきました。 (社会人)
学科や装具のことがよくわかりました。採型では石膏を切るのが難しかったです。 (社会人)
学生の方の素早い行動、学校についての説明が気持ちよかったです。義肢装具士の仕事、この学校の様子がわかりました。ありがとうございました。 (保護者)
今回は短下肢装具の採型を体験して頂きましたが、次回7月20日に行われるオープンキャンパスでは、下腿義足ユーザーのフィッティングと歩行観察を行います!また違った視点から義肢装具士の仕事をのぞいてみてくださいね!
7月20日の第2回オープンキャンパスの体験授業では、先生から下腿義足についての講義の後、実際に下腿義足の歩行観察を行います。義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">第1回オープンキャンパスの様子をご紹介します!
" target="_blank">第1回オープンキャンパスの様子をご紹介します! 踵の高さと形状は、靴の機能と見た目の美しさにとても重要な個所です。最後まで気を抜かずに!
踵の高さと形状は、靴の機能と見た目の美しさにとても重要な個所です。最後まで気を抜かずに! 仕上げた靴をピカピカに磨いている様子。
靴の製作だけでなく、手入れ方法もしっかり学習します!
仕上げた靴をピカピカに磨いている様子。
靴の製作だけでなく、手入れ方法もしっかり学習します! 全員完成し、いよいよ適合評価です!
全員完成し、いよいよ適合評価です! 靴を装着し、一つ一つチェックポイントを確認していきます。
靴を装着し、一つ一つチェックポイントを確認していきます。 痛いところはないですか?左右のデザインは揃っていますか?
痛いところはないですか?左右のデザインは揃っていますか? もちろん歩いてみた時の履き心地や姿勢も大切なチェックポイント!
一人一人、クラスメイトの前で歩いて観察します。
もちろん歩いてみた時の履き心地や姿勢も大切なチェックポイント!
一人一人、クラスメイトの前で歩いて観察します。 2年生はこの靴を履いて、8月下旬からの臨床実習に臨みます!
長い時間履くことで、適合の良し悪しがちゃんとわかります。
装着者の気持ちを、身を以て知ることが沢山あるはずです。
2年生はこの靴を履いて、8月下旬からの臨床実習に臨みます!
長い時間履くことで、適合の良し悪しがちゃんとわかります。
装着者の気持ちを、身を以て知ることが沢山あるはずです。自分が製作したものをしっかり自己分析して下さいね!" target="_blank">2年生 ついに靴型装具が完成しました!
 実践を交えて護身術を教えていただきました。
実践を交えて護身術を教えていただきました。備えあれば憂いなし!自分の身を守る術をしっかり覚えていてくださいね! 中村警察署の警察官の方、貴重なお話ありがとうございました。" target="_blank">中村署の警察官による防犯講和が行なわれました。
 そして学生たちの適合が始まりました。
まずはソフトインサートを装着していただきます。
学生たちは自分の修正が間違っていなかったかどうか、緊張の一瞬です!切断端が違和感なくソケット内に収まると良いですが・・・。
そして学生たちの適合が始まりました。
まずはソフトインサートを装着していただきます。
学生たちは自分の修正が間違っていなかったかどうか、緊張の一瞬です!切断端が違和感なくソケット内に収まると良いですが・・・。 次にソケットの適合を確認し、スタティックアライメントを調整します。ベンチアライメントで組み立てたソケット角度から修正が必要な場合は、様々な現象となって立ち姿に現れます。
次にソケットの適合を確認し、スタティックアライメントを調整します。ベンチアライメントで組み立てたソケット角度から修正が必要な場合は、様々な現象となって立ち姿に現れます。 現れた現象とモデルさんの言葉をヒントに原因を考えます。どのように対処するべきか、学生たちが各自で答えを導き出します。
現れた現象とモデルさんの言葉をヒントに原因を考えます。どのように対処するべきか、学生たちが各自で答えを導き出します。 ソケット適合とスタティックアライメントが調整できたら、次はダイナミックアライメントを調整します。試歩行していただくと義足が外側に傾いたり、膝が前に押し出されたりします。これらの問題点を考えて、1つ1つ答えを導き出し対処していきます。
ソケット適合とスタティックアライメントが調整できたら、次はダイナミックアライメントを調整します。試歩行していただくと義足が外側に傾いたり、膝が前に押し出されたりします。これらの問題点を考えて、1つ1つ答えを導き出し対処していきます。 完全に歩行が安定するまで何度も何度も調整を繰り返します。しかし、歩けば歩くほどモデルさんは疲れてしまします。いかにモデルさんに負担をかけず、少ない回数で対処できるか、だんだん学生たちの目線にもプロ意識が芽生えてきたようです。
完全に歩行が安定するまで何度も何度も調整を繰り返します。しかし、歩けば歩くほどモデルさんは疲れてしまします。いかにモデルさんに負担をかけず、少ない回数で対処できるか、だんだん学生たちの目線にもプロ意識が芽生えてきたようです。 この下腿義足の実習を通して、義足ユーザーと接する機会を持つことで、より深く義肢装具の世界の奥深さと面白さを学生たちは学んでいきます。
この下腿義足の実習を通して、義足ユーザーと接する機会を持つことで、より深く義肢装具の世界の奥深さと面白さを学生たちは学んでいきます。次回は、ダイナミックアライメントを調整した下腿義足にフォームカバーと呼ばれる外装を削り出し、納品できる状態に仕上げる講義を行います。そして特別講師として長年この作業をしてこられたスペシャリストに来校いただきます。学生たちがスペシャリストの技術をどこまで吸収できるか楽しみです!
7月20日の第2回オープンキャンパスの体験授業では、先生から下腿義足についての講義の後、実際に下腿義足の歩行観察を行います。義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">2年生 下腿義足の適合評価が行われました。
" target="_blank">2年生 下腿義足の適合評価が行われました。 足関節の継手部分の加工は、とても精密に行います。
足関節の継手部分の加工は、とても精密に行います。
 次に、支柱を足のトレースにあわせて曲げ加工していきます。
次に、支柱を足のトレースにあわせて曲げ加工していきます。
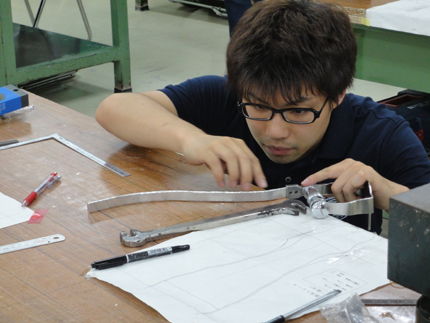 曲げ加工によって支柱に捻じれが生じていないか確認をします。
曲げ加工によって支柱に捻じれが生じていないか確認をします。
 トレースは患者様の大切な情報です。設定どおり、正確に合わせます。
トレースは患者様の大切な情報です。設定どおり、正確に合わせます。
 もう少し曲げて微調整!
もう少し曲げて微調整!
 金属の曲げ加工は手が慣れるまで、なかなか難しい作業です。
一つずつ、丁寧に頑張りましょう!
金属の曲げ加工は手が慣れるまで、なかなか難しい作業です。
一つずつ、丁寧に頑張りましょう!
2013年オープンキャンパス第2回が7月20日(土)に開催されます!体験授業では、先生から下腿義足のアライメントについての講義の後、実際に下腿義足ユーザーさんの歩行観察を行います。義肢装具学科で実際に行なわれているホントの授業を体験するチャンスです!この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみに待っています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">1年生 両側金属支柱付短下肢装具の製作実習が始まりました。
" target="_blank">1年生 両側金属支柱付短下肢装具の製作実習が始まりました。 吊り込むための準備をします。
吊り込むための準備をします。
 いよいよ、吊り込みの本番です!1足吊りこみが終わるまで作業を止めることができないため、ここは集中力が必要です。
いよいよ、吊り込みの本番です!1足吊りこみが終わるまで作業を止めることができないため、ここは集中力が必要です。
 シワのできないように、クギを1本1本、丁寧に打ち込んでいきます。
シワのできないように、クギを1本1本、丁寧に打ち込んでいきます。
 いつも先生のチェックは厳しいですが、学生たちはここから良い靴づくりのマインドを学びます。
いつも先生のチェックは厳しいですが、学生たちはここから良い靴づくりのマインドを学びます。
 吊りこみ終わったもの!
吊りこみ終わったもの!
次は靴底の加工をしていよいよ完成です!! 試着する日が待ち遠しいですね!" target="_blank">2年生 靴型装具の吊り込みが行われました。
 チェックソケットという透明なソケットで、適合状態を確認します。局所的に皮膚の色が変わっていないか、無駄な空間は無いか、しっかり観察ていきます。
チェックソケットという透明なソケットで、適合状態を確認します。局所的に皮膚の色が変わっていないか、無駄な空間は無いか、しっかり観察ていきます。 大腿義足ソケットは、断端全体を均一に加圧(コンプレッション)できていれば、皮膚は全体的に少し白みがかった色になります。このソケットならば切断端を快適に収納し、しっかりと義足を懸垂させることができそうですね。
大腿義足ソケットは、断端全体を均一に加圧(コンプレッション)できていれば、皮膚は全体的に少し白みがかった色になります。このソケットならば切断端を快適に収納し、しっかりと義足を懸垂させることができそうですね。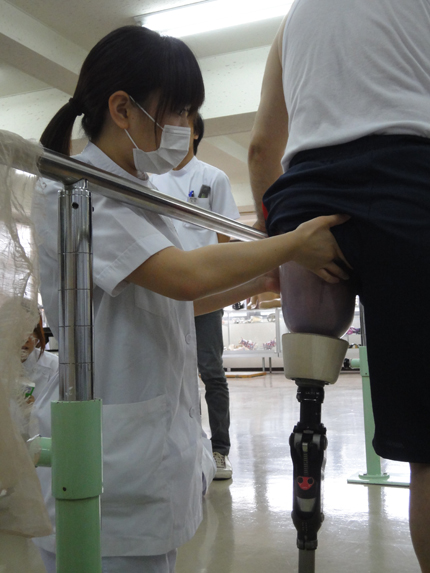 今回製作した四辺形ソケットは、“坐骨”と呼ばれる骨で体重を支えます。そのため、ソケット上縁で確実に支持されていることが大切です。
今回製作した四辺形ソケットは、“坐骨”と呼ばれる骨で体重を支えます。そのため、ソケット上縁で確実に支持されていることが大切です。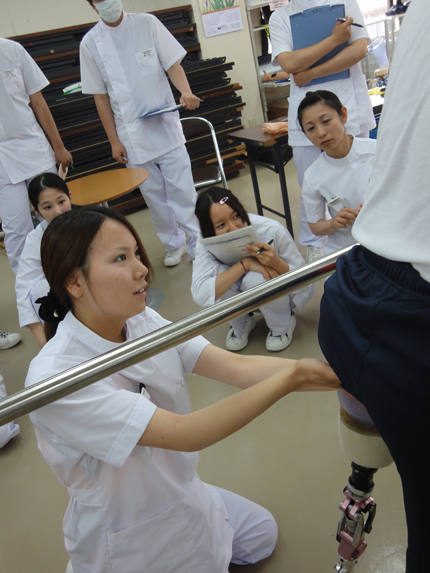 それぞれ坐骨の位置を確認しています。坐骨とソケットとの間に指が挟まって痛くなれば、しっかりと体重支持されていることの証です。
それぞれ坐骨の位置を確認しています。坐骨とソケットとの間に指が挟まって痛くなれば、しっかりと体重支持されていることの証です。 ソケットが適合し、スタティックアライメントに問題がなければ、次はダイナミックアライメントに移行します。様々なパターンの異常歩行の原因を観察し、的確に調整していきます。
ソケットが適合し、スタティックアライメントに問題がなければ、次はダイナミックアライメントに移行します。様々なパターンの異常歩行の原因を観察し、的確に調整していきます。これで前期の大腿義足の実習が終了しました。後期にはさらに難易度の高いソケットデザインとなる坐骨収納型ソケットの実習が始まります!" target="_blank">3年生 大腿義足の適合評価が行なわれました。
 アライメントラインが床面に垂直立ち上がるように調整していきます。
アライメントラインが床面に垂直立ち上がるように調整していきます。 ネジの締め具合でソケットの角度や足部の位置が大きく変わってしまうため、緻密に調整していきます。
ネジの締め具合でソケットの角度や足部の位置が大きく変わってしまうため、緻密に調整していきます。 ベンチアライメントが組み立てられたら先生にチェックをしてもらいます。学生はこの瞬間がドキドキです。
ベンチアライメントが組み立てられたら先生にチェックをしてもらいます。学生はこの瞬間がドキドキです。 ベンチアライメントを組み立てられたらいよいよモデルさんに義足を装着してもらいます。
ベンチアライメントを組み立てられたらいよいよモデルさんに義足を装着してもらいます。次回は、実際に下腿切断のモデルさんに義足を装着してもらい、適合評価を行います。これまでの工程が正確に行われていれば、うまく適合するはずですが…どうなるか楽しみですね!" target="_blank">2年生 下腿義足のベンチアライメント組み立てが行われました。

 " target="_blank">6月22日(土)開催 オープンキャンパスのご案内!
" target="_blank">6月22日(土)開催 オープンキャンパスのご案内! " target="_blank">義肢装具製作施設見学ツアーのご案内。
" target="_blank">義肢装具製作施設見学ツアーのご案内。 アライメントの全ての基準となるラインが正しく引けているか、先生が厳しくミリ単位でチェックします。
アライメントの全ての基準となるラインが正しく引けているか、先生が厳しくミリ単位でチェックします。
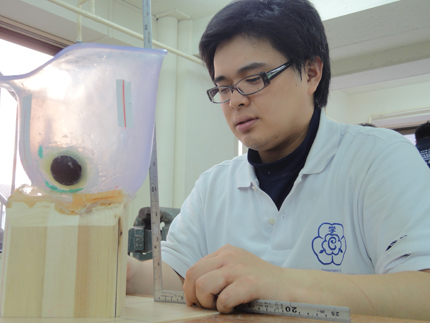 ソケットが出来上がった学生は、このソケットを木製のブロックに埋め込みます。
ソケットが出来上がった学生は、このソケットを木製のブロックに埋め込みます。
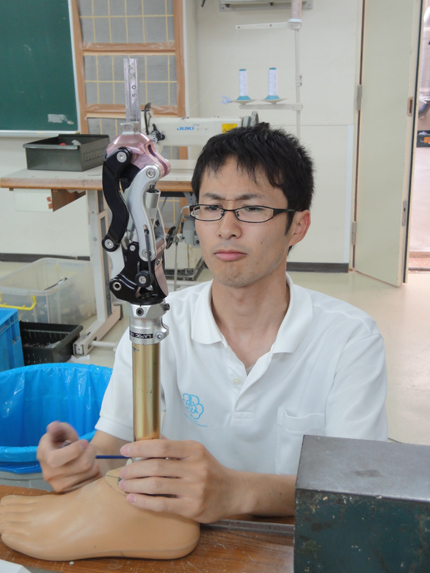 大腿義足のアライメントは、義足足部・膝継手・ソケットの相対的位置関係です。まずは足部と膝継手が正しい位置関係になるようしっかりと調整します。
大腿義足のアライメントは、義足足部・膝継手・ソケットの相対的位置関係です。まずは足部と膝継手が正しい位置関係になるようしっかりと調整します。
 こっちを緩めて、こっちを締めて・・・。
こっちを緩めて、こっちを締めて・・・。
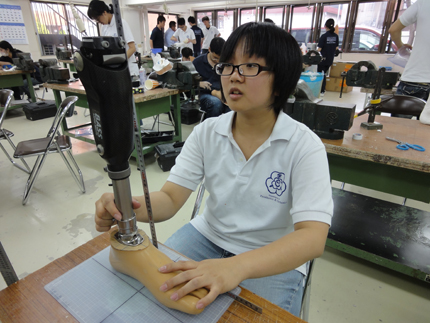 しっかりラインを確認して・・・。
しっかりラインを確認して・・・。
 まだ少し基準線からずれていたようですね。
まだ少し基準線からずれていたようですね。
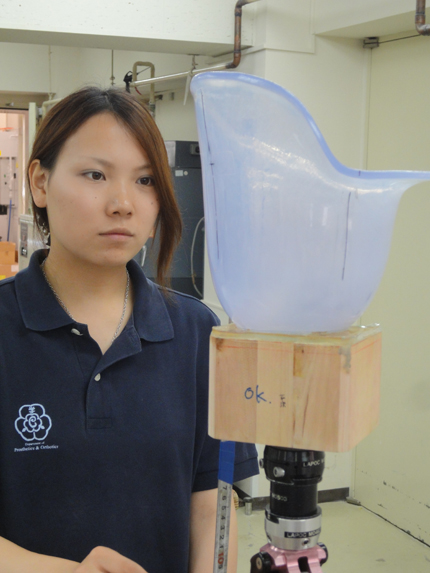 義足足部、膝継手の上にソケットが組み上がりました。義足足部、膝継手、ソケットの3つの部品をそれぞれ正しい位置に調整します。
義足足部、膝継手の上にソケットが組み上がりました。義足足部、膝継手、ソケットの3つの部品をそれぞれ正しい位置に調整します。
 難しい顔で調整していましたが、もう少しで完成ですね!
次回はいよいよ大腿義足の仮合わせの様子を紹介します!
難しい顔で調整していましたが、もう少しで完成ですね!
次回はいよいよ大腿義足の仮合わせの様子を紹介します!
平成25年度の義肢装具学科のオープンキャンパスは、6月22(土)、7月20日(土)、8月18日(土)に開催されます。 初回となります6月22日(土)は、今回紹介した下腿義足の採型体験ができますよ!!7・8月は夏休み中の開催になりますので、最終的な進路を決定するための良い情報が得られると思います。ご家族の方や友人と一緒でも構いませんので、この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみにまっています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">3年生 大腿義足のベンチアライメントの実習が行われました。
" target="_blank">3年生 大腿義足のベンチアライメントの実習が行われました。 会社に到着し早速、社内をグループに分かれて案内していただきました。
川村義肢株式会社は製販分離で、製品は分業制で作られます。
それぞれのプロフェッショナルが集まって義肢装具を製作している様子に、学生たちは圧倒されていました。
会社に到着し早速、社内をグループに分かれて案内していただきました。
川村義肢株式会社は製販分離で、製品は分業制で作られます。
それぞれのプロフェッショナルが集まって義肢装具を製作している様子に、学生たちは圧倒されていました。
 古くから作られていた義手や義足が展示されているコーナーでの様子です。
古くから作られていた義手や義足が展示されているコーナーでの様子です。
 福祉用具の展示コーナーの様子です。
人工ボディのあまりの精巧さに学生たちは興味津々です。
福祉用具の展示コーナーの様子です。
人工ボディのあまりの精巧さに学生たちは興味津々です。
 パシフィックサプライの岡田さんに車いすについてのお話をお聴きしました。
パシフィックサプライの岡田さんに車いすについてのお話をお聴きしました。
今回は「企業が求める義肢装具士とは?」というタイトルで3名の方にご講義をして頂きました。学内では学ぶことのできない貴重なお話をたくさん聞くことができました。 ご講義をして下さった野田正樹さん、石田晃一さん、岡田裕生さん、ありがとうございました。
さて、この会社見学で学生が感じたことを一部紹介しましょう!!
今回、見学をさせて頂いて義肢装具士について理解を深めると共に、自分がどの分野に興味があるのか見つめ直すよい機会になりました。貴重な時間をありがとうございました。 (1年生 女子学生)
これから基本工作論では「両側金属支柱付短下肢装具」の製作が始まります。今回の見学で感じたことを持ち帰り、新たな視点からモノつくりを学んでいきましょう!!" target="_blank">1年生 川村義肢株式会社へ会社見学に行ってきました。
 うまく位置が決まったようですね。位置が決まったらパーツがずれないように固定します。
うまく位置が決まったようですね。位置が決まったらパーツがずれないように固定します。 もう一度作業の流れをよく確認し、いよいよ樹脂注型が始まります。
もう一度作業の流れをよく確認し、いよいよ樹脂注型が始まります。 積層材と呼ばれる繊維に樹脂を含浸させていきます。余分な樹脂があるとソケットが重くなってしまうため、均一な厚みになるように作業していきます。
積層材と呼ばれる繊維に樹脂を含浸させていきます。余分な樹脂があるとソケットが重くなってしまうため、均一な厚みになるように作業していきます。 うまくソケットができているか、次回が楽しみですね!
うまくソケットができているか、次回が楽しみですね!次回はいよいよ義足を組み上げるベンチアライメント組み立ての工程を紹介します!" target="_blank">2年生 下腿義足ソケットの樹脂注型が行われました。
 スポンジ材をきれいに貼り合わせるために息を止めて手先に神経を集中させます。
スポンジ材をきれいに貼り合わせるために息を止めて手先に神経を集中させます。 もう少しでソフトインサートが完成ですね。モデルさんに満足してもらえるような出来映えになっているでしょうか。
もう少しでソフトインサートが完成ですね。モデルさんに満足してもらえるような出来映えになっているでしょうか。 モノづくりは1つ1つの工程の積み重ねですが大切です。
少しずつ上手になっていきましょう!
モノづくりは1つ1つの工程の積み重ねですが大切です。
少しずつ上手になっていきましょう!次回は切断端を収納し、体重を支える役割をするソケット樹脂注型の工程を紹介します!" target="_blank">2年生 下腿義足のソフトインサート製作が行われました。
 今回、座長を務めるのは2年生です。緊張しながらも、しっかりと司会進行をしてくれました!来年は2年生が発表する立場ですから、貴重な経験になったと思います。
今回、座長を務めるのは2年生です。緊張しながらも、しっかりと司会進行をしてくれました!来年は2年生が発表する立場ですから、貴重な経験になったと思います。 同級生や後輩たちからいろんな意見を聞き、今後の研究をどのように進めていくかを考えます。
同級生や後輩たちからいろんな意見を聞き、今後の研究をどのように進めていくかを考えます。 質疑応答も活発で、後輩たちからも多くの質問が出され、とても有意義な時間となりました。
質疑応答も活発で、後輩たちからも多くの質問が出され、とても有意義な時間となりました。 実際に模擬義手を使って研究内容を分かり易く説明している様子です。
実際に模擬義手を使って研究内容を分かり易く説明している様子です。この報告会が終わると、3年生はそれぞれの臨床実習に向かいます。8月中旬、臨床実習を終えると卒業研究が本格的に進んでいきます。 3年生の皆さん、まずは充実した臨床実習を送ってください。" target="_blank">3年生 卒業研究中間報告会が行なわれました。
 (株)今仙技術研究所は岐阜県各務原市にあります。この東海地域に義足パーツメーカーがあると知って、学生たちはとても親近感を持ったようです。
(株)今仙技術研究所は岐阜県各務原市にあります。この東海地域に義足パーツメーカーがあると知って、学生たちはとても親近感を持ったようです。
大腿義足の実習では、LAPOCの膝継手を使用して義足を組み立てます。今日の講義をしっかり理解して、ベンチアライメントを正確に組み上げられるようにしましょう!
平成25年度の義肢装具学科のオープンキャンパスは、6月22(土)、7月20日(土)、8月18日(土)に開催されます。 初回となります6月22日(土)は、今回紹介した下腿義足の採型体験ができますよ!!7・8月は夏休み中の開催になりますので、最終的な進路を決定するための良い情報が得られると思います。ご家族の方や友人と一緒でも構いませんので、この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみにまっています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">3年生 LAPOC膝継手の特別講義が行われました。
" target="_blank">3年生 LAPOC膝継手の特別講義が行われました。 先生による仮合わせのデモンストレーションです。
実際の患者さまの歩行を想定しながら、装具の不具合をチェックしていきます。
先生による仮合わせのデモンストレーションです。
実際の患者さまの歩行を想定しながら、装具の不具合をチェックしていきます。
 今回はクラスメイトをモデルに、装具を製作します。
今回はクラスメイトをモデルに、装具を製作します。
 いところはないでしょうか?
きつい、緩いところはないでしょうか?
アライメントは適切に設定できているでしょうか?
患者さまの気持ちになって一つ一つ細かくチェックをしていきます。
いところはないでしょうか?
きつい、緩いところはないでしょうか?
アライメントは適切に設定できているでしょうか?
患者さまの気持ちになって一つ一つ細かくチェックをしていきます。
 仮合わせの調整で患者様にお渡しする装具の良し悪しが決まります。
適合のチェックポイントをしっかりおさえて、エビデンスのある装具を完成させましょう!
仮合わせの調整で患者様にお渡しする装具の良し悪しが決まります。
適合のチェックポイントをしっかりおさえて、エビデンスのある装具を完成させましょう!
次回は最終調整に入り、いよいよ完成です!
義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ! 平成25年度の義肢装具学科のオープンキャンパスは、6月22(土)、7月20日(土)、8月18日(土)に開催されます。 初回は日程も近づいた6月、7・8月は夏休み中の開催になりますので、最終的な進路を決定するための良い情報が得られると思います。ご家族の方や友人と一緒でも構いませんので、この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみにまっています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ)

 " target="_blank">1年生 シューホーンブレースの仮合わせが行われました。
" target="_blank">1年生 シューホーンブレースの仮合わせが行われました。参加者(保護者)の声 授業の事、入試の事など知りたかった事を詳しく教えていただけたのでとても参考になりました。 (高3女子)
義肢装具学科ではどんな勉強をするのか、どういう仕事なのか、より理解を深める事ができたので良かったです。説明も丁寧で分かりやすかったです。 (高3男子)
授業について細かい事まで教えていただき、とても参考になりました。 (高3男子)
説明していただいた事がとても分かりやすかったです。娘も入学し、頑張ってくれたらと思います。 (保護者)
義肢装具士という職業がよくわかりました。親切な説明をいただきありがとうございました。娘とよく話し合うことができそうです。 (保護者)
 休憩時間中も在校生から積極的に声をかけ、講義のこと、実習のこと、学生生活について楽しくお話しします。
1年生も2年生もいるので、学年ごとの違いについても詳しく聞けますよ!
休憩時間中も在校生から積極的に声をかけ、講義のこと、実習のこと、学生生活について楽しくお話しします。
1年生も2年生もいるので、学年ごとの違いについても詳しく聞けますよ!
 学生企画の様子
「一週間の学生生活」と題して、起床して自宅を出発するところから、学校到着、授業、昼休み、放課後と一日の流れを紹介し、続いて月曜日から金曜日までの講義内容についても紹介します。リアリティのあるプレゼンに、参加者の方も、保護者の方も興味津々です。
学生企画の様子
「一週間の学生生活」と題して、起床して自宅を出発するところから、学校到着、授業、昼休み、放課後と一日の流れを紹介し、続いて月曜日から金曜日までの講義内容についても紹介します。リアリティのあるプレゼンに、参加者の方も、保護者の方も興味津々です。
 昼食の様子
在校生と一緒に昼食をとりながら、さらに詳しく学校生活についてお話ができます。
※プライバシー保護の為、一部画像を加工しています。
昼食の様子
在校生と一緒に昼食をとりながら、さらに詳しく学校生活についてお話ができます。
※プライバシー保護の為、一部画像を加工しています。
 食事を忘れるほど話が盛り上がる場面もしばしば見られます。実は、参加者のアンケートではこの昼食の時間がとても好評です。
※プライバシー保護の為、一部画像を加工しています。
食事を忘れるほど話が盛り上がる場面もしばしば見られます。実は、参加者のアンケートではこの昼食の時間がとても好評です。
※プライバシー保護の為、一部画像を加工しています。
参加者(保護者)の声 学生の方も先生方も気軽に話しかけて下さり、就職の事や学校生活について詳しくお話を聞く事ができました。 (高3女子)
在校生の方々がとても優しく、積極的に話しかけてくれるところがとても良かったです。 (高3女子)
在校生の方々の話を聞くことができて良かったです。 (社会人26歳男性)
社会人経験者の方のお話が聞けてとても有意義でした。 (社会人30歳男性)
昼食の際に、積極的に話しかけていただいたおかげで、様々なことを気軽に聞くことができ、義肢装具士にとても興味が湧きました。 (社会人19歳男性)
在校生の方々との昼食では、とても勉強になりました。さらにこの学校への意欲が湧きました。 (高1女子)
社会人を経験された方との話ができて良かったです。大学卒の方、高校卒の方と違う目線からの話が聞けて良かったです。得る物がたくさんありました。 (保護者)
在校生の方々が身近に感じられて良かったです。 (保護者)
先生方、在校生の皆さんに親切に対応していただいき、子供は楽しんでいたようです。 (保護者)
先生方や学生さんが丁寧に説明して下さり、義肢装具士への理解が深まりました。有意義なオープンキャンパスとなりました。 (保護者)
とても良い体験ができ、参加して良かったです。在校生の方のお話も大変参考になりました。 (保護者)
 体験授業の様子
ここからは少し緊張した雰囲気に変わります。
まずは映像を使って、疾患の説明、適応となる装具についての講義。実際の装具使用者の映像と、聞いたことのない専門用語が飛び交う、まさに「ホントの授業」が受けられます。
講義の後、石膏モデルを使って「短下肢装具」と「下腿義足」の採型実習を行います。
※プライバシー保護の為、一部画像を加工しています。
体験授業の様子
ここからは少し緊張した雰囲気に変わります。
まずは映像を使って、疾患の説明、適応となる装具についての講義。実際の装具使用者の映像と、聞いたことのない専門用語が飛び交う、まさに「ホントの授業」が受けられます。
講義の後、石膏モデルを使って「短下肢装具」と「下腿義足」の採型実習を行います。
※プライバシー保護の為、一部画像を加工しています。
 先生のデモンストレーション。
採型はすべての義肢装具の製作におけるスタート地点、最も重要なポイントです。
※プライバシー保護の為、一部画像を加工しています。
先生のデモンストレーション。
採型はすべての義肢装具の製作におけるスタート地点、最も重要なポイントです。
※プライバシー保護の為、一部画像を加工しています。
 いよいよ、実践!
初めて触れるギプス包帯に緊張しながらも、とても楽しそうな姿が印象的です。
いよいよ、実践!
初めて触れるギプス包帯に緊張しながらも、とても楽しそうな姿が印象的です。
 2年生が中心となって採型実習をサポートします。
「ギプス包帯を引っ張らないように!」
「よくこすって!」
「硬くなってしまうので急ぎましょう!」
学生スタッフからも的確にアドバイスしてもらえるので、安心してチャレンジして下さい。
※プライバシー保護の為、一部画像を加工しています。
2年生が中心となって採型実習をサポートします。
「ギプス包帯を引っ張らないように!」
「よくこすって!」
「硬くなってしまうので急ぎましょう!」
学生スタッフからも的確にアドバイスしてもらえるので、安心してチャレンジして下さい。
※プライバシー保護の為、一部画像を加工しています。
 下腿義足の採型実習の様子
実際の切断端から作り出した石膏モデルを使います。そのリアルさに少し戸惑う場面も・・・。
下腿義足の採型実習の様子
実際の切断端から作り出した石膏モデルを使います。そのリアルさに少し戸惑う場面も・・・。
参加者(保護者)の声 なかなか思うようにはできませんでしたが、とても楽しかったです。 (高3男子)
知らない言葉に興味が湧き、もっと知りたい!と思えたのでとても良い体験授業になりました。分かりやすい説明だったので大変満足しています。今回参加して本当に良かったです。 (高3女子)
体験授業はとても面白く、もっと深く学びたいと思いました。次回も参加したいです。 (高3男子)
義肢を実際に装着する様子や、色々な義肢装具を初めて見せていただく事ができ、勉強になりました。 (高3女子)
初めて石膏に触れてみて最初は不安でしたが、在校生の方に手伝ってもらいながら完成したものを見て、とても達成感がありました。楽しかったです。 (高1女子)
先生の体験授業が非常に分かりやすかったです。 (保護者)
いかがでしたでしょうか? 短い時間ですがとても内容の濃いオープンキャンパスです。今年もさらにバージョンアップした内容を企画中ですので、ぜひ皆様のご参加をお待ちしています!
 " target="_blank">昨年のオープンキャンパスの様子をご紹介します!
" target="_blank">昨年のオープンキャンパスの様子をご紹介します! 大切な陽性モデルです。削り始める前にしっかりと修正箇所を確認しましょう。
大切な陽性モデルです。削り始める前にしっかりと修正箇所を確認しましょう。
 PTB式ソケットは削り修正と盛り修正を施す箇所が明確に区分けされています。採型時のマーキングがいかに重要か、ここで実感します。
PTB式ソケットは削り修正と盛り修正を施す箇所が明確に区分けされています。採型時のマーキングがいかに重要か、ここで実感します。
PTB式下腿義足の製作では、まず講義で義足で体重を支えるための理論を学び、それを実習で実践することで理解を深めていきます。 次回はソフトインサート製作の様子を紹介します!
平成25年度の義肢装具学科のオープンキャンパスは、6月22(土)、7月20日(土)、8月18日(土)に開催されます。 初回となります6月22日(土)は、今回紹介した下腿義足の採型体験ができますよ!!7・8月は夏休み中の開催になりますので、最終的な進路を決定するための良い情報が得られると思います。ご家族の方や友人と一緒でも構いませんので、この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみにまっています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">2年生 下腿義足の陽性モデル修正が行われました。
" target="_blank">2年生 下腿義足の陽性モデル修正が行われました。 陽性モデルからチェックシューズを丁寧に取り外します。
陽性モデルからチェックシューズを丁寧に取り外します。
 早速、仮合わせ。ここで自分の靴の適合が決まるので入念にチェックします。
早速、仮合わせ。ここで自分の靴の適合が決まるので入念にチェックします。
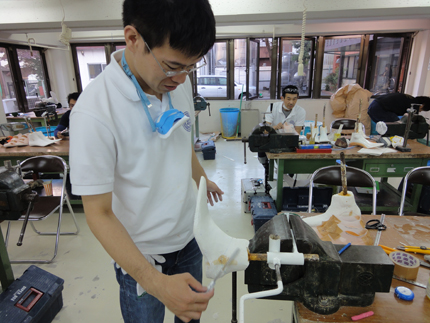 チェックシューズで確認した修正箇所を陽性モデルに反映させ、より適合の良い靴を目指します。
チェックシューズで確認した修正箇所を陽性モデルに反映させ、より適合の良い靴を目指します。
 来週からいよいよ、甲革(アッパー)を靴のラストに吊り込んでいきます!
少しずつ靴に近づいていくのが楽しみですね。
来週からいよいよ、甲革(アッパー)を靴のラストに吊り込んでいきます!
少しずつ靴に近づいていくのが楽しみですね。

 " target="_blank">2年生 靴型装具のチェックシューズを製作しました。
" target="_blank">2年生 靴型装具のチェックシューズを製作しました。 これは日本で最初に開発されたコンピュータ制御膝継手です。講義に続き、実際の製品を使用して調整を体験しました。
これは日本で最初に開発されたコンピュータ制御膝継手です。講義に続き、実際の製品を使用して調整を体験しました。
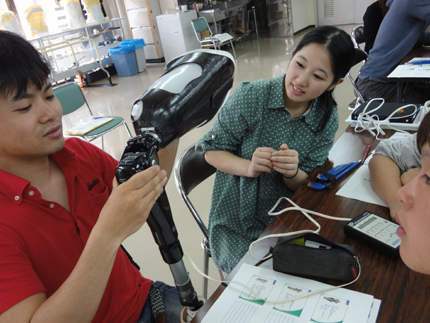 メカ好きな学生は楽しそうにあれこれ触って確かめます。
まずは興味を持つことが学習への第一歩ですね!
メカ好きな学生は楽しそうにあれこれ触って確かめます。
まずは興味を持つことが学習への第一歩ですね!
 義足使用者を想定して、膝継手に内蔵されたマイコンを専用コントローラで調整します。歩く速さに合わせて膝の振り出し速度が変わっていく様子を見て、学生たちから驚きの声があがりました。
義足使用者を想定して、膝継手に内蔵されたマイコンを専用コントローラで調整します。歩く速さに合わせて膝の振り出し速度が変わっていく様子を見て、学生たちから驚きの声があがりました。
 先生たちも興味津々です。
先生たちも興味津々です。
義足パーツメーカーの方から直接お話を聞くことができる貴重な機会です。製品に対する知識を深めることが、将来、担当する患者さまの幸せにつながります。 坂田先生、本日は誠にありがとうございました!
平成25年度の義肢装具学科のオープンキャンパスは、6月22(土)、7月20日(土)、8月18日(土)に開催されます。 初回は日程も近づいた6月、7・8月は夏休み中の開催になりますので、最終的な進路を決定するための良い情報が得られると思います。ご家族の方や友人と一緒でも構いませんので、この機会にぜひ参加してみてください。教員、学生スタッフ一同、楽しみにまっています! (義肢装具学科オープンキャンパスの詳細はコチラ) (昨年のオープンキャンパスの様子はコチラ)

 " target="_blank">3年生 ナブテスコ膝継手の特別講義が行われました。
" target="_blank">3年生 ナブテスコ膝継手の特別講義が行われました。
 " target="_blank">義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ
" target="_blank">義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ 自分で採型をした陽性モデルが実際の足の形を再現できているか、緊張の一瞬です。
自分で採型をした陽性モデルが実際の足の形を再現できているか、緊張の一瞬です。
 陽性モデルのアライメント(※)を確認します。
陽性モデルのアライメント(※)を確認します。
 アライメントの見方も大切なポイントです!
アライメントの見方も大切なポイントです!
 石膏の削り方、盛り方に慣れていきましょう!
石膏の削り方、盛り方に慣れていきましょう!
※アライメント・・・物と物との相対的な位置関係を表す用語。" target="_blank">1年生 シューホーンブレースの陽性モデル修正が行われました。
なお、当日ご都合がつかない場合は、 お気軽に学校の見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。 (学校見学は、聴能・補聴 両学科対象です。)
 " target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ
" target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ 陽性モデル作成のための前準備
次の工程を考えて陽性モデルを作成することが重要です。
陽性モデル作成のための前準備
次の工程を考えて陽性モデルを作成することが重要です。
 大切な陰性モデル、失敗はできません!
大切な陰性モデル、失敗はできません!
 香川先生による陽性モデル修正のデモンストレーション。
目の前で次々と形が変わっていく様子を、必死にメモを取ります。
香川先生による陽性モデル修正のデモンストレーション。
目の前で次々と形が変わっていく様子を、必死にメモを取ります。
 いざ、実践!
いざ、実践!
 大腿義足四辺形ソケットで体重を支持するために最も重要なポイント、「坐骨支持棚」の削り修正。製作理論通りに、正確に!
大腿義足四辺形ソケットで体重を支持するために最も重要なポイント、「坐骨支持棚」の削り修正。製作理論通りに、正確に!
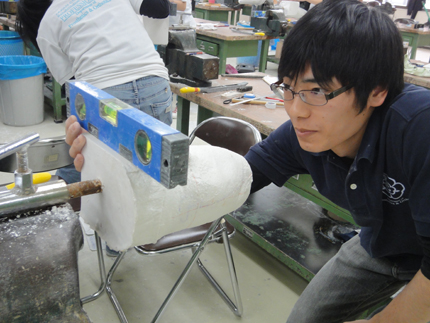 削るたびに水準器でチェック。今日の出来映えはどうですか?
削るたびに水準器でチェック。今日の出来映えはどうですか?
次回はソケットモールドとラミネーションの様子をお伝えします!" target="_blank">3年生 大腿義足の陽性モデル修正が行われました。
 骨の位置を正確に触診し、採型に必要なマーキングポイントを理解しましょう!
骨の位置を正確に触診し、採型に必要なマーキングポイントを理解しましょう!
 初めて使うギプス包帯を上手に使いこなすことが、義肢装具士への第一歩!
初めて使うギプス包帯を上手に使いこなすことが、義肢装具士への第一歩!
 いよいよ実戦!
いよいよ実戦!
採型は義肢装具士の腕の見せどころです!一つずつ、習得していきましょう。 " target="_blank">1年生 シューホーンブレースの採型実習が行われました。
 初めて触れる切断端に、緊張しながらもしっかりと観察します。
初めて触れる切断端に、緊張しながらもしっかりと観察します。
 次の工程の陽性モデル修正で重要となるマーキングを行います。
次の工程の陽性モデル修正で重要となるマーキングを行います。
 ギプス包帯を断端に巻いて、PTB式ソケットの採型で一番大切な「手技」を加えます。
ギプス包帯を断端に巻いて、PTB式ソケットの採型で一番大切な「手技」を加えます。
この後、採型で得られた陰性モデルにギプス泥を流し込んで陽性モデルを作成し、いよいよ陽性モデル修正を行います。 次回はその様子をお伝えします! " target="_blank">2年生 下腿義足の採型実習が行なわれました。
 先生による陽性モデル修正のデモンストレーションです。
先生による陽性モデル修正のデモンストレーションです。

 自分の足型から靴のラストとなる陽性モデルを作っていきます。
自分の足型から靴のラストとなる陽性モデルを作っていきます。
 靴の形に近づいてくると楽しみですね!" target="_blank">2年生 靴型装具の陽性モデル修正が行われました。
靴の形に近づいてくると楽しみですね!" target="_blank">2年生 靴型装具の陽性モデル修正が行われました。 自分の目と手で、しっかりと断端の状況を把握します。
自分の目と手で、しっかりと断端の状況を把握します。
 採型を終えた陰性モデル。仮合わせが楽しみです。
採型を終えた陰性モデル。仮合わせが楽しみです。
次の工程は陽性モデル修正です。 理論をしっかり理解して、確実な作業を心がけましょう!" target="_blank">3年生 大腿義足の採型実習が行なわれました。
 大切なキーワードは聞き逃さないように、しっかりとメモをとります。
大切なキーワードは聞き逃さないように、しっかりとメモをとります。
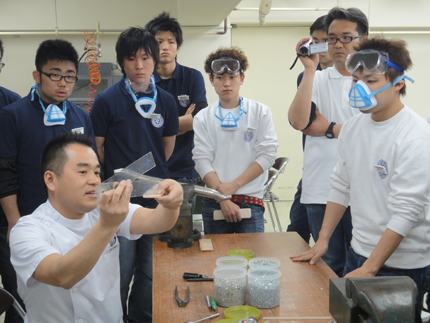 先生のデモンストレーションをしっかりと観察することが大切です!
先生のデモンストレーションをしっかりと観察することが大切です!
 まずは、材料を寸法通りに切り出すことから作業が始まります。
まずは、材料を寸法通りに切り出すことから作業が始まります。

患者さまが装着する義足や装具を製作する義肢装具士。 安全で、きれいな製品を作れるように1年間しっかり基礎を学びましょう!" target="_blank">新入生、初めての製作実習!
 先輩たちも新入生の自己紹介に興味津々です。
先輩たちも新入生の自己紹介に興味津々です。
同級生、先輩方と積極的にコミュニケーションをとって、充実した学生生活を送ってください!" target="_blank">新入生歓迎会が行われました!
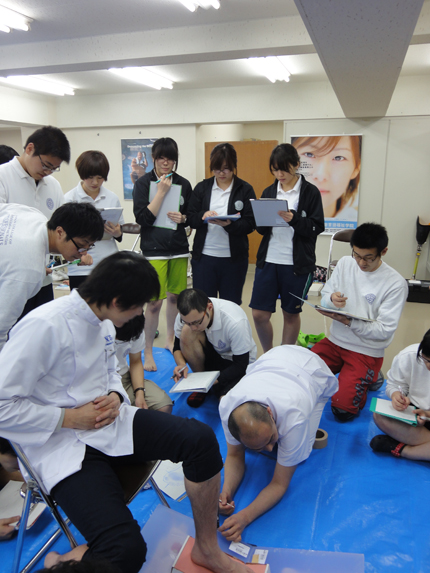 先生のデモンストレーションを真剣に見学します。
先生のデモンストレーションを真剣に見学します。
 さぁ、いよいよ実践です!
さぁ、いよいよ実践です!
 自分で履く靴を作るので、みんな真剣です。
自分で履く靴を作るので、みんな真剣です。
「かっこいい靴」を目指して、頑張って作りましょう!!" target="_blank">2年生 靴型装具の採型実習が行なわれました。
 義肢装具学科では6月22日(土)、7月20日(土)、8月17日(土)にオープンキャンパスを開催しますので、義肢装具士の仕事に興味を持たれた方は、ぜひご参加下さい。
たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">平成25年度がスタートしました。
義肢装具学科では6月22日(土)、7月20日(土)、8月17日(土)にオープンキャンパスを開催しますので、義肢装具士の仕事に興味を持たれた方は、ぜひご参加下さい。
たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">平成25年度がスタートしました。 学院長より卒業証書を授与される義肢装具学科総代
学院長より卒業証書を授与される義肢装具学科総代
 謝辞を読み上げる卒業生代表
謝辞を読み上げる卒業生代表
卒業式後には、卒業生の保護者の皆さま、OB会長様のほか在校生も集まり、義肢装具学科卒業証書授与式が行われました。一人一人に卒業証書の授与、各種表彰が行われました。
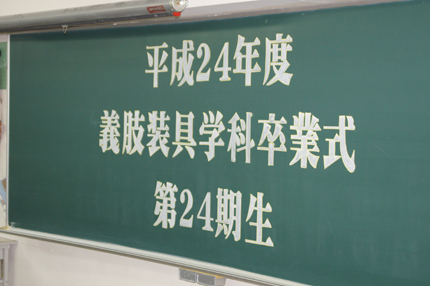 学生会一同による渾身の力作(学生会の皆さんありがとうございました。)
学生会一同による渾身の力作(学生会の皆さんありがとうございました。)
 高見学科長から理事長賞が授与されました。
高見学科長から理事長賞が授与されました。
 OB会長より薫風会賞が授与されました。
OB会長より薫風会賞が授与されました。
 教室に戻っての卒業証書授与式では終始和やかな雰囲気でした。
教室に戻っての卒業証書授与式では終始和やかな雰囲気でした。
 在校生代表から記念品の贈呈。
在校生代表から記念品の贈呈。
4月から全国各地で活躍されることをお祈りします。 ご卒業おめでとうございました。" target="_blank">平成24年度 卒業式・義肢装具学科卒業証書授与式
 " target="_blank">「集中講義が行なわれました!」
" target="_blank">「集中講義が行なわれました!」本年度の入学試験も残り2回となりました(4次&5次一般入試)。4次の出願期間は1月2日~15日・試験日は1月19日(土)となっていますので、受験をされる方・検討中の方は宜しくお願いします。

また、義肢装具学科では、進路を検討中の皆様に個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています! あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">明けましておめでとうございます!
" target="_blank">明けましておめでとうございます!なお、当日のご都合がつかない場合には、 ぜひお気軽に学校見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。 (学校見学は、聴能・補聴 両学科対象です。)
 " target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ
" target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ 空腹&早くお代わりしたいために、ほぼ無言で食してました(笑)
空腹&早くお代わりしたいために、ほぼ無言で食してました(笑)
 満面の笑みで、一人平均2杯以上はモリモリ食べていました!
満面の笑みで、一人平均2杯以上はモリモリ食べていました!
ということで、 本年度の入学試験も残り2回となりました(4次&5次一般入試)。4次の出願期間は1月2日~となっていますので宜しくお願いします。
 " target="_blank">年末大掃除とカレーと冬休み!
" target="_blank">年末大掃除とカレーと冬休み!義肢装具学科では、進路を検討中の皆様に個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!
" target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内! 筋電義手が、きちんと制御されて動くかどうかを確認中!
筋電義手が、きちんと制御されて動くかどうかを確認中!
 最終的に、使用者の方がコントロールできるかを評価中!
最終的に、使用者の方がコントロールできるかを評価中!
 恒例の記念写真!モデルの皆様、本年度もありがとうございました!" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の適合評価!~
恒例の記念写真!モデルの皆様、本年度もありがとうございました!" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の適合評価!~姿勢を保持することの重要性を理解するため実例を交えながらの講義に加え、採型機器によるシミュレーションと採型、また、様々な車いすの特徴を理解するための試乗、といった幅広い内容を実体験することによって、より実践に即した学習ができたと思います。
 特殊採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中①!
特殊採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中①!
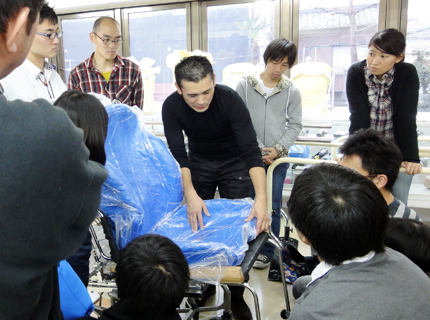 特殊採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中②!
特殊採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中②!
 特殊採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中③!
特殊採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中③!
 車いすの試乗で利用者の視点で考察①
車いすの試乗で利用者の視点で考察①
 車いすの試乗で利用者の視点で考察②" target="_blank">座位保持装置の講義が実施されました!
車いすの試乗で利用者の視点で考察②" target="_blank">座位保持装置の講義が実施されました!ぜひお気軽に学校見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、 仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。
 " target="_blank">授業紹介(実技演習)
" target="_blank">授業紹介(実技演習) ソケットが不適合だと義手自体がNGしなのでしっかり確認しています!
ソケットが不適合だと義手自体がNGしなのでしっかり確認しています!
 義手長も決めて様々なポジションでも使いやすく動くことが大事です!
義手長も決めて様々なポジションでも使いやすく動くことが大事です!
 筋電義手ハンドを取り付け装着者の思いのまま手が開閉するか確認中!" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の仮合わせ~
筋電義手ハンドを取り付け装着者の思いのまま手が開閉するか確認中!" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の仮合わせ~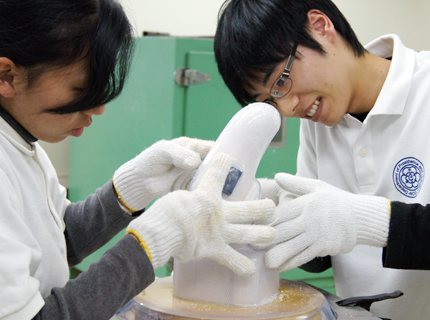 石膏モデルに沿うように真空成型機と手技を使って型をだしています!
石膏モデルに沿うように真空成型機と手技を使って型をだしています!
 仮合わせ用ため筋電義手がちゃんと機能するか動作確認しています!
仮合わせ用ため筋電義手がちゃんと機能するか動作確認しています!
 どうやら仮合わせの準備は万全みたいです!!" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の製作①!~
どうやら仮合わせの準備は万全みたいです!!" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の製作①!~ 80名を超える多数の聴講者のなか発表会が開催されました!
80名を超える多数の聴講者のなか発表会が開催されました!
 質疑応答では来賓の方からも貴重なアドバイスを沢山頂けました!
質疑応答では来賓の方からも貴重なアドバイスを沢山頂けました!
 卒業研究活動で作った製作物、実験道具や器具なども各班が展示!
卒業研究活動で作った製作物、実験道具や器具なども各班が展示!
 まだまだ頑張って!!賞として国家試験合格祈願セットをもらいました!
まだまだ頑張って!!賞として国家試験合格祈願セットをもらいました!
 24期生の記念撮影。お疲れ様でした!あと数ヶ月…頑張っていこう!" target="_blank">卒業研究発表会が開催されました!
24期生の記念撮影。お疲れ様でした!あと数ヶ月…頑張っていこう!" target="_blank">卒業研究発表会が開催されました!なお、当日のご都合がつかない場合には、 ぜひお気軽に学校見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、 仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。
 " target="_blank">オープンキャンパス!!
" target="_blank">オープンキャンパス!! 採型の様子②型がちゃんと採れているか?はめ合いを確認中!
採型の様子②型がちゃんと採れているか?はめ合いを確認中!
 採型の様子③モデルさんとのコミュニケーションも大事です!
採型の様子③モデルさんとのコミュニケーションも大事です!
 採型が義手適合のカナメなのでしっかり教わってます!" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の採型!~
採型が義手適合のカナメなのでしっかり教わってます!" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の採型!~なお、当日のご都合がつかない場合には、 ぜひお気軽に学校見学にいらしてください。 学校見学では、オープンキャンパスの内容に準じ、 仕事紹介や学科説明を行います。 専任教員が1対1で対応させて頂き、ご質問にも直接お答えいたします。
 " target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ
" target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ見学時には、言語訓練を実施する2年生の先輩や教員から、 事前に訓練の目的などを説明してもらい、 訓練の後にも質疑応答の時間を設けてもらいます。 訓練の中で、患者様と少しお話させて頂いたり、 患者様が子どもさんの場合は一緒に遊んだりと、 関わる機会も設けてもらいます。 1年生のこの時点では、専門科目が始まったばかりなので、 分かることも少ない状態です。 しかしこのような見学を通じて、言語聴覚士の卵として、 改めてこの仕事への理解と興味を高めてもらえればと考えています。
見学に参加した1年生は、初めての訓練見学に緊張しながらも、 真剣なまなざしで見学をし (あまり真剣だと2年生や患者さんが緊張してしまいますが)、 訓練後の質疑応答でも熱心に2年生や教員に質問する姿が見られました。
見学後にレポートを課しているのですが、見学した感想を聞いてみると、
「失語症の方が思ったよりもよく話されていて驚きました」 「患者様と初めて関わってとても緊張しました」 「先輩の手技を見て、工夫されているなあと思いました。 対応もとても自然で勉強になりました。 1年後自分が出来るようになるか不安ですが、 今出来る勉強をしっかりしていきたいです」
今回の見学で得た経験を、今後の勉強に是非活かして頑張ってほしいです。

 義肢装具学科では8月18日(土)に本年度最後のオープンキャンパス(*詳細リンク)を開催します!また今年受験を検討中の高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">山本篤選手がNHK Eテレに出演します(8/10)!
義肢装具学科では8月18日(土)に本年度最後のオープンキャンパス(*詳細リンク)を開催します!また今年受験を検討中の高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">山本篤選手がNHK Eテレに出演します(8/10)! (伊良湖の灯台 結構歩きました…)
2日目はお疲れ模様の学生もちらほら。
(伊良湖の灯台 結構歩きました…)
2日目はお疲れ模様の学生もちらほら。
 (帰りはお土産屋に寄るものの、バスで爆睡の人たちも)
夏前は試験も重なり大変でしょうが、8月には初めての
見学実習があります。
学外授業の時の元気さで乗り切ってください。
" target="_blank">夏はやっぱり海です!! ~補聴2年 学外授業~
(帰りはお土産屋に寄るものの、バスで爆睡の人たちも)
夏前は試験も重なり大変でしょうが、8月には初めての
見学実習があります。
学外授業の時の元気さで乗り切ってください。
" target="_blank">夏はやっぱり海です!! ~補聴2年 学外授業~ ロンドンパラリンピック日本選手団(リレーメンバーとコーチ)
*右側から2番目の帽子をかぶった人が山本選手!
*写真:障害者スポーツ専門サイトMASPORTSより引用(*リンク)
ロンドンパラリンピック日本選手団(リレーメンバーとコーチ)
*右側から2番目の帽子をかぶった人が山本選手!
*写真:障害者スポーツ専門サイトMASPORTSより引用(*リンク) 2012ロンドンパラリンピック陸上競技チーム切断男子(中央が山本選手)
*写真:障害者スポーツ専門サイトMASPORTSより引用(*リンク)
2012ロンドンパラリンピック陸上競技チーム切断男子(中央が山本選手)
*写真:障害者スポーツ専門サイトMASPORTSより引用(*リンク)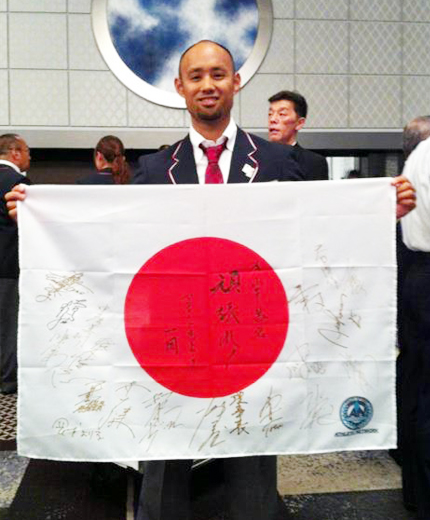 サイン入り国旗を送られる山本選手
*写真:障害者スポーツ専門サイトMASPORTSより引用(*リンク)
サイン入り国旗を送られる山本選手
*写真:障害者スポーツ専門サイトMASPORTSより引用(*リンク)
また、8月29日に開幕する「ロンドン・パラリンピックのTV-CMに全世界から絶賛の声」と、テレビコマーシャルが話題になっている、色んなことを物語っている凄い映像だと思いますのでリンク紹介します(制作したのはイギリス公共テレビ局のチャンネル4)! CMのテーマは、“Meet The Superhuman”です!! *山本篤選手鈴木徹選手もチラッとでています!!!
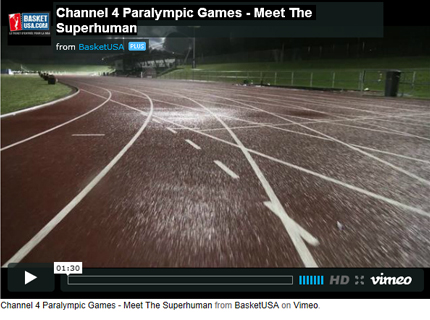 *注)画像をクリックすると別サイト(ブログタイムズ)に切り替わります。
TVCMの映像は、そのサイト内の動画にてご覧になれます。
*注)画像をクリックすると別サイト(ブログタイムズ)に切り替わります。
TVCMの映像は、そのサイト内の動画にてご覧になれます。
 義肢装具学科では8月18日(土)に本年度最後のオープンキャンパス(*詳細リンク)を開催します!また今年受験を検討中の高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">ロンドンパラリンピック団結式&TVCM&学科最終OC告知!
義肢装具学科では8月18日(土)に本年度最後のオープンキャンパス(*詳細リンク)を開催します!また今年受験を検討中の高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">ロンドンパラリンピック団結式&TVCM&学科最終OC告知! 皆で食べると美味しいですね!でも、食事に夢中でほぼ無言でした(笑)
皆で食べると美味しいですね!でも、食事に夢中でほぼ無言でした(笑)
 若人は食欲旺盛!一人平均2杯~3杯くらいは食べていたのでは!?
若人は食欲旺盛!一人平均2杯~3杯くらいは食べていたのでは!?
 ということで、その夏休み期間中に義肢装具学科では7月21日(土)、8月18日(土)と、あと2回オープンキャンパス(*詳細リンク)を開催しますので、この番組をご覧になって興味を持たれた方は、ぜひご参加下さい。また、とくに高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">大掃除とカレーと夏休み!
ということで、その夏休み期間中に義肢装具学科では7月21日(土)、8月18日(土)と、あと2回オープンキャンパス(*詳細リンク)を開催しますので、この番組をご覧になって興味を持たれた方は、ぜひご参加下さい。また、とくに高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">大掃除とカレーと夏休み!“人工ボディ”は、先天性の障害、事故、病気により手足、胸、耳などの身体の一部を失ってしまった人々のために、各自の特徴に合わせて人体用のシリコーンで復元するもので、それは「失われた身体とともに心のケアもできる!」と、最も大事なのは、つくる前に相手の悩みをじっくり聴き、背景を察して、日常生活に合わせたものを考えること。その結果、技術・技能を磨くために真摯に接客(情報収集)や使用者&他機関との三者連携を続けていくことが、プロフェッショナルとしての醍醐味であるといった話を聞くことができました。
福島先生、榎本先生、お忙しいところ本当にありがとうございました!
 身振り+テンポの良い大阪弁!!で、懇切丁寧に指導をしてもらってます!
身振り+テンポの良い大阪弁!!で、懇切丁寧に指導をしてもらってます!
 顔面の型を採っている様子。*呼吸はストローを加えてしています!
顔面の型を採っている様子。*呼吸はストローを加えてしています!
 講義終了後にくれいの記念撮影!
講義終了後にくれいの記念撮影!
工房アルテのブログで福島先生がこの講義について記事を書いてくれています!(*リンク)" target="_blank">人工ボディの特別講義が実施されました!
 大阪体育大学のトラックでスピード練習をする山本選手
*写真:障害者スポーツ専門サイトMASPORTSより引用(*リンク)
大阪体育大学のトラックでスピード練習をする山本選手
*写真:障害者スポーツ専門サイトMASPORTSより引用(*リンク)
 義肢装具学科では7月21日(土)、8月18日(土)と、あと2回オープンキャンパス(*詳細リンク)を開催しますので、この番組をご覧になって興味を持たれた方は、ぜひご参加下さい。また、とくに高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">ロンドンパラリンピック 山本篤選手をみんなで応援しよう!
義肢装具学科では7月21日(土)、8月18日(土)と、あと2回オープンキャンパス(*詳細リンク)を開催しますので、この番組をご覧になって興味を持たれた方は、ぜひご参加下さい。また、とくに高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">ロンドンパラリンピック 山本篤選手をみんなで応援しよう! " target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ
" target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ*関連記事リンク ‘Blade Runner’ Oscar Pistorius Selected for London Olympics / abc NEWS 義足のランナー初の五輪へ/NHK NEWS
彼は生後11か月で両ひざから下を切断(下腿切断)となり、2008年にスポーツ仲裁裁判所の裁定により健常者の大会には出場できるようになりましたが、残念ながら2008年の北京五輪には出場できませんでした。これで、障がい者と健常者が共に同じフィールドで競い合う時代がようやくやってきたと言えます。
 Oscar Pistorius
tests out the Athletics track at the London 2012 Olympic Stadium.
© • Getty Images(*写真引用先リンク)
Oscar Pistorius
tests out the Athletics track at the London 2012 Olympic Stadium.
© • Getty Images(*写真引用先リンク)
 義肢装具学科では7月21日(土)、8月18日(土)と、あと2回オープンキャンパス(*詳細リンク)を開催しますので、この番組をご覧になって興味を持たれた方は、ぜひご参加下さい。また、とくに高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">義足の世界についに新しい時代がやってきました!
義肢装具学科では7月21日(土)、8月18日(土)と、あと2回オープンキャンパス(*詳細リンク)を開催しますので、この番組をご覧になって興味を持たれた方は、ぜひご参加下さい。また、とくに高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">義足の世界についに新しい時代がやってきました!義肢装具学科では7月21日(土)、8月18日(土)と、あと2回オープンキャンパス(*詳細リンク)を開催しますので、この番組をご覧になって興味を持たれた方は、ぜひご参加下さい。また、とくに高校生、大学生の方はこの夏休みの期間を利用して「義肢装具製作施設見学ツアー(*詳細リンク)」にも、ぜひご参加下さい。たくさんの方からのご連絡をお待ちしています。" target="_blank">CBCテレビ「イッポウ」で義肢装具学科が紹介されました!
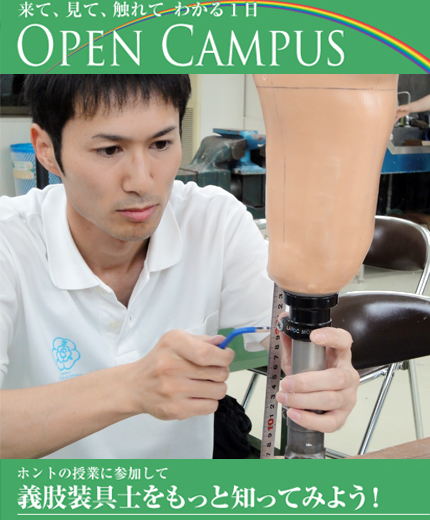
 " target="_blank">義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ②!
" target="_blank">義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ②!
義肢装具学科では『義肢装具士』への進路を検討中の方への情報提供としてオープンキャンパス(*詳細リンク)に加えて、個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています。 番組をご覧になって、もっと知りたい!と興味をもった方はぜひ参加してみてください!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">CBCテレビが義肢装具学科を取材に来ました!
" target="_blank">CBCテレビが義肢装具学科を取材に来ました! 報告会の様子②
…聴講する2年生も興味深く聞いて活発な質疑をしてくれました!
報告会の様子②
…聴講する2年生も興味深く聞いて活発な質疑をしてくれました!
 報告会の様子③
…第1班「スポーツ用義手」に関する研究です!
報告会の様子③
…第1班「スポーツ用義手」に関する研究です!
 報告会の様子④
…第2班「脊髄損傷者のQOL」に関する研究です!
報告会の様子④
…第2班「脊髄損傷者のQOL」に関する研究です!
 報告会の様子⑤
…第3班「整形靴の製作方法」に関する研究です!
報告会の様子⑤
…第3班「整形靴の製作方法」に関する研究です!
 報告会の様子⑥
…第4班「義足ソケット内環境」に関する研究です!
" target="_blank">卒研中間報告会が開催されました!
報告会の様子⑥
…第4班「義足ソケット内環境」に関する研究です!
" target="_blank">卒研中間報告会が開催されました! 慣れない工具に苦労…でも、自分が履く靴の出来上がりが楽しみです!
慣れない工具に苦労…でも、自分が履く靴の出来上がりが楽しみです!
 途中までできました…最後まで集中力を切らさないよう頑張ろう!" target="_blank">2年生の実習をレポート②!!
途中までできました…最後まで集中力を切らさないよう頑張ろう!" target="_blank">2年生の実習をレポート②!! ソケットだけでなく、義足構成部品の調整も大事な要素です!
ソケットだけでなく、義足構成部品の調整も大事な要素です!
 ソケット適合の様子…使用者とのコミュニケーションも重要な要素です!" target="_blank">3年生の実習をレポート③!!
ソケット適合の様子…使用者とのコミュニケーションも重要な要素です!" target="_blank">3年生の実習をレポート③!!義肢装具学科では、本年度も進路を検討中の皆様にオープンキャンパスに加えて、個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!
" target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!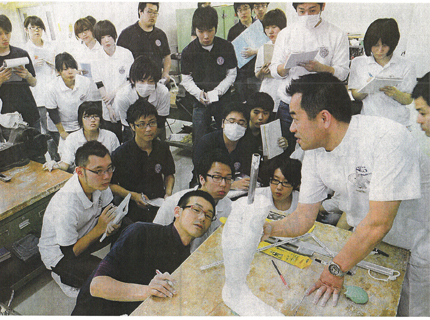 掲載された写真①大きい画像で見る
掲載された写真①大きい画像で見る
 掲載された写真②
掲載された写真②
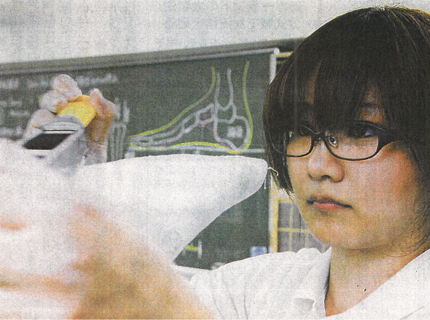 掲載された写真③
掲載された写真③
 掲載された写真④" target="_blank">毎日新聞に義肢装具学科が紹介されました!
掲載された写真④" target="_blank">毎日新聞に義肢装具学科が紹介されました! 製作場面②ソケットを木の土台に埋め込む下準備中!
製作場面②ソケットを木の土台に埋め込む下準備中!
 製作場面③埋め込んだソケットのライン設定を確認中!
製作場面③埋め込んだソケットのライン設定を確認中!
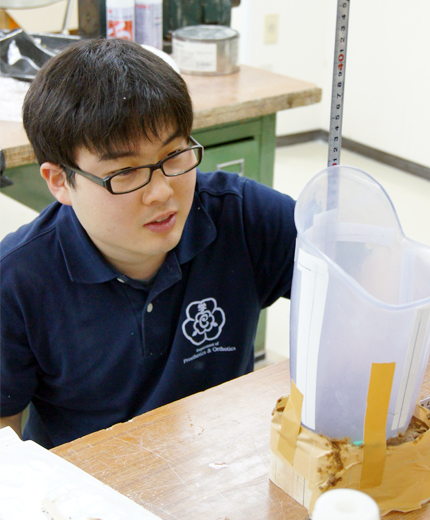 製作場面④埋め込んだソケットのライン設定を確認中!
製作場面④埋め込んだソケットのライン設定を確認中!
 おまけ…平成24年度 義肢装具学科学生 全員大集合!
大きい画像でみる!?
" target="_blank">3年生の実習をレポート②!!
おまけ…平成24年度 義肢装具学科学生 全員大集合!
大きい画像でみる!?
" target="_blank">3年生の実習をレポート②!!
 " target="_blank">義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ①!
" target="_blank">義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ①!


 " target="_blank">1年生の実習をレポート①!!
" target="_blank">1年生の実習をレポート①!!


 " target="_blank">2年生の実習をレポート①!!
" target="_blank">2年生の実習をレポート①!! 香川先生による採型のデモンストレーション!
香川先生による採型のデモンストレーション!
 採型をする前に様々な情報の収集を行います!
採型をする前に様々な情報の収集を行います!
 いざ、採型!…ココの良しあしが適合に影響を及ぼします!
いざ、採型!…ココの良しあしが適合に影響を及ぼします!
 笑顔ですが、実は思っているよりも力がいります!" target="_blank">3年生の実習をレポート①!!
笑顔ですが、実は思っているよりも力がいります!" target="_blank">3年生の実習をレポート①!!4月23日の体育は、スポンジボールを使ってのテニス のような競技でした。思った以上に体力を使い、 息を切らしながらも真剣勝負。
年齢に関わらず、かなり張り切ってプレイして いました。
明日の筋肉痛が心配です!!
日々の生活にメリハリをつけて、6月末から始まる 臨床実習への準備も着々と進めてくださいね。
補聴言語学科 教員 " target="_blank">「見よ!この華麗なる動き!! 保健体育Ⅱ」
義肢装具学科では、本年度も進路を検討中の皆様にオープンキャンパスに加えて、個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!
" target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!補聴言語学科 80 %
全国平均 62.3%
今回は昨年(69.3%)に比べて全国の合格率が低く、 60%台前半のため比較的難易度の高い年であったといえます。 そんな中、聴能・補聴とも健闘しました! 苦しい国家試験勉強を乗り切って、 見事STへの入り口に立てた聴能26期・補聴18期のみなさん、 本当におめでとう! これまでの道のりは、決してラクなものではなかったと思います。 本当に良く頑張りました。 学生達を支え導いてくださった実習指導の先生方、 講師の先生方、本当にありがとうございました。 そして、いよいよ、新しいスタートをきる時がきましたね。 たくさんの皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに、 これから始まるST人生、 対象者のみなさんにより良い臨床を提供できる専門家・臨床家として、 日々努力を重ねてがんばってくださいね。 いつまでも応援しています。 教員一同 " target="_blank">言語聴覚士国家試験合格発表!
自己採点での予想で確信はしていたものの、本発表があるまではナニカト不安が残るものでしたが、第23期生をはじめ保護者の皆様方、本当におめでとうございました。そして、本学科非常勤講師の先生方、臨床実習先の指導者の皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
全国平均が80.3%と過去最低だったのですが、全員合格は当該受験生の努力の賜であり、三年間の学生生活の一つの目標達成ができたことは素晴らしいことだと思います。24期生の後輩の皆さん、春からプレッシャーはたっぷりかかりますが、気合いと気合いと気合いで(笑)、来年も頑張って素敵な伝統を継承していきましょう!
23期生の卒業生諸君、これからが本番、スタートです。これからも今まで以上に頑張って「義肢装具士」を磨いていってください。
 " target="_blank">義肢装具士国家試験に全員合格しました!!
" target="_blank">義肢装具士国家試験に全員合格しました!! 空腹&早くお代わりしたいために、ほぼ無言で飲んでました(笑)
空腹&早くお代わりしたいために、ほぼ無言で飲んでました(笑)
 満面の笑みで、一人平均2杯以上はモリモリ食べていました!
" target="_blank">年度末大掃除とカレーと春休み!
満面の笑みで、一人平均2杯以上はモリモリ食べていました!
" target="_blank">年度末大掃除とカレーと春休み! 適合評価の様子②
適合評価の様子②
 適合評価の様子③
適合評価の様子③
 適合評価を終えて…集合写真!
大きいサイズで見る!?
" target="_blank">製作実習の様子~上腕義手の適合評価!~
適合評価を終えて…集合写真!
大きいサイズで見る!?
" target="_blank">製作実習の様子~上腕義手の適合評価!~ 義肢装具学科授与式の様子…在校生全員が見守る卒業証書の授与式
義肢装具学科授与式の様子…在校生全員が見守る卒業証書の授与式
 義肢装具学科授与式の様子…各々に髙見学科長より卒業証書の授与
義肢装具学科授与式の様子…各々に髙見学科長より卒業証書の授与
 式後の記念撮影大きい画像でみる!?
" target="_blank">平成23年度卒業式&義肢装具学科卒業証書授与式!
式後の記念撮影大きい画像でみる!?
" target="_blank">平成23年度卒業式&義肢装具学科卒業証書授与式!受験生である第23期の三年生は、前日から受験地である東京に出発して試験に備えます。!また、国試受験前の恒例イベント「壮行会」では、学院長・学科長、教務から激励の挨拶を頂き、また、在校生からは恒例の「日聴・応援団」が登場して、受験生の気持ちを盛り上げてくれました!
合格発表は、今月末の28日の午後2時…今までの努力、自分を信じて当日は体調万全で試験に挑んで欲しいと思います。試験が終われば、残す一大イベントの卒業式、学校生活最後の行事である楽しい卒業記念パーティーの準備ですから! 三年生の皆さん、日聴魂のひとつ「気合いっ!」で思う存分に実力を発揮してきて下さいね!
 壮行会の様子①…棚橋学院長からの激励!
壮行会の様子①…棚橋学院長からの激励!
 壮行会の様子②…髙見学科長からの激励!
壮行会の様子②…髙見学科長からの激励!
 壮行会の様子③…日聴応援団による激励!
壮行会の様子③…日聴応援団による激励!
 壮行会の様子④…在校生によるお見送り!
" target="_blank">いざ、義肢装具士国家試験の受験へ!
壮行会の様子④…在校生によるお見送り!
" target="_blank">いざ、義肢装具士国家試験の受験へ! 発表&受賞後の記念撮影!おめでとうございました!
発表&受賞後の記念撮影!おめでとうございました!
 中川教務主任(代読)による表彰状の授与(再び)!
中川教務主任(代読)による表彰状の授与(再び)!
 全学年の学生が揃って、受賞の報告会を催しました!
" target="_blank">また×6 !!!!!!の6年連続で卒研が受賞!
全学年の学生が揃って、受賞の報告会を催しました!
" target="_blank">また×6 !!!!!!の6年連続で卒研が受賞! 義手を使用する方の身体状況を細かくチェックして製作に反映させます!
義手を使用する方の身体状況を細かくチェックして製作に反映させます!
 いざギプスによる採型!この型採りの良しあしが適合を左右します!
いざギプスによる採型!この型採りの良しあしが適合を左右します!
 ただ単にギプスを巻くのではなく、手技やライン設定などを行います!
ただ単にギプスを巻くのではなく、手技やライン設定などを行います!
 もの作りだけでなく要の使用者とのコミュニケーション能力も磨きます!" target="_blank">製作実習の様子~上腕義手の採型!~
もの作りだけでなく要の使用者とのコミュニケーション能力も磨きます!" target="_blank">製作実習の様子~上腕義手の採型!~ということで、 本年度の入学試験も残り2回となりました(4次&5次一般入試)。4次の出願期間は1月4日~17日・試験日は1月21日(土)となっていますので、受験をされる方・検討中の方は宜しくお願いします。

また、個別での学校見学は随時受付ていますので、今年受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(受験当該学年ではない中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒にお気軽に申し込みをして頂き、情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。
 " target="_blank">新年明けましておめでとうございます!
" target="_blank">新年明けましておめでとうございます!義肢装具学科では、本年度も進路を検討中の皆様にオープンキャンパスに加えて(本年度分は全て終了)、個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!
" target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内! 空腹&早くお代わりしたいために、ほぼ無言で食してました(笑)
空腹&早くお代わりしたいために、ほぼ無言で食してました(笑)
 満面の笑みで、一人平均2杯以上はモリモリ食べていました!
満面の笑みで、一人平均2杯以上はモリモリ食べていました!
ということで、 本年度の入学試験も残り2回となりました(4次&5次一般入試)。4次の出願期間は1月4日~となっていますので宜しくお願いします。

また、冬休み中にも個別での学校見学は随時受付ていますので、今年受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(受験当該学年ではない中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒にお気軽に申し込みをして頂き、情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。
 " target="_blank">年末大掃除とカレーと冬休み!
" target="_blank">年末大掃除とカレーと冬休み! マンツーマンでの親切丁寧な指導に学生真剣そのもの!
マンツーマンでの親切丁寧な指導に学生真剣そのもの!
 各自がデザインした型紙を持って集合写真!
*大きい画像でみる
" target="_blank">靴型装具の特別講義が実施されました!
各自がデザインした型紙を持って集合写真!
*大きい画像でみる
" target="_blank">靴型装具の特別講義が実施されました! 最終的に、使用者の方がコントロールできるかを評価中!
最終的に、使用者の方がコントロールできるかを評価中!
 恒例の記念写真!モデルの皆様、本年度もありがとうございました!
*大きい画像でみる!?
" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の適合評価!~
恒例の記念写真!モデルの皆様、本年度もありがとうございました!
*大きい画像でみる!?
" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の適合評価!~ 記念品(中川先生)
大きい画像でみる
記念品(中川先生)
大きい画像でみる
 明治記念館(表彰式会場)
明治記念館(表彰式会場)
 明治記念館(全景)" target="_blank">中川主任が平成23年度中央職業能力開発協会会長表彰を受けられました!
明治記念館(全景)" target="_blank">中川主任が平成23年度中央職業能力開発協会会長表彰を受けられました! 被写体①からの肖像画…似すぎていて飛び出してきそうです(笑)
被写体①からの肖像画…似すぎていて飛び出してきそうです(笑)
 被写体②
被写体②
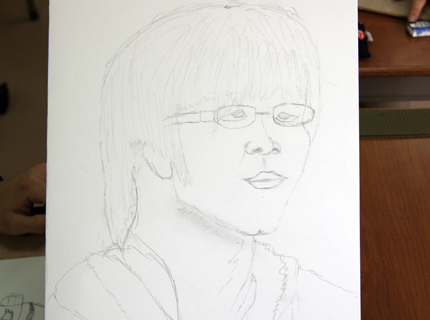 被写体②からの肖像画…ある意味で似てますね…千差万別と(笑)
被写体②からの肖像画…ある意味で似てますね…千差万別と(笑)
 芥川先生の誕生日祝い①…サプライズで2年生が特大プリンを贈呈!?
芥川先生の誕生日祝い①…サプライズで2年生が特大プリンを贈呈!?
 芥川先生の誕生日祝い②…美術が反映されてないデコレーション(笑)
芥川先生の誕生日祝い②…美術が反映されてないデコレーション(笑)
 2012年・年賀状撮影…学院屋上にて!
2012年・年賀状撮影…学院屋上にて!
 2年生教室からの夕焼け風景" target="_blank">「美術」の授業でで芸術性を磨く②…からの!?
2年生教室からの夕焼け風景" target="_blank">「美術」の授業でで芸術性を磨く②…からの!? 美術の授業の様子②
美術の授業の様子②
 美術の授業の様子③
美術の授業の様子③
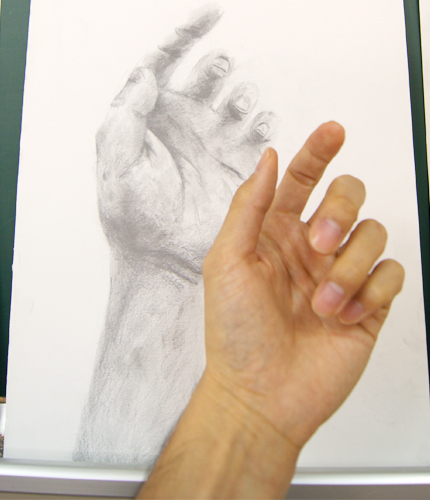 出来上がった作品①" target="_blank">「美術」の授業でで芸術性を磨く…秋!!
出来上がった作品①" target="_blank">「美術」の授業でで芸術性を磨く…秋!! ソケットが不適合だと義手自体がNGしなのでしっかり教わってます!
ソケットが不適合だと義手自体がNGしなのでしっかり教わってます!
 筋電義手ハンドを取り付け装着者の思いのまま手が開閉するか確認中!
筋電義手ハンドを取り付け装着者の思いのまま手が開閉するか確認中!
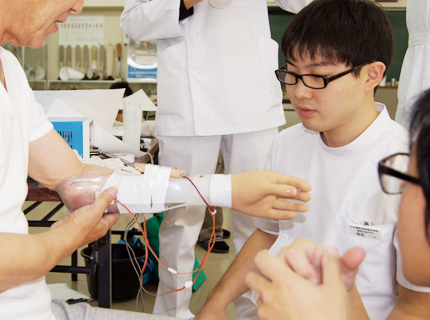 義手長も決めて様々なポジションでも使いやすく動くことが大事です!
義手長も決めて様々なポジションでも使いやすく動くことが大事です!
 もの作りだけでなく要の使用者とのコミュニケーション能力も磨きます!" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の仮合わせ!~
もの作りだけでなく要の使用者とのコミュニケーション能力も磨きます!" target="_blank">製作実習の様子~筋電義手の仮合わせ!~姿勢を保持することの重要性を理解するため実例を交えながらの講義に加え、採型機器によるシミュレーションと採型、また、様々な車いすの特徴を理解するための試乗、といった幅広い内容を実体験することによって、より実践に即した学習ができたと思います。
 関西(大阪)人二人の話はテンポ良く、熱い講演をして頂けました!
関西(大阪)人二人の話はテンポ良く、熱い講演をして頂けました!
 特殊採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中①!
特殊採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中①!
 特殊採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中②!
特殊採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中②!
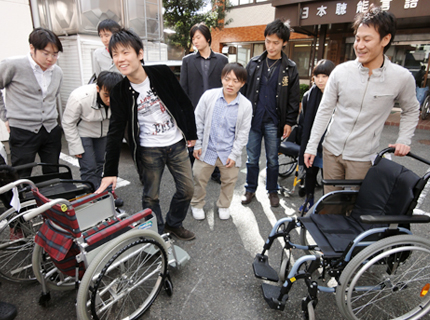 車いすの選び方、採寸法、収納法など色んな機能の説明を聞いてます!
車いすの選び方、採寸法、収納法など色んな機能の説明を聞いてます!
 車いすの試乗で利用者の視点で考察…この連帯は今後も大切です(笑)
" target="_blank">座位保持装置の講義が実施されました!
車いすの試乗で利用者の視点で考察…この連帯は今後も大切です(笑)
" target="_blank">座位保持装置の講義が実施されました! 90名を超える多数の聴講者のなか発表会が開催されました!
90名を超える多数の聴講者のなか発表会が開催されました!
 座長は2年生です!2年生も年明けから卒業研究が始まります!
座長は2年生です!2年生も年明けから卒業研究が始まります!
 発表後の質疑応答の様子!活発な質問が多かったのは賜物です!
発表後の質疑応答の様子!活発な質問が多かったのは賜物です!
 質疑応答では来賓の方からも貴重なアドバイスを沢山頂けました!
質疑応答では来賓の方からも貴重なアドバイスを沢山頂けました!
 発表後の質疑を待つ時間…この時間の緊張感は何ともいえません!
発表後の質疑を待つ時間…この時間の緊張感は何ともいえません!
 卒業研究活動で作った製作物、実験道具や器具なども各班が展示!
卒業研究活動で作った製作物、実験道具や器具なども各班が展示!
 恒例の国家試験合格祈願セットを中川主任からもらっています!
恒例の国家試験合格祈願セットを中川主任からもらっています!
 23期生の記念撮影。お疲れ様でした!あと数ヶ月…頑張っていこう!
23期生の記念撮影。お疲れ様でした!あと数ヶ月…頑張っていこう!
 お疲れ様会の模様。3年生は寝不足からか妙なテンションでした(笑)" target="_blank">卒業研究発表会が開催されました!
お疲れ様会の模様。3年生は寝不足からか妙なテンションでした(笑)" target="_blank">卒業研究発表会が開催されました!義肢装具学科では、本年度も進路を検討中の皆様にオープンキャンパスに加えて(本年度分は全て終了)、個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!
" target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!また、勉強はもちろんですが、学会参加のもう一つの醍醐味である卒業生との再会、臨床現場の方と就職・求人の状況や臨床実習のこと、学校教育について話ができたのも大きな収穫でした。
なお、本学科では毎年1回、学生全員で学会に参加しています。来年は日本義肢装具士教会(*リンク)の第19回学術大会が札幌、日本義肢装具学会(*リンク)の第28回学術大会が地元名古屋開催されるので、また学生全員を引率して参加する予定です。
 " target="_blank">日本義肢装具学会学術大会に参加してきました!
" target="_blank">日本義肢装具学会学術大会に参加してきました!各部署を回りながら説明を受け、また、担当の佐口さんには業界の歴史かについてもプレゼンを行って頂きました!参加した1年生も幅広く、しかも専門性の高い義肢装具士として仕事に携わる姿勢に感銘し、良い刺激を受けて帰ってきました。担当者の方をはじめ会社の皆様に感謝致します。お忙しいところ、貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。
 " target="_blank">㈱松本義肢製作所様に見学実習に行ってきました!
" target="_blank">㈱松本義肢製作所様に見学実習に行ってきました!■推薦入試(一次) 試験日 :平成23年10月8日(土) 出願期間:平成23年10月1日(土)~平成23年10月5日(水) 必着 ■一般入試(一次) 試験日 :平成23年10月15日(土) 出願期間:平成23年10月1日(土)~平成23年10月12日(水)必着
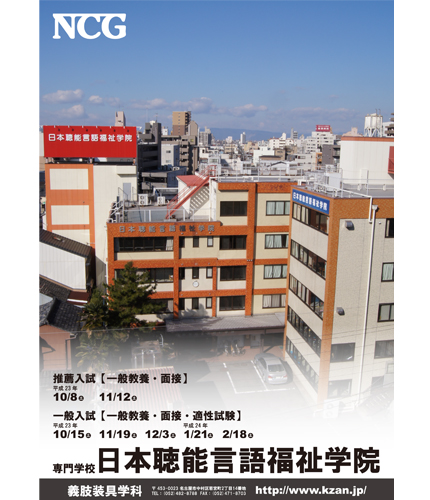 " target="_blank">いよいよ入試の出願受付がはじまります!
" target="_blank">いよいよ入試の出願受付がはじまります!義肢装具学科では、本年度も進路を検討中の皆様にオープンキャンパスに加えて(本年度分は全て終了)、個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施しています!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!
" target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!連載の読売新聞「魂~プロの背中」シリーズ「人工ボディーを究める」http://www.yomiuri.co.jp/osaka/feature/kansai1291012768085_02/index.htm
以前にも書きましたが、福島先生をはじめスタッフの皆さんの技術はもちろん、ひととの接し方、態度、人柄、そのすべてが、より良いものを提供するための“プロフェッショナリズム”に繋がっているんだと思いました。そんな先生方と年1回ですが、特別講義を通じて知り合えたこと、繋がりを持てていることを嬉しく思います! ということで、本件や特別講義のことなども書いて頂いている工房アルテのブログも合わせてリンク紹介です(*ブログリンク)!
 特別講義も取材されましたが記事には…お蔵入りって言うですかね(笑)" target="_blank">福島先生が読売新聞で特集連載されています!
特別講義も取材されましたが記事には…お蔵入りって言うですかね(笑)" target="_blank">福島先生が読売新聞で特集連載されています! OCの様子①足の型取りから製作までオリジナルを自分で作ります!
OCの様子①足の型取りから製作までオリジナルを自分で作ります!
 OCの様子②ものづくりは教員&学生スタッフがしっかりサポート!
OCの様子②ものづくりは教員&学生スタッフがしっかりサポート!
 OCの様子③緊張しながらも初めて使う特殊機械にドキドキです!
OCの様子③緊張しながらも初めて使う特殊機械にドキドキです!
 OCの様子④自分専用のインソールが完成…履き心地はいかに!?
OCの様子④自分専用のインソールが完成…履き心地はいかに!?
 当日は専任教員、学生スタッフ一同、楽しみにまっています!
当日は専任教員、学生スタッフ一同、楽しみにまっています!
 *作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!" target="_blank">8/20sat義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ!
*作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!" target="_blank">8/20sat義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ!義肢装具学科では、本年度も進路を検討中の皆様にオープンキャンパスに加えて、個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施します!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内!
" target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内! 若人は食欲旺盛!一人平均2杯~3杯くらいは食べていたのでは!?
若人は食欲旺盛!一人平均2杯~3杯くらいは食べていたのでは!?
 皆で食べると美味しいですね!でも、食事に夢中でほぼ無言でした(笑)
皆で食べると美味しいですね!でも、食事に夢中でほぼ無言でした(笑)
 どえりゃ~うみゃ~でいかんわ!て、大掃除日に寄って頂ければ…!?
どえりゃ~うみゃ~でいかんわ!て、大掃除日に寄って頂ければ…!?
 ということで、学生は夏休みですが、
義肢装具学科のオープンキャンパスは、7月23日(土)&8月20日(土)の夏休み期間中に2回開催されます!最終的な進路を決定するための良い情報が得られると思います。お申し込みは開催日前日の午後5時まで受け付けしますので、ご家族の方や友人と一緒でも構いませんので、この機会にぜひ参加してみてください。
教員、当日の学生スタッフ一同、楽しみにまっています!
*義肢装具学科のオープンキャンパスの詳細はコチラ" target="_blank">大掃除とカレーと夏休み!
ということで、学生は夏休みですが、
義肢装具学科のオープンキャンパスは、7月23日(土)&8月20日(土)の夏休み期間中に2回開催されます!最終的な進路を決定するための良い情報が得られると思います。お申し込みは開催日前日の午後5時まで受け付けしますので、ご家族の方や友人と一緒でも構いませんので、この機会にぜひ参加してみてください。
教員、当日の学生スタッフ一同、楽しみにまっています!
*義肢装具学科のオープンキャンパスの詳細はコチラ" target="_blank">大掃除とカレーと夏休み! 段々形になっていきます…もの作りのセンスが問われる作業です!
段々形になっていきます…もの作りのセンスが問われる作業です!
 ついに念願のブログ初登場!これで良かったですよね…(笑)
ついに念願のブログ初登場!これで良かったですよね…(笑)
 見るのと実際では…柔らかいものを形良く削る難しさを体感中!
見るのと実際では…柔らかいものを形良く削る難しさを体感中!
 恒例の記念写真!高山先生…後期は3年生も宜しくお願いします!
*写真を別ウィンドウで開く
" target="_blank">高山先生の特別講義が実施されました(2年生ver.)!
恒例の記念写真!高山先生…後期は3年生も宜しくお願いします!
*写真を別ウィンドウで開く
" target="_blank">高山先生の特別講義が実施されました(2年生ver.)! お待ちしてます!
" target="_blank">就職活動が始まっています&オープンキャンパスお知らせ
お待ちしてます!
" target="_blank">就職活動が始まっています&オープンキャンパスお知らせ“人工ボディ”は、先天性の障害、事故、病気により手足、胸、耳などの身体の一部を失ってしまった人々のために、各自の特徴に合わせて人体用のシリコーンで復元するもので、それは「失われた身体とともに心のケアもできる!」と、最も大事なのは、つくる前に相手の悩みをじっくり聴き、背景を察して、日常生活に合わせたものを考えること。その結果、技術・技能を磨くために真摯に接客(情報収集)や使用者&他機関との三者連携を続けていくことが、プロフェッショナルとしての醍醐味であるといった話を聞くことができました。
学生はもちろん、一緒に聴講させて頂いた自分自身も、義肢装具士を目指す・なってからの、「あたりまえが、あたりまえじゃない」こと、提供者側の自己満足でなく、様々なニーズに対して、より良いものを提供する“プロとしての姿勢”を学ばせて頂き、再認識させてました。あらめて、この仕事のやり甲斐、汗をかくことの大切さを感じることができたました。
福島先生、榎本先生、お忙しいところ本当にありがとうございました!
 接客から身につけた、生まれた技術について講義をして頂いています!
接客から身につけた、生まれた技術について講義をして頂いています!
 身振り+テンポの良い大阪弁で、懇切丁寧に指導をしてもらってます!
身振り+テンポの良い大阪弁で、懇切丁寧に指導をしてもらってます!
 福島先生に密着取材中の大阪読売新聞の記者の方もいました(右)
福島先生に密着取材中の大阪読売新聞の記者の方もいました(右)
 顔面の型を採っている様子。*呼吸はストローを加えてしています!
顔面の型を採っている様子。*呼吸はストローを加えてしています!
 特殊材料で(左)目、(中)顔右半分、(左)舌の型を採っている様子!
特殊材料で(左)目、(中)顔右半分、(左)舌の型を採っている様子!
 採型後…手の指紋、毛穴、皺(しわ)までくっきりリアルに採れます!
採型後…手の指紋、毛穴、皺(しわ)までくっきりリアルに採れます!
 記念撮影!*今年はプロカメラマンによる撮影なのでボケてません(笑)
*写真を別ウィンドウで開く
" target="_blank">人工ボディの特別講義が実施されました!
記念撮影!*今年はプロカメラマンによる撮影なのでボケてません(笑)
*写真を別ウィンドウで開く
" target="_blank">人工ボディの特別講義が実施されました! OCの様子①専用のインソール製作のために足型もちゃんと採ります!
OCの様子①専用のインソール製作のために足型もちゃんと採ります!
 OCの様子②ものづくりは教員&学生スタッフがしっかりサポート!
OCの様子②ものづくりは教員&学生スタッフがしっかりサポート!
 OCの様子③ものづくり中に現役学生に色々と聞いてみてください!
OCの様子③ものづくり中に現役学生に色々と聞いてみてください!
 OCの様子④ちゃんと自分の足に合うかドキドキしながら作ります!
OCの様子④ちゃんと自分の足に合うかドキドキしながら作ります!
 OCの様子⑤いろいろな材料や道具を使って工夫しながら作ります!
OCの様子⑤いろいろな材料や道具を使って工夫しながら作ります!
 OCの様子⑥同伴された保護者&友人の方も興味津々で見ています!
OCの様子⑥同伴された保護者&友人の方も興味津々で見ています!
 *作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!" target="_blank">義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ③
*作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!" target="_blank">義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ③学術大会のテーマ「義肢装具と新たな潮流」に関連した講演の聴講、商業展示での新製品の見聞が行え、また一般演題では昨年の卒業研究の全ての班が演題がエントリーして発表しました。数百人の義肢装具士の前での発表は緊張したことと思いますが、学内での研究でも「目的」がしっかりあり、実験方法が合致していれば、結果や考察は今後の継続研究、積み重ねによる課題でしかなく、聴講された方々からのアドバイスを受けるだけでも大きな収穫だったと思います(逆に質疑のないのは興味を持って頂けなかった…と、反省するくらいが丁度いいです)。ぜひとも日々の臨床活動は多忙と思いますが「義肢装具ユーザーのための研究」活動も地道に行っていって欲しいと思います!
残念ながら大阪名物たこ焼きは食べれなかったのですが、会場では臨床現場の方と就職・求人の状況や臨床実習のこと、学校教育について話ができ、また数多くの卒業生と再会できたのは何よりの収穫でした。
なお、本学科では毎年1回、学生全員で学会に参加しています。今秋には東京で第27回日本義肢装具学会学術大会(*リンク)が開催されるため、学生全員を引率して参加する予定です。
 学会会場であった国指定重要文化財の大阪市中央公会堂!
学会会場であった国指定重要文化財の大阪市中央公会堂!
 学院の展示ブースも出展しました!ココに卒業生が集まってきます(笑)
" target="_blank">大阪の学会に参加してきました!
学院の展示ブースも出展しました!ココに卒業生が集まってきます(笑)
" target="_blank">大阪の学会に参加してきました!
 学科説明:学科特色や入試対策に関しても詳しく説明をします!
学科説明:学科特色や入試対策に関しても詳しく説明をします!
 受験を検討中の方も、保護者の方々も多数付き添われています!
受験を検討中の方も、保護者の方々も多数付き添われています!
 ものづくり体験中は、教員&在校生がしっかりサポートします!
ものづくり体験中は、教員&在校生がしっかりサポートします!
 相談コーナーで在校生に学校生活の事等の疑問を聞いて下さい!
相談コーナーで在校生に学校生活の事等の疑問を聞いて下さい!
 *作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!" target="_blank">義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ②
*作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!" target="_blank">義肢装具学科オープンキャンパスのお知らせ②各部署を回りながら説明を受け、また、ご多忙中のところ川村慶社長には急遽ながら125分ものプレゼンを行って頂きました! 参加した1年生も今後の学校生活はもとより、幅広くしかも専門性の高い義肢装具士として仕事に携わる姿勢に感銘し、良い刺激を受けて帰ってきました。担当者の方をはじめ会社の皆様に感謝致します。お忙しいところ、貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。
 見学の様子:初めて見る現場の機械や設備にも驚き!
見学の様子:初めて見る現場の機械や設備にも驚き!
 川村慶社長の熱いプレゼンの様子!
川村慶社長の熱いプレゼンの様子!
PS.秘かでなく更新を楽しみにしてる慶社長のブログ(*リンク)の紹介! *行動指針+会社食堂&出張時などの飲食系のネタが好きです(笑) " target="_blank">大阪に見学実習に行ってきました!
 先生の説明を真剣に聞いています!
先生の説明を真剣に聞いています!
 初製作した装具の仮合わせに緊張…出来上がったら1日、履きます!
初製作した装具の仮合わせに緊張…出来上がったら1日、履きます!
 実際に歩いてみて適合を見極めます!" target="_blank">1年生の実習をレポート①!!
実際に歩いてみて適合を見極めます!" target="_blank">1年生の実習をレポート①!! 慣れない工具に苦労…でも、自分が履く靴の出来上がりが楽しみです!
慣れない工具に苦労…でも、自分が履く靴の出来上がりが楽しみです!
 途中までできました…最後まで集中力を切らさないよう頑張ろう!
" target="_blank">2年生の実習をレポート②!!
途中までできました…最後まで集中力を切らさないよう頑張ろう!
" target="_blank">2年生の実習をレポート②!! ソケット適合の様子…ココが合わないと元も子もありません!
ソケット適合の様子…ココが合わないと元も子もありません!
 ソケットだけでなく、義足構成部品の調整も大事な要素です!" target="_blank">3年生の実習をレポート②!!
ソケットだけでなく、義足構成部品の調整も大事な要素です!" target="_blank">3年生の実習をレポート②!! 報告会の様子②
…聴講する2年生も興味深く聞いて活発な質疑をしてくれました!
報告会の様子②
…聴講する2年生も興味深く聞いて活発な質疑をしてくれました!
 報告会の様子③
…第1班「下肢装具の足継手」に関する研究です!
報告会の様子③
…第1班「下肢装具の足継手」に関する研究です!
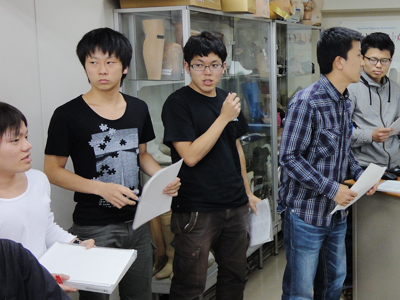 報告会の様子④
…第2班「体幹装具の選択方法」に関する研究です!
報告会の様子④
…第2班「体幹装具の選択方法」に関する研究です!
 報告会の様子⑤
…第3班「整形靴の製作方法」に関する研究です!
報告会の様子⑤
…第3班「整形靴の製作方法」に関する研究です!
 報告会の様子⑥
…第4班「義足ソケット内環境」に関する研究です!" target="_blank">卒研中間報告会が開催されました!
報告会の様子⑥
…第4班「義足ソケット内環境」に関する研究です!" target="_blank">卒研中間報告会が開催されました!昨年参加して下さった方のコメント(一部抜粋) ・学校の内容がよく分かり、雰囲気も良いと思いました。 ・貴校を知る上で大変参考になりました。やってみて面白かった。 ・授業の体験ができ、学校の特徴が分かりやすかった。 ・生徒の人達ともいろいろな話ができてとても良かったです。 ・簡易ながらも仕事の一端を体験できて、さらに興味が湧きました。 ・学生の方や教員の方が、やさしく教えていただき楽しめました。
参加して頂く皆さんには、実際に授業で使用している工作機械や材料を使い、簡単なインソール(靴の中に入れる中敷きのようなもの)を作って頂きます。教員による模擬授業に加えて、モノづくりを体験することで義肢装具士の仕事の楽しさ、奥深さをしっかりと理解することができます。もちろん、参加費用は無料、作ったインソールはオープンキャンパスの記念にお持ち帰り頂けます!ぜひ、この機会に教員や学生スタッフと一緒に模擬授業の体験してみませんか?


 *作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)まで
に行ってください!
" target="_blank">模擬授業でインソールをつくろう!
*作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)まで
に行ってください!
" target="_blank">模擬授業でインソールをつくろう!義肢装具学科では、本年度も進路を検討中の皆様にオープンキャンパス(6,7,8月に各1回)に加えて、個別での学校見学、義肢装具製作施設の見学ツアーを実施します!
あなたのご都合の良い時間を利用して、義肢装具士が実際に働いている職場を見学してみませんか?本校の専任教員が義肢装具製作施設まで案内します!見学日や集合時間などは個別に調整させていただきますので、参加ご希望の方は担当者(義肢装具学科教務主任:中川)までご連絡ください(*当日はご本人だけでなく、保護者の皆様の同伴も可能です)。
見学日時 : 個別に調整をいたします(日曜日以外)。 集合場所 : 本校(日本聴能言語福祉学院) *学校に来て頂き、そこから専用車で施設まで送迎します。 見学施設 : ㈱松本義肢製作所(愛知県小牧市 *ホームページ) 所要時間 : 約2~3時間(見学1時間+移動1時間30分)。 その他等 : 参加費は不要です(本校までの交通は自己負担願います)。
 " target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内②!
" target="_blank">義肢装具製作会社見学ツアーのご案内②! お待ちしてます!
" target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ
お待ちしてます!
" target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ (2年生)ミシンだって使いこなします!
(2年生)ミシンだって使いこなします!
 (3年生)義足ソケットの樹脂注型中!
(3年生)義足ソケットの樹脂注型中!
 (3年生)義足の組み立て作業の確認中!
" target="_blank">2,3年生の実習をレポート①!!
(3年生)義足の組み立て作業の確認中!
" target="_blank">2,3年生の実習をレポート①!!補聴言語学科 87.5 %
全国平均 69.3% 聴能は昨年度に引き続き100%で全員合格、 補聴は昨年度よりも良い結果と、 両学科とも好成績を収めることができました。 苦しい国家試験勉強を乗り切って、 見事STへの入り口に立てた聴能25期・補聴17期のみなさん、 本当におめでとう! そして、いよいよ、新しいスタートをきる時がきましたね。 いつもいつも言っていましたが、スタートはここから。 これから始まるST人生、 対象者のみなさんにより良い臨床を提供できる専門家・臨床家として、 日々努力を重ねてがんばってください。 (ちょっと疲れたり、迷ったときは、学院に相談に(遊びに?)きてくださいね。) 教員一同 " target="_blank">速報!! ST国家試験合格発表ありました!
 義肢装具学科授与式の様子…各々に髙見学科長より卒業証書の授与
義肢装具学科授与式の様子…各々に髙見学科長より卒業証書の授与
 式後の記念撮影①…艶やかな着物部隊(笑)
式後の記念撮影①…艶やかな着物部隊(笑)
 式後の記念撮影④…全員で!
" target="_blank">平成22年度卒業式&義肢装具学科卒業証書授与式!
式後の記念撮影④…全員で!
" target="_blank">平成22年度卒業式&義肢装具学科卒業証書授与式! 日聴応援団の様子…決して普段着ではありません(笑)" target="_blank">壮行会&国家試験が終わりました!
日聴応援団の様子…決して普段着ではありません(笑)" target="_blank">壮行会&国家試験が終わりました! 発表&受賞後の記念撮影!おめでとうございました!
発表&受賞後の記念撮影!おめでとうございました!
 全学年の学生が揃って、受賞の報告会を催しました!
全学年の学生が揃って、受賞の報告会を催しました!
 中川教務主任(代読)による表彰状の授与(再び)!
中川教務主任(代読)による表彰状の授与(再び)!
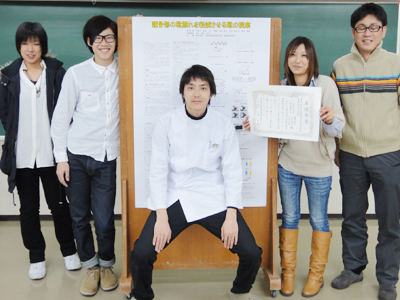 卒研4班と指導教員の芥川先生(中央)で記念撮影!
卒研4班と指導教員の芥川先生(中央)で記念撮影!
なお、毎年、恒例となっている日本義肢装具士協会が主催する学術大会での卒業研究発表を本年度も継続して行います。来る平成23年6月18日・19日に開催される「第18回日本義肢装具士協会学術大会(大阪)*リンク」に一般演題として、その他すべての班のエントリーが済んでおり、発表予定となっています!
" target="_blank">また×5!!!!!の5年連続で卒研が受賞!
そして、毎年この時期になると、一昨年や去年・一昨年の卒業生(3年生と被っていた期生)が受験生のために合格グッズ(合格祈願バージョンのお菓子や滋養強壮ドリンク、今年は消毒液や目薬なども)を差し入れてくれ、もう一踏ん張りの“元気”を貰っています。こういった心遣いには「良い伝統が受け継がれているな~教員やっていて良かった」と、実感する一幕でもあります(教員分もあれば言うことありません(笑)。差し入れをしてくれた卒業生の皆さん、本当にありがとうございました!
「この学校・学科のウリは何ですか?」と、よく学校見学の方に聞かれるのですが、授業カリキュラム、就職率や国家試験合格率といった実績はもちろん、それをサポートするコノ“ひととひとの繋がりのある温かい環境”こそが日聴・義肢装具学科のカラー、一番の誇りだと思っています!
また、2年生は週に3日、下腿義足&長下肢装具&上腕義手のハードスケジュールで実習、1年生は基本工作論を年末に終えて、初めての専門科目の実習である体幹装具がスタートしているため、学科全体の雰囲気はほど良い緊張感に包まれています。
しかし、ここ数週間、季節性のインフルエンザの流行、風邪などで体調を崩す学生が多くなってきているので、皆さん体調管理・自己管理に務めるのも大切なことなのでしっかり手荒い&うがいをして対策して下さいね!
 安心環境で!?自習する3年生!!チームワークが合格の秘訣です!!
安心環境で!?自習する3年生!!チームワークが合格の秘訣です!!
ということで、 本年度の入学試験も残り1回となりました(第5次一般入試)。出願期間は1月31日~2月14日・試験日は「2月18日(金)」となっていますので、受験をされる方・検討中の方は、今年最後のチャンスなので宜しくお願いします。

また、個別での学校見学は随時受付ていますので、来年に受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒でも構いませんので、お気軽に申し込みをして頂き情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。
 " target="_blank">心温まる差し入れ…国試&進級!?まであと僅か!!
" target="_blank">心温まる差し入れ…国試&進級!?まであと僅か!! 佳作…義肢ダルマだそうで…ちっとも義肢っぽくないセンスに(笑)
佳作…義肢ダルマだそうで…ちっとも義肢っぽくないセンスに(笑)
 入選…やけに中途半端に終わってしまったカマクラ風かまくら(笑)" target="_blank">何年かぶりの大雪で休講になりました!
入選…やけに中途半端に終わってしまったカマクラ風かまくら(笑)" target="_blank">何年かぶりの大雪で休講になりました! お待ちしてます!
" target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ★聴能言語(2年コース)★
お待ちしてます!
" target="_blank">オープンキャンパスのお知らせ★聴能言語(2年コース)★ ・・・そんなこんなで無事に会は始まりました。
鍋を囲みながら和やかに進行。
折しもこの日、1年生は、2月に始まる見学実習のオリエンテーションがあったばかり。
「実習」をより現実的なものとしてとらえられるようになってきた、
そんな中でのこの会でしたから、
先輩たちの実習体験談を聞く1年生たちは、みな真剣な顔つきでした。
また後輩にアドバイスを送る2年生は、
実習壮行会でチラホラみられた不安気な表情とは一転、頼もしい顔つきに。
実習を無事に終え、
ここからは国家試験に向けてスパートするのみ!ですね。
" target="_blank">『実習おつかれさま会』
・・・そんなこんなで無事に会は始まりました。
鍋を囲みながら和やかに進行。
折しもこの日、1年生は、2月に始まる見学実習のオリエンテーションがあったばかり。
「実習」をより現実的なものとしてとらえられるようになってきた、
そんな中でのこの会でしたから、
先輩たちの実習体験談を聞く1年生たちは、みな真剣な顔つきでした。
また後輩にアドバイスを送る2年生は、
実習壮行会でチラホラみられた不安気な表情とは一転、頼もしい顔つきに。
実習を無事に終え、
ここからは国家試験に向けてスパートするのみ!ですね。
" target="_blank">『実習おつかれさま会』ということで、 本年度の入学試験も残り2回となりました(4次&5次一般入試)。4次の出願期間は1月4日~17日・試験日は1月21日(金)となっていますので、受験をされる方・検討中の方は宜しくお願いします。

また、個別での学校見学は随時受付ていますので、今年受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(受験当該学年ではない中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒にお気軽に申し込みをして頂き、情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。
 " target="_blank">新年明けましておめでとうございます!
" target="_blank">新年明けましておめでとうございます! 空腹&早くお代わりしたいために、ほぼ無言で食してました(笑)
空腹&早くお代わりしたいために、ほぼ無言で食してました(笑)
 満面の笑みで、一人平均2杯以上はモリモリ食べていました!
満面の笑みで、一人平均2杯以上はモリモリ食べていました!
ということで、 本年度の入学試験も残り2回となりました(4次&5次一般入試)。4次の出願期間は1月4日~となっていますので宜しくお願いします。

また、冬休み中にも個別での学校見学は随時受付ていますので、今年受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(受験当該学年ではない中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒にお気軽に申し込みをして頂き、情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。
 " target="_blank">大掃除とカレーと冬休み!
" target="_blank">大掃除とカレーと冬休み!また、同日は姉妹校の日本医療福祉専門学校の作業療法学科の学生さん達がが見学に訪れ、本科の2年生も何故か(笑)…いつもより張り切って実習&説明をしていました!
 筋電義手の適合チェックポイントのデモンストレーション中!
筋電義手の適合チェックポイントのデモンストレーション中!
 筋電義手が、きちんと制御されて動くかどうかを確認中!
筋電義手が、きちんと制御されて動くかどうかを確認中!
 最終的に、使用者の方がコントロールできるかを評価中!
最終的に、使用者の方がコントロールできるかを評価中!
 見学をしている作業療法学科の学生さんも真剣そのもの!" target="_blank">筋電義手の適合評価が行われました!
見学をしている作業療法学科の学生さんも真剣そのもの!" target="_blank">筋電義手の適合評価が行われました!より使用者の多様なニーズに応えられる義肢装具士(PO)になるために、これまでの実習授業における靴の製作技術に加えて、オリジナルの靴デザインが施せるノウハウを学ぶことは、靴型装具を装具としてだけでなく、ファッションの一部としても提供できる技術はPOとしての幅も広がり非常に有益なことです。
また、授業では眞殿先生の経験と技術の教授はもとより、何とか若い人達に「使用者の気持ちに応える技術」を伝えたいという熱い気持ちと、関西人?弁?ならではのテンポの良い進行、明るい雰囲気の中で学べたことは、なによりの財産になったと思います。眞殿先生、毎年のことながら、遠路からお越し頂きありがとうございました!
 デモンストレーションの手業の凄さに沈黙!
デモンストレーションの手業の凄さに沈黙!
 学生各自がオリジナルの靴をデザインしてます!
学生各自がオリジナルの靴をデザインしてます!
 マンツーマンでの親切丁寧な指導に学生真剣そのもの!
マンツーマンでの親切丁寧な指導に学生真剣そのもの!
 各自がデザインした型紙を持って集合写真!" target="_blank">靴型装具の特別講義が実施されました!
各自がデザインした型紙を持って集合写真!" target="_blank">靴型装具の特別講義が実施されました!姿勢を保持することの重要性を理解するため実例を交えながらの講義に加え、採型機器によるシミュレーションと採型、また、様々な車いすの特徴を理解するための試乗、といった幅広い内容を実体験することによって、より実践に即した学習ができたと思います。
 大阪人二人の話はテンポ良く、情熱を持って講演して頂けました!
大阪人二人の話はテンポ良く、情熱を持って講演して頂けました!
 特殊な採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中!
特殊な採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中!
 シミュレーション後に陽性モデル作成のためにギプスを貼り付け中!
シミュレーション後に陽性モデル作成のためにギプスを貼り付け中!
 車いすの選び方、採寸法、収納法など色んな機能の説明を聞いてます!
車いすの選び方、採寸法、収納法など色んな機能の説明を聞いてます!
 車いすの試乗で利用者の視点から考察…後ろ姿に哀愁感が大で(笑)" target="_blank">座位保持装置の講義が実施されました!
車いすの試乗で利用者の視点から考察…後ろ姿に哀愁感が大で(笑)" target="_blank">座位保持装置の講義が実施されました! 緊張しながらも大きな声で聞き取りやすくプレゼンしています!
緊張しながらも大きな声で聞き取りやすくプレゼンしています!
 質疑応答では来賓の方からも貴重なアドバイスを沢山頂けました!
質疑応答では来賓の方からも貴重なアドバイスを沢山頂けました!
 研究で作った製作物も展示!合格祈願セットはくれぐれもなくさ…
研究で作った製作物も展示!合格祈願セットはくれぐれもなくさ…
 22期生の記念撮影。お疲れ様でした!あと数ヶ月…頑張っていこう!
22期生の記念撮影。お疲れ様でした!あと数ヶ月…頑張っていこう!
 打ち上げの模様。3年生は寝不足からか妙なテンションでした(笑)" target="_blank">卒業研究発表会が開催されました!
打ち上げの模様。3年生は寝不足からか妙なテンションでした(笑)" target="_blank">卒業研究発表会が開催されました! ずらり揃った芸術品の数々!
ずらり揃った芸術品の数々!
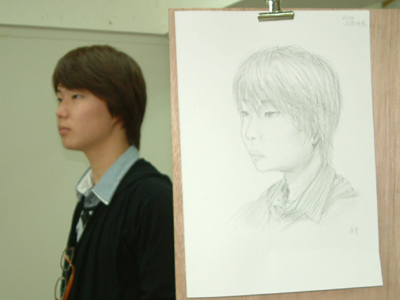 見る人がみたら分かるはず(笑)①隠れた才能ですね!!
見る人がみたら分かるはず(笑)①隠れた才能ですね!!
 見る人がみたら分かるはず(笑)②隠れてていい??才能はないですね!?" target="_blank">美術で芸術性を磨く…秋!!
見る人がみたら分かるはず(笑)②隠れてていい??才能はないですね!?" target="_blank">美術で芸術性を磨く…秋!!
 ↑ 人工内耳です ↑
↑ 人工内耳です ↑
 マッピングの様子
説明会では、
人工内耳の手術を手がけていらっしゃる
名古屋大学医学部付属病院の曾根三千彦先生の講演とともに、
私の方では人工内耳の仕組みや言語聴覚士が行うリハビリについて、
詳しい説明を行います。
また、当事者の方たちの声も聞くことができます。
******************************************************************************
松田先生は、
当学院の講義でも毎回分かりやすく人工内耳や臨床のお話をして下さいますので、説明会でも貴重なお話が聴けることでしょう。
聴覚障害や人工内耳などに興味がある方は、
是非足を運んでみてはいかがでしょうか。
" target="_blank">若宮診療所の松田先生が講演を行います!
マッピングの様子
説明会では、
人工内耳の手術を手がけていらっしゃる
名古屋大学医学部付属病院の曾根三千彦先生の講演とともに、
私の方では人工内耳の仕組みや言語聴覚士が行うリハビリについて、
詳しい説明を行います。
また、当事者の方たちの声も聞くことができます。
******************************************************************************
松田先生は、
当学院の講義でも毎回分かりやすく人工内耳や臨床のお話をして下さいますので、説明会でも貴重なお話が聴けることでしょう。
聴覚障害や人工内耳などに興味がある方は、
是非足を運んでみてはいかがでしょうか。
" target="_blank">若宮診療所の松田先生が講演を行います! 段々形になっていきます…もの作りのセンスが問われる作業です!
段々形になっていきます…もの作りのセンスが問われる作業です!
 髙見学科長も混ざって、恒例の記念写真です!お疲れ様でした!" target="_blank">高山先生の特別講義が実施されました!
髙見学科長も混ざって、恒例の記念写真です!お疲れ様でした!" target="_blank">高山先生の特別講義が実施されました!各部署を回りながら説明を受け、また、担当の藤井さんには業界の歴史かについてもプレゼンを行って頂きました!参加した1年生も幅広く、しかも専門性の高い義肢装具士として仕事に携わる姿勢に感銘し、良い刺激を受けて帰ってきました。担当者の方をはじめ会社の皆様に感謝致します。お忙しいところ、貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。
 説明の様子*担当の藤井さんは本学科OB(8期生)です!
説明の様子*担当の藤井さんは本学科OB(8期生)です!
 見学の様子*手作業によるものづくりの奥深さを再認識!" target="_blank">会社見学に行ってきました②!
見学の様子*手作業によるものづくりの奥深さを再認識!" target="_blank">会社見学に行ってきました②! 企業説明会の様子" target="_blank">臨床実習報告会と企業説明会が開催されました!
企業説明会の様子" target="_blank">臨床実習報告会と企業説明会が開催されました!
参加して頂く皆さんには、実際に授業で使用している工作機械や材料を使い、簡単なインソール(靴の中に入れる中敷きのようなもの)を作って頂きます。教員による模擬授業に加えて、モノづくりを体験することで義肢装具士の仕事の楽しさ、奥深さをしっかりと理解することができます。もちろん、参加費用は無料、作ったインソールはオープンキャンパスの記念にお持ち帰り頂けます!ぜひ、この機会に教員や学生スタッフと一緒に模擬授業の体験してみませんか?
 *作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)まで
に行ってください!
" target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう③!
*作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)まで
に行ってください!
" target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう③!第1回目に参加して下さった方のコメント(一部抜粋) ・インソール作りがとても楽しかったです。 ・義肢装具士になりたい気持ちが強くなりました。 ・生徒の人達ともいろいろな話ができてとても良かったです。 ・色々な質問に答えていただき不安な点が解消できました。 ・学生の方や教員の方が、やさしく教えてくれ魅力を感じました。 ・実体験でき進路を熟考する上で貴重な体験ができよかったです。
参加して頂く皆さんには、実際に授業で使用している工作機械や材料を使い、簡単なインソール(靴の中に入れる中敷きのようなもの)を作って頂きます。教員による模擬授業に加えて、モノづくりを体験することで義肢装具士の仕事の楽しさ、奥深さをしっかりと理解することができます。もちろん、参加費用は無料、作ったインソールはオープンキャンパスの記念にお持ち帰り頂けます!ぜひ、この機会に教員や学生スタッフと一緒に模擬授業の体験してみませんか?
 模擬授業のインソール作りの説明中!
模擬授業のインソール作りの説明中!
 実際の製作工程をに皆さんが体験中!
実際の製作工程をに皆さんが体験中!
 自分の靴に合わせるのも一苦労です!
自分の靴に合わせるのも一苦労です!
 *作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)まで
に行ってください!
" target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう②!
*作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)まで
に行ってください!
" target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう②!なお、上記日程でご都合が合わない方は、 個別の学校見学が可能です。 専任教員が細かな質問まで丁寧に対応いたします。 お申込みはメール st@kzan.jp か お電話 0120-112-436(フリーダイヤル) にてお気軽にどうぞ。 お待ちしています! " target="_blank">オープンキャンパス開催報告
 大量のご飯とカレー!何杯でも満足いくまでお代わり可能です!!
大量のご飯とカレー!何杯でも満足いくまでお代わり可能です!! 若人は食欲旺盛!一人平均2杯~3杯くらいは食べていたのでは!?
若人は食欲旺盛!一人平均2杯~3杯くらいは食べていたのでは!?
 皆で食べると美味しいですね!でも、食事に夢中でほぼ無言でした(笑)
皆で食べると美味しいですね!でも、食事に夢中でほぼ無言でした(笑)
 どえりゃ~うみゃ~がね!て、大掃除日に学校に寄って頂ければ…!?
どえりゃ~うみゃ~がね!て、大掃除日に学校に寄って頂ければ…!?
ということで、 学生は夏休みですが7&8月の学科行事には以下があります!
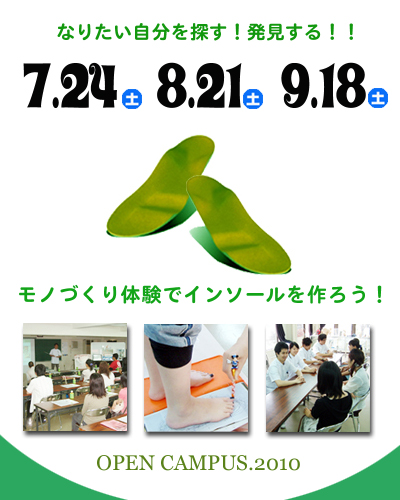
 *作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)まで
に行ってください!
*作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)まで
に行ってください!
オープンキャンパスは、前日までに参加申込みをして頂ければ構いませんので、今年、受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(受験当該学年ではない中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒にお気軽に参加をして頂き、色々な情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。 教員、当日の学生スタッフ一同、楽しみにまっています! (*義肢装具学科のオープンキャンパスの詳細はコチラ)" target="_blank">大掃除とカレーと夏休み!
各部署を回りながら説明を受け、また、佐熊さんには【ウミガメ義肢プロジェクト*リンク(産経新聞HD)】についてもプレゼンを行って頂きました! 参加した1年生も今後の学校生活はもとより、幅広くしかも専門性の高い義肢装具士として仕事に携わる姿勢に感銘し、良い刺激を受けて帰ってきました。担当者の方をはじめ会社の皆様に感謝致します。お忙しいところ、貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。
 見学の様子①義肢や装具だけでなく福祉機器も沢山!
見学の様子①義肢や装具だけでなく福祉機器も沢山!
 見学の様子②初めて見る現場の機械や設備にも驚き!
見学の様子②初めて見る現場の機械や設備にも驚き!
 説明の様子*担当の佐熊さんは本学科OB(8期生)です!
説明の様子*担当の佐熊さんは本学科OB(8期生)です!
PS.秘かに更新を楽しみにしてる川村慶社長ブログ(*リンク)の紹介! *本日のDMPおはようメッセージ!&会社食堂ネタが好きです(笑)" target="_blank">会社見学に行ってきました(大阪)!
“人工ボディ”は、先天性の障害、事故、病気により手足、胸、耳などの身体の一部を失ってしまった人々のために、各自の特徴に合わせて人体用のシリコーンで復元するもので、それは「失われた身体とともに心のケアもできる。」と、最も大事なのは、つくる前に相手の悩みをじっくり聴き、背景を察して、日常生活に合わせたものを考えること。その結果、技術・技能を磨くために真摯に接客(情報収集)や使用者&他機関との三者連携を続けていくことが、プロフェッショナルとしての醍醐味であるといった話を聞くことができました。
学生はもちろん、一緒に聴講させて頂いた自分自身も、義肢装具士を目指す・なってからの、「あたりまえが、あたりまえじゃない」こと、提供者側の自己満足でなく、より良いものを提供する“プロとしての姿勢”を学ばせて頂きました。あらめて、この仕事のやり甲斐、汗をかくことの大切さを感じることができたました。
福島先生、中郡先生、お忙しいところ誠にありがとうございました!
 接客から身につけた、生まれた技術について講義をして頂いています!
接客から身につけた、生まれた技術について講義をして頂いています!
 顔面の型を採っている様子。*呼吸はストローでしています!
顔面の型を採っている様子。*呼吸はストローでしています!
 手の型を採っている様子。*取り外すのにも工夫がいります!
手の型を採っている様子。*取り外すのにも工夫がいります!
 指の型を採っている様子。*つめ、指紋までくっきり採れます!
指の型を採っている様子。*つめ、指紋までくっきり採れます!
 最後に記念撮影!*2名ほど裸なのはちゃんと理由があります(笑)
最後に記念撮影!*2名ほど裸なのはちゃんと理由があります(笑)
PS.来年こそはのご当地・風来坊…教務一同楽しみにしています!! 義手担当教員:K't" target="_blank">人工ボディの特別講義が実施されました!
実習先での指導者の先生やスタッフの方々、なにより患者様、 そのご家族とのきっと一生忘れられないであろう「出会い」に乾杯! " target="_blank">臨床実習が始まります
昨年参加して下さった方のコメント(一部抜粋) ・学校の内容がよく分かり、雰囲気も良いと思いました。 ・貴校を知る上で大変参考になりました。やってみて面白かった。 ・授業の体験ができ、学校の特徴が分かりやすかった。 ・生徒の人達ともいろいろな話ができてとても良かったです。 ・簡易ながらも仕事の一端を体験できて、さらに興味が湧きました。 ・学生の方や教員の方が、やさしく教えていただき楽しめました。
参加して頂く皆さんには、実際に授業で使用している工作機械や材料を使い、簡単なインソール(靴の中に入れる中敷きのようなもの)を作って頂きます。教員による模擬授業に加えて、モノづくりを体験することで義肢装具士の仕事の楽しさ、奥深さをしっかりと理解することができます。もちろん、参加費用は無料、作ったインソールはオープンキャンパスの記念にお持ち帰り頂けます!ぜひ、この機会に教員や学生スタッフと一緒に模擬授業の体験してみませんか?

 *作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)まで
に行ってください!
" target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう!
*作ったインソールを装着するため、当日は中敷きの取り外しが可能な
運動靴を履いて&服装も軽装でお越し下さい!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)まで
に行ってください!
" target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう! 見学授業にきている作業療法学科の学生さんの前で良い格好を…!?" target="_blank">3年生の臨床実習がスタート!
見学授業にきている作業療法学科の学生さんの前で良い格好を…!?" target="_blank">3年生の臨床実習がスタート!そんな都筑先生の講義を受講した学生の感想です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「都筑先生」といえば、ことあるごとに名前を耳にする伝説の先生。 始まってみると、「吃音」の講義ではあるものの、 これまでに学んだすべての科目の知識が必要とされる、 まさに「STのSTによるSTのための講義」。 軽快に冗談を飛ばしながらも、 強い科学性と明快な論理が根底に流れる解説で 一つ一つの知識が連なっていき、 自らの不勉強を実感するとともに新しい考え方に気づかされました。 そんな先生とのお食事会、 「貴重な機会で光栄!」と思う反面、 「そんなすごい先生とどんな話をすれば…」という不安もありました。 ですが、講義を離れると本当に気さくに話してくださいました。 いきなり笑顔で「発語失行の一貫性とは何か?」と訊かれたときは焦りましたが…。 その中でも印象的だったのは、 「この学院で学んだ学生がいつか自分のところにやって来て、 (研究内容について)論争を挑んでくれるのを待っている」 とおっしゃっていたこと。 「自分がその学生になります!」 と言えるほどの自信はまだありませんが、 少しでも先生に近づけるよう、仲間と切磋琢磨する毎日です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 聴能言語学科2年生 " target="_blank">集中講義がありました-「吃音」-
 報告会の様子②
…分かりやすく伝える手法を学ぶのも卒研の大事なポイントです!
報告会の様子②
…分かりやすく伝える手法を学ぶのも卒研の大事なポイントです!
 報告会の様子③
…問題解決のため今後も汗をかきエビデンスを追求して下さい!" target="_blank">卒研中間報告会が開催されました!
報告会の様子③
…問題解決のため今後も汗をかきエビデンスを追求して下さい!" target="_blank">卒研中間報告会が開催されました!" target="_blank">三校合同OPEN CAMPUSのお知らせ②
 修正点を中川先生から指導を受け適合に向けての微?調整をします!
修正点を中川先生から指導を受け適合に向けての微?調整をします!
 まだ1ヶ月弱ですが、すでに専用の機械も使いこなしているはず!?" target="_blank">1年生の製作実習をレポート!!
まだ1ヶ月弱ですが、すでに専用の機械も使いこなしているはず!?" target="_blank">1年生の製作実習をレポート!!以下は、講義を受けた学生の感想です。
熊倉先生の器質性構音障害の集中講義では、様々ながん治療後の患者様のご様子を実際のVTRで見せていただくことができました。 私が特に印象に残っているのは、上顎がんの患者様の映像で、手術によって顔を半分失った状態での構音の様子は衝撃的でした。しかし同時に、そのような患者様でも、エピテーゼを使用したりリハビリを行ったりすることで、構音は改善するということがよくわかりました。 その後参加させていただいた食事会では、高名な先生とのお食事ということで、大変緊張していたのですが、会はとても和やかな雰囲気で、授業中には聞くことのできない先生の思い出などもお聞きすることができました。中でも先生が「初めて受け持った患者様の名前は忘れない」と仰られていたことは特に印象に残っています。先生のお人柄に触れ、翌日の講義がより楽しみになりました。参加できて本当に良かったと思います。
聴能言語学科 2年生 " target="_blank">集中講義がありました~器質性構音障害~
 先生によるデモンストレーションを真剣に視聴する3年生!
そのデジタルな風景に時代の流れを感じているこの頃です…" target="_blank">春。新年度がスタートしています③
先生によるデモンストレーションを真剣に視聴する3年生!
そのデジタルな風景に時代の流れを感じているこの頃です…" target="_blank">春。新年度がスタートしています③
また、今年は姉妹校の中部リハビリテーション専門学校(理学療法士)と 中部看護専門学校(看護師)とのコラボレーション企画、3校(4職種)の 合同オープンキャンパスも開催されます!
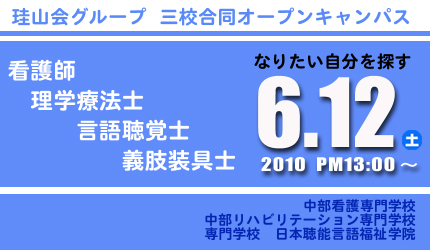
" target="_blank">平成22年度オープンキャンパスのお知らせ!
それはなんと!「フルーツ大福」!
えっっ!? 作ったの!?
お菓子作りがいい気分転換になるんだとか・・。 普段の彼からはちょっと想像できない趣味に 教員一同おどろきつつ、 おいしく頂きました。 " target="_blank">春。新年度がスタートしています②
 新任紹介で教育に対する熱血の挨拶をする芥川先生!" target="_blank">平成22年度がスタートしました!
新任紹介で教育に対する熱血の挨拶をする芥川先生!" target="_blank">平成22年度がスタートしました!自己採点での予想で確信はしていたものの、本発表があるまではナニカト不安が残るものでしたが、第21期生をはじめ保護者の皆様方、本当におめでとうございました。そして、本学科非常勤講師の先生方、臨床実習先の指導者の皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
全国平均は未だ発表されていませんが、4年連続の全員合格は当該受験生の努力の賜であり、3年間の学生生活の一つの目標達成ができたことは素晴らしいことだと思います。22期生の後輩の皆さん、春からプレッシャーはたっぷりかかりますが、気合いと気合いと気合いで(笑)、来年も頑張って素敵な伝統を継承していきましょう!
21期生の卒業生諸君、これからが本番、スタートです。これからも今まで以上に頑張って「義肢装具士」を磨いていってください。
 " target="_blank">義肢装具士国家試験に全員合格しました!!
" target="_blank">義肢装具士国家試験に全員合格しました!! 小児の嚥下訓練をしている様子
小児の嚥下訓練をしている様子 クラスで絵カード取りゲームをしている様子
クラスで絵カード取りゲームをしている様子今後も続報が届きましたらご紹介いたします。" target="_blank">海外で活躍する卒業生②
 卒業証書授与式の模様です!
卒業証書授与式の模様です!
 卒業記念パーティー会場の様子です!
卒業記念パーティー会場の様子です!
 一番お世話になった保護者の方へ感謝の花束を贈呈!
一番お世話になった保護者の方へ感謝の花束を贈呈!
 2次会もアットホームな雰囲気で大いに盛り上がりました!" target="_blank">卒業式&謝恩会が行われました!
2次会もアットホームな雰囲気で大いに盛り上がりました!" target="_blank">卒業式&謝恩会が行われました! 職員+在校生+他の皆様方でお見送りです!
職員+在校生+他の皆様方でお見送りです!
 雨にも負けず!に、いざ受験地へ出発です!" target="_blank">壮行会&国家試験が終わりました!
雨にも負けず!に、いざ受験地へ出発です!" target="_blank">壮行会&国家試験が終わりました!より使用者の多様なニーズに応えられる義肢装具士(PO)になるために、これまでの実習授業における靴の製作技術に加えて、オリジナルの靴デザインが施せるノウハウを学ぶことは、靴型装具を装具としてだけでなく、ファッションの一部としても提供できる技術はPOとしての幅も広がり非常に有益なことです。
また、授業では眞殿先生の経験と技術の教授はもとより、何とか若い人達に「使用者の気持ちに応える技術」を伝えたいという熱い気持ちと、関西人?弁?ならではのテンポの良い進行、明るい雰囲気の中で学べたことは、なによりの財産になったと思います。眞殿先生、毎年のことながら、遠路からお越し頂きありがとうございました!
 靴は履いて、立って歩いて使うものだから!
靴は履いて、立って歩いて使うものだから!
 もちろん靴の機能、履き心地はありきです!
もちろん靴の機能、履き心地はありきです!
 デモンストレーションの手業の凄さに沈黙!
デモンストレーションの手業の凄さに沈黙!
 オリジナリティー溢れるデザインを考え中!
オリジナリティー溢れるデザインを考え中!
 各自がデザインした型紙を持って集合写真!" target="_blank">靴型装具の特別講義が実施されました!
各自がデザインした型紙を持って集合写真!" target="_blank">靴型装具の特別講義が実施されました! ポスター確認とプレゼンの準備、予行演習を国試勉強の合間に!!
ポスター確認とプレゼンの準備、予行演習を国試勉強の合間に!!
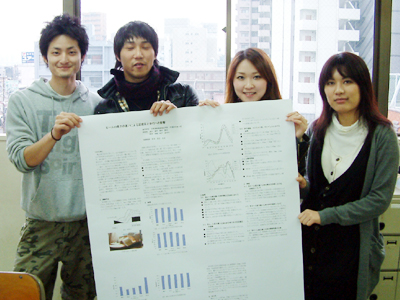 発表前の準備完了…!?班員揃っての記念撮影!!
発表前の準備完了…!?班員揃っての記念撮影!!
 発表&表彰式後の記念撮影!4班の皆さんおめでとうございました!
発表&表彰式後の記念撮影!4班の皆さんおめでとうございました!
なお、毎年、恒例となっている日本義肢装具士協会が主催する学術大会での卒業研究発表を本年度も継続して行います。来る平成22年7月17日・18日に開催される「第17回日本義肢装具士協会学術大会」に一般演題として第1、2、3、5班のエントリーが済んでおり発表予定となっています!
PS. 先日、2年生の卒業研究テーマ検討会(2年次の年明けからテーマ検討、班編制を行って3年生の4月から研究計画に則り実験などをスタートさせます)に、ふと突然多くの3年生の有志が参加してくれ沢山のアドバイスをしてくれました。その後、2年生の教室に残って、経験談や卒研成功の秘訣?等の相談にのっている姿、光景は嬉しくも&頼もしくもありました!
 授業でもルールでもないのに自然に先輩・後輩の間でディスカッション!
授業でもルールでもないのに自然に先輩・後輩の間でディスカッション!
 PS-2.
もちろん、1年生も初めてのセミナーの準備でちゃんと?大忙しです(笑)
" target="_blank">また×4の4年連続で卒研が受賞!
PS-2.
もちろん、1年生も初めてのセミナーの準備でちゃんと?大忙しです(笑)
" target="_blank">また×4の4年連続で卒研が受賞!そして、毎年この時期になると、一昨年や去年の卒業生(3年生と被っていた期生)が受験生のために合格グッズ(合格祈願バージョンのお菓子や滋養強壮ドリンクなど)を差し入れてくれ、もう一踏ん張りの“元気”を貰っています。こういった心遣いは心温まり「良い伝統が受け継がれているな~教員やっていて良かった。」と、実感する一幕でもあります(教員分もあれば言うことありません(笑)
また、2年生は週に3日、下腿義足&長下肢装具&上腕義手のハードスケジュールで実習、1年生は基本工作論を年末に終えて、初めての専門科目の実習である体幹装具がスタートしているため、学科全体の雰囲気はほど良い緊張感に包まれています。
が、ここ数週間、季節性のインフルエンザの流行、風邪などで体調を崩す学生が多くなってきているので、皆さん体調管理・自己管理に務めるのも大切なことなのでしっかり手荒い&うがいをして対策して下さいね!
 安心環境で!?自習する3年生!!付き合っている教員も夜食は我慢(笑)
安心環境で!?自習する3年生!!付き合っている教員も夜食は我慢(笑)
 実際の義手使用者の方の義手を製作するために型取りをしています!
実際の義手使用者の方の義手を製作するために型取りをしています!
ということで、 本年度の入学試験も残り1回となりました(第5次一般入試)。出願期間は2月1日~15日・試験日は2月19日(金)となっていますので、受験をされる方・検討中の方は今年最後のチャンスなので宜しくお願いします。

また、個別での学校見学は随時受付ていますので、来年に受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒でも構いませんので、お気軽に申し込みをして頂き情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。
 " target="_blank">国試&卒業!進級!?まであと僅かです!!!
" target="_blank">国試&卒業!進級!?まであと僅かです!!!ということで、 本年度の入学試験も残り2回となりました(4次&5次一般入試)。4次の出願期間は1月4日~18日・試験日は1月22日(金)となっていますので、受験をされる方・検討中の方は宜しくお願いします。

また、個別での学校見学は随時受付ていますので、今年受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(受験当該学年ではない中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒にお気軽に申し込みをして頂き、情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。
 " target="_blank">新年明けましておめでとうございます!
" target="_blank">新年明けましておめでとうございます! 空腹&早くお代わりしたいために、ほぼ無言で食してました(笑)
空腹&早くお代わりしたいために、ほぼ無言で食してました(笑)
ということで、 本年度の入学試験も残り2回となりました(4次&5次一般入試)。4次の出願期間は1月4日~となっていますので宜しくお願いします。

また、冬休み中にも個別での学校見学は随時受付ていますので、今年受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(受験当該学年ではない中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒にお気軽に申し込みをして頂き、情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。
 " target="_blank">大掃除とカレーと冬休み!
" target="_blank">大掃除とカレーと冬休み! 筋電義手が、きちんと制御されて動くかどうかを確認中!
筋電義手が、きちんと制御されて動くかどうかを確認中!
 最終的に、使用者の方がコントロールできるかを評価中!
最終的に、使用者の方がコントロールできるかを評価中!
 プロのカメラマンによる撮影は一段と緊張するものですね!" target="_blank">筋電義手の適合評価と撮影会!?
プロのカメラマンによる撮影は一段と緊張するものですね!" target="_blank">筋電義手の適合評価と撮影会!? シミュレーション後に陽性モデル作成のためにギプスを貼り付け中!
シミュレーション後に陽性モデル作成のためにギプスを貼り付け中!
 車いすの選び方、採寸法、収納法など色んな機能の説明を聞いてます!
車いすの選び方、採寸法、収納法など色んな機能の説明を聞いてます!
 車いす(普通型・スポーツタイプ・電動)を試乗するために外に出発!
車いす(普通型・スポーツタイプ・電動)を試乗するために外に出発!
 車いすを試乗して利用者の視点から考察中…危険も体験!?
" target="_blank">座位保持装置の特別講義が実施されました!
車いすを試乗して利用者の視点から考察中…危険も体験!?
" target="_blank">座位保持装置の特別講義が実施されました!■平成21年度卒業研究テーマ 第1班 義足ソケットの不適合を解決する一考察 班員 奥野 雅大・柏 宗太郎・近藤 菜津子・武田 明久 指導 高見 健二 先生
第2班 PTB下腿義足における腱の圧迫を除外した懸垂装置の試作 班員 山口 幸平・稲垣 祐・水野 翔太・水野 諒 指導 中川 三吉 先生
第3班 塗装による「装具外観の質の向上」の試み 班員 加藤 裕・浅野 慎太郎・原 忠士・三輪 浩二 指導 利田 雅之 先生
第4班 ヒールの高さの違いによる足底圧と歩行への影響 班員 須川 健司・篠田 晃司・舟戸 あゆみ・鈴木 綾那 指導 宮本 武志 先生
第5班 弓道用前腕義手の試作 班員 小川 浩司・井出 晋平 寺崎 雄喜・不破 充・横濱 歩 指導 金髙 寿之 先生
 緊張しながら大きな声で聞き取りやすくプレゼンテーションしています!
緊張しながら大きな声で聞き取りやすくプレゼンテーションしています!
 卒業生、関連施設から参加して下さった方の人数は過去最多でした!
卒業生、関連施設から参加して下さった方の人数は過去最多でした!
 質疑応答の時間には、先生方から貴重なアドバイスを沢山頂けました!
質疑応答の時間には、先生方から貴重なアドバイスを沢山頂けました!
 21期生の記念撮影。お疲れ様でした!あと数ヶ月…頑張っていこう!
21期生の記念撮影。お疲れ様でした!あと数ヶ月…頑張っていこう!
 打ち上げ後の記念撮影。3年生は寝不足からか妙なテンションでした(笑)
打ち上げ後の記念撮影。3年生は寝不足からか妙なテンションでした(笑)
" target="_blank">卒業研究発表会が開催されました!
また、2,3年生からは、夜には各養成校の同学年の学生との懇親会が開催され盛り上がったと聞いています…翌日は眠そうな顔で会場にいましたが何時まで歌って?いたのでしょうか(笑)でも、そのうような交流は大変素敵なことだと思いますので、学生時代のみならず卒後も、そして1年生や後輩も続けていってくれたらと思います!
 表彰式に於いて~飛松学会会長より表彰状&記念品の授与!
表彰式に於いて~飛松学会会長より表彰状&記念品の授与!
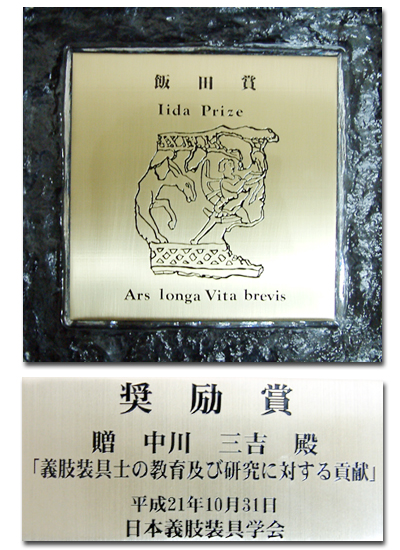 " target="_blank">中川主任が飯田賞奨励賞を受賞!
" target="_blank">中川主任が飯田賞奨励賞を受賞!
 " target="_blank">臨床実習報告会と企業説明会が開催されました!
" target="_blank">臨床実習報告会と企業説明会が開催されました! " target="_blank">秋の雑感~オープンキャンパスのお誘い~
" target="_blank">秋の雑感~オープンキャンパスのお誘い~■本年度の入試の詳細はコチラ
本年度のオープンキャンパスは全て終了しましたが、「個別の学校見学および会社見学ツアー」は随時受付をしていますので、お気軽にお問い合せ下さい(*日時等の事前予約が必要です)。
 " target="_blank">秋…いよいよ後期&入試シーズン!
" target="_blank">秋…いよいよ後期&入試シーズン!聞くと昨日はこの地方の同期の仲間と「川下り」して来たんだそう。 さらによくよく聞くと2泊3日の旅行で 1日目 長良川で川下り 2日目 伊勢神宮(これも別の同期の車で行った) 3日目 瀬戸へ陶器などを見に行った というスケジュール。帰る間際に学院によってくれたのです。
しかし・・・この辺りの地理に詳しい人なら分かると思いますが この3ヶ所って、全然「近く」ないんですけど。方向も全く違うし・・。 1日目と2日目にいたっては愛知県ですらないんですけど。 いったいどれだけアクティブなんでしょうか(笑)。
でも普段はなかなか会えない卒業生が「帰るついで」 というには少し遠回りな学院にわざわざ寄って近況を聞かせてくれる・・ って良いですね(特に彼女は「そういうタイプ」ではないのに)。 考えてみれば学会や同窓会の企画などで会う時は、 卒業生だらけで一人とゆっくり話すって、できそうでできないですものね。 話題もどうしても臨床的学術的な話や転職情報のやりとりなど、仕事に直結したことが多くなりますし・・。
仕事の話だけでなく、趣味の話、同期の話(さすがに関東以外の卒業生の話は私の方が良く知っている)、○○の話・・・いっぱい話して 「あー明日から仕事だー」と帰って行きました。 頑張れー!
聴能教員P
 " target="_blank">関東在住卒業生現るー言語聴覚士専門学校教員のつぶやき(18)-
" target="_blank">関東在住卒業生現るー言語聴覚士専門学校教員のつぶやき(18)-その学会の各種表彰の中、本学科の非常勤講師でお世話になっている高山平次先生が、技術報告「股義足における外装仕上げの取り組み」の論文にて、第4回POアカデミー論文賞を受賞しました!高山先生が長年培ってきた臨床での技術を活字にて、後進に伝える作業…大変だ会ったと思いますが、お疲れ様でした!そして、おめでとうございました!!
また、宮本先生は座長をして、担当セッションを過度の緊張しながらも上手く進行をしていました!!なお、10月31日・11月1日に神戸で開催される第25回日本義肢装具学会学術大会には、全学年の学生でツアーを組んで参加する予定です。
 授賞式後の記念撮影!高山先生、これからも頑張って下さい!!" target="_blank">高山先生が論文賞を受賞!
授賞式後の記念撮影!高山先生、これからも頑張って下さい!!" target="_blank">高山先生が論文賞を受賞!
 *作ったインソールを装着するため、中敷きの取り外しが可能な運動靴を履いて
きてください!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)までに
行ってください!
*作ったインソールを装着するため、中敷きの取り外しが可能な運動靴を履いて
きてください!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)までに
行ってください!

" target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう!③
 若人は食欲旺盛!一人平均2杯~3杯くらいは食べていたのでは?
若人は食欲旺盛!一人平均2杯~3杯くらいは食べていたのでは?
 皆で食べると美味しいですね!でも、食事に夢中でほぼ無言でした(笑)
皆で食べると美味しいですね!でも、食事に夢中でほぼ無言でした(笑)
ということで、 学生は夏休みですが7,8月の学科行事には以下があります。
 ■7月25日(土) 学科オープンキャンパス
■8月22日(土) 学科オープンキャンパス
■7月25日(土) 学科オープンキャンパス
■8月22日(土) 学科オープンキャンパス


オープンキャンパスは、前日までに参加申込みをして頂ければ構いませんので、今年、受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(受験当該学年ではない中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒にお気軽に参加をして頂き、色々な情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。" target="_blank">大掃除とカレーと夏休み!
“人工ボディ”は、先天性の障害、事故、病気により手足、胸、耳などの身体の一部を失ってしまった人々のために、各自の特徴に合わせて人体用のシリコーンで復元するもので、それは「失われた身体とともに心のケアもできる。」と、最も大事なのは、つくる前に相手の悩みをじっくり聴き、背景を察して、日常生活に合わせたものを考えること。その結果、技術・技能を磨くための情報収集や研鑽を続けていくことが、プロフェッショナルとしての醍醐味であるといった話を聞くことができました。
学生はもちろん、一緒に聴講させて頂いた自分自身も、義肢装具士を目指す・なってからの、「あたりまえが、あたりまえじゃない」こと、提供者側の自己満足でなく、より良いものを提供する“プロとしての姿勢”を学ばせて頂きました。あらめて、この仕事のやり甲斐、汗をかくことの大切さを感じることができたました。
福島先生、園田先生、お忙しいところ誠にありがとうございました!
 福島先生に指紋やシワまで復元できる印象材を塗ってもらってます!
福島先生に指紋やシワまで復元できる印象材を塗ってもらってます!
 印象材を冷水で攪拌している様子。注)アクエリアスではないです(笑)
印象材を冷水で攪拌している様子。注)アクエリアスではないです(笑)
 顔面全体の型を採ってます。左側で座って塗っているのは現在、
オーストラリアの義肢装具の大学に留学中の卒業生(冬休みで
帰国)が学校に寄ってくれなぜか??序でに特別講義も一緒に
参加していました!!
顔面全体の型を採ってます。左側で座って塗っているのは現在、
オーストラリアの義肢装具の大学に留学中の卒業生(冬休みで
帰国)が学校に寄ってくれなぜか??序でに特別講義も一緒に
参加していました!!
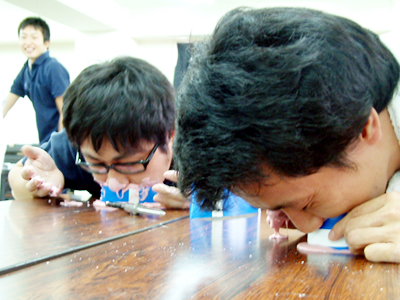 口の型を採っている学生…この光景は何かを出しているようで(笑)
口の型を採っている学生…この光景は何かを出しているようで(笑)
 最後に記念撮影!少しピントが合っていないのは撮影を卒●生が…
最後に記念撮影!少しピントが合っていないのは撮影を卒●生が…
PS.お帰りの際、名古屋名物味噌カツはご賞味できましたでしょうか? また、大阪に行った際には工房の「本社」にも寄らせてもらいます!! 義手担当教員:K't" target="_blank">人工ボディの特別講義が実施されました!
 出来上がった靴を履いて評価を待つ学生達の足並み!
出来上がった靴を履いて評価を待つ学生達の足並み!
 靴の適合評価のチェックポイントの指導を受ける様子!
靴の適合評価のチェックポイントの指導を受ける様子!
 装着評価は他の人が作った靴をお互いに評価し合います!
装着評価は他の人が作った靴をお互いに評価し合います!
 履くだけではなく、靴のメンテナンス、手入れの方法までを学びます!
履くだけではなく、靴のメンテナンス、手入れの方法までを学びます!
 最後に記念撮影!全員うまく適合したようで何よりです!!" target="_blank">ついに靴が完成しました!
最後に記念撮影!全員うまく適合したようで何よりです!!" target="_blank">ついに靴が完成しました!
さて、本年度の義肢装具学科オープンキャンパスも、残すところあと2回になりました。7月、8月と夏休み中の開催になりますので、最終的な進路を決定するための良い情報が得られると思います。ご家族の方や友人と一緒でも構いませんので、この機会にぜひ参加してみてください。教員、当日の学生スタッフ一同、楽しみにまっています。
 *作ったインソールを装着するため、中敷きの取り外しが可能な運動靴を履いて
きてください!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)までに
行ってください!
*作ったインソールを装着するため、中敷きの取り外しが可能な運動靴を履いて
きてください!
*材料準備などの都合上、参加お申し込みは前日の夕方(午後5時)までに
行ってください!

 " target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう!②
" target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう!②各部署を回りながら説明を受け、また、社長様にもプレゼンを行って頂きました。参加した1年生も今後の学校生活はもとより義肢装具士として仕事に携わる姿勢に感銘し、良い刺激を受けて帰ってきました。担当者の方をはじめ会社の皆様に感謝致します。お忙しいところ、貴重な体験をさせて頂き、ありがとうございました。
 見学の様子①初めて見る現場の機械や設備にも驚き!
見学の様子①初めて見る現場の機械や設備にも驚き!
 見学の様子②義肢や装具だけでなく福祉機器も沢山!
見学の様子②義肢や装具だけでなく福祉機器も沢山!
 ちょうど臨床実習で、お世話になっている3年生を発見!
" target="_blank">会社見学に行ってきました(大阪)!
ちょうど臨床実習で、お世話になっている3年生を発見!
" target="_blank">会社見学に行ってきました(大阪)! 報告会の様子②
…聴講する2年生も興味深く聞いて活発な質疑をしてくれました!
報告会の様子②
…聴講する2年生も興味深く聞いて活発な質疑をしてくれました!
 報告会の様子③
…問題解決のため今後も汗をかきエビデンスを追求して下さい!
報告会の様子③
…問題解決のため今後も汗をかきエビデンスを追求して下さい!
 21期生Tシャツを着こなす3年生
…バラバラなカラーですが、気持ちは一色です!
21期生Tシャツを着こなす3年生
…バラバラなカラーですが、気持ちは一色です!
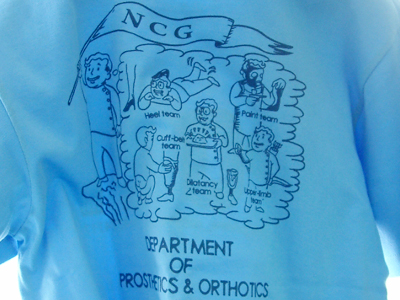 21期生オリジナル
…イラストは各卒研チームのテーマを現したたものだそうです!
21期生オリジナル
…イラストは各卒研チームのテーマを現したたものだそうです!
3年生担任K't " target="_blank">卒研中間報告会と日聴カラー!!

インソールとは、靴の中に入れる中敷きのことで、靴店やスポーツショップなどで売られているものを見たことがあると思います。このような中敷きは、ある程度は誰にでも合うように設計されています。
しかし、義肢装具士が製作するインソールは、「医師の指示のもとに、一人一人に合わせて精巧に型をとり、その方にしか合わない 世界に一つだけの製品」を作っています。
今回、参加して頂く皆さんには、実際に授業で使用している工作機械や材料を使い、簡単なインサートを作って頂きます。教員による模擬授業に加えて、モノ作りを体験することで、義肢装具士の仕事の楽しさ、奥深さをしっかりと理解することができます。
もちろん、作ったインソールは、オープンキャンパスの記念にお持ち帰り頂けます! ぜひ、この機会に教員や学生スタッフと一緒に模擬授業の体験してみませんか?



 " target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう!
" target="_blank">模擬授業でインソールを作ろう!■2年生 2年生は週2回、下腿義足と靴型装具があります。靴型装具では、学生個々の足型を採って、木型製作から製甲、仕上げまでの一足を全て手作りで製作します。また、出来上がった靴は、臨床実習に赴く際に履いていく予定です。
 慣れない工具に苦労…でも、自分が履く靴の出来上がりが楽しみです!
慣れない工具に苦労…でも、自分が履く靴の出来上がりが楽しみです!
■1年生 1年生は週1回、義肢装具基本工作論があります。1年次の年明け、2年生から始まる専門科目(実習)に向けた義肢装具の製作・適合のために、必要最低限の製作技術習得、諸材料の特性を知るために、実際の義肢や装具を製作しながら基本工作を学んでいきます。
 初製作した装具の仮合わせに緊張…出来上がったら1日、履きます!" target="_blank">製作実習の授業経過をレポート!!
初製作した装具の仮合わせに緊張…出来上がったら1日、履きます!" target="_blank">製作実習の授業経過をレポート!!
なお、個別の学校見学は随時受け付けています(事前予約が必要です)。 義肢装具士&言語聴覚士の仕事紹介や、学校の説明など、すべて各科 の専任教員が直接対応いたします。お気軽にお問い合わせください!
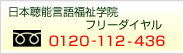 " target="_blank">合同オープンキャンパスのお知らせ!
" target="_blank">合同オープンキャンパスのお知らせ!義肢装具学科教員K't" target="_blank">新入生・新先生・新年度がスタート!!
義肢装具学科教員K't " target="_blank">義肢装具士国家試験に全員合格しました!!
 卒業証書授与式後の記念撮影
卒業証書授与式後の記念撮影
 全学年・専任教員との記念撮影
全学年・専任教員との記念撮影
 謝恩会での卒業生催し(20期生少年・少女?)" target="_blank">平成20年度卒業式・謝恩会
謝恩会での卒業生催し(20期生少年・少女?)" target="_blank">平成20年度卒業式・謝恩会さて、前回の話の1年後、同じ嚥下学会での話です。 学会長は「嚥下の神様」と、この領域の医師やSTなら誰もが知っているF島先生でした。その先生が冒頭のあいさつで開口一番「今日は『嚥下の神様』がいらっしゃっていますので、皆さん活発なディスカッションをどうぞ。」と会場の後ろの方を見ながらおっしゃいました。
「?・・神様に『神様』って言われる人って?」と皆が一斉に振り向くと・・そう、もうお分かりでしょう。そこには我が学院長。
手前みそですか?
でもその時は「あなたのお父さんってすてきね」と褒められて、恥ずかしくって必死に否定する娘(?)の気分・・。
当の「カミサマ」はそう呼ばれたことには全く無頓着で、「素朴な疑問なんだけど」とでもいうような顔をして、「実はするどーい質問」の連発で発表者は皆タジタジ・・でした。
「こんな時に発表してたら大変だったなあ」と不謹慎ながら、おかしいような、そして発表者に対して同情的な気持ちになりました。でもそれと同時に研究者としてうらやましい気持ちも・・。やっぱり学会発表は質問されて、つっこまれて研ぎ澄まされていくものですからね。それが「神様」級ならいうことなし・・です。
研究には現役で(すごい!)容赦なく真剣勝負の我が学院長話はまだまだ続きます。 次は忘れないようにしなければ・・(忘れてたらまた教えてください)。
聴能教員P
 " target="_blank">学院長カッコ良すぎです!その弐―言語聴覚士専門学校教員のつぶやき(13)―
" target="_blank">学院長カッコ良すぎです!その弐―言語聴覚士専門学校教員のつぶやき(13)―上肢(指や手、腕)に使用する装具の難しさと重要性を理解するため、講義に加え、臨床現場で注意しなければならない事項を、より実践に即した形で実技指導を行って頂けました。
小田純生先生、お忙しいところ誠にありがとうございました。
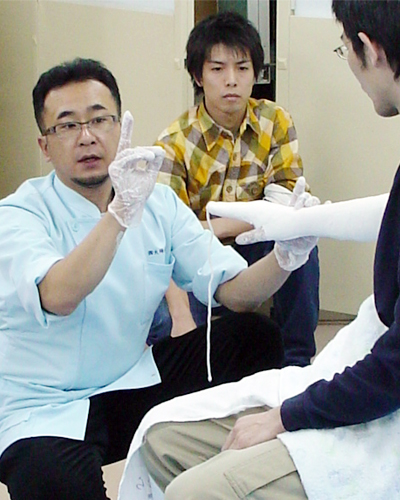 小田先生の指導に、あと数ヶ月で臨床現場にたつ学生の表情も真剣っ!!" target="_blank">上肢装具の特別講義が実施されました!
小田先生の指導に、あと数ヶ月で臨床現場にたつ学生の表情も真剣っ!!" target="_blank">上肢装具の特別講義が実施されました!*学院(事務)は2008.12.31~2009.1.4までお休みさせて頂きますのでご了承下さい。 " target="_blank">入試日程(特別入試含む)のお知らせ!!
年明けの1月23日には、「推薦入学試験(2次)」、 2月20日には「一般入学試験(2次)」があります! ■募集要項の詳細はコチラ
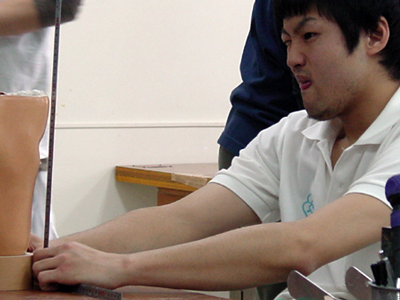 総論試験
…期間中に定められた義肢装具を製作!~1年の実習集大成です!
総論試験
…期間中に定められた義肢装具を製作!~1年の実習集大成です!
 大掃除の後
…疲れた身体におしるこで食べ納め!~中川先生の味付けです!
大掃除の後
…疲れた身体におしるこで食べ納め!~中川先生の味付けです!
 スキー合宿
…2泊3日で野沢温泉でスキーを満喫!~宿泊先の前で集合写真!" target="_blank">年末の各種行事報告です!
スキー合宿
…2泊3日で野沢温泉でスキーを満喫!~宿泊先の前で集合写真!" target="_blank">年末の各種行事報告です!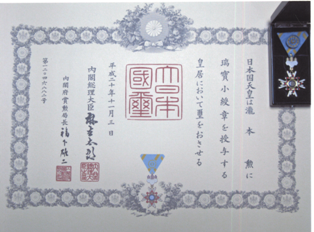 前理事長に続き学院関係者二人目の受章ですが、
やはり受章を知ってから数日は
「こういう時は何をどうすれば良いのか?」
「まずは先生に『おめでとうございます』と言うべき?お祝いは?」
とあたふたしてしまいました。
思い起こせば私が学院に新任教員として赴任したばかりの時。
前職場の病院では
言語聴覚士としてある程度様々な経験を積んだつもりでしたが、
教育の現場では全く勝手が違い、
毎日学生の対応と自分の講義の準備をするだけでも精一杯でした。
そんな私に瀧本先生は
「教員というものは
『教育・臨床・研究』の3つをきちんとしていかなければならない」
と常々仰っていました。
その時は「教員なのだから、まず教育ではないのか?」と疑問に思い、
毎年課された業績報告書
(自分がした学会発表や論文など研究の記録をまとめたもの)
提出のシーズンになると少し憂鬱な気分になっていました。
でも気が付けばかなり長い年月がたち、
苦しみながらも自分なりに教育・臨床・研究を続けてきて
振り返ってみると先生は教員にとってとても大切なことを教えて下さったと思います。
言語聴覚療法の領域は日進月歩。
新しい知見は書籍を読めばある程度入手可能で授業もできるかもしれないけれど、臨床の場でそれを実践しなければ分からないこともたくさんあります。
しかし、ただ漫然と臨床をしているだけではだめで、
臨床の中で生じた疑問を解決したり、
アイディアを形にして臨床能力をよりグレードアップする手段の一つが研究です。
そして、そういう一連の流れに取り組んでいる時、
なによりも言語聴覚士としてワクワクしている自分がいる。
それを「学生に伝えたい!」という気持ちが教育の源かもしれない、
それなしでは教育の質を保ちながら継続していくのは困難だ
というのが今の私の考えです。
瀧本先生の教えがなければ私は底の浅い教育しかできず、
時代の流れの中、どこかで行き詰まり、
もしかしたら教育の現場にはいられなかったかもしれません。
偉そうなことを書いてしまいましたが、まだまだ私は道半ばです。
これからも先生の教えを日々丁寧に実践していきたいと思っています。
先生本当におめでとうございます。
前理事長に続き学院関係者二人目の受章ですが、
やはり受章を知ってから数日は
「こういう時は何をどうすれば良いのか?」
「まずは先生に『おめでとうございます』と言うべき?お祝いは?」
とあたふたしてしまいました。
思い起こせば私が学院に新任教員として赴任したばかりの時。
前職場の病院では
言語聴覚士としてある程度様々な経験を積んだつもりでしたが、
教育の現場では全く勝手が違い、
毎日学生の対応と自分の講義の準備をするだけでも精一杯でした。
そんな私に瀧本先生は
「教員というものは
『教育・臨床・研究』の3つをきちんとしていかなければならない」
と常々仰っていました。
その時は「教員なのだから、まず教育ではないのか?」と疑問に思い、
毎年課された業績報告書
(自分がした学会発表や論文など研究の記録をまとめたもの)
提出のシーズンになると少し憂鬱な気分になっていました。
でも気が付けばかなり長い年月がたち、
苦しみながらも自分なりに教育・臨床・研究を続けてきて
振り返ってみると先生は教員にとってとても大切なことを教えて下さったと思います。
言語聴覚療法の領域は日進月歩。
新しい知見は書籍を読めばある程度入手可能で授業もできるかもしれないけれど、臨床の場でそれを実践しなければ分からないこともたくさんあります。
しかし、ただ漫然と臨床をしているだけではだめで、
臨床の中で生じた疑問を解決したり、
アイディアを形にして臨床能力をよりグレードアップする手段の一つが研究です。
そして、そういう一連の流れに取り組んでいる時、
なによりも言語聴覚士としてワクワクしている自分がいる。
それを「学生に伝えたい!」という気持ちが教育の源かもしれない、
それなしでは教育の質を保ちながら継続していくのは困難だ
というのが今の私の考えです。
瀧本先生の教えがなければ私は底の浅い教育しかできず、
時代の流れの中、どこかで行き詰まり、
もしかしたら教育の現場にはいられなかったかもしれません。
偉そうなことを書いてしまいましたが、まだまだ私は道半ばです。
これからも先生の教えを日々丁寧に実践していきたいと思っています。
先生本当におめでとうございます。
 聴能教員P" target="_blank">秋の叙勲:瀧本前学院長の受章に思うこと-言語聴覚士専門学校教員のつぶやき(11)-
聴能教員P" target="_blank">秋の叙勲:瀧本前学院長の受章に思うこと-言語聴覚士専門学校教員のつぶやき(11)-■平成20年度卒業研究テーマ 第1班 義肢ソケットの抗菌加工~お手軽抗菌加工~ 班員 花實隆歩・村上寛幸・大床悠馬・杉山綾乃 指導 高見健二 先生
第2班 サッカーの運動特性を考慮したスポーツインソールの考案 班員 伊藤貴之・川久保淳司・齋藤昌宏・高野裕章 指導 中川三吉 先生
第3班 コントロールケーブルによる手先具の随意的な回旋を可能にする手継手の開発 班員 浜田篤至・大貫 祥・石井辰也・大竹琢磨 指導 利田雅之 先生
第4班 幼児用上履きの調査~歴史的背景から考察する現状~ 班員 馬場直子・嶋本麻里・松原優花・村中未来・山中良恵 指導 宮本武志 先生
第5班 コルゲーションの形状が短下肢装具の撓み特性に及ぼす影響 班員 古川拓海・亀山 勲・川瀬裕子・戸田光帆子 指導 出井裕司 先生
第6班 下腿義足使用者の階段降段に求められる足部の機能と与える影響 班員 金森晴香・石垣広志・梅津理恵・澤田美希子・杉森拓也・太田喜士 指導 小川淳夫 先生
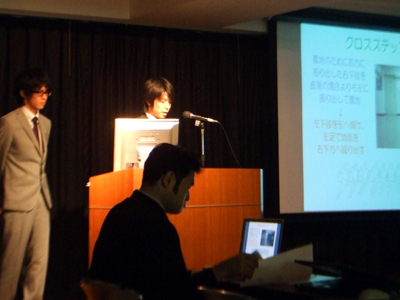 緊張しながらも大きな声で頑張って発表する学生達!
緊張しながらも大きな声で頑張って発表する学生達!
 発表会後、恒例の国家試験合格祈願セットをもらって…
発表会後、恒例の国家試験合格祈願セットをもらって…
 発表者(20期生)と教務で記念撮影…お疲れ様でした!" target="_blank">三年生が卒業研究発表を行いました!
発表者(20期生)と教務で記念撮影…お疲れ様でした!" target="_blank">三年生が卒業研究発表を行いました!

" target="_blank">中学生が「福祉体験学習」のため来校しました!
姿勢を保持することの重要性を理解するため実例を交えながらの講義に加え、学生各自がオーダーメイドによるシート(クッション)の製作、圧力分布測定装置を使用しての考察、各種採型機器によるシミュレーションと採型、また様々な車いすの特徴を理解するための試乗、といった幅広い内容を実体験することによって、より実践に即した学習ができたと思います(国家試験対策まで実施して頂けました)。
また、評価機器は*タカノ㈱健康福祉部の柏原様、採型機器および車いすは*東名ブレース㈱オルソペディックサービス事業部エンド・シーティング担当の木部様にご協力を頂きました。お忙しいところ誠にありがとうございました。
 自分の座面を採寸したデータを元に削りだしマイクッションの製作中!
*これからの国家試験対策勉強に向けたデスクワークにも最適っ!!
自分の座面を採寸したデータを元に削りだしマイクッションの製作中!
*これからの国家試験対策勉強に向けたデスクワークにも最適っ!!
 特殊な採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中!
特殊な採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中!
 特殊な採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中!
特殊な採型機器を用いて座位を保持する姿勢をシミュレーション中!
 車いす(普通型・スポーツタイプ・電動)を試乗するために外に出発!
車いす(普通型・スポーツタイプ・電動)を試乗するために外に出発!
 グループごとに各種の車いすを試乗して利用者の視点から考察中!" target="_blank">座位保持装置の特別講義が実施されました!
グループごとに各種の車いすを試乗して利用者の視点から考察中!" target="_blank">座位保持装置の特別講義が実施されました!内容は、学生向けの紙面の「おしごとファイル」というコーナーにて 言語聴覚士の仕事について紹介するという企画で、 9月15日の朝刊に掲載されました。
その内容については中日新聞のホームページで閲覧できます。 ぜひご覧ください。
◎中日新聞「中高生WEEKLY」バックナンバー
先日のブログでも紹介しましたとおり、 言語聴覚士はまだまだ不足しています。 待っている方々のためにも、少しでも多くの方に言語聴覚士を知っていただき、 志す方が増えることを願ってやみません。
" target="_blank">中日新聞に言語聴覚士を紹介する記事(学院:田島先生)が掲載されました。
" target="_blank">推薦入学試験1次の願書受付が始まりました!
■パラリンピック山本が銀メダル…陸上の男子走り幅跳び [9月16日21時35分配信 毎日新聞] ■パラ五輪走り幅跳び 実業団所属の山本篤が銀 [9月16日17時10分配信 産経新聞] ■パラリンピック・銀メダルの山本 [9月16日14時33分配信 時事通信] ■パラリンピック・銀メダルのジャンプ [9月16日14時33分配信 時事通信]
" target="_blank">卒業生の山本篤選手が銀メダル!!
現在、山本選手が使用している義足(脚のスポーツ用部品)は、数年前より日本の義肢パーツメーカー(㈱今仙技術研究所)と教育機関(本学科の青山前・学科長・高見学科長・中川教務主任)、臨床のチームが連携して開発してきたものです!!本学科は教育機関としてだけではなく、研究機関としても「義肢装具の発展」のための役割を果たしています。
 ■LAPOC SOPRTS「侍」:モジュール型スポーツレクレーション用義足を使用して跳躍する山本選手
■LAPOC SOPRTS「侍」:モジュール型スポーツレクレーション用義足を使用して跳躍する山本選手
さて、9月6日から北京パラリンピックで各国の代表選手をサポートするために、オットーボック・リペアサービス(義肢や車いすなどの公式リペアサービスの提供)を行っている、本学科専任教員の出井裕司先生は、義肢や車いすの修理・メンテナンスなどはもちろん、現地で外国人スタッフと交流を深めながら(非常に貴重な体験ができているとのこと…)英会話の勉強を頑張っているそうです!大会も今週末で終わりますが、体調管理に気を付けて頑張ってもらいたいです!!
 ■各国からの外国人スタッフと…
■各国からの外国人スタッフと…
 ■現地のボランティアスタッフと…
■現地のボランティアスタッフと…
" target="_blank">北京パラリンピック(出井先生レポ②)
9月6日に北京に赴き、開会式に参加して感銘を受けた後、日々リペアサービスにて作業をしながら、空き時間には多くの試合を観戦をし、目前で見る各種競技の“迫力”に圧倒されているそうです!!
また、ご飯も安くて美味いらしく(ビールは約100円だそうです)、外国人スタッフとの英会話の勉強、ルームシェアの方とも仲良く頑張っているみたいです!それでは、気候や環境が異なる現地での出井先生の奮闘の様子など、また報告が入り次第にレポートします!!!
■北京パラリンピック公式ホームページ ■NHK 2008北京パラリンピック関連番組 放映予定表
 100m走と走り幅跳び日本代表の山本篤選手(本学科OB)の練習風景
100m走と走り幅跳び日本代表の山本篤選手(本学科OB)の練習風景
 出井先生とルームシェアしているリペアサービススタッフのMr.Kay(German)
出井先生とルームシェアしているリペアサービススタッフのMr.Kay(German)
" target="_blank">北京パラリンピック(出井先生レポ①)
 ごちそうさまでした!
夏休み期間中のひとコマでした。
" target="_blank">「カキ氷で涼みました」~夏休みのひとコマ
ごちそうさまでした!
夏休み期間中のひとコマでした。
" target="_blank">「カキ氷で涼みました」~夏休みのひとコマまた、学生は夏休みですが7,8月の学科行事には以下があります。
■7月26日(土)オープンキャンパス② *詳細はコチラ ■7月30日(木)リクルート進学わくわくライブ *詳細はコチラ ■8月23日(土)オープンキャンパス③ *詳細はコチラ
オープンキャンパスは、前日までに参加申込みをして頂ければ構いませんので、今年、受験を考えている方はもちろん、義肢・装具、義肢装具士に興味のある方、医療系、技術系で進路を検討中の方(受験当該学年ではない中学生、高校1,2年生、大学2,3年生、社会人の方も、もちろん大丈夫です!)、保護者の方や友人とご一緒にお気軽に参加をして頂き、色々な情報収集をして進路を検討して頂ければと思います。 (*参加して頂いた方全員に図書券のプレゼントがあります!)
7月30日(水)に名古屋ドームで開催される「リクルート進学わくわくライブ:名古屋」では、学院ブースの出展と、仕事発見コーナー(義肢装具士)を実施しますので是非ご参加下さい!" target="_blank">大掃除とカレーと夏休み!
より使用者の多様なニーズに応えられる義肢装具士(PO)になるために、これまでの実習授業における靴の製作技術に加えて、オリジナルの靴デザインが施せるノウハウを学ぶことは、靴型装具を装具としてだけでなく、ファッションの一部としても提供できる技術はPOとしての幅も広がり非常に有益なことです。
また、授業では眞殿先生の経験と技術の教授はもとより、何とか若い人達に「使用者の気持ちに応える技術」を伝えたいという熱い気持ちと、関西人?弁?ならではのテンポの良い進行、明るい雰囲気の中で学べたことは、なによりの財産になったと思います。眞殿先生、毎年のことながら、遠路からお越し頂きありがとうございました!
" target="_blank">靴型装具の特別講義(眞殿先生)
■山本篤選手の関連ニュース記事 ・2008北京パラリンピック競技大会 日本代表選手発表 ・「挑戦すれば、道は開ける」 義足ランナー、北京照準…山本さん ・「走りを究めて 頂点へ~義足のスプリンター・山本篤~」
 " target="_blank">北京パラリンピックに…っ!!
" target="_blank">北京パラリンピックに…っ!!■第24回日本義肢装具学会研修セミナー 内容:知っておきたい大腿義足の基礎知識-処方から訓練法まで- 会期:8月9日(土)~10日(日) 主催:日本義肢装具学会
■平成20年度日本義肢装具士協会全国研修セミナー 内容:脳性麻痺と義肢装具士 会期:9月6日(土)~7日(日) 主催:日本義肢装具士協会
*その他にも多くありますが、厚生労働省主催の「義肢装具技能検定」の会場としても毎年利用されています。
" target="_blank">卒後、生涯教育の“場”として…っ!!





 " target="_blank">靴型装具の実習がスタート!!
" target="_blank">靴型装具の実習がスタート!!■本学科の臨床実習の主な施設は*コチラを参照下さい。" target="_blank">3年生が臨床実習に赴きました!
昨年の第14回大会(名古屋:本学科の中川教務主任が大会長を務めた)と同様に盛況に開催され、学術大会のテーマ「他職種から学ぶ適合のあり方」に関連した講演の聴講、商業展示での新製品の見聞が行え様々な角度からの情報収集が行えました。
また、一般演題では教職員の利田、出井、小川の発表と、昨年の卒業研究の3演題がエントリーして発表しました。
昼食と夜に食べた牛タンはもちろん、臨床現場の方と就職や臨床実習のこと、学校教育についてなど熱く話ができたこと、また、卒業生にも数多く会うことができたのが何よりの収穫でした。
余談ですが、昨年に引き続き仙台でも学会の夜に各養成校の学生さんが集まり懇親会が開かれ(各学年ごとに?)、もの凄く盛り上がったそうです…何よりです!!
また、今秋には東京で第24回日本義肢装具学会学術大会が開催されるため、本学科学生全員を引率して参加する予定です。
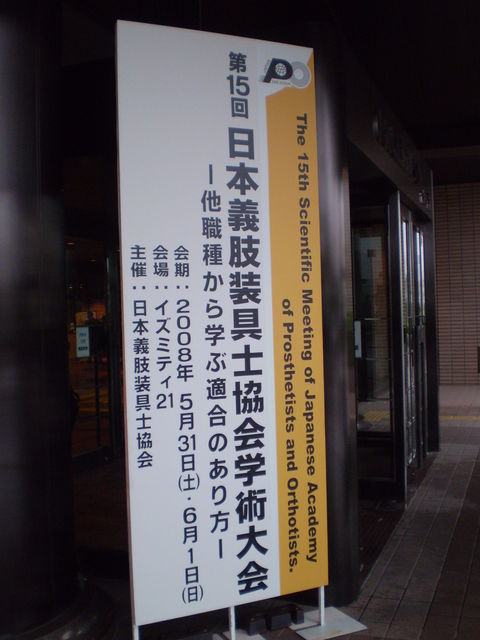 " target="_blank">仙台の学会に参加してきました!
" target="_blank">仙台の学会に参加してきました!また、本年度も7月30日(水)に名古屋ドームで開催される「リクルート進学わくわくライブ:名古屋」に学院ブースの出展と、仕事発見コーナー(義肢装具士)を実施しますので是非ご参加下さい!
■リクルート進学わくわくライブ:名古屋の詳細はコチラ" target="_blank">本年度学科オープンキャンパスのお知らせ!
■義足外装仕上げ特別講義 ④㈱松本義肢製作所:高山先生


 " target="_blank">大腿義足の実習がスタート!!
" target="_blank">大腿義足の実習がスタート!!
また、夕方からの謝恩会には、(社)日本義肢協会中部支部長の奥 幹男様をはじめ、お世話になった講師の先生、実習先指導者、就職先の方々、卒業生も多数参加頂いて開催されました。 卒業生らによる最後の出しもの、1,2年生の在校生による出しものもあり笑いあり、泣きありの盛大でココロ温まる会でした。


3月末の国家試験合格発表は気になるところですが、4月から職場で頑張って下さい。" target="_blank">平成19年度卒業式・謝恩会
 *澤村誠志大会長より表彰される班員(学生)
*澤村誠志大会長より表彰される班員(学生)
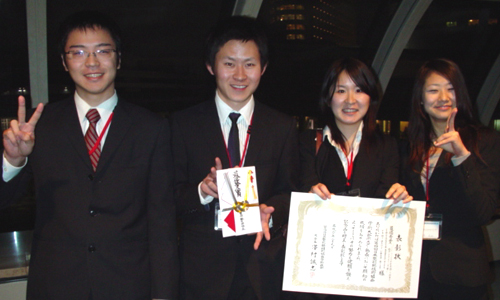 *表彰式後の記念写真(左から溝上・中島(班長)・勝見・加藤)
ハイヒールによる中足骨頭への荷重を軽減させるための一考察
Consideration of reduce load to metatarsal head with high-heeled shoes
卒業研究 第3班
中島 徹也 勝見 加代子 加藤 真那 溝上 直幸
研究指導者 利田 雅之 " target="_blank">「最優秀賞」を受賞しました!
*表彰式後の記念写真(左から溝上・中島(班長)・勝見・加藤)
ハイヒールによる中足骨頭への荷重を軽減させるための一考察
Consideration of reduce load to metatarsal head with high-heeled shoes
卒業研究 第3班
中島 徹也 勝見 加代子 加藤 真那 溝上 直幸
研究指導者 利田 雅之 " target="_blank">「最優秀賞」を受賞しました! 三年生の写真(合格祈願)" target="_blank">国家試験まであと24日!!
三年生の写真(合格祈願)" target="_blank">国家試験まであと24日!!
 " target="_blank">特別講義(高山先生)が実施されました!
" target="_blank">特別講義(高山先生)が実施されました! ★発表会終了後の集合写真はコチラ
平成19年度義肢装具学科卒業研究
第1班 初心者に義足のアライメント調節を正しく理解させるための教育システムの研究
班員 ■樋上 大・千田 弦・林 伸彦・永井孝治・大崎嘉巳・山田智則
指導 青山 孝 先生
第2班 女性義足ユーザー向け生活支援マニュアルの作成
班員 ■近藤宏美・鶴田あすみ・山口詩織
指導 中川三吉 先生
第3班 ハイヒールによる中足骨頭への荷重を軽減させるための一考察
班員 ■中島徹也・加藤真那・勝見加代子・溝上直幸
指導 利田雅之 先生
第4班 PTB短下肢装具のパッテン底の位置の違いによる歩行への影響
班員 ■丹羽加津晃・伊藤泰崇・佐藤 光・山田大輔
指導 宮本武志 先生
第5班 箸を使った食事動作のための手先具の開発
班員 ■永井智裕・大蔵史景・野本 葵・古山 拓
指導 出井裕司 先生
第6班 スポーツ用下腿義足のアライメントと走行速度が身体に及ぼす影響
班員 ■塩野弘季・永橋 侑・原 健・間藤基之・眞鍋 健人・諸岡功一
指導 小川淳夫 先生" target="_blank">卒業研究発表会
★発表会終了後の集合写真はコチラ
平成19年度義肢装具学科卒業研究
第1班 初心者に義足のアライメント調節を正しく理解させるための教育システムの研究
班員 ■樋上 大・千田 弦・林 伸彦・永井孝治・大崎嘉巳・山田智則
指導 青山 孝 先生
第2班 女性義足ユーザー向け生活支援マニュアルの作成
班員 ■近藤宏美・鶴田あすみ・山口詩織
指導 中川三吉 先生
第3班 ハイヒールによる中足骨頭への荷重を軽減させるための一考察
班員 ■中島徹也・加藤真那・勝見加代子・溝上直幸
指導 利田雅之 先生
第4班 PTB短下肢装具のパッテン底の位置の違いによる歩行への影響
班員 ■丹羽加津晃・伊藤泰崇・佐藤 光・山田大輔
指導 宮本武志 先生
第5班 箸を使った食事動作のための手先具の開発
班員 ■永井智裕・大蔵史景・野本 葵・古山 拓
指導 出井裕司 先生
第6班 スポーツ用下腿義足のアライメントと走行速度が身体に及ぼす影響
班員 ■塩野弘季・永橋 侑・原 健・間藤基之・眞鍋 健人・諸岡功一
指導 小川淳夫 先生" target="_blank">卒業研究発表会
平成18年度 卒業研究内容 *■は班長 第1班 ソケットに加わる力からみた坐骨収納型ソケットと四辺形ソケットの比較 班員 ■名和大輔 後藤宏友 谷川大輔 櫻木玄徳 指導 青山 孝 第2班 下肢の役割補助を前提にした装具への提案 班員 ■山崎健治 柴 丈司 大石園子 近藤由貴子 指導 青山 孝 第3班 骨折固定時の内部環境調査 班員 ■小野寺翔太朗 橋本裕紀 今井宏美 長谷川幸弘 佐藤敬太 指導 中川三吉 第4班 車いすユーザーの日常生活におけるバリアフリー状況の調査 班員 ■岡部泰士 長尾泰史 牛田結花 村上晃一 田所直樹 指導 利田雅之 第5班 靴と足底装具の不適合が歩行に及ぼす影響 班員 ■高橋大輔 吉井宏騎 岡部貴広 桃崎 晃 安原弘晃 指導 宮本武志 第6班 「装具取扱説明書作成の為のガイドライン」の提案 班員 ■石垣朋子 井土太一 小池奈々 寺西七穂 指導 出井裕司" target="_blank">卒業研究発表会
 次期大会は、本学科教務主任の中川三吉が大会長を務めて名古屋で
開催されます。来年の学生さんは学術大会当日の運営スタッフとして、
活躍してもらうことになります。
■第14回日本義肢装具士協会学術大会" target="_blank">第13回POアカデミー研究会大阪大会
次期大会は、本学科教務主任の中川三吉が大会長を務めて名古屋で
開催されます。来年の学生さんは学術大会当日の運営スタッフとして、
活躍してもらうことになります。
■第14回日本義肢装具士協会学術大会" target="_blank">第13回POアカデミー研究会大阪大会